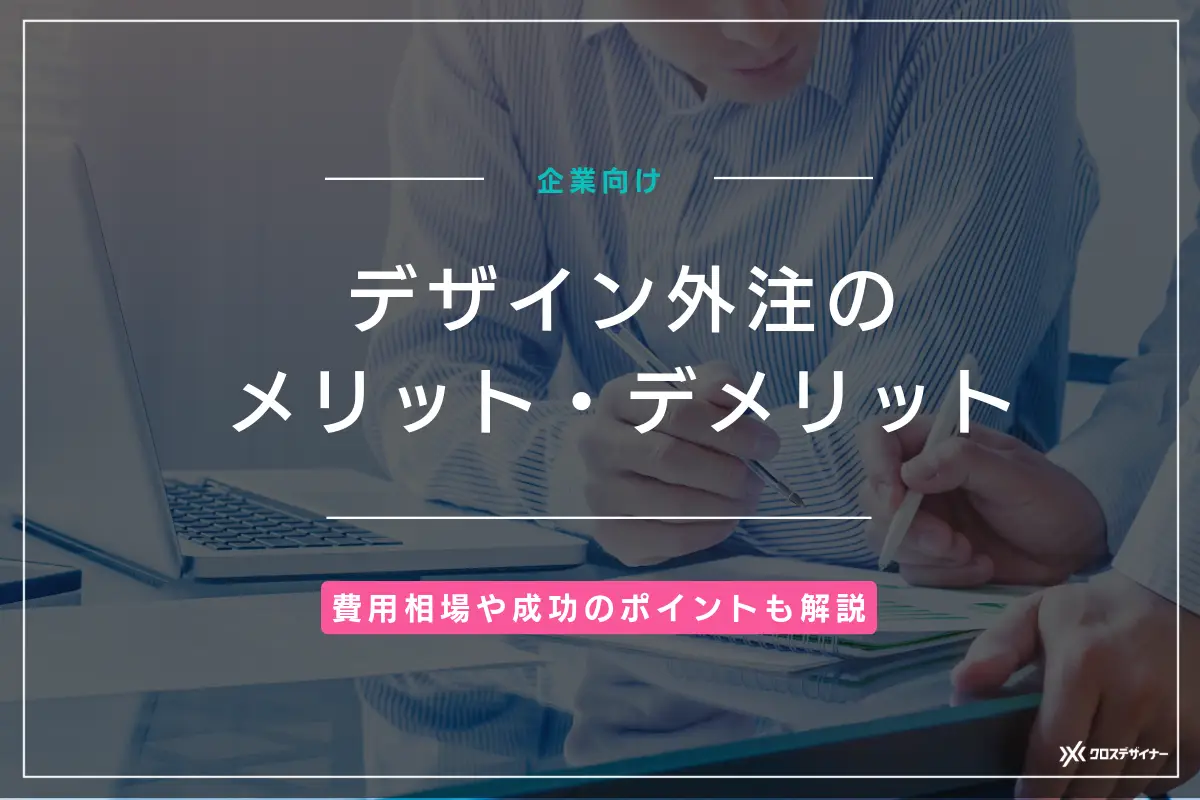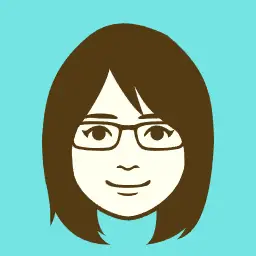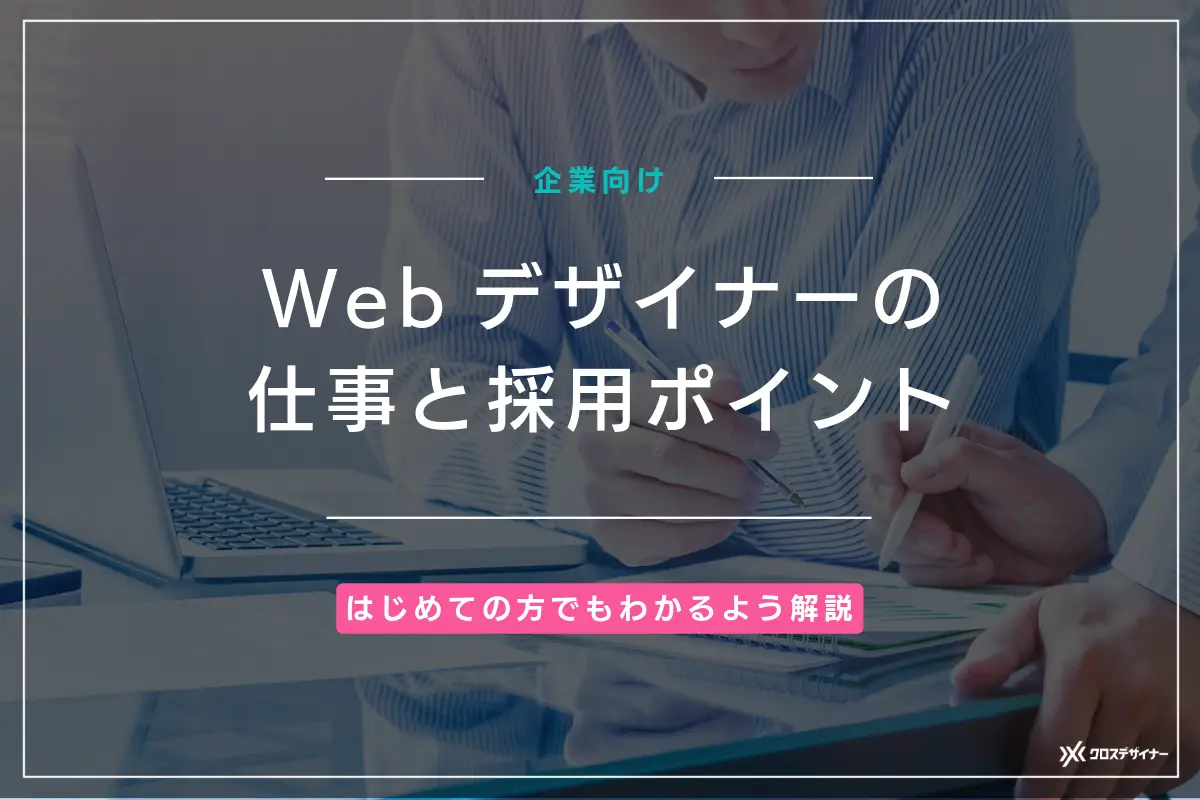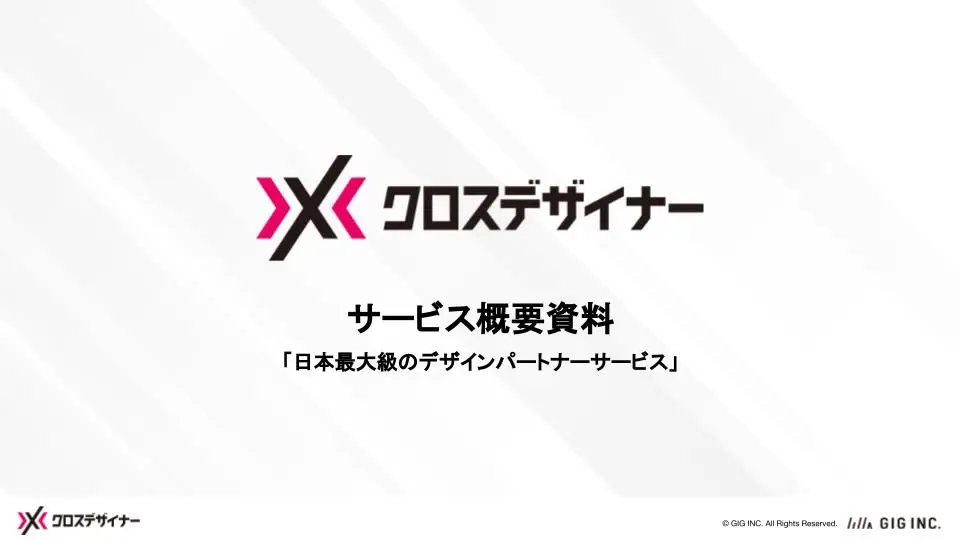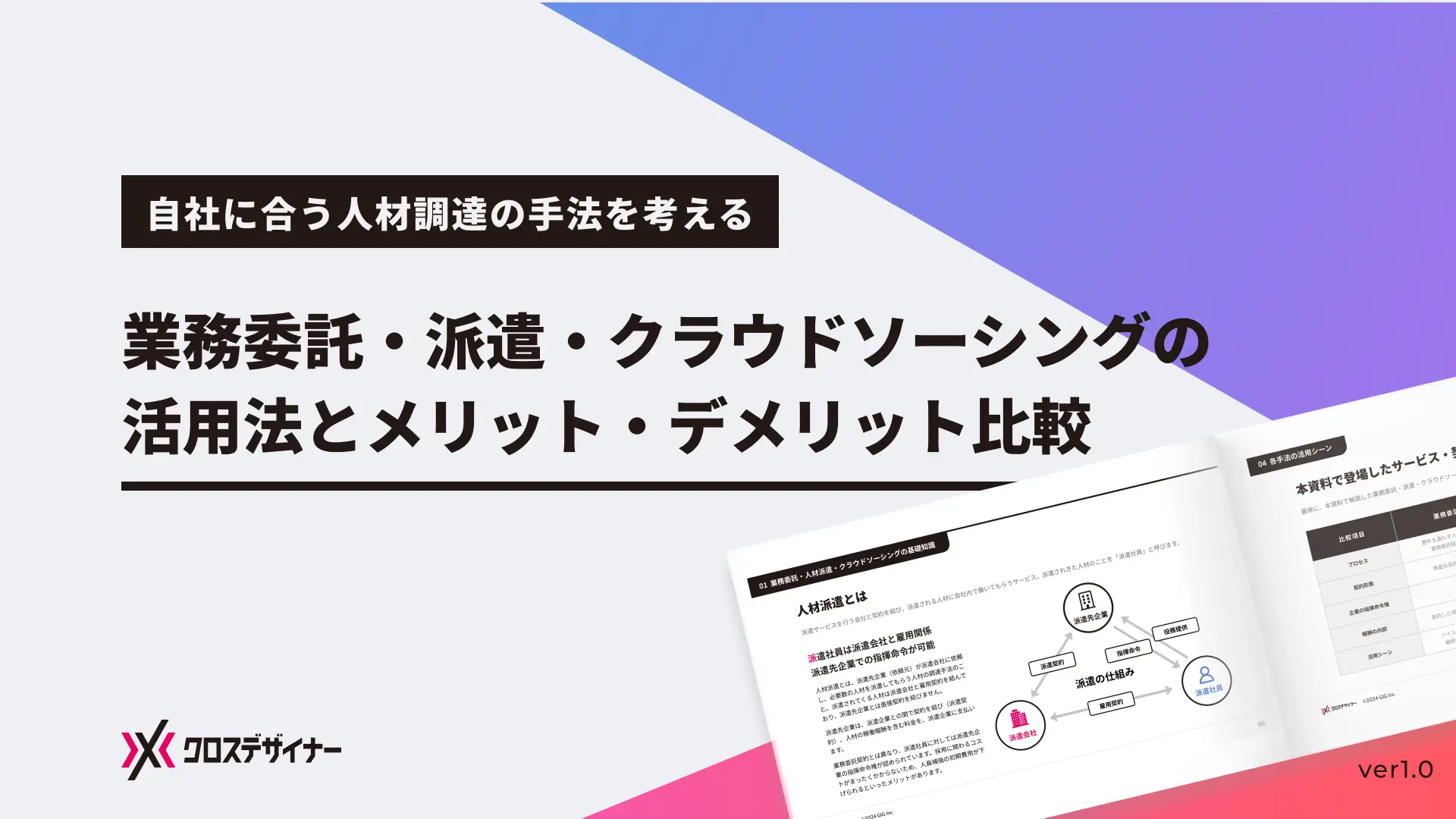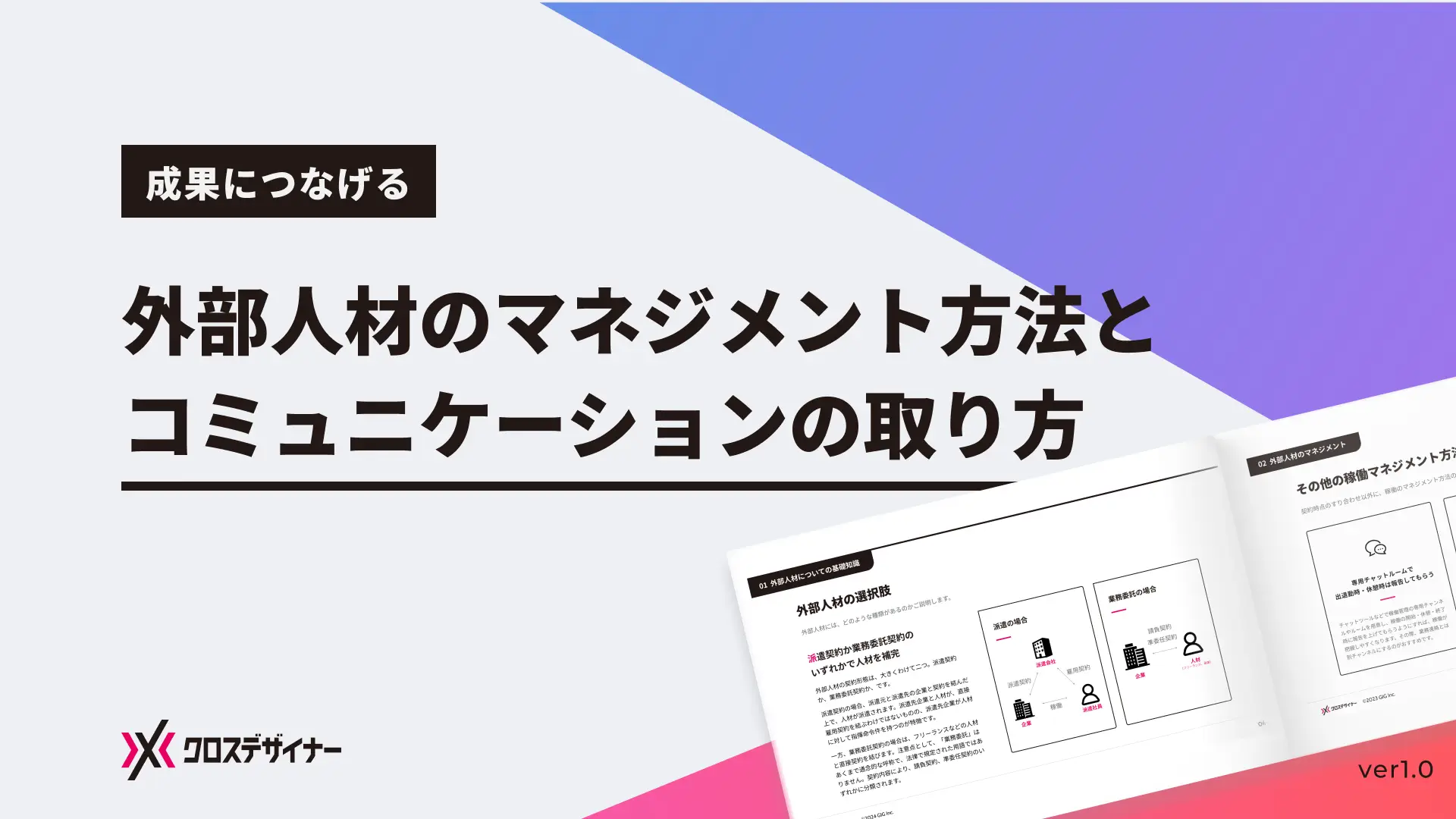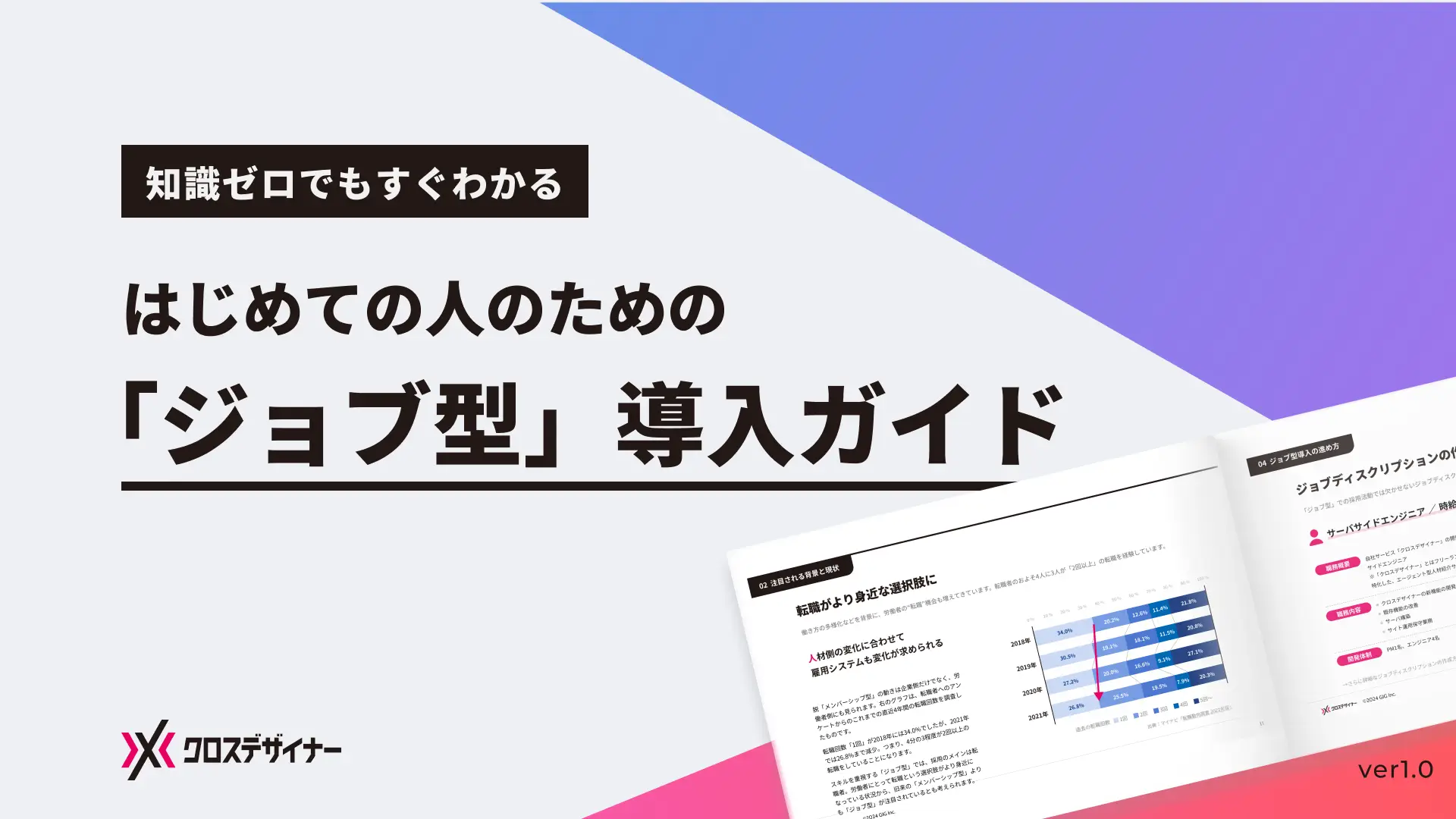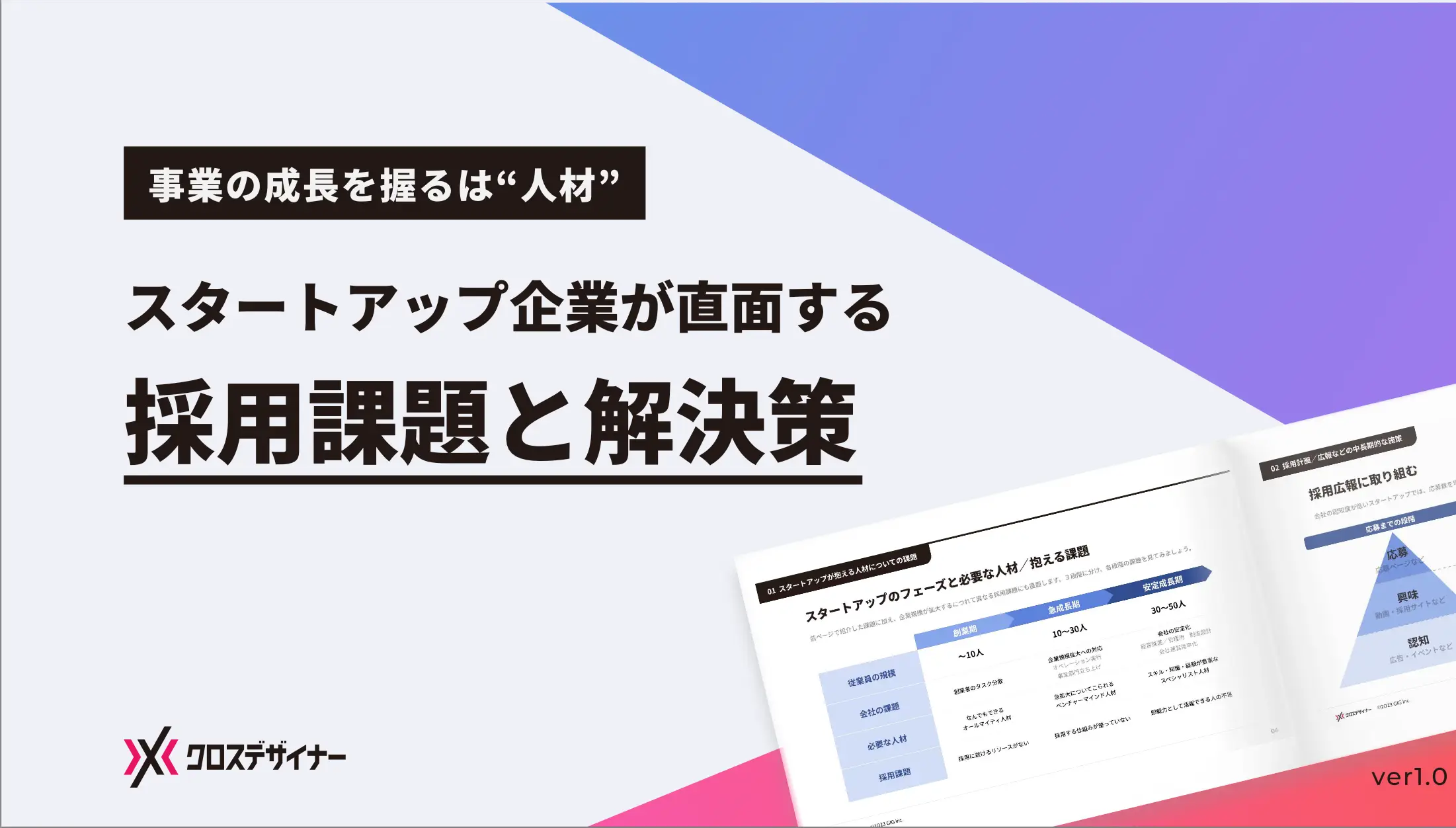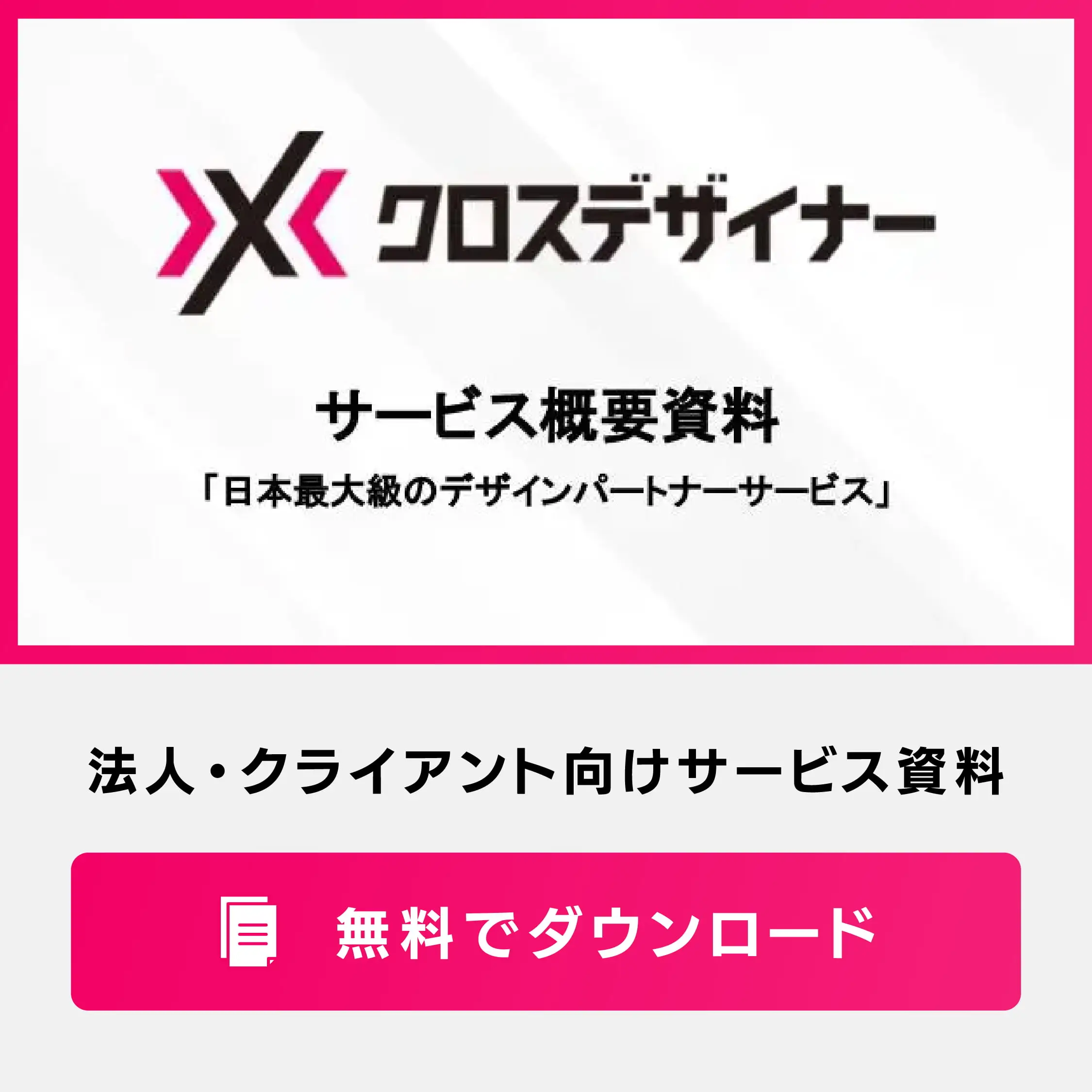企業のブランドイメージの構築や顧客とのコミュニケーションにおいて、デザインは重要な役割を果たします。しかし、すべての企業が社内に専門のデザイナーを抱えているわけではありません。そこで注目されるのが「デザイン外注」です。
この記事では、デザイン外注のメリット・デメリットや費用相場、外注を成功させるためのポイントなどを徹底解説します。デザイン外注を検討している企業の方はぜひ参考にしてください。
デザイン外注の定義
デザイン外注とは、企業が自社内にデザイナーを常駐させるのではなく、フリーランスや制作会社などの外部にデザイン業務を委託することを指します。
具体的には、ロゴやWebサイトのデザイン、広告クリエイティブ、パッケージデザイン、販促物のビジュアル制作など、視覚的な表現に関わる幅広い業務が対象です。
外注の形態には、プロジェクト単位で依頼するスポット型と、継続的な契約に基づいて業務を委託するレギュラー型があります。
前者はキャンペーンや新商品開発といった一時的なニーズに対応するのに適しており、後者はブランドの一貫性を保ちながら長期的なクリエイティブ戦略を構築する際に有効です。
社内制作との違い
社内制作とは、企業内に在籍するデザイナーが自社のクリエイティブ業務を担う体制を指します。
最大のメリットは、ブランドへの理解が深く、社内コミュニケーションが円滑に行える点です。
社内のデザイナーは、企業の理念や商品・サービスの特徴を日常的に理解しており、関係部署との連携もスムーズなため、一貫性のあるデザインが期待できます。
一方、デメリットとしてリソースの制約や表現の幅が限られる点が挙げられます。
そのため、デザイン外注と社内制作のどちらの体制を選択するかは、双方のメリット・デメリットを把握したうえで、プロジェクトの目的、予算、スケジュール、社内におけるクリエイティブリソースの状況などから総合的に判断することが必要です。
以下の資料では、デザインのリソースを確保する二つの手法として、外注と採用について比較しながらご紹介します。無料でダウンロードできるので、ぜひご活用ください。
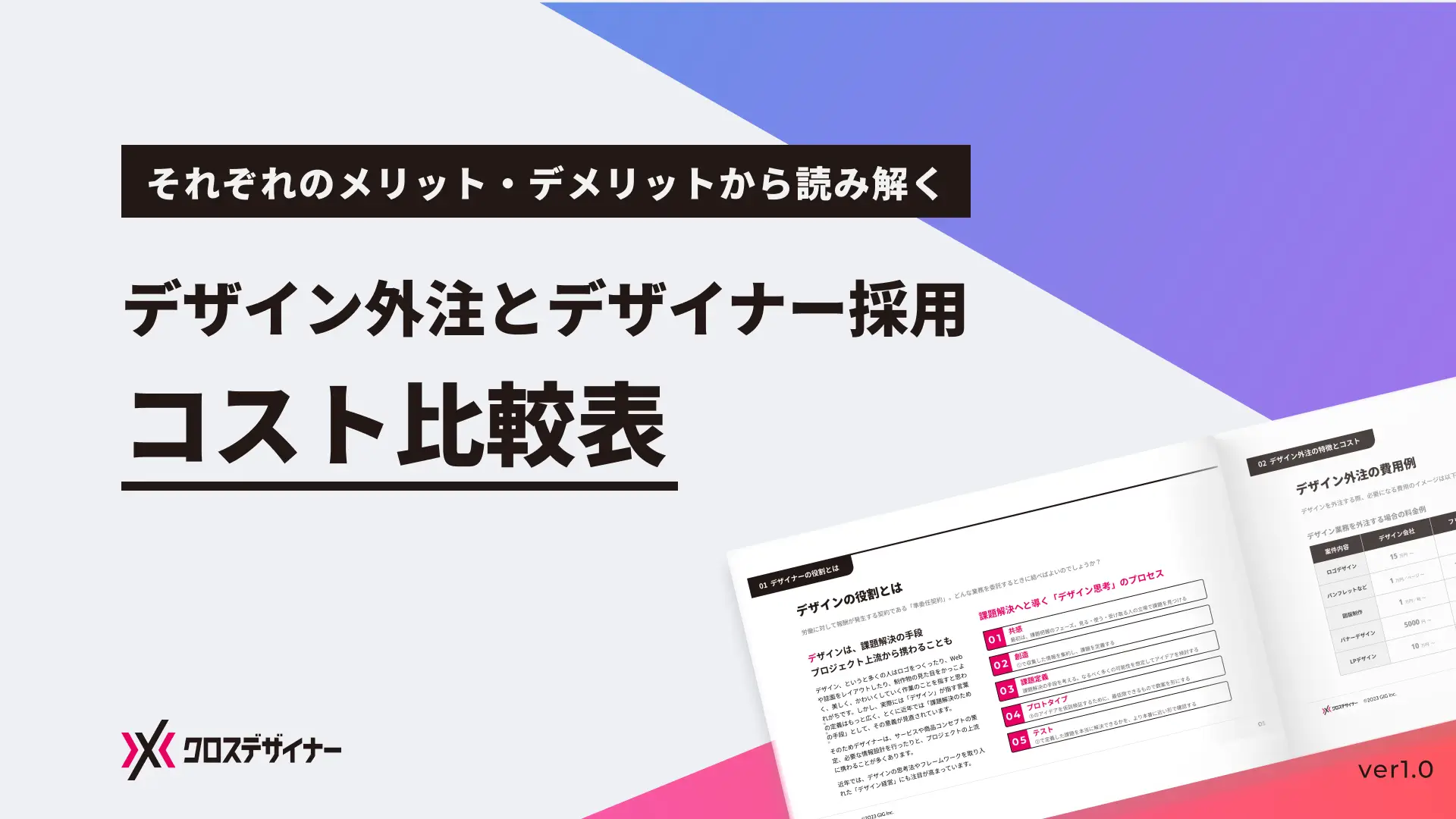
次章から、デザイン外注のメリット・デメリットについて解説していきます。
関連記事:デザインのコスト比較 採用と外注はどちらがおすすめ?
関連記事:インハウスデザイナーとは?直接雇用と外注のメリットや選び方を企業向けに解説
デザイン外注のメリット
企業がデザイン業務を外部に委託することで、以下のように多岐に渡るメリットが得られます。
- 専門家のスキルを活用できる
- 最新の技術やトレンドを導入できる
- スピード感のある制作が可能になる
- コスト削減につながる
- 柔軟な対応が期待できる
- 業務効率化につながる
それぞれ詳しく説明します。
1.専門家のスキルを活用できる
外部のデザイナーや制作会社は、日々さまざまな案件に取り組んでおり、豊富な経験と専門的なスキルがあります。
特に、社内では対応が難しい複雑な表現、戦略的なデザイン設計を必要とするプロジェクト、ブランディングやUI/UXなど、高度なスキルが求められる分野においては、専門家に外注することで質の高いアウトプットが期待できます。
2.最新の技術やトレンドを導入できる
デザイン業界は常に進化しており、トレンドや技術も日々更新されています。
外部のデザイナーは、業界の動向を把握し変化に対応していくため、最新のツールや表現手法を積極的に取り入れています。
このような知見や技術を取り入れることによって、社内では生まれにくい新しい視点やデザイン表現で、自社の魅力をより効果的に広く伝えることが可能となり、競合との差別化にもつながります。
3.スピード感のある制作が可能になる
スキルと実績のあるフリーランスは、スピード感のある制作が可能です。優秀なデザイナーが所属する制作会社や広告代理店も、納期を意識した効率的な制作体制を整えています。
そのため、社内リソースが限られている場合でも、外部のリソースを活用することで、短期間での制作が可能となり、マーケティング施策のタイミングを逃すことなく展開できます。
特にキャンペーンやプロモーションなど、スピードが求められるプロジェクトにおいては大きなメリットです。
また、社内リソースが限られている場合でも、外注することで複数のプロジェクトを並行して進めることができます。
4.コスト削減につながる
社内に専任のデザイナーを雇用する場合、採用費や人件費、教育コストが発生します。
一方、外注ならデザイン業務が必要になったタイミングで依頼できるため、固定費を抑えつつ品質の高いクリエイティブが得られます。
特に短期的なプロジェクトやスポット業務においては、コストパフォーマンスが高くなる傾向があります。
5.柔軟な対応が期待できる
多くのデザイン事務所や制作会社は、急な仕様変更や追加依頼といった企業のニーズに対応可能な体制を整えています。優秀なフリーランスデザイナーも、柔軟に対応してくれることがあります。
そのため、ブランドリニューアルや新規事業の立ち上げなど、変化の激しいフェーズにおいても、外注ならスピーディーで的確な対応が期待できます。
6.業務効率化につながる
デザイン業務は専門性が高い上に工数を要するため、社内で対応する場合は他業務への影響が避けられません。
高度なデザイン業務を外注すれば、社内のリソースをコア業務に集中させることが可能です。
マーケティングや商品企画など、企業の成長に直結する業務に注力できる環境を整えることで、全体の業務効率が向上します。
特に短期的なキャンペーンや繁忙期においては、フリーランスへの外注が有効です。
以下の資料では、業務委託のメリットと注意点を網羅的に解説しています。現在フリーランスへの依頼を検討している企業の方はもちろん、契約中の企業の方もぜひご覧ください。
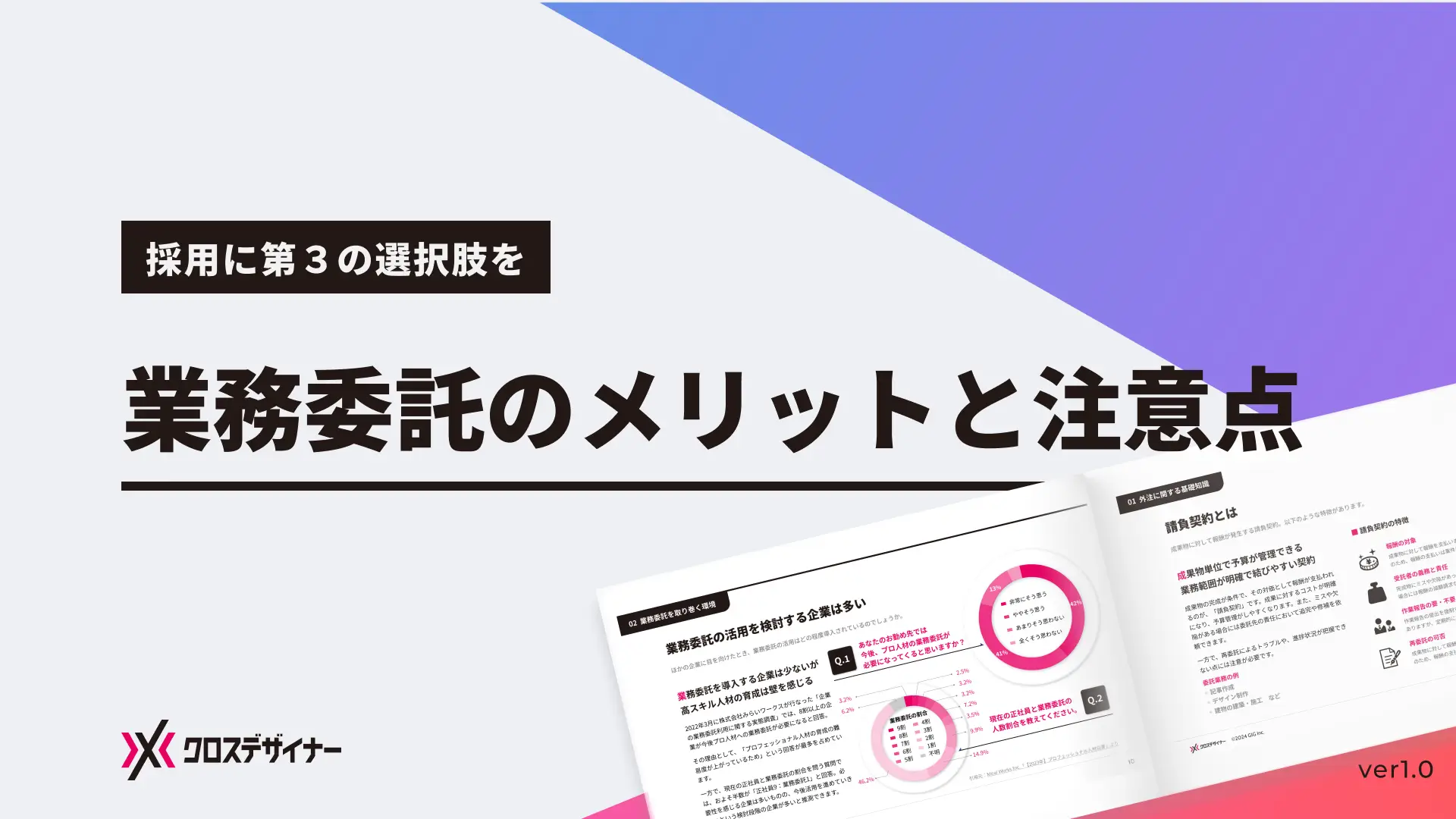
関連記事:はじめて外注する際のポイントとは?流れやメリットデメリットも解説
関連記事:デザイナー業務委託のメリットは? 採用や派遣との違いも解説
デザイン外注のデメリット
デザインを外部に委託することで多くのメリットが得られる一方で、いくつかのデメリットも存在します。
外注を検討する際には、以下のようなリスクや課題についても十分に理解しておく必要があります。
- コミュニケーションコストが発生する
- 理解不足や認識のズレにより品質が低下する
- 情報漏洩のリスクがある
- 費用が高額になる場合がある
- スケジュール調整が必要になる場合がある
それぞれ詳しく説明します。
1.コミュニケーションコストが発生する
外部のデザイナーや制作会社と業務を進める際には、要件の共有や進捗確認、修正依頼など、継続的なコミュニケーションが必要になります。
その際、社内制作に比べて情報伝達の手間が増える点がデメリットです。
特に初期段階では、企業のブランドや業務内容を正確に伝えるために、より多くの時間と労力がかかる場合があります。
2.理解不足や認識のズレにより品質が低下する
外注先が企業のブランドや商品・サービスについて十分に理解していない場合、意図と異なるデザインが仕上がる可能性があります。
特に、抽象的なコンセプトや感性的な要素を含む案件では、認識のズレが品質に直結するため、事前の情報共有とフィードバックの仕組みが不可欠です。
フィードバックの精度が低いと、修正の手間が増えるため注意しましょう。
3.情報漏洩のリスクがある
外注先に対して機密情報を開示したり未公開のプロジェクトの情報を共有したりする必要があるため、情報漏洩のリスクが伴います。
契約書やNDA(秘密保持契約)を締結することで一定のリスクは軽減できますが、情報管理体制が整っていない外注先を選定すると、漏洩リスクが高まる可能性があります。
そのため、信頼できる外注先を選ぶことが重要です。
4.費用が高額になる場合がある
外注費用は、依頼内容、デザイナーのスキルと実績、納期などによって変動します。
特に、短納期や複雑な要件を伴う案件では、追加費用が発生するリスクが高くなります。
また、修正回数の増加や追加対応が発生すると、当初の見積もりを超えることもあるため、予算管理には注意が必要です。
そのようなケースでは、短期的には外注によって効率化が図れますが、継続的に外注すると社内にデザイナーを雇用するよりもコストが高くなる可能性があります。
5.スケジュール調整が必要になる場合がある
外部のデザイナーは他のクライアントの案件も抱えていることが多く、希望するスケジュールで対応できない場合があります。
また、複数回の修正が必要な場合や、急な変更が発生した場合には、スケジュール調整が求められることもあります。
特に繁忙期や人気の高いデザイナーに依頼する場合は、事前のスケジュール調整が不可欠です。納期に余裕を持った計画を立てることで、スムーズな進行が可能になります。
関連記事:デザイン外注と内製のメリット/デメリットは? 判断すべきポイントも解説
関連記事:業務委託のメリットとデメリット、企業がやるべきことや注意点を解説
デザイン外注の費用相場
ここからは、企業がデザイン業務を外部に委託する際に必要となる費用について、制作物ごとの相場を中心に解説していきます。
外注費は制作物の種類や規模、求められるクオリティによって大きく異なるため、予算策定の参考にしてください。
制作物別の費用目安
制作物のデザインを依頼した際の案件単価の目安は以下のとおりです。
制作物 | 案件単価 (円) |
Webデザイン(小規模サイト) | 約40万〜300万円 |
Webデザイン(大規模サイト) | 約150万〜1,000万円 |
UI/UXデザイン | 約50万〜800万円 |
アプリデザイン | 約15万〜100万円 |
プロダクトデザイン | 約30万~80万円 |
ロゴデザイン | 約5万〜30万円 |
バナーデザイン | 約1.5万〜3万円 |
パッケージデザイン | 約15万~ 50万円 |
LPデザイン | 約5万~30万円 |
ポスター、チラシデザイン | 1万5,000円~8万円 |
グッズデザイン | 約3万〜10万円 |
イラスト制作 | 約3万〜10万円 |
動画制作(短編) | 約5万〜80万円 |
動画制作(長編) | 約80万〜200万円 |
アニメーション制作 | 約10万〜300万円 |
ブックデザイン(表紙) | 約10万円 |
ブックデザイン(全体) | 約20万〜60万円 |
営業資料デザイン | 1スライドあたり約3,000円~1万5,000円 |
カタログデザイン | 約30万〜70万円 |
キャラクターデザイン | 約3万〜30万円 |
名刺デザイン | 約3,000円〜5万円 |
パンフレットデザイン | 約5万〜30万円 |
上記の価格はあくまで目安であり、実際の費用は依頼内容やデザイナーのスキル、納期、修正回数などによって変動します。
関連記事:デザイナーの時給単価や制作物別の費用相場を徹底解説
関連記事:【種類別】デザイン依頼にかかる費用/料金相場は? 費用を抑えるコツも解説!
関連記事:デザイン制作を依頼するには?相場や依頼先の種類、おすすめまで紹介
外注の料金体系別の特徴・メリット・デメリット
外注先によって料金体系は異なり、自社の目的や社内体制によって最適な選択肢は異なります。
以下に、代表的な料金体系の特徴やメリット・デメリットをまとめました。
料金体系 | 特徴 | メリット | デメリット |
固定料金制 | ・月額の定額制または成果物ごとに料金が決まっている。 | ・予算管理がしやすい。 ・想定以上の成果が出た場合でも、追加料金が発生しない。 | ・成果が少ない場合でも、一定の費用が発生する。 |
従量課金制 | ・作業時間に応じて料金が発生する。 | ・実際に利用した分だけ費用が発生するため、無駄が少ない。 ・成果に応じて費用が増減するため、成果を出すインセンティブになる。 | ・料金が変動するため、費用が予測しにくい。 ・業務量が多い場合は、高額になる可能性がある。 |
パッケージプラン | ・複数の制作物をセットにした料金プラン。 | ・複数の制作物の依頼が容易かつスピーディーに行える。 ・コストパフォーマンスが高い場合がある。 | ・イレギュラーな要望や急な変更に対応するのが難しい場合がある。 ・内製できる業務の外注費が発生する可能性がある。 |
たとえば、予算が明確なプロジェクトには固定料金制が適しており、柔軟な対応が求められる場合は従量課金制が有効です。一方で、複数の制作物を一括で依頼したい場合には、パッケージプランが効率的です。
外注を成功させるためには、料金体系のメリット・デメリットも把握したうえで、契約内容やクリエイティブの品質、コミュニケーション体制などを総合的に判断することが重要です。
見積もり時に確認すべきポイント
デザイン業務を外注する際に、見積もりの段階で以下のポイントを確認・合意しておくことで、見積もりの精度が高まります。
- 制作範囲(企画・構成・デザイン・納品形式など)
- 修正回数と対応範囲
- 納期とスケジュール
- 著作権の取り扱い(使用権・譲渡の有無)
- デザインデータの納品形式(AI、PSD、PDFなど)
上記の項目について事前に社内で整理しておき、依頼先と協議のうえ明確にしておきましょう。後々の認識違いや追加費用の発生といったトラブルを未然に防ぐことができ、納得感のある契約につながります。
関連記事:【企業向け】Webデザイナーの単価相場は?作業工程ごとの費用を解説
関連記事:Webデザインにかかる費用は?外注料金相場や制作会社とフリーランスの選び方も解説
関連記事:グラフィックデザインを外注する際の料金相場を項目、制作物別で徹底解説
デザイン外注費に影響する要素
デザインを外注する際にかかる費用は一律ではなく、以下のようなさまざまな要素によって変動します。
- デザイナーの経験・実績
- 納期の緊急度
- 修正の回数や内容
- 使用する媒体
- ブランド戦略やマーケティング要素の有無
特に短納期の場合、割増になるケースが多いため注意が必要です。
また、Webや動画、印刷物など使用する媒体によって費用が異なる場合があります。
納期や媒体の違いによる費用差は見落とされがちのため、事前の確認と調整が重要です。
上記の要素を踏まえて見積もりを検討することで、予算と成果のバランスを取ることができます。
関連記事:プロダクトデザインにかかる費用の相場は? コストを抑える方法も合わせて解説
関連記事:ホームページデザインの相場は?コストを抑える方法も解説
デザイン外注を成功させるためのポイント
デザイン外注を効果的に活用するためには、単に依頼するだけでなく、プロジェクト全体を見据えた準備と対応が不可欠です。
以下の4つのポイントを押さえることで、外注先との連携がスムーズになり、品質の高いクリエイティブにつながります。
- 依頼内容を明確にする
- ニーズに合ったデザイナーを選ぶ
- コミュニケーションを密にする
- 契約書を取り交わしておく
それぞれ詳しく説明します。
1.依頼内容を明確にする
外注先には、どのようなデザインを求めているのか、具体的なイメージや要望を具体的に伝えることが重要です。
事前に目的・ターゲット・使用媒体・希望するトーンやスタイルなどを明確にしておきましょう。
曖昧なまま依頼すると、認識のズレが生じ、修正が増える原因になります。
参考資料や過去の制作物を共有することも有効です。
2.ニーズに合ったデザイナーを選ぶ
デザイナーは一人ひとりスキルや実績、得意分野が異なります。
Webデザインに強い人、UI/UXに精通している人、ブランディングに長けた人など、スキルや経験は多様です。
そのため、必ずポートフォリオを確認し、自社の業界に詳しく依頼内容に合った実績を持つデザイナーを選ぶことが重要です。
ポートフォリオを確認する際は、以下のポイントをチェックしてニーズに合ったデザイナーかどうかを判断します。
- 過去の制作物のテイストや表現力
- 自社の属する業界や依頼する媒体の経験
- ブランド理解力やコンセプトの表現力
- 実績のある企業との取引履歴
自社のニーズに合った専門性を持つデザイナーを選定することで、クリエイティブの質が大きく向上します。
関連記事:外注デザイナーを探す方法は?おすすめサービス10選と注意点を解説!
3.コミュニケーションを最適化する
外注先とのコミュニケーションは、プロジェクトの成否を左右する重要な要素です。
以下のような体制を整えることで、スムーズな進行が可能になります。
- 担当者を明確にし、窓口を一本化する
- 初期段階でブランド情報や参考資料を共有する
- 定期的な進捗報告やレビューの場を設ける
- フィードバックは具体的かつ建設的に伝える
特にプロジェクト開始時に、定期的な進捗確認やフィードバックのタイミングを予め設定しておくことで、方向性のズレを早期に修正できます。
進行中は、レスポンスのスピードや対応の柔軟性も、信頼関係の構築において重要なポイントです。
4.契約書を取り交わしておく
口頭やメールでのやり取りだけでは、万が一のトラブル時に対応が難しくなります。
そのため重要事項を明記した契約書を交わしておくことで、双方の責任範囲が明確になり、安心して業務を進めることができます。
契約書には以下の項目と内容を明確にしておくことが重要です。
項目 | 内容 |
納期 | 具体的なスケジュールとマイルストーンの設定 |
成果物の範囲 | デザインだけでなく、企画・構成・データ納品の有無 |
修正対応 | 回数制限、対応期間、追加費用の有無 |
著作権・使用権 | 成果物の権利の帰属と使用範囲 |
支払い条件 | 支払いタイミング、キャンセルポリシー |
以下の資料では、4つの契約書のテンプレートを紹介し、わかりにくい箇所には補足解説を添えています。無料でダウンロードできますので、契約にかかる工数削減と自社に適したテンプレートの作成にお役立てください。

また、以下の資料では「初めて外注を活用する」という方に向けて、外注の流れをステップとして解説しています。こちらも無料でダウンロードできるので、お気軽にご覧ください。

関連記事:Webデザインの外注できる内容や依頼する際のステップ6つ、費用相場や注意点を徹底解説
デザイン外注先の選び方
デザイン業務を外注する際は、依頼先の特性を理解したうえで、自社の目的や予算、求めるクオリティに合ったパートナーを選定することが重要です。
主な外注先には以下の4つがあり、それぞれにメリット・デメリットがあります。
- フリーランス
- デザイン事務所
- 制作会社
- 広告代理店
1.フリーランス
フリーランスは個人で活動しており、柔軟な対応が可能で、企業に依頼する場合と比較すると費用が安く抑えられます。
直接コミュニケーションを取れるため、意思疎通がスムーズな点もメリットです。
ただし、対応できる業務範囲やスケジュールに限りがある場合もあるため、事前の確認が必要です。また、個人のスキルに依存し、品質のばらつきがあることもデメリットといえるでしょう。
フリーランスへの依頼方法はクラウドソーシングサイトやマッチングサイトなど複数ありますが、エージェントサービスを利用して要件に合ったデザイナーを紹介してもらう方法がおすすめです。マッチング精度が高く、条件交渉や契約締結までサポートが受けられます。
以下では、デザイナー専門のエージェントサービス『クロスデザイナー』に登録している一部の注目デザイナーのリストをダウンロードしていただけます。
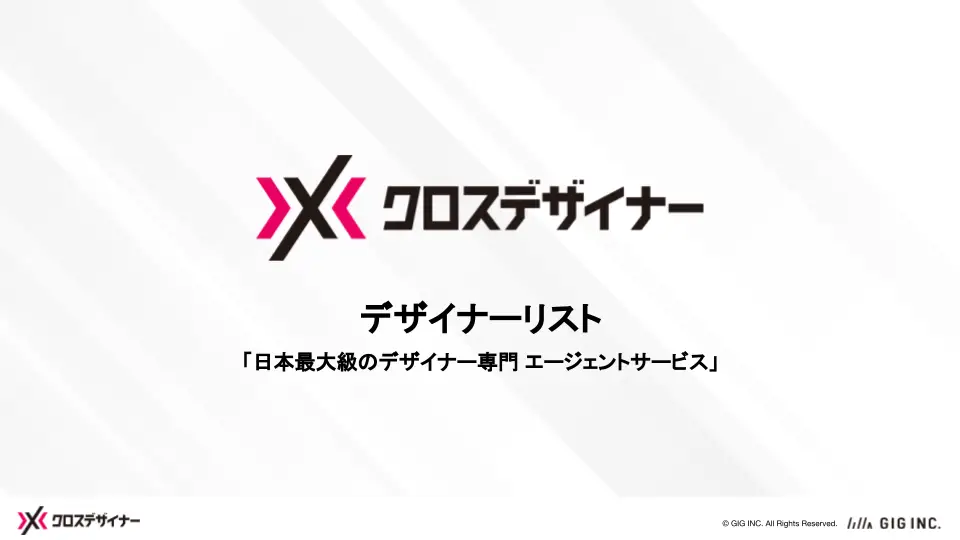
また、以下の資料では、デザイナーを取り巻く採用環境について解説したうえで、『クロスデザイナー』を通してデザイナーを採用した事例をご紹介しています。こちらも無料でダウウンロードできるので、ぜひぜひご活用ください。

関連記事:グラフィックデザインの外注依頼にフリーランスがおすすめな理由と人材サービス8選を解説
2.デザイン事務所
デザイン事務所は少人数のデザイナーで運営されている専門性の高いチームです。
ブランディングやアートディレクションなど、企画段階からの提案力に優れている事務所も多く、クオリティ重視の案件に適しています。
品質・納期の安定性が高い点がメリットですが、費用はフリーランスより高くなる傾向があります。
3.制作会社
制作会社はWebサイトや動画、印刷物など、幅広い媒体に対応できる体制を持っています。
複数のデザイナーやディレクターが在籍しており、プロジェクトの規模に応じて組織的な対応が可能です。
進行管理や品質管理がしっかりしているため、安定した成果が期待できますが、費用はフリーランスやデザイン事務所より高めです。
関連記事:Webデザインの外注先の選び方を制作会社とフリーランスで徹底比較
4.広告代理店
広告代理店は、デザイン・制作だけでなく、マーケティング戦略やプロモーションも含めてトータルで依頼することが可能です。
そのため、デザイン単体ではなく、広告効果やブランド価値を意識したクリエイティブが求められる場合に適しています。
費用は最も高額になる可能性がありますが、総合的な支援が受けられます。
デザインを外注するならクロスデザイナーがおすすめ!
本記事では、デザイン外注のメリット・デメリットや費用相場、外注を成功させるためのポイントなどを詳細に解説しました。デザイン外注を検討している企業の方はぜひ参考にしてください。
デザイン業務を外注する際は、依頼先の特性を理解したうえで、自社の目的や予算、求めるクオリティに合ったパートナーを選定することが重要です。
主な外注先には「フリーランス」「デザイン事務所」「制作会社」「広告代理店」の4つがあり、それぞれにメリット・デメリットがありますが、フリーランスなら柔軟な対応が期待できるうえ、比較的コストを抑えることができます。
フリーランスへの依頼方法はクラウドソーシングサイトやマッチングサイトなど複数ありますが、フリーランスへの依頼に慣れていない企業は、デザインの知識やスキル、費用相場について熟知した、実績と信頼のあるデザイナー専門のエージェントサービスを活用すれば、業界に詳しく安心して任せられるでしょう。
デザイナー専門の国内最大級エージェントサービス『クロスデザイナー』なら、厳正な審査を通過した即戦力デザイナーが7,000人以上在籍。採用コンサルタントが、自社に必要なデザイナーのスキルや要件をヒアリングして最適な人材を紹介します。
以下では、『クロスデザイナー』のサービス資料を無料でダウンロードできます。ぜひ貴社の採用活動にお役立てください。
- クロスデザイナーの特徴
- クロスデザイナーに登録しているデザイナー参考例
- 各サービスプラン概要
- 支援実績・お客様の声
Documents