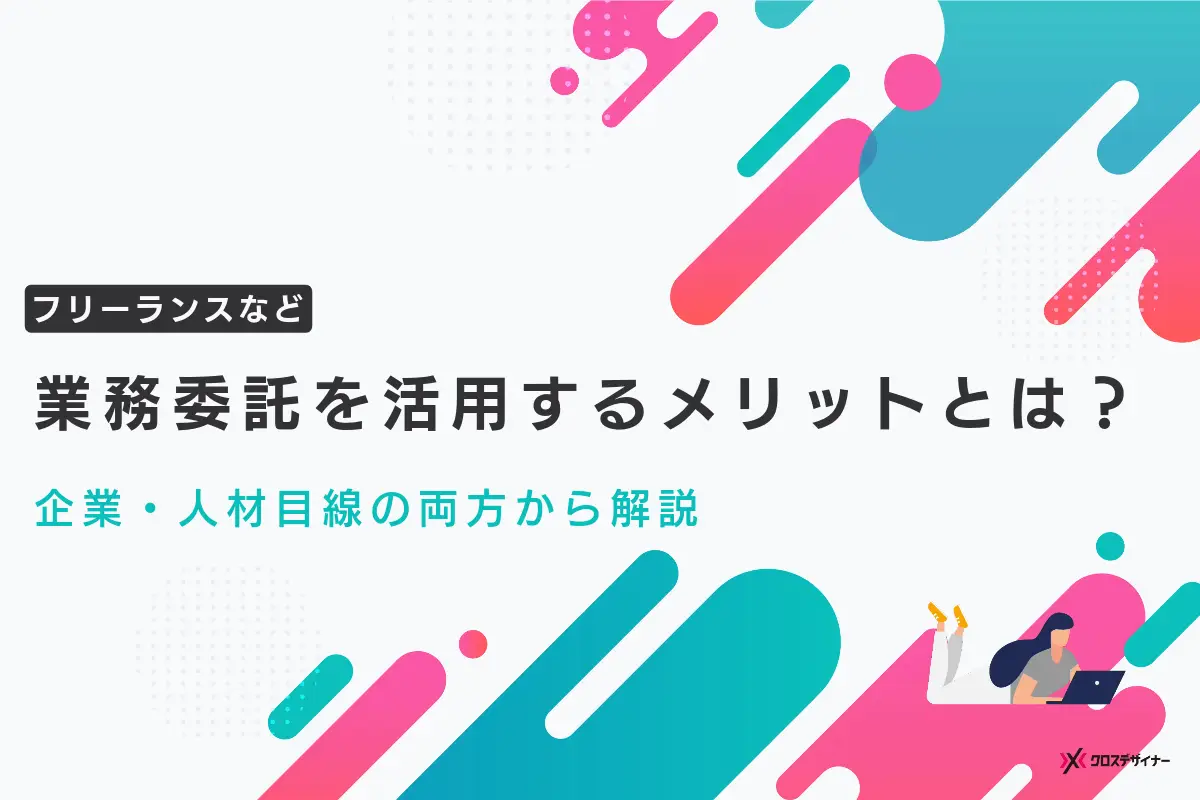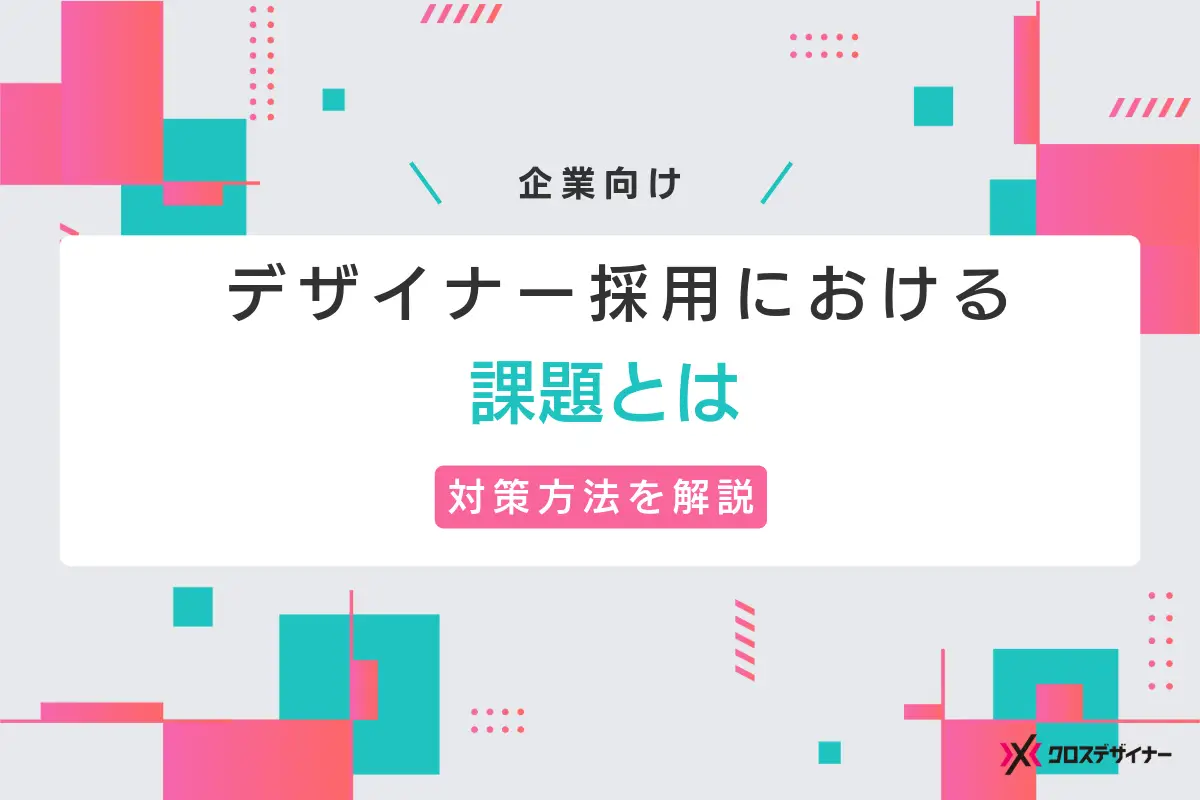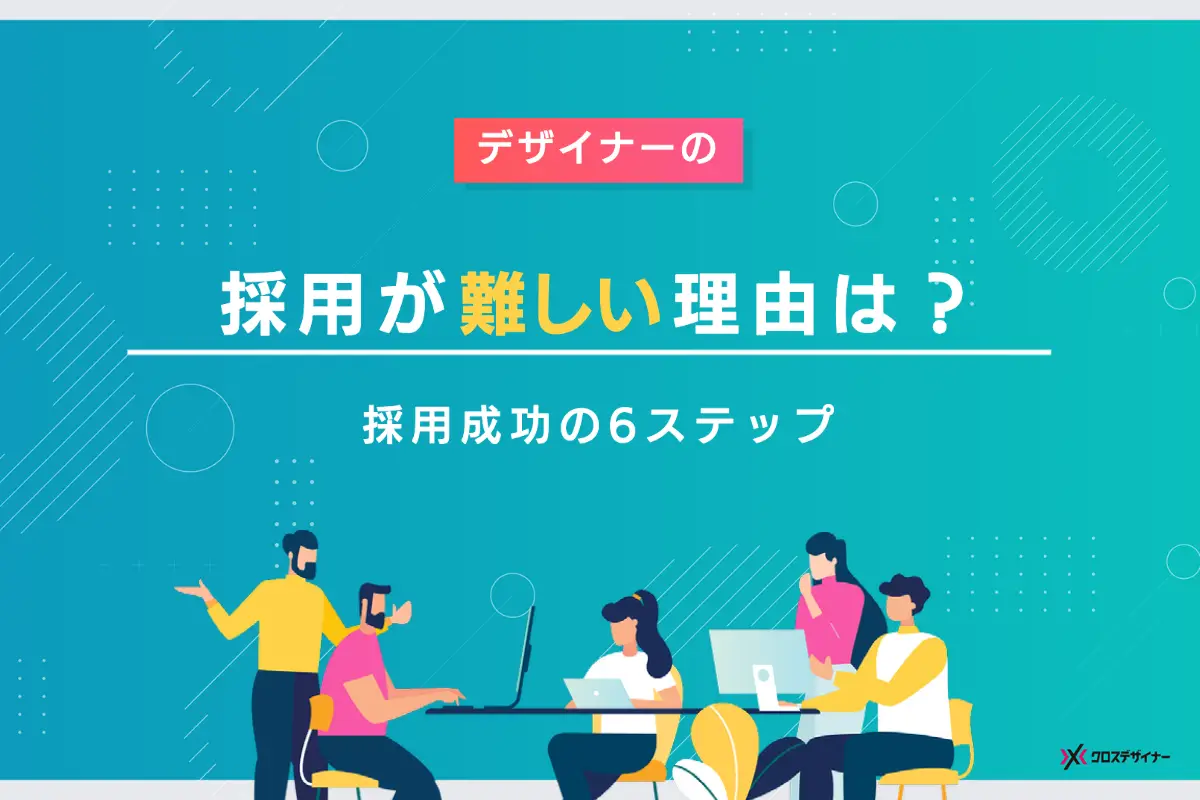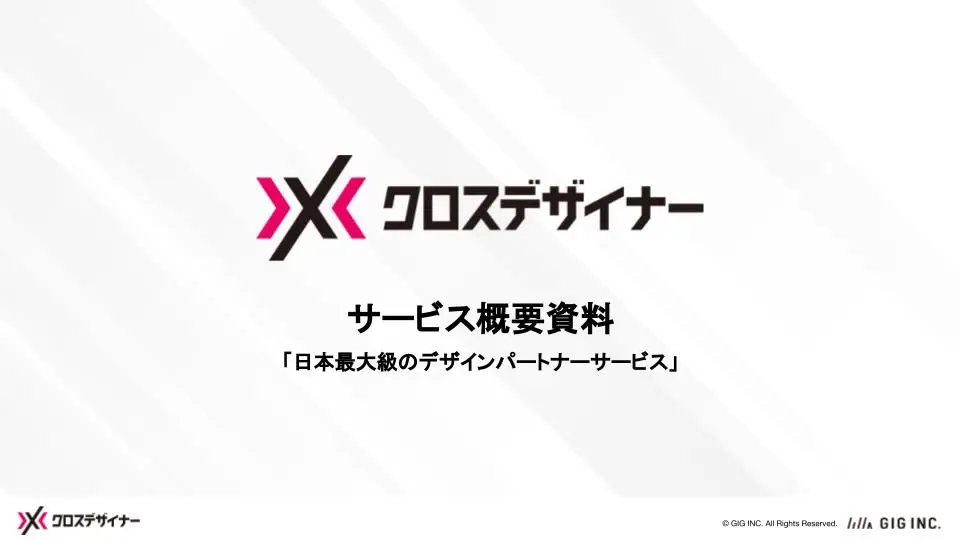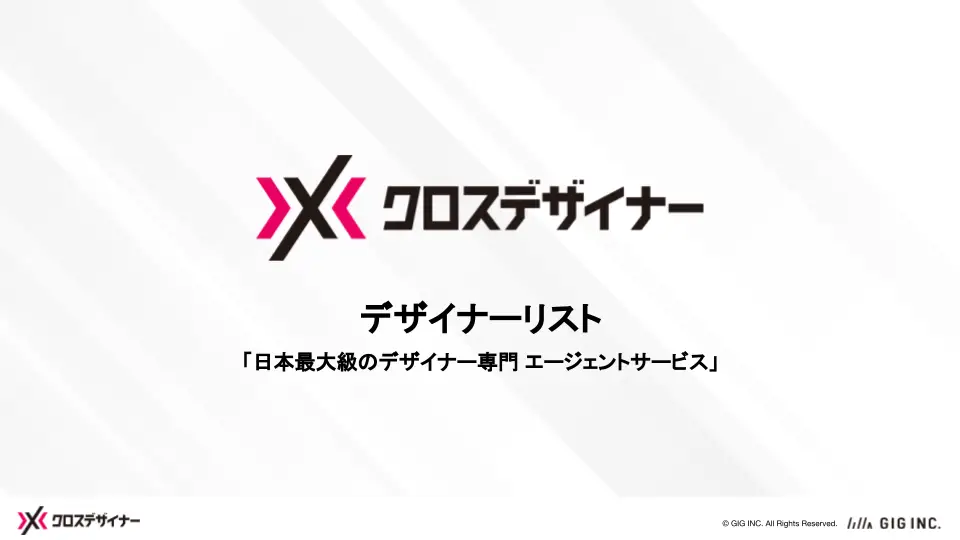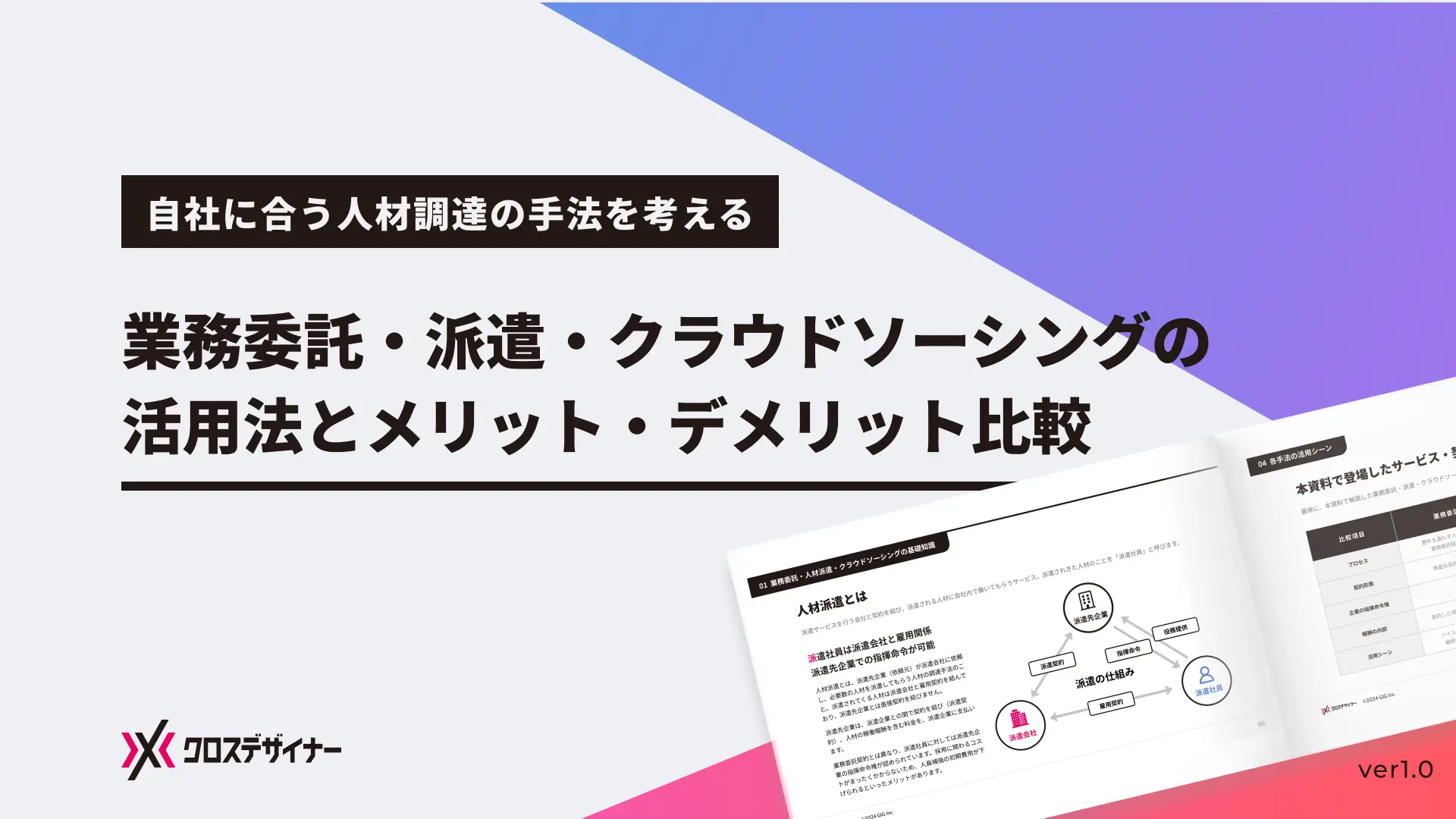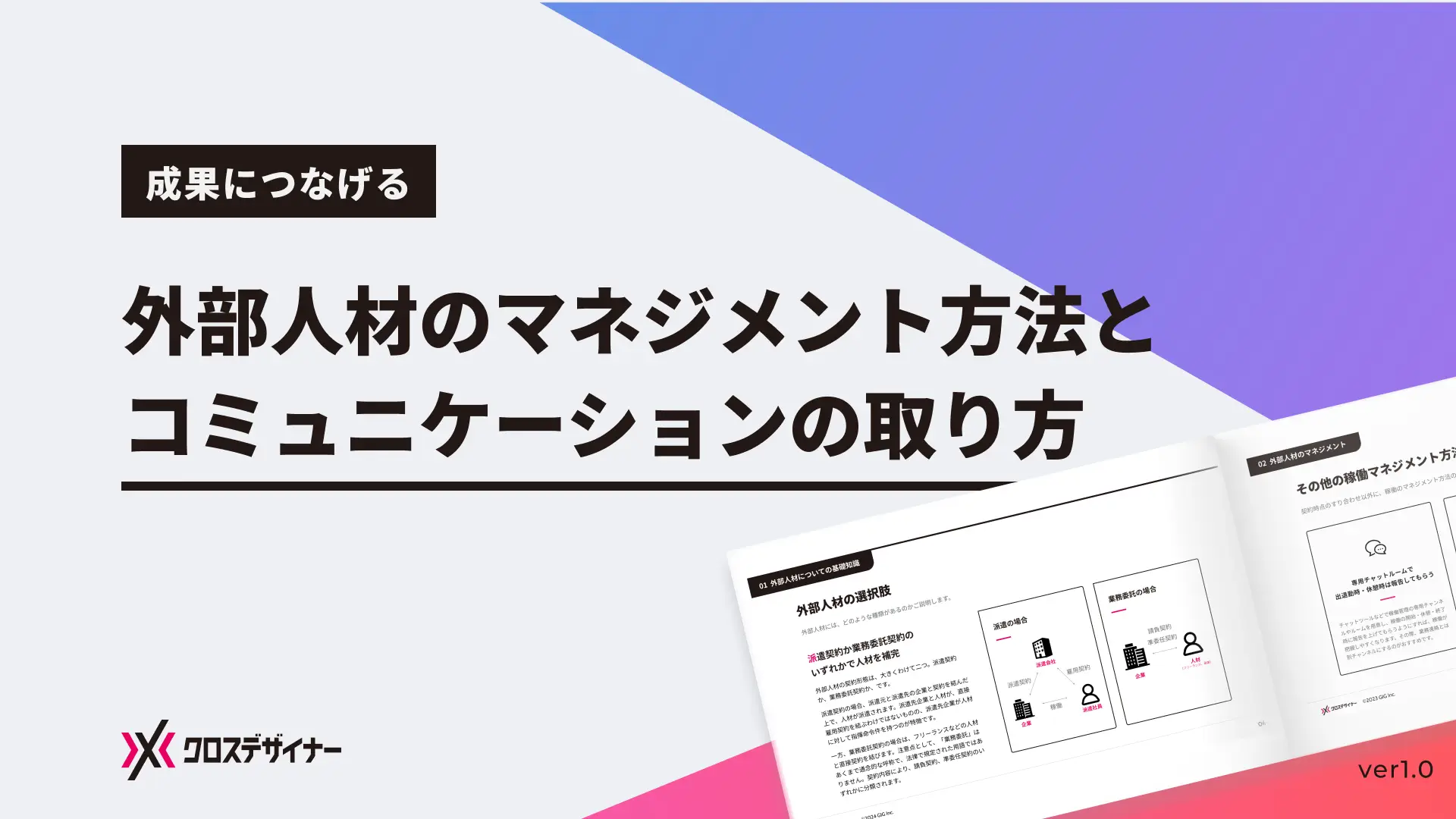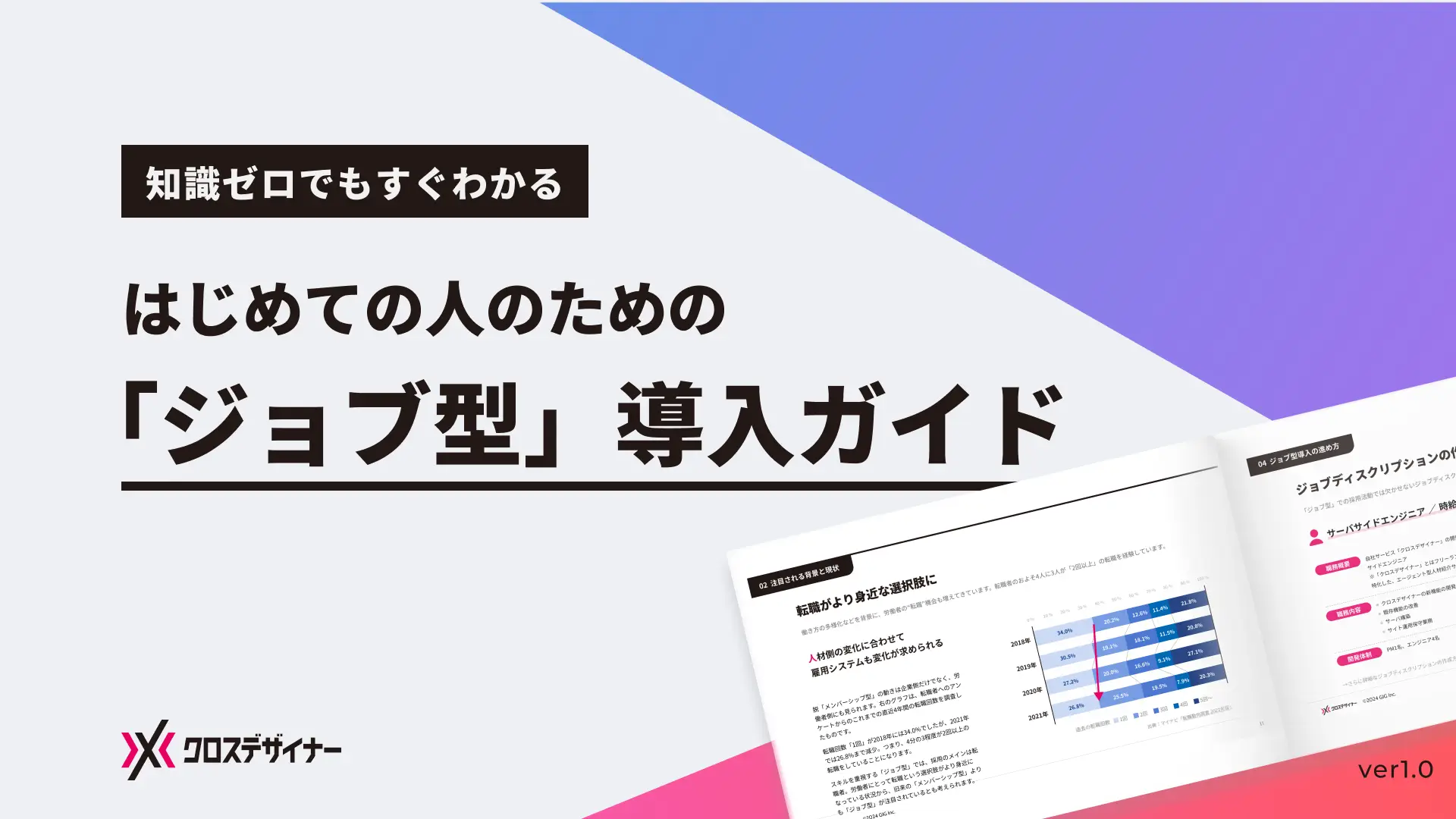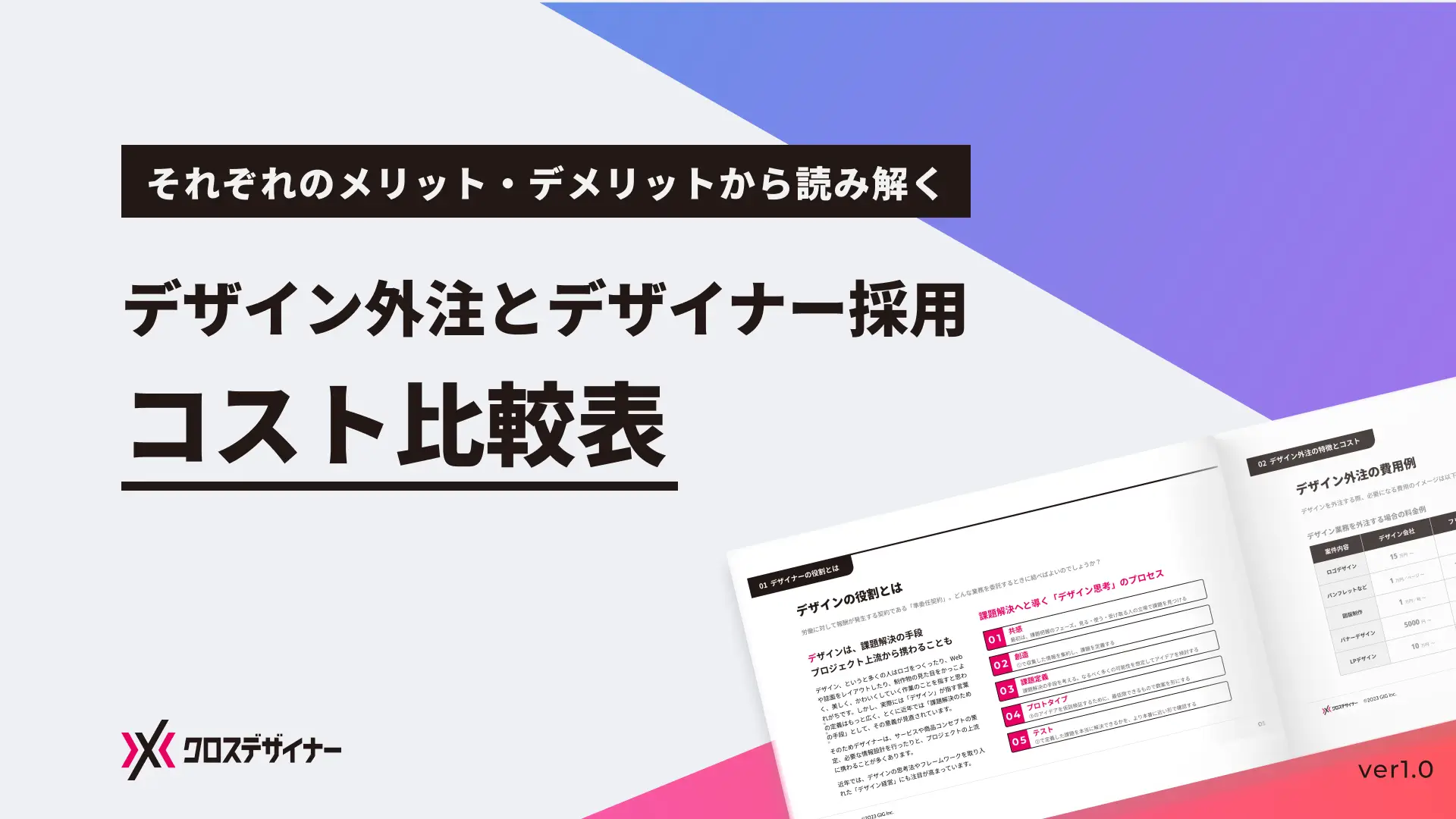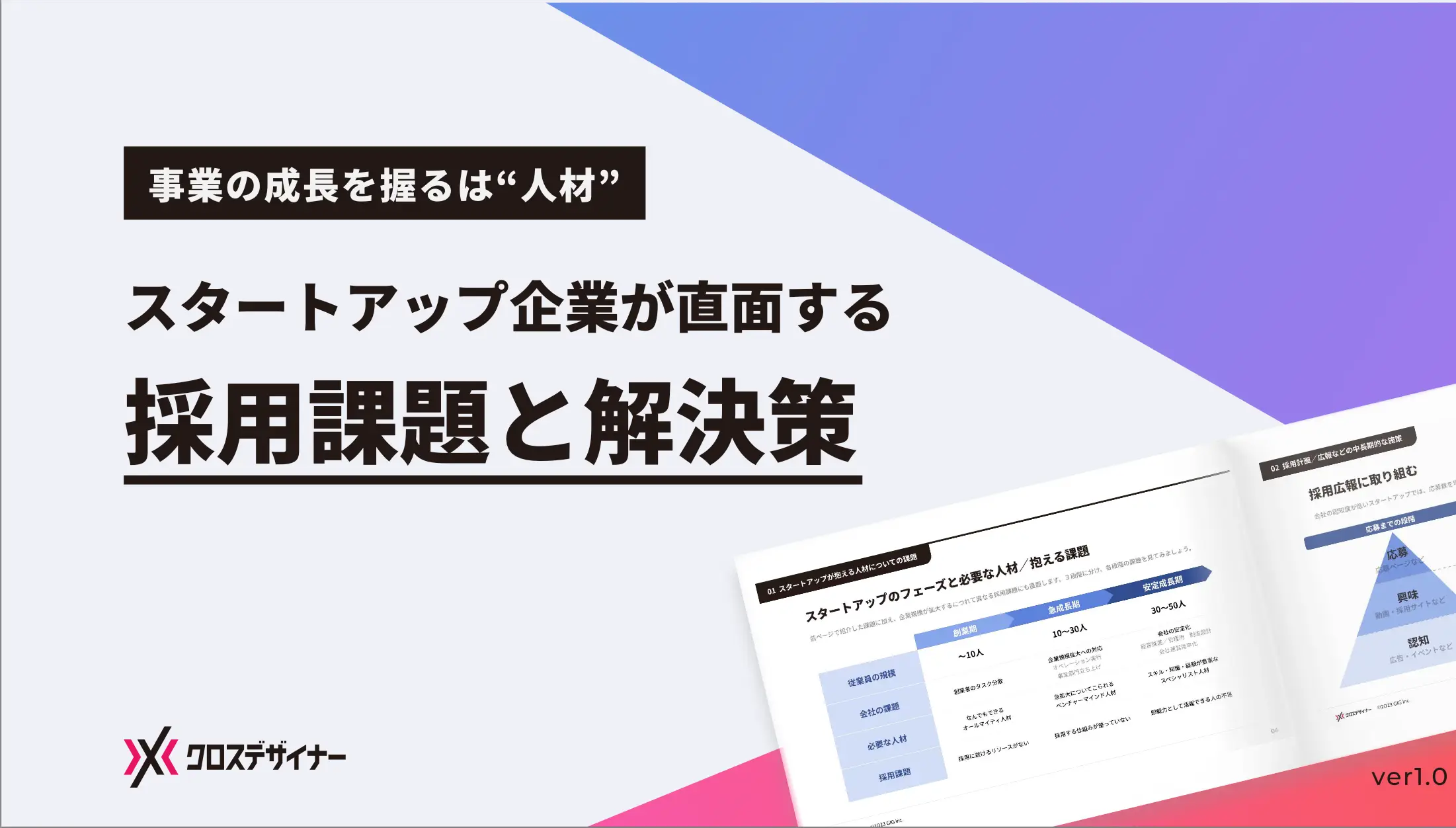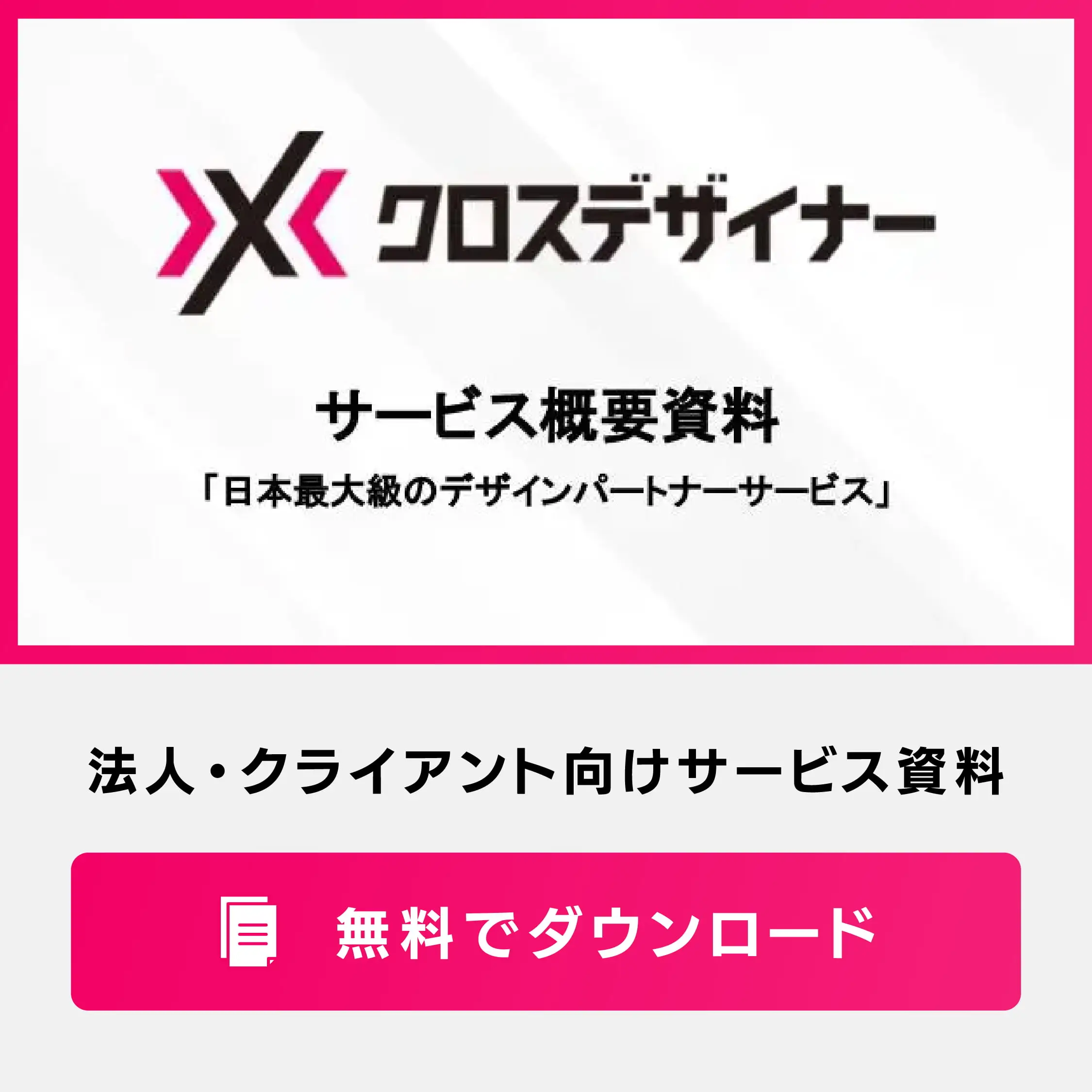多種多様な働き方が認められるようになった今、「業務委託」という働き方が注目を浴びています。
自社のリソースで対処できない、専門的な業務を外部の人材に任せたいと考えている企業の担当者の方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、業務委託とは何か、派遣との違いに加え、企業と人材の双方の視点からのメリット・デメリット、契約の流れや企業側から見た注意点などを解説します。
業務委託を活用する前に、チェックすべきポイントを把握するためにお役立てください。
業務委託とは?注目される理由5つを解説
業務委託とは、企業が自社の業務を他社の企業や個人など、外部の人に依頼しておこなう業務形態のことです。
業務委託では、成果物や業務に対して報酬が発生します。企業と雇用契約を結んでいる会社員やアルバイトとは違い、業務委託では「企業=雇用主」という形ではなく、対等な関係としてやり取りをおこなうのが特徴です。
業務委託が注目される理由5つ
業務委託が注目される理由としては、主に次の5つの要因が挙げられます。
1.企業環境や市場が変化したこと
現代のビジネス環境は、急速な技術革新とグローバル化により、常に変化し続けています。
企業はこの変化に柔軟に対応する必要があり、そのためには外部の専門知識やリソースを活用することが効果的です。
業務委託は、企業が市場の変動に迅速に適応し、新しいビジネスチャンスを捉えるための手段として重要視されています。
2.専門的な知識や技術の必要性が上がったこと
現代のビジネスでは、デジタル化やAIの進展など、専門的な技術が求められる業務が増加しています。
これらの分野では、高度な専門知識が必要とされるため、企業が社内にスキルセットを持つ人材を雇用するよりも、専門家や専門企業に業務を委託するケースが増えているのです。
3.人材コストを削減する必要性が上がったこと
企業が正規雇用する人材を増やすことは、固定的な人件費や福利厚生費を増やすことにつながります。
これは、企業を運営する上で大きな負担となる問題です。そこで業務委託を活用することにより、これらのコストを変動費に変え、必要な時に必要な人材を確保することができます。
これにより、コスト削減と経営の柔軟性を実現することが可能です。
4.柔軟な働き方が求められていること
近年は、労働者がワークライフバランスを重視する傾向が強くなり、個々人のライフスタイルに合わせた働き方へのニーズが高まっています。
業務委託は、個人と企業の両方にとって、より柔軟な働き方を可能にする選択肢として注目されています。
5.リスクマネジメントの必要性が上がったこと
業務委託を採用することで、プロジェクトや特定の業務に伴うリスクを企業が単独で負うのではなく、外注先と分散させることができます。
業務委託を活用すれば、リスクを委託先と共有できるため、万が一の事態における影響を軽減することが可能です。
これらの理由から、業務委託は多くの企業にとって魅力的な選択肢となり、ビジネスの効率化、コスト削減、リスク管理の観点からも注目されているのです。
また、労働者の目線からみても、自身の専門性や強みを活かしながら柔軟な働き方を実現する手段として、業務委託は価値が高い働き方と言えるでしょう。
▼下記の資料では、業務委託・正社員・派遣など複数の雇用形態を比較し、特徴を解説しています。無料でダウンロードできますので、ぜひ貴社の外注業務にお役立てください。

業務委託の種類3つ|請負・委任・準委任契約の違いを解説
業務委託契約という言葉は正式名称ではなく、法律上は「請負契約」「委任契約」「準委任契約」の3つの契約形態の総称として使われています。それぞれの契約形態の違いは、業務の目的にあります。
請負契約型
請負契約は、成果物の完成で報酬が発生する契約形態です。請負契約は、どのように業務を進めたか、何時間作業したかなどのプロセスは一切問わないのが特徴です。
業務を請負う側には「完成責任」があり、発注者側が依頼したものを完成させて納品することを目的とします。なお、発注者は受注者の仕事が完成してから報酬を支払うのが一般的です。(民法第633条、後払いの原則)
期日までに成果物が上がらない、もしくは依頼水準に満たなかった場合は、発注者側は業務上の不利益を被ったとして、契約を解除することができます。契約解除となった場合、発注者は受注者から対価を請求されても報酬を支払う義務はありません。
また、納品したものに不備や不具合があった場合に、受注者側に修正の義務が生じるのも請負い契約の特徴です。これを「契約不適合責任」と呼びます。
委任契約型と準委任契約
一方、委任契約や準委任契約は、契約期間中に「契約内容通りに業務を遂行すること」が報酬発生の条件となります。
請負契約とは違い、成果物の完成責任を負うことはありません。契約期間中、契約内容通りに業務を遂行することが報酬発生の条件となるのが特徴です。
委任契約や準委任契約では、成果物の質などは問われず、業務の遂行が対象となります。また、発注者はいつでも契約を解除できるのが特徴です。(民法第651条1項)
なお、依頼する業務の内容が法律行為に該当する場合は「委任契約」となります。これには、法律行為を弁護士に依頼したり、決算業務を税理士に依頼するといった行為が該当します。
一方、「準委任契約」は法律以外のあらゆる業務が対象です。そのため、成果物を対象としない業務委託のほとんどが準委任契約に当たると考えられます。
▼下記の資料では、準委任契約と請負契約の比較や、実際に契約を締結する際のポイントなどを詳しく解説しています。無料でダウンロードできますので、ぜひご一読ください。

請負・委任・準委任契約の違いを比較
次に、請負契約、委任契約、準委任契約の主な違いを比較します。
項目 | 請負契約 | 委任契約 | 準委任契約 |
目的 | 仕事の完成 | 法律行為の委託 | 事実行為の委託 |
成果物 | 必要 | 不要 | 不要 |
報酬支払い | 仕事完成後 | 事務処理後 | 事務処理後 |
指揮監督 | なし | あり | あり |
責任 | 成果物の完成義務と契約不適合責任 | 善管注意義務 | 善管注意義務 |
例 | 建設工事、システム開発など | 代理人による契約締結など | コンサルティング、システム保守など |
関連記事:業務委託の準委任契約とは?請負や委任契約との違い、メリットや注意点を解説
▼下記の資料では、業務委託の各契約形態ごとの概要や特徴を詳しく解説しています。無料でダウンロードできますので、ぜひ参考にしてください。

企業が業務委託を活用するメリット4つ
次に、企業側から見た業務委託のメリットを解説します。企業が業務委託を行うメリットとしては、主に次の4つが挙げられます。
- 専門性の高い業務をすぐに任せられる
- 人材育成のコストを抑えられる
- 社内人材を基幹業務に充てられる
- プロジェクトに柔軟に対応できる
それぞれ解説します。
1. 専門性の高い業務をすぐに任せられる
業務委託で活躍する人は企業に属さずとも案件が受注できるような専門性の高いスキルを持った人が多くいます。
正社員や派遣社員を採用するよりも、専門性の高いスキルを持った人と出会える可能性は高くなるため、プロジェクトで専門性の高い業務があった場合にすぐに任せられるのがメリットです。
2. 人材育成のコストを抑えられる
業務委託を利用すれば、必要なスキルを持った人に委託できるため、自社の人材育成のコストを抑えることができます。
仮に社員で採用しようと思えば、専門スキルを持った優秀な人であればあるほど、企業として支払う給与は高くなるでしょう。また、優秀な人は中途採用市場に出てくることも少なく、採用コストも上がります。
業務委託を利用することで、採用にかかる手間やコストをすべてカットできるだけでなく、必要なときに専門性の高いスキルを導入することが可能です。また、人材教育のコストや離職のリスクを抑えられることも、経営上の大きなメリットと言えるでしょう。
3. 社内人材を基幹業務に充てられる
業務委託を利用すれば、これまでその業務に時間をかけていた社内人材をコア業務に集中させることができます。業務委託は自社で業務の管理をする必要もないため、人材を余分に割く必要もありません。必要な分だけを業務委託することで、業務の効率化にもつながります。
4. プロジェクトに柔軟に対応できる
業務委託は必要な時期だけに依頼することができます。急ぎのプロジェクトが発生した際も専門的なスキルを持った人に必要部分のみを任せられるため、プロジェクトに柔軟に対応することができます。また、常時雇用よりも経費を抑えることもできます。
▼業務委託はコスト削減や柔軟性などのメリットが多い一方で、経験がないと不安を感じやすいのがデメリットです。下記の資料では、業務委託のメリットと注意点を網羅的に解説してますので、ぜひご参照ください。
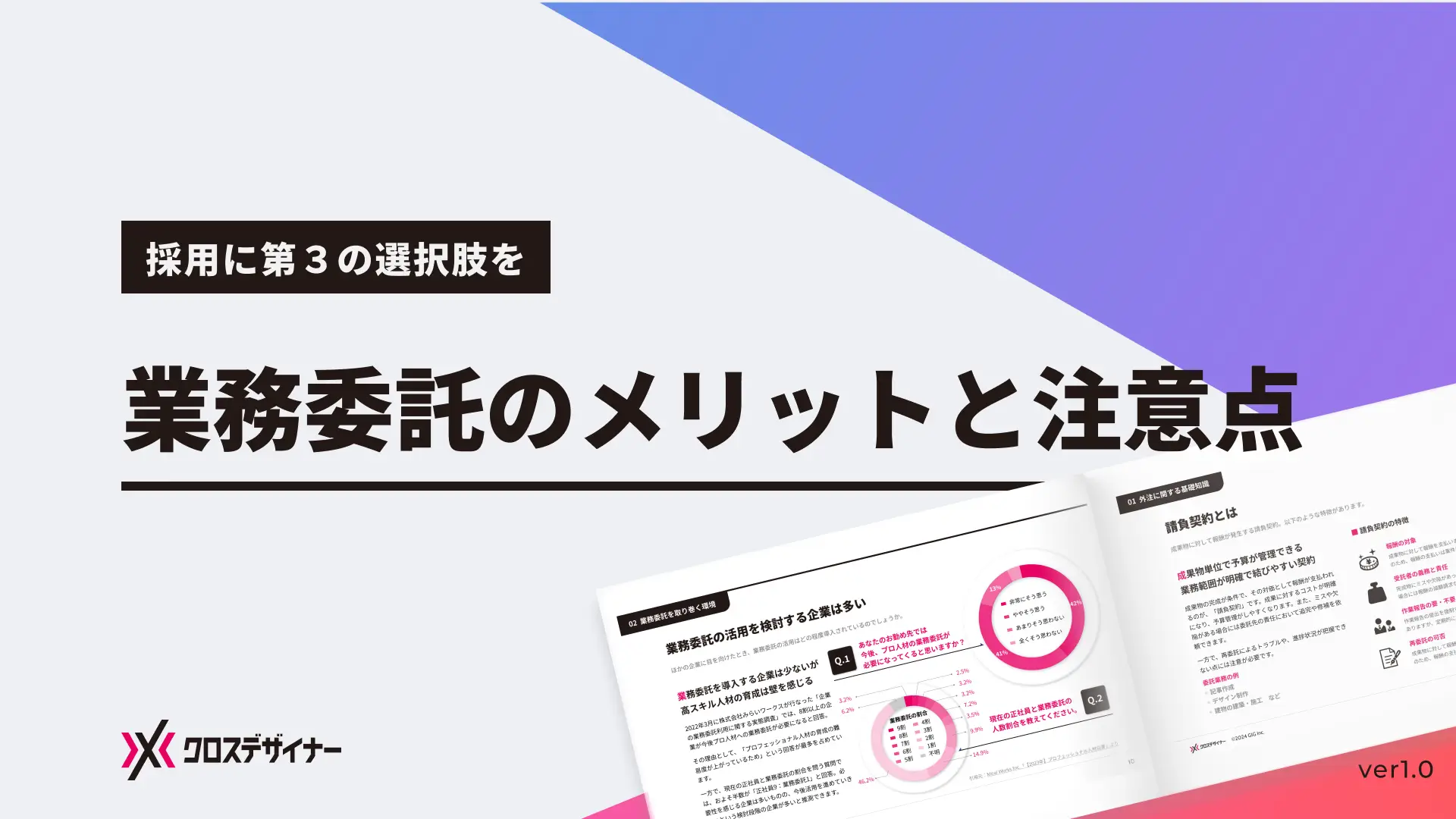
企業が業務委託を活用するデメリット4つ
企業が業務委託する際には、以下のようなデメリットも存在します。次の4つを理解したうえで、業務委託するべきかどうかを検討しましょう。
- 専門性が高いとコストが割高になることもある
- 業務管理が難しく仕事の質が下がることもある
- 社内に知見やノウハウが蓄積されにくい
- 情報漏洩のリスクがある
それぞれ解説します。
1. 専門性が高いとコストが割高になることもある
業務委託の報酬は、スキルや専門性が高いほど割高になる傾向があります。
社内で不足しているリソースであれば必要業務としてやむを得ない反面、委託する業務の内容によっては、報酬が自社で人材を採用し、教育するコストよりも高くなる可能性も否定できません。
ただし、委託範囲や業務内容を精査することで任せる範囲を限定するなど、コストを抑制することも可能です。
2. 業務管理が難しく仕事の質が下がることもある
業務委託では、原則として発注者が受注者に直接の仕事の指揮命令を下すことができません。
そのため、業務管理や成果物の質に問題が生じるおそれがあります。仕事の質は会社の評価にも関わるため、任せる範囲は慎重に精査しましょう。
質を落とさないためにも、契約時に業務の進め方や連絡方法などをしっかりすり合わせをしてルールを決めることがおすすめです。また、業務委託前に、面談を行ったり、ポートフォリオを確認するなどしてミスマッチを防ぐのも重要です。
▼下記の資料では、契約をはじめとした業務委託人材の労務管理について詳しく解説しています。リスクを抑えて外部人材を活用するために、ぜひご活用てください。

3. 社内に知見やノウハウが蓄積されにくい
業務委託の大きなメリットは、社内では専門性が高くて困難な業務を、高いクオリティで完成させられることにあります。
しかし、業務委託に頼りすぎると社内に知見やノウハウが蓄積されず、優秀な人材が育ちにくくなるおそれがあります。
すでにその業務に対するノウハウがあれば別ですが、知見やノウハウを蓄積させたい場合は、定期的にミーティングを開催して、情報の共有を図りましょう。
4. 情報漏洩のリスクがある
業務委託では社内の情報を外部に共有する必要があるため、常に情報漏洩のリスクが伴います。最悪の場合、情報流出に伴う賠償責任などが生じるだけでなく、自社の業界での評判が落ちることも否めません。
そこで、情報漏洩の対策方法として、委託前にNDA(秘密保持契約)を締結しましょう。NDAを結んでおけば、何が秘密情報に値するか明確に定義することができます。万が一情報漏洩があった際も責任の所在を明らかにすることが可能であり、有効な対策となりえます。
▼下記の資料では、業務委託契約に不可欠な契約書の作成ポイントを網羅的に解説しています。無料でダウンロードできますので、ぜひご活用ください。

企業が業務委託を成功させるためにやるべきこと3つ
企業が業務委託を成功させるには、次の3つのポイントを押さえた行動が不可欠です。ぜひ参考にしてください。
1.適切なパートナー(委託先)を選ぶ
業務委託を成功させるには、適切なパートナー選びが欠かせません。そこで、委託先の実績や専門性、信頼性を慎重に評価することが重要です。
また、自社の企業文化や価値観との相性も重要な要素です。複数の候補を比較し、面談を重ねることで、長期的なパートナーシップを築ける委託先を見つけられるでしょう。
適切なパートナーの選定は、円滑な業務遂行と高品質な成果物の確保につながります。
▼下記の資料では、採用活動で必要となるペルソナの作成方法を、すぐに使えるフォーマット付きで解説しています。無料でダウンロードできますので、ぜひご活用ください。

2.業務内容と範囲を明確にする
業務委託の成功には、委託する業務の内容と範囲を明確に定義することが不可欠です。具体的な目標、期待される成果物、納期、品質基準を詳細に記述した仕様書を作成しましょう。
また、責任範囲や権限の所在も明確にすることも重要です。これらを契約書に明記しておくことで、委託先との認識のずれを防ぎ、トラブルを回避できます。
明確な業務定義は、効率的な進行と高品質な成果につながる重要なプロセスです。
▼下記の資料では、ジョブディスクリプションの作成方法を初めての方でも安心のテンプレート付きで解説しています。無料でダウンロードできますので、ぜひご活用ください。
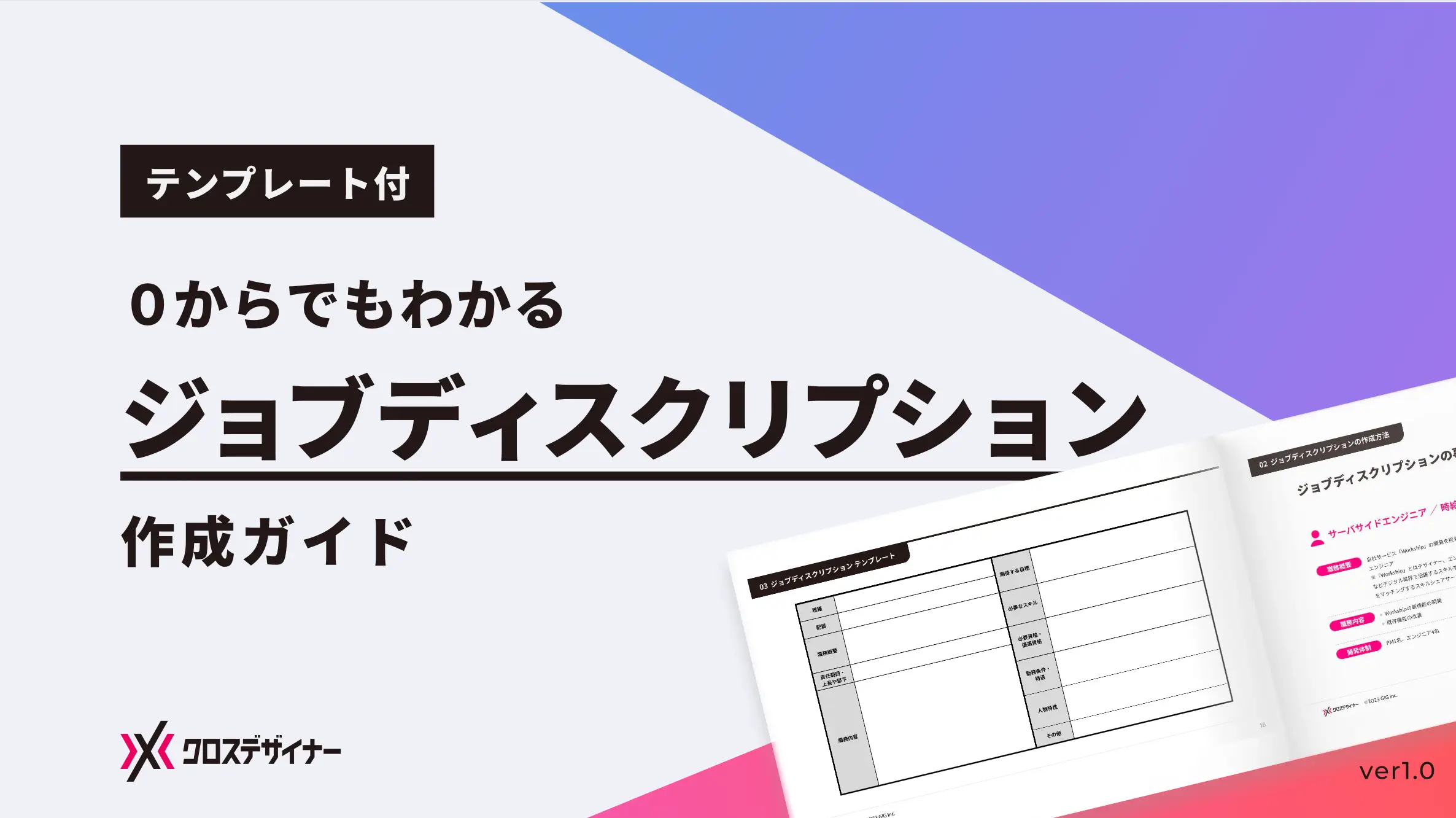
3.効果的なコミュニケーションと品質管理を徹底する
業務委託の成功には、委託先との効果的なコミュニケーションと徹底した品質管理が欠かせません。定期的に進捗報告や成果物の確認を行い、問題点を早期に発見・解決することが重要です。
また、明確な品質基準を設定した上で、評価を行う必要があります。オープンで建設的なフィードバックを心がけ、継続的な改善を促すことが、高品質な成果物の実現に寄与します。
業務委託を活用する際の注意点3つ
次に、業務委託を活用する際の注意点を3つ紹介します。
- 適切な業務委託契約書を作成する
- 偽装請負に気を付ける
- 適切な人材を探すのにかかる時間を考慮する
1. 適切な業務委託契約書を作成する
業務委託契約書は、委託内容や条件を明確にし、トラブルを防ぐ重要な文書です。そこで、業務内容、報酬、期間、成果物の権利、秘密保持などの重要項目を具体的に記載しましょう。また、双方で内容を十分に確認し、必要に応じて専門家のサポートを受けるのもおすすめです。
なお、契約書の作成は原則として委託者が主導し、受託者との交渉を経て完成させるのが一般的です。
関連記事:デザイナーとの業務委託契約書で注意すべき点とは? 必須の記載事項も解説
▼下記の資料では、業務委託に必要な4種類の契約書の作り方を、テンプレート付きで解説しています。無料でダウンロードできますので、ぜひ参考にしてください。

2. 偽装請負に気を付ける
業務委託契約であるにも関わらず、直接具体的な指示や命令を出したり、就業時間の管理をおこなっている場合、偽装請負に該当してしまいます。
業務委託契約書には、請負または準委任契約であることを明記し、発注側が受注側に直接の指示を行わないことを記載しましょう。偽装請負とみなされた場合、職業安定法上の処罰を受けることになってしまうため、注意が必要です。
3. 適切な人材を探すのにかかる時間を考慮する
業務委託を活用しようと思っても、すぐに適切な人材が見つかるとは限りません。特に限られた専門スキルの場合、対象となる人材も少なく、優秀な人はすぐに採用されるため見つけることもできません。探すのに時間がかかることも考慮して、業務委託や副業のマッチングサービスの活用も検討してみましょう。
▼下記の資料では、クロスデザイナーの特徴や登録人材例、導入事例、契約形態などを詳しく紹介しています。無料でダウンロードできますので、ぜひ参考にしてください。
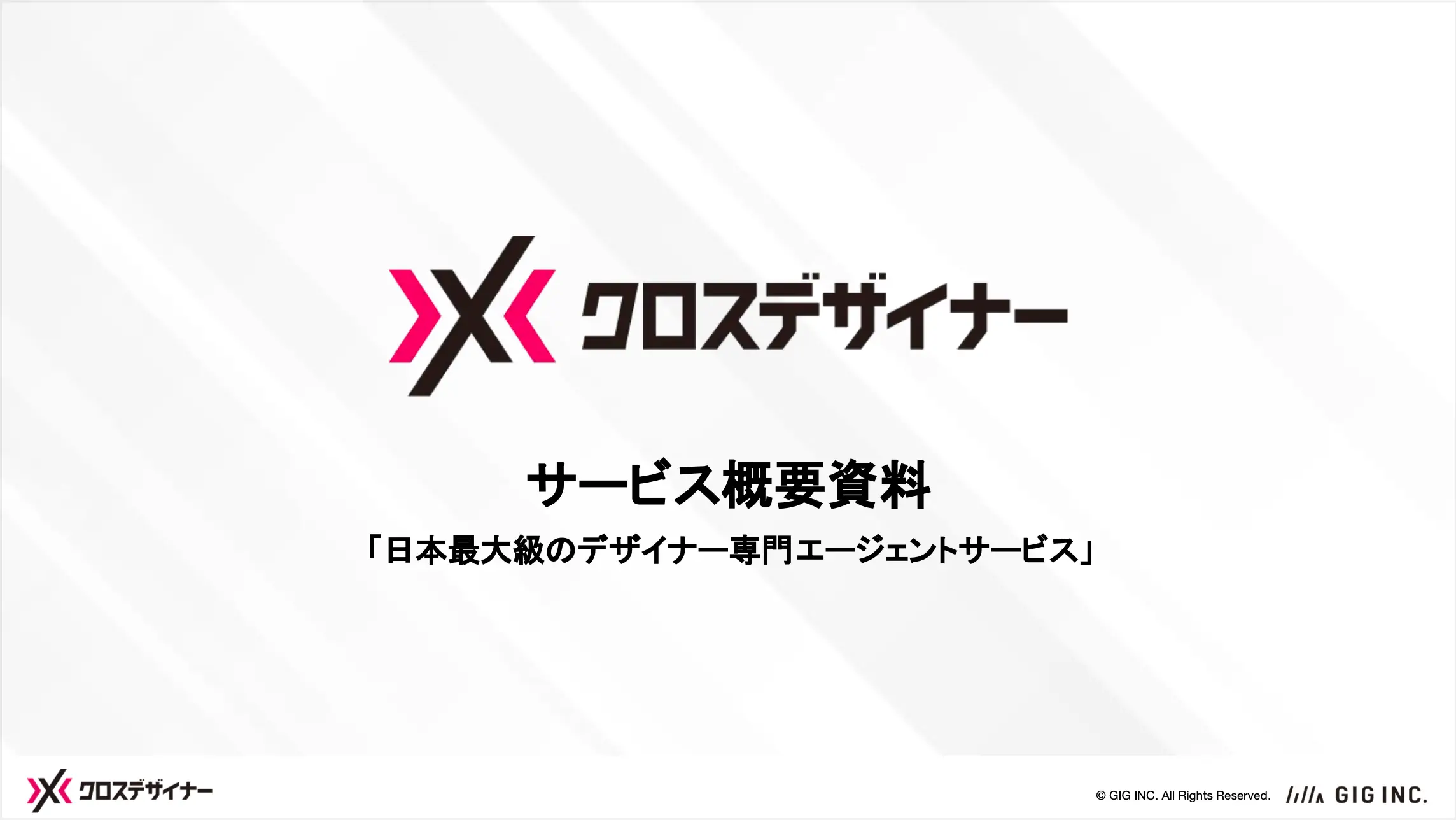
業務委託契約を結ぶ際のステップ6つ
業務委託する際は、支払い条件や期日、秘密保持などの項目を事前にクリアすることが重要です。認識にズレがあると、企業側は「期待していた成果物を得られない」、労働者側は「納品したにもかかわらず報酬が支払われない」といったトラブルにつながるおそれもあります。
このようなトラブルを防止するためにも、業務委託契約を結びましょう。一般的な流れは次の通りです。
- 契約内容のすり合わせ
- 契約書の作成
- 契約書の締結
- 業務の実施
- 業務完了確認
- 報酬支払い手続き
それぞれ解説します。
1. 契約内容のすり合わせ
発注者である企業は、業務委託する内容を提案書や募集要項にまとめます。受注者はこの提案書や募集要項を元に見積書を作成し、双方合意の上で内容をすり合わせていきます。
2. 契約書の作成
提案書と見積書が合意に至ったら、正式な契約書を作成します。契約書には法的な規定や責任範囲だけでなく、業務の範囲や支払い条件、期日、秘密保持や知的財産権、損賠賠償などの項目を明記します。
3. 契約書の締結
契約書の内容に合意すれば、契約書の締結になります。契約締結後は、法的な拘束力が発生するため、契約の遵守が求められます。
4. 業務の実施
契約の締結後、業務を開始します。受注者は納期や品質基準を満たすべく、自らコントロールして業務を遂行します。企業はクオリティや進捗状況を管理するためにも、定期的な報告やミーティングを開催します。
5. 業務完了確認
企業は納品報告を受けたら契約書通りの業務が行われたかの確認を行います。修正がある場合は、訂正場所を明確に指示します。
6. 報酬支払い手続き
業務の完了後、契約書の支払い条件に沿って報酬の支払い手続きを行います。
▼自社業務をはじめて外注する際は不安を感じる方も多いはず。下記の資料では、外注の流れとポイントをステップ別に解説しています。無料でダウンロードできますので、ぜひご活用ください。

専門性の高いフリーランスデザイナーに最短で仕事を依頼したいのならクロスデザイナーがおすすめ!
企業、人材の両方の面から業務委託を活用するメリットについて解説してきました。正社員を採用することは会社の成長のためにも重要なことではありますが、コスト削減の面やプロジェクトの進行スピードの面からも業務委託を活用することは非常に有効と言えるのではないでしょうか。
メリット、デメリット両方を把握して、積極的に業務委託を利用していきましょう。その中でもエージェントの活用はおすすめです。エージェントは契約書関連の業務を任せられる、適切な人材を探してくれるなど、採用担当者の負担軽減にもなります。
フリーランスデザイナーへの業務委託なら、クロスデザイナーがおすすめです。
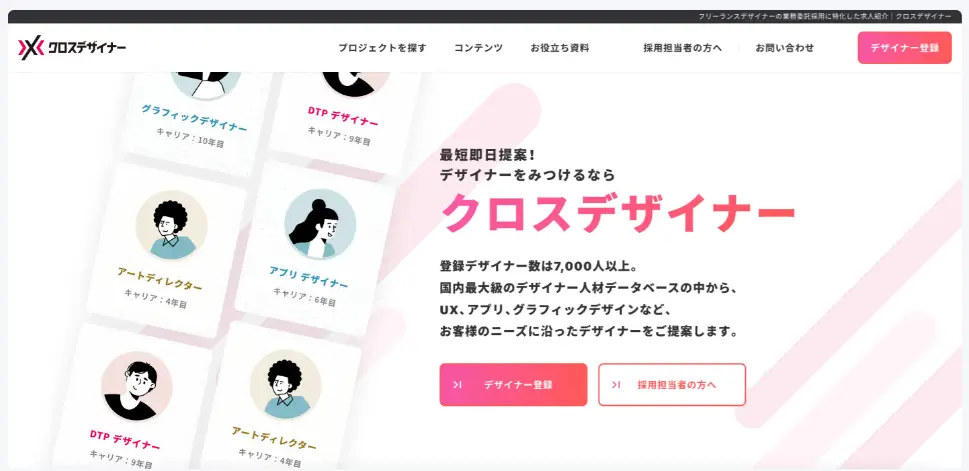
クロスデザイナーは、国内最大規模のデザイナー登録者から、厳正したデザイナーを最適なタイミングでご提案するデザイナー専門のエージェントサービスです。現在、7,000人以上のデザイナーが在籍しています。
登録しているデザイナーとの合意があれば正社員採用も可能です。また、スカウトや人材紹介機能もあるため、採用難易度の高い、即戦力デザイナーの採用機会を最大限サポートしています。
エージェントに相談いただければ、最短3営業日でのアサインも可能です。また、週2〜3日の柔軟な依頼も可能なので、自社の作業量に応じて効率的に外注することができます。
こちらより、クロスデザイナーのサービス資料を無料でダウンロードできますので、即戦力の優秀な人材をお探しの方は、ぜひ【お問合わせ】ください。平均1営業日以内にご提案いたします。
- クロスデザイナーの特徴
- クロスデザイナーに登録しているデザイナー参考例
- 各サービスプラン概要
- 支援実績・お客様の声
Documents