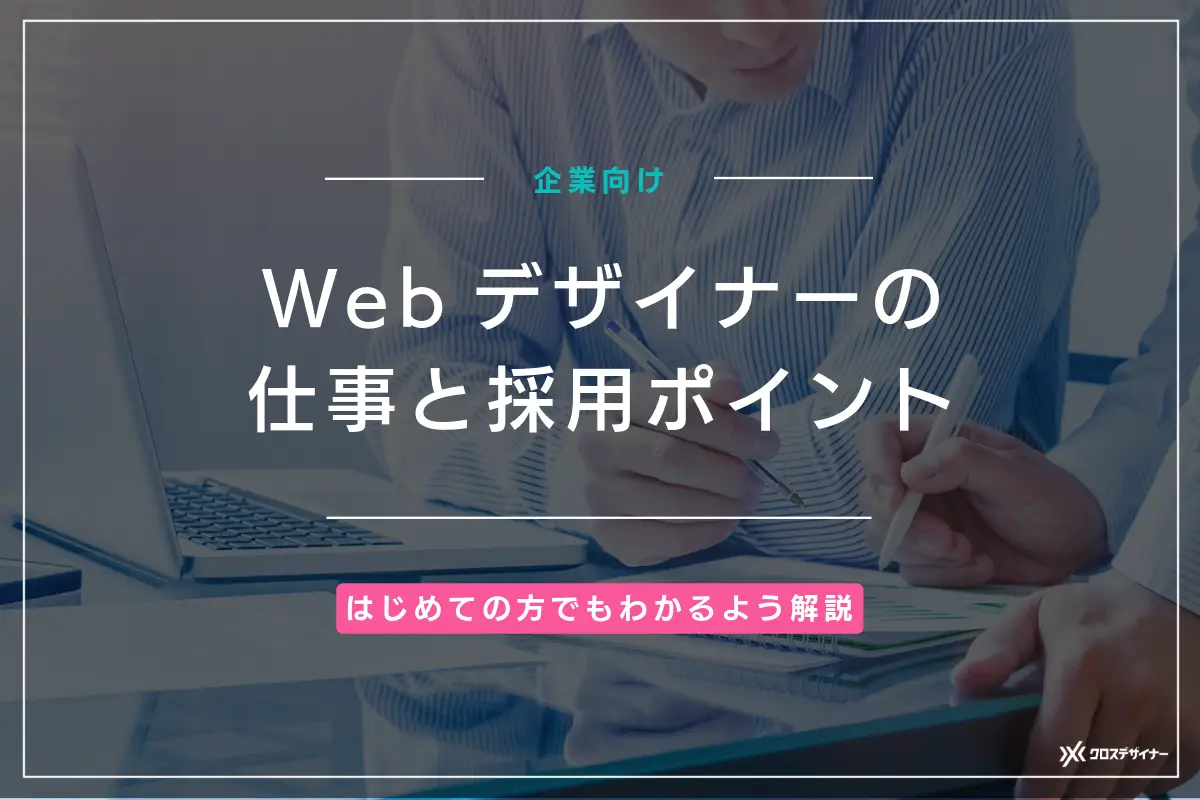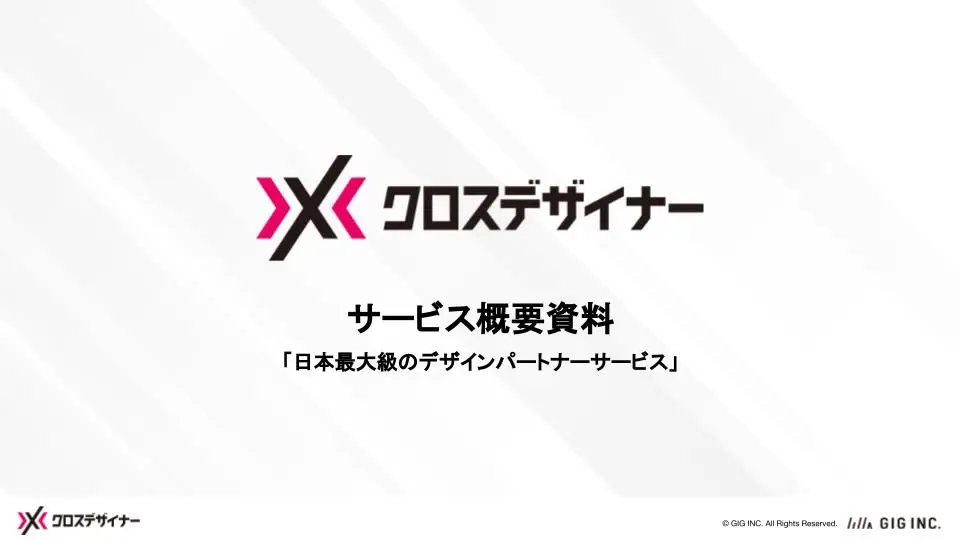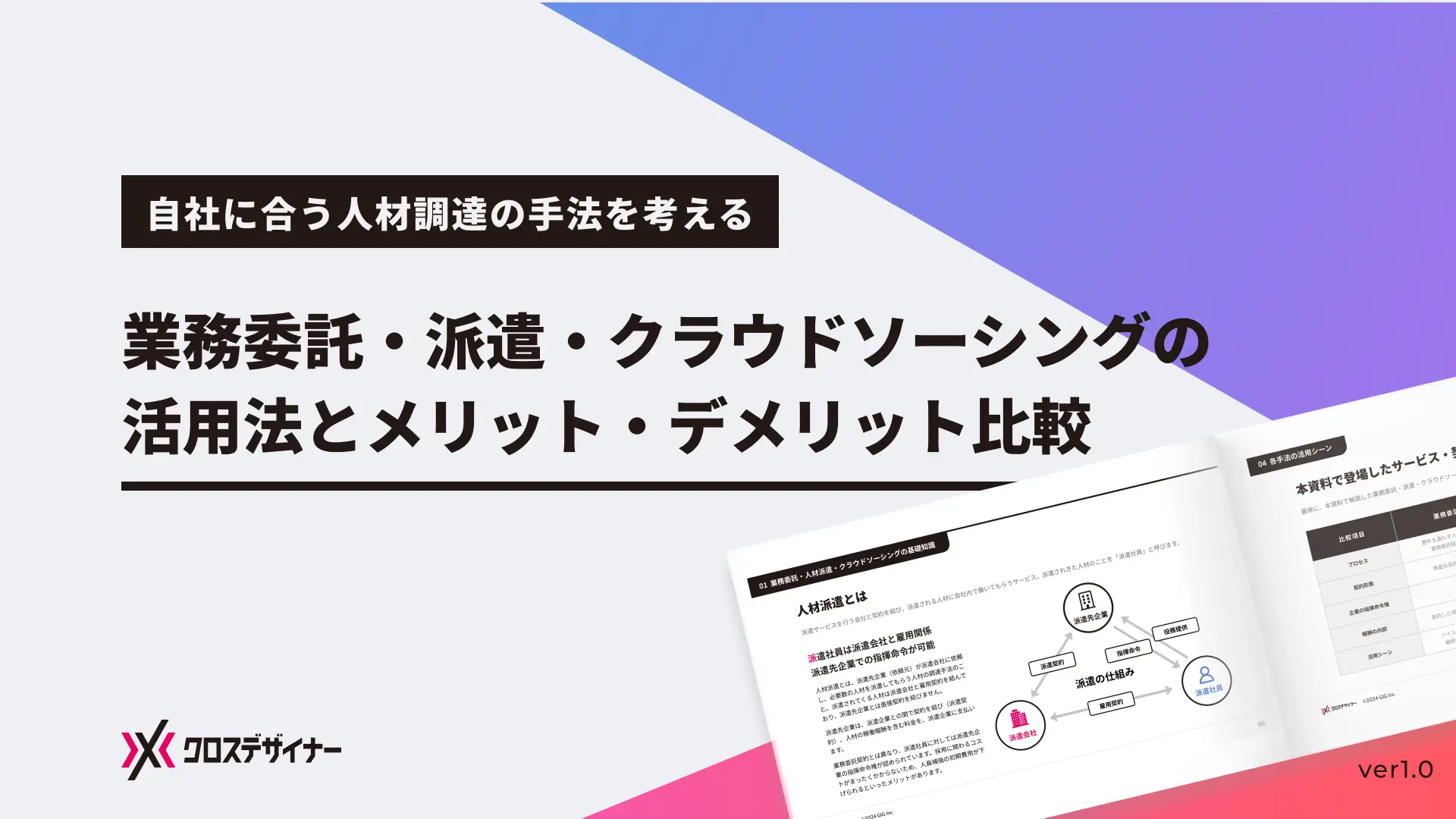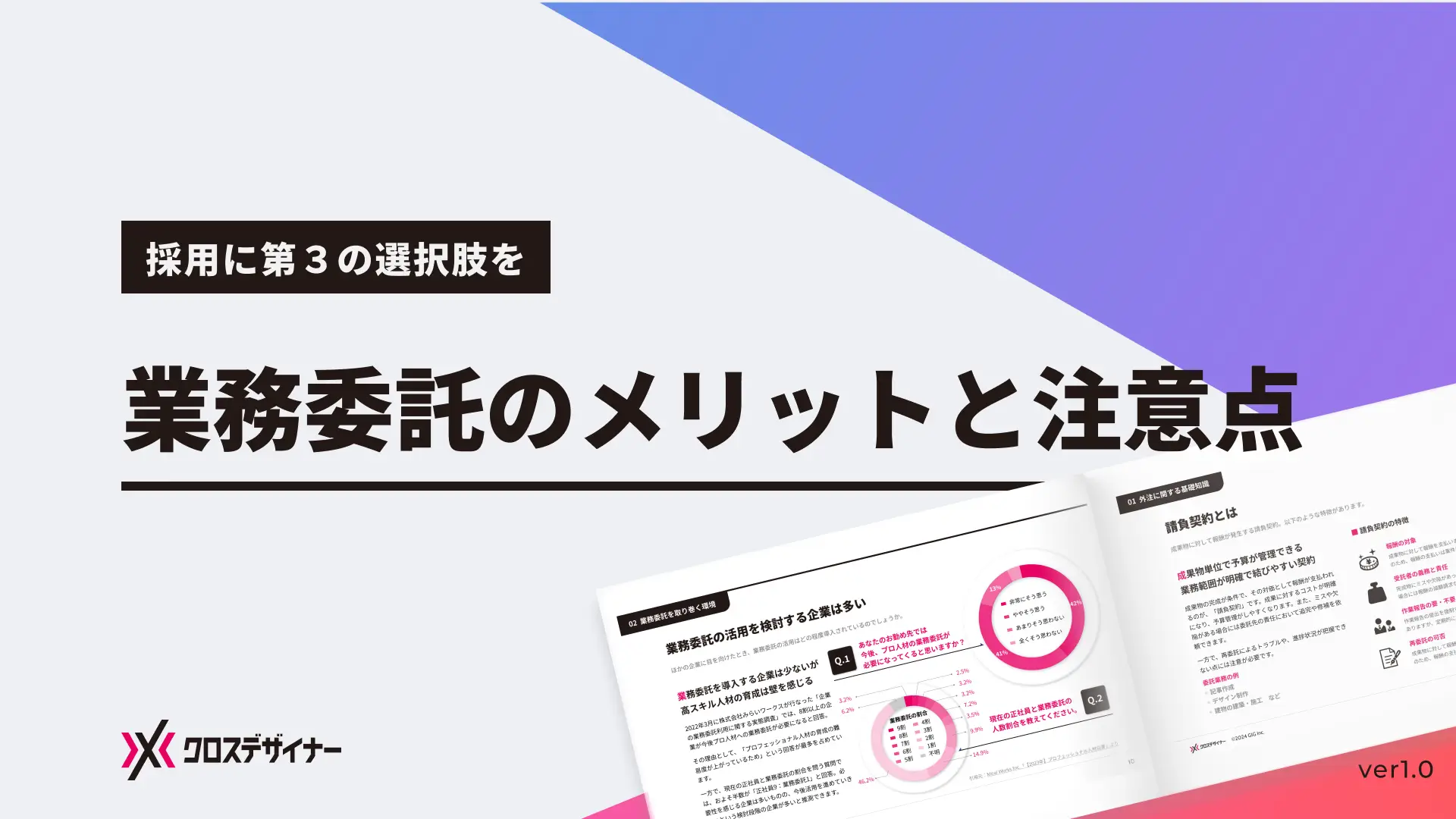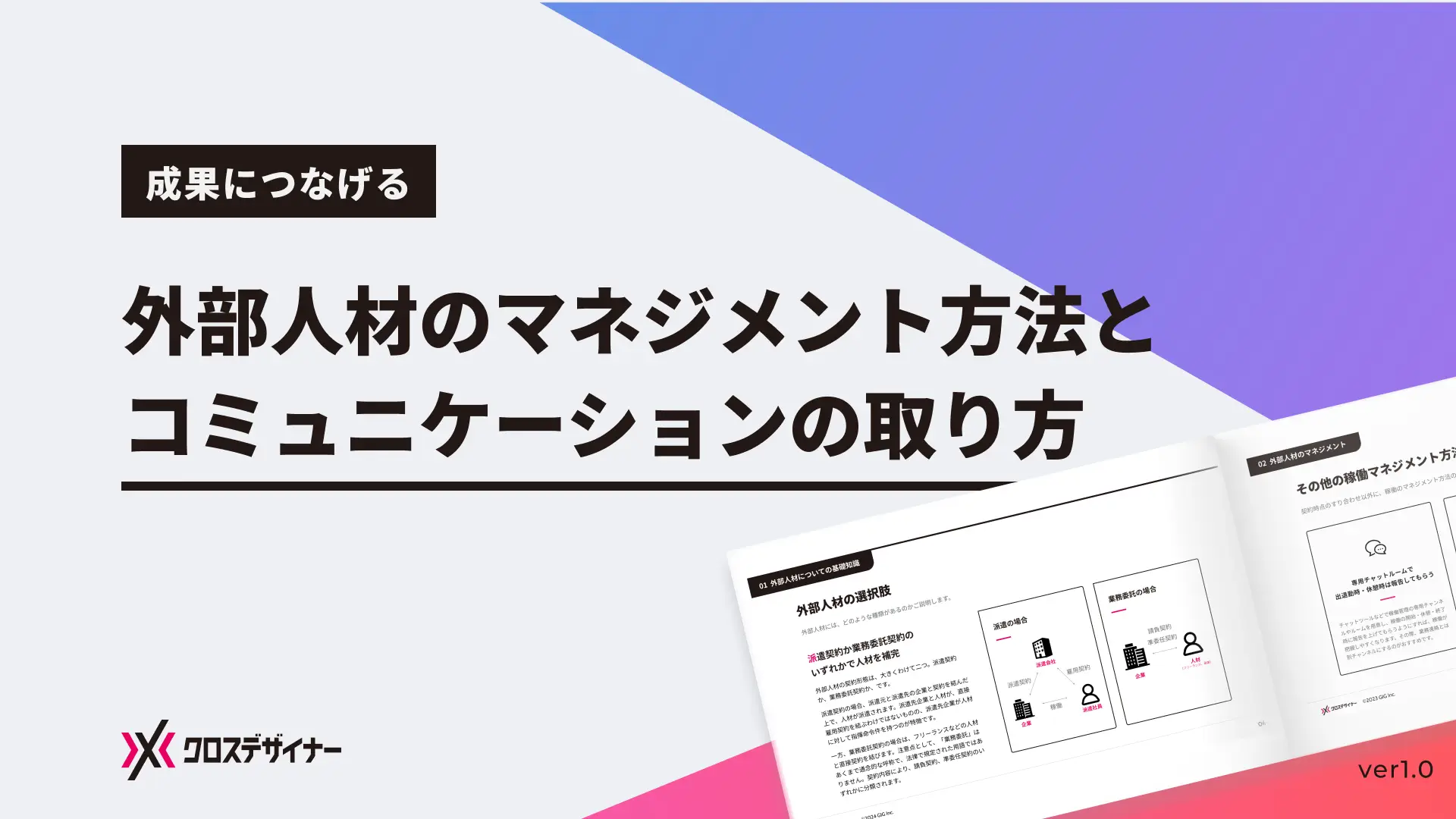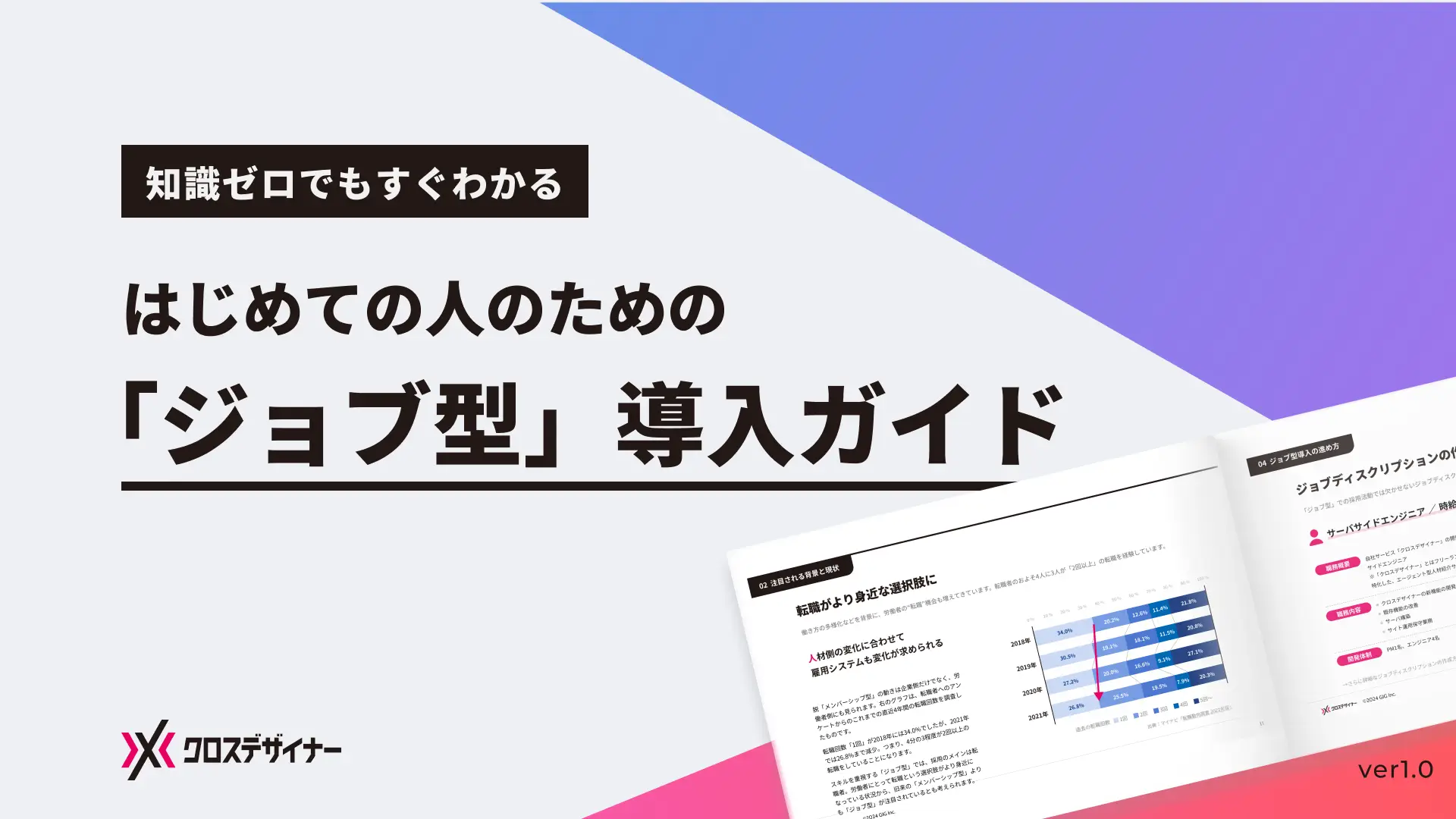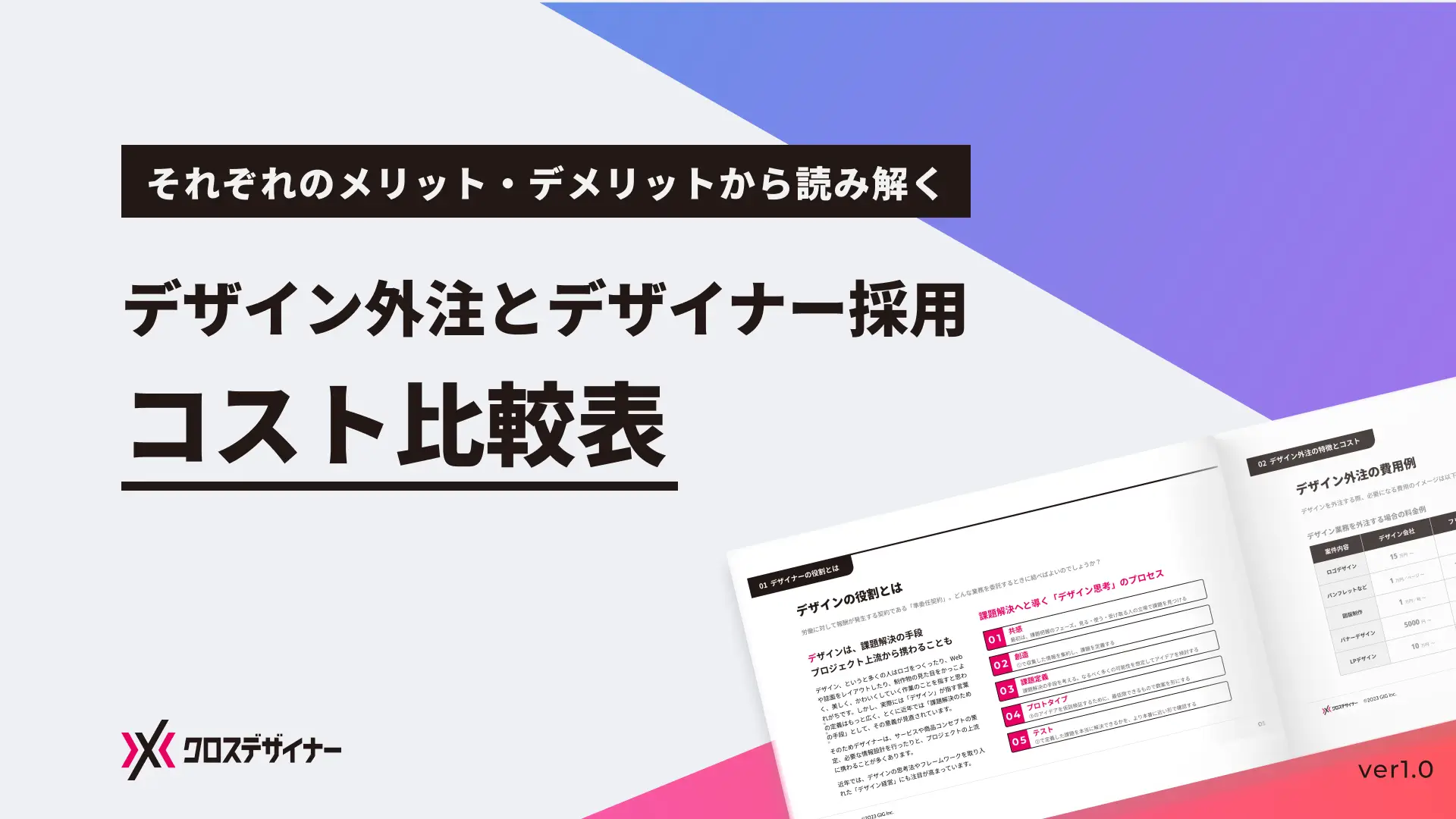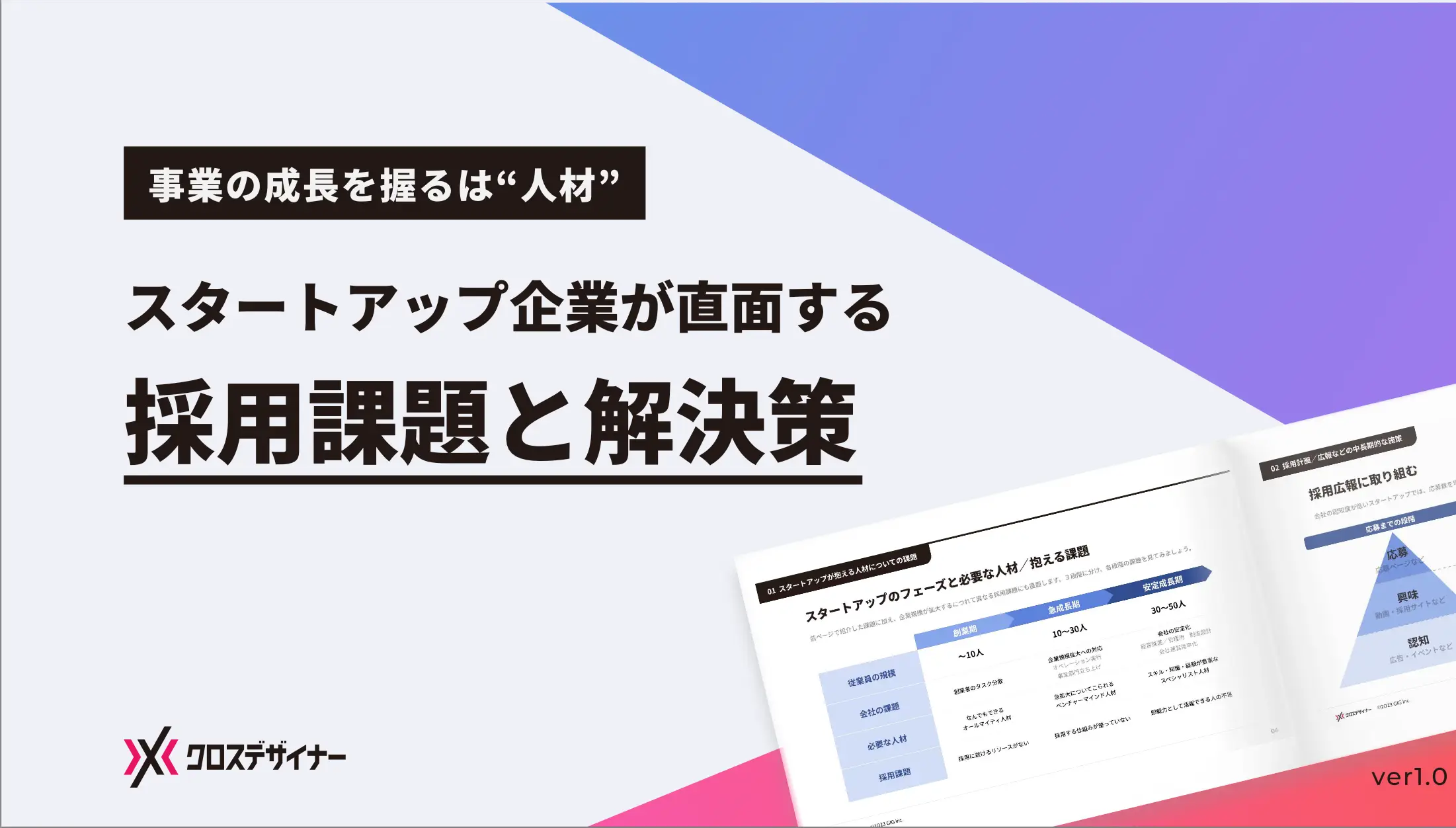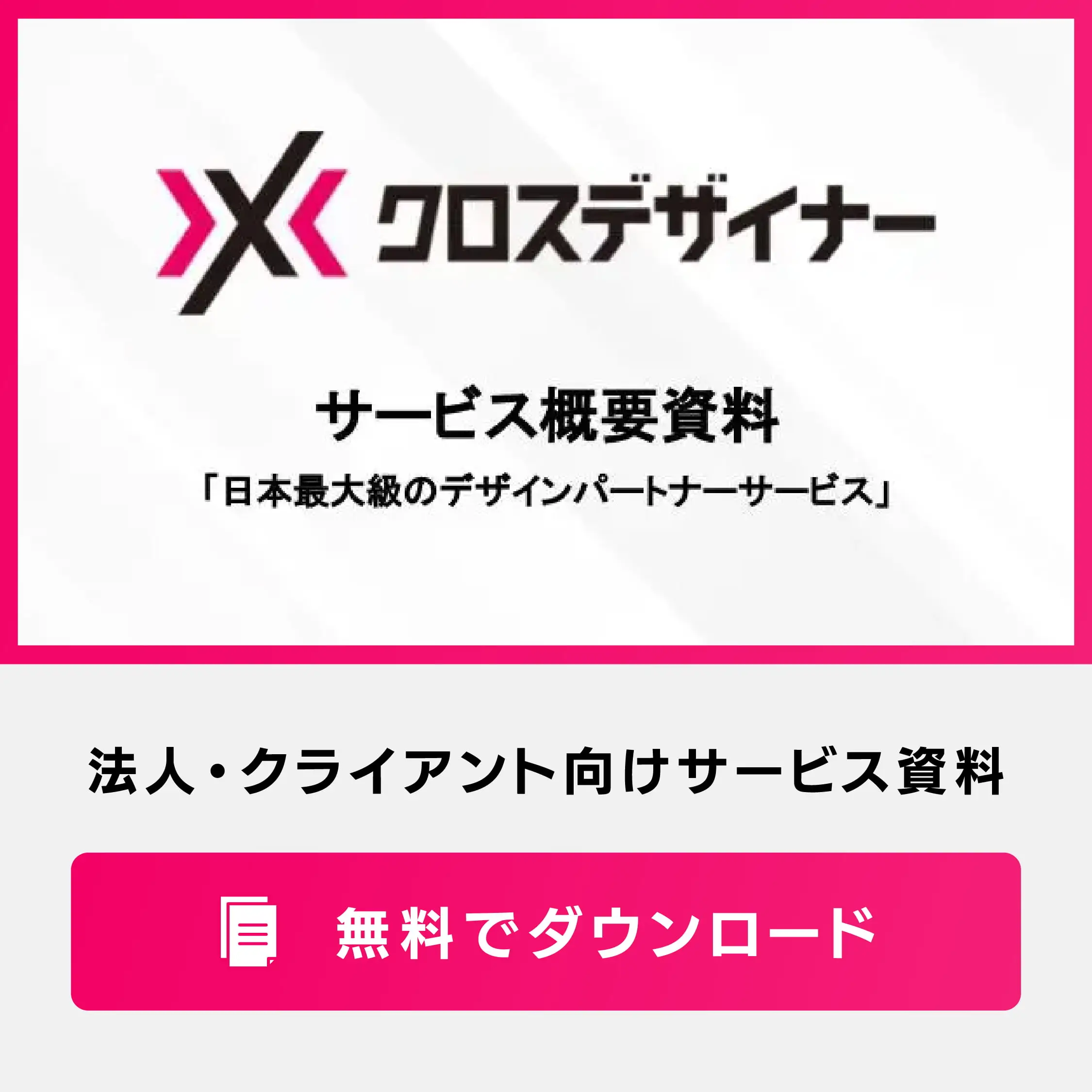障がいのある人や高齢者ら製品のデザインの過程で軽視されてきた人たちを含め、多様な人々の使いやすさや心地よさを追求する「インクルーシブデザイン」が注目されています。
ただ、多くの方々にとって耳にしたことはあってもどういうことなのか、明確にわからないという方が大半なのではないでしょうか。
そこで本記事では、インクルーシブデザインの定義や具体的な事例、導入のポイントなどについてご紹介します。
インクルーシブデザインとは?
インクルーシブデザインとは、高齢者や障がいのある人、外国人など、これまでデザインの過程で除外されがちだった人々を、企画の初期段階から巻き込み、一緒に考えながら製品・サービスを設計する手法です。
「インクルーシブ(inclusive)」は「内包」「包含」を意味し、対義語である「exclusive(排除)」と対比されます。これまでデザインの中で見過ごされてきた人たちを含め、その視点を取り入れることで、多数派の意見だけでは見えにくい潜在ニーズを掘り起こし、新たな価値を創造していくことが目的です。
この考え方は、使いやすさの追求だけでなく、社会全体の多様性を尊重し、誰もが心地よく利用できるデザインを実現する上で重要なアプローチです。
生まれた背景
インクルーシブデザインという概念を最初に提唱したのは、イギリスのロイヤル・カレッジ・オブ・アートのロジャー・コールマン教授です。
1991年、教授の友人である車いす利用者の女性からキッチンデザインを依頼されたことがきっかけでした。教授は当初、車いす利用に最適化した機能的な設計を考案しましたが、依頼者は「ほかの人がうらやむようなキッチンが良い」と語りました。
この体験を通じて、機能性だけでなく「当事者の価値観や希望を共有し、同じ視点に立つこと」の重要性に気づき、これがインクルーシブデザインの思想の原点となりました。
「抱括的」の意味とアプローチ
「インクルーシブ(inclusive)」は直訳すると「包括的な」「すべてを含む」といった意味があります。
この言葉の本質は、「排除を前提としないこと」にあります。インクルーシブデザインは、何かを追加で対応するのではなく、初めからさまざまな人々の存在を前提としてデザインするのです。
たとえば障がいのある人や高齢者を特別なケースとして扱うのではなく、初めから不自由さを想定したうえでデザインを考えるのです。その結果、多くの人にとって使いやすいデザインが完成します。
このように、インクルーシブデザインは単なる配慮にとどまらず、最初から多様性を取り込むことで、社会全体の利便性や体験価値を高めることを目的としています。
ユニバーサルデザインとの違い
ユニバーサルデザインとインクルーシブデザインは、どちらも「誰もが使いやすいデザイン」を目指すという点で似ていますが、そのアプローチや考え方の違いについて解説します。
出発点
ユニバーサルデザインは、「できるだけ多くの人に使いやすく」という発想から生まれた考え方です。年齢や障がいの有無に関係なく、すべての人々にとって不便が少ないことを目指します。
インクルーシブデザインは、むしろ最初から排除されがちな人々の視点を出発点とします。その声をプロセスの最初から取り入れ、そこからすべての人にとっての価値を広げていくアプローチです。
設計思想
ユニバーサルデザインは、なるべく誰にでもわかりやすく、使いやすいことを前提にデザインされます。平均的な使いやすさをひとつの形にするといった点が特徴です。
一方でインクルーシブデザインは、多様性そのものを前提としています。ある特定の人が抱える課題を深掘りするなかで、そこから得られる学びを広げていき、あえて万人向けにしないことも選択肢に含まれます。
成果物
ユニバーサルデザインは、完成した製品やサービスの「使いやすさそのもの」に価値を置きます。できあがったものが、誰にとっても不自由なく使えるようになっていることが重視されます。
インクルーシブデザインは「どう作るか」のプロセスに重点を置きます。たとえば、視覚や聴覚に障害のある人、高齢者、小さな子どもなど、特定の使いづらさを感じやすい人たちと一緒にアイデアを出し合い、試作を重ねていくのが特徴です。
その結果、さまざまなユーザーの視点が自然と反映されたプロダクトに仕上がっていきます。
インクルーシブデザインが注目される背景
インクルーシブデザインに内包される高齢者や障がい者らは「リードユーザー(未来へと導いてくれる人)」とも呼ばれ、施設やWebデザイン、ビジネスプロセスのデザインなどにも幅広く活用されています。
多様性を受け入れる時代背景
インクルーシブデザインが注目されている背景として、昨今は「ダイバーシティ」という価値観が浸透し、多様性を受け入れる流れが強まっています。
障がいの有無や性別、性的嗜好、人種などさまざまな違いを認め合い、お互いの人権と尊厳を尊重し合いながら生きていく「インクルーシブ(共生)社会」という言葉も使われます。
「インクルーシブ」という理念は、不況や移民の増加により社会的排除が問題となっていた1970年代のフランスで誕生しました。1980年代にアメリカで障がい児教育の分野で用いられるようになり、日本でも労働人口の減少や価値観の多様化などを背景に徐々に広まっていきました。
現在はデザインだけでなく、教育や施設などさまざまな場でその理念が広まっています。
SDGsとの関連性
インクルーシブデザインは「持続可能な開発目標」である「SDGs」とも深い関係があります。
「インクルーシブ(包摂的)」という言葉はSDGsの目標17のうち5項目(4、8、9、11、16)で使われています。
▲出典:外務省
とくに「地球上の誰一人取り残さない(leave no one behind)」ことを誓う項目は、あらゆる人が排除されないことを意味するインクルーシブと、非常に近い理念といえます。
こうしたことから世界中の人たちが取り組むSDGsは、インクルーシブの理念と相まって注目を集めています。
潜在ニーズの掘り起こしと新たな価値の創造
このほか、インクルーシブデザインは、潜在ニーズの掘り起こしと新たな価値の創造において注目されています。
競争が激化するなかで、平均的なユーザーのニーズを取り込んでもすでに他社が取り組んでいるなど、価値を生むことは難しくなっています。
障がいのある人をはじめとしたマイノリティのニーズを取り込むことで、マジョリティ(大多数)の視点からは気づかなかった潜在的なニーズの引き出しにつなげることもできます。
2000年代以降、普及してきた「デザイン思考」とともに、インクルーシブデザインを通じてユーザーの多様性や潜在的なニーズを深く理解することがより求められています。
関連記事:デザイン思考とは?概要から活用方法をわかりやすく解説|導入するメリットやフレームワークも紹介
ビジュアルデザインへの活かし方
インクルーシブデザインの7原則は、WebやUI/UX、パッケージなど幅広い分野に応用できます。近年は誰にとっても使いやすいアクセシブルデザインが重視され、設計時の工夫が求められています。ここでは7原則をもとに、実践的な活用法を紹介します。
誰もが同等に楽しめる体験を設計する
色覚や視覚特性の違いがあっても、同じ品質の体験が得られるよう配慮しましょう。たとえば視覚に制約のある方でも文字やアイコンが識別しやすいよう、色やコントラストを調整し、曖昧さの少ない情報提示を心がけます。
このような「同等の体験を提供する」設計は、見た目の美しさと使いやすさを両立させる上で、アクセシブルデザインにおける重要なポイントです。
利用状況を考慮した柔軟なデザイン
ユーザーが直面するさまざまな利用環境を想定しましょう。視覚障がい者が音声読み上げを使いやすいように、文字サイズや配色の変更を許容するなど、柔軟な設計が求められます。たとえばiPhoneの音声読み上げ機能は、音量や色味などを個人に合わせて調整できることで、利用者それぞれの状況に応じた使いやすさを実現しています。
プロダクトの分野でも、花王の『アタックZEROボトル』のように、握力が弱い方や高齢者、手指の不自由な方に配慮したデザインは、状況に応じた柔軟な使い方を可能にする好例です。
握力が弱い方や高齢者、手指の不自由な方に配慮し、片手で操作できるノズル構造が特徴です。使い方の自由度を高め、ストレスのない利用体験を提供しています。従来の洗剤は粉を専用スプーンで入れたり、液体タイプの容器のフタを回し開けて入れたりするというものでしたが、こちらは片手で入れられるため、とても便利です。
慣れ親しんだ要素で一貫性を保つ
ナビゲーションの位置や操作・色のパターンなど、ユーザーが慣れている要素を設計上で一貫して用いることで、直感的な操作を促せます。
これにより経験値の少ないユーザーや高齢者でも迷わずに利用できます。「一貫性」は混乱を防ぎ、安心感を与える重要な要素です。
利用者が自ら操作を調整できる仕組み
ユーザー自身がフォントサイズ、背景色、表示モード(例:ダークモード)などを変更できるように設計することで、「利用者に制御させる」原則を体現できます。
また音声やテキスト表示の切替など、ニーズに応じた設定の自由が快適さを向上させます。
多様な使い方に対応する選択肢の設計
タッチ操作、音声入力、キーボード操作など、異なる方法で操作できる選択肢を提供することで多様なユーザーが利用しやすくなります。この「選択肢を提供する」原則は、インクルーシブなプロダクト設計で重要な対応です。
情報の優先順位を整理したデザイン
ユーザーがもっとも必要とする情報をすぐに見つけられるよう、視覚的な強弱や配置順を工夫しましょう。「コンテンツの優先順位を付ける」ことで、利用者が重要なタスクに集中できる設計が可能になります。
この考え方は、ウェブアクセシビリティ(WCAG)のガイドラインでも強調されています。構造的な見出しの使い分けや、視認性の高いボタン配置など、誰もが迷わず情報にたどり着ける仕組みづくりが求められます。
付加価値を意識したデザイン改善
ただ使いやすいだけでなく、色・質感・動きなどで体験の心地よさや楽しさを演出することも重要です。
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社の絆創膏「バンドエイド」は、多様な肌の色に対応したカラーバリエーションを展開しています。
▲出典:BAND-AID®
従来の絆創膏と比べて、さまざまなスキンカラーのユーザーに使いやすくなり、世界各国で「肌になじむので目立たず、使い勝手が良い」などと反響がありました。
こうした人の肌の色に馴染むバンドエイドのカラーバリエーションは「価値を付加する」好例と言えます。
インクルーシブデザインの実践プロセス
インクルーシブデザインは「包括的な思想」だけでなく、具体的なプロセスに落とし込むことが重要です。設計から実装、検証・改善にいたるまで、意図的かつ継続的な取り組みが求められます。
デザイン思考を活かして設計する
インクルーシブデザインの設計段階では、ユーザーの視点を深く理解するためにデザイン思考の活用が効果的です。とくに、特定の制約を持つユーザーを初期段階から巻き込み、共感や観察を通じて課題を発見することが重要です。
こうした「共創的な姿勢」は、解決すべきニーズをより本質的に捉えたプロトタイプ設計につながります。視覚・身体的な制限だけでなく、文化的・言語的な背景にも目を向けることで、ユーザーの多様性を設計に活かすことができます。
関連記事:デザイン思考とは?概要から活用方法をわかりやすく解説|導入するメリットやフレームワークも紹介
ウェブアクセシビリティをもとに実装する
WebやUI/UXの領域でインクルーシブデザインを具現化する際は、WCAG(Web Content Accessibility Guidelines)などのアクセシビリティガイドラインをベースに実装を進めることが効果的です。
たとえば「キーボード操作でもすべての機能にアクセスできるようにする(達成基準2.1.1)」や「背景と文字のコントラスト比を十分に確保する(達成基準1.4.3)」といった基準を意識することで、誰もが情報や機能にアクセスしやすい設計が実現します。
コード面では、HTMLのセマンティクスやARIA属性の活用なども、アクセシブルデザインの実装において大切な要素です。
ユーザー視点で検証・改善をおこなう
設計と実装の完了後には、実際にさまざまなユーザーを対象とした利用テストを実施し、検証と改善を行うことが欠かせません。ユーザーの操作中の迷いや不便さに気づくことで、見落とされがちなバリアを洗い出すことができます。
とくに、リードユーザーと呼ばれる「制約のあるユーザー」を継続的にフィードバックの主体とすることで、より実践的でリアルな改善が進みます。この段階では、定量的なテスト結果だけでなく、定性的な感想や印象も重要な改善ヒントとなります。
関連記事:人間中心設計とは? 6つの原則や具体的な設計方法と事例を徹底解説
インクルーシブデザインの導入事例
インクルーシブデザインは、理念だけでなく実践的なプロセスを通じて形になります。ここでは「設計」「実装」「検証・改善」という3つの観点から、その進め方を紹介します。
IT分野:Microsoftのアクセシビリティ機能
▲出典:Windows のアクセシビリティ機能 - マイクロソフト アクセシビリティ
Microsoftはインクルーシブデザインのリーダー的存在で、たとえばWindowsやOffice製品の設計において、視覚、聴覚、運動機能などに制約がある人でも使いやすい機能を開発しています。
「Narrator」というスクリーンリーダー機能で、視覚障害者が画面上の内容を音声で確認できるようにしたり、「Eye Control」という目の動きでPCを操作できる機能もあります。体の動きに制約があるユーザーでもPCを自由に使えるようになっています。
さらに、アクセシビリティへの配慮を含むデザインガイドラインを提供し、他社やデベロッパーもこの方向に進めるように支援しています。
このほか日本マイクロソフト株式会社は、一般社団法人PLAYERSと「聴覚障害者が熱狂するエンタメコンテンツを共創する」をテーマとしたワークショップを開催したり、顔が見える筆談アプリを企画したりしています。
アパレル業界
▲出典: 株式会社ロイネ|プレスリリース
株式会社ロイネは、20歳の時に右手と両足を失った山田千紘さんと「1秒でボタンが留まる!ラクなのに”きちん”と見える高機能シャツ」を共同開発しました。
クラウドファンディングサイト「Makuake」と期間限定でのリリースのため、現在は販売していませんが、クラウドファンディングでは目標金額150,000円を大きく上回る2,314,710円が集まるなど大きな反響がありました。
こちらのシャツは、脱ぎ着が簡単なマグネットボタンを使用し、朝の忙しい時間にもスムーズに着替えられるのが特徴です。
「どんなに着やすい服でもダサい恰好はしたくない」と「障害者向けとか健常者向けとかではなく、誰でもかっこ良く着られる服」を目指し、試行錯誤を繰り返し1年以上かけて「時短シャツ」が完成しました。
インクルーシブ遊具を取り入れた施設
▲出典:株式会社ボーネルンド|Digtal PR Platform
教育玩具・遊具の輸入・開発・販売などを行う株式会社ボーネルンドは、神戸市にある「三井アウトレットパーク マリンピア神戸」の全面建替えに伴い新設される「LAGOON COMMUNITY PARK」内に、全天候型あそび場「ボーネルンドあそびのせかい 三井アウトレットパーク マリンピア神戸店」を2024年11月にオープンします。
年齢や性別、身体的能力に関係なく、誰もが楽しめるように、車いすからスムーズに乗り移れたり、座った状態で遊べたりするなどインクルーシブな遊具も取り入れています。
インクルーシブデザインを依頼できるデザイナー
インクルーシブデザインを効果的に取り入れるには、専門性を持つデザイナーの力が欠かせません。Webサイトやアプリ、製品、サービスの各フェーズで適切な人材をアサインすることで、多様なユーザーに対応した設計が可能になります。
ここでは主な5つの職種について、それぞれの担当領域と依頼時のポイントをご紹介します。
Webデザイナー
Webデザイナーは、WebサイトのレイアウWebデザイナーは、Webサイトの構成やデザイン全体を設計します。インクルーシブデザインの実装においては、視認性の高い色使いや読みやすいフォント選定、直感的なレイアウト設計を通じて、誰にとっても使いやすいWebサイトの構築を支援します。
依頼するときは、「アクセシビリティ対応の経験」や「ガイドライン準拠の制作実績」があるかを確認すると安心です。
関連記事:Webデザイナーの職種と仕事内容|必要なスキルや資格、雇用形態も解説
UIデザイナー
UIデザイナーは、Webサイトやアプリケーションなどのインターフェースにおける操作性を設計する役割を担います。ボタンの配置やサイズ、ナビゲーションのわかりやすさなど、ユーザーの動線を意識したデザインを行います。
依頼時には「高齢者や障害のあるユーザーに配慮したUI設計ができるか」を事前にヒアリングすると良いでしょう。
関連記事:UIデザイナーの仕事内容は?採用で確認すべきスキルと知識
UXデザイナー
UXデザイナーは、製品やサービスを通して得られるユーザー体験を総合的に設計します。インクルーシブデザインの考え方を取り入れることで、多様なユーザーの課題や感情に寄り添い、誰にとっても心地よく使える体験設計が可能となります。
プロジェクトの初期段階から参画してもらうことで、リサーチやペルソナ設定など上流工程からインクルーシブな視点を組み込めます。
関連記事:UXデザイナーとは? 仕事内容やスキルについても解説
サービスデザイナー
サービスデザイナーは、サービス全体の仕組みや運用フローを構築します。インクルーシブデザインの文脈では、顧客の接点(受付・手続き・問い合わせなど)において誰もがストレスなく利用できるような設計を行います。
さまざまなユーザー視点に立ったカスタマージャーニーの設計経験があるかをチェックしましょう。
関連記事:サービスデザイナーとは?主な役割と仕事内容、必要なスキルや採用のポイントなどを徹底解説
プロダクトデザイナー
プロダクトデザイナーは、製品の形状や素材、操作方法など、実際の「モノ」の設計を担当します。ユニバーサルデザインの考え方に加え、特定の制約を持つユーザーの使いやすさにも配慮した設計ができる人材です。
たとえば、片手で扱える洗剤ボトルや多様な肌色に合わせた絆創膏などが好例で、実際にユーザーの声を取り入れた開発経験があるかがカギとなります。
関連記事:【企業向け】プロダクトデザイナーとは?その仕事内容や探し方を解説
デザイナー採用はエージェントを活用しよう
インクルーシブデザインを推進する上で、自社に適したデザイナーを採用することは大きな課題です。そこで活用してほしいのがエージェントです。経験やスキルのある人材と効率的にマッチングでき、プロジェクトのスピードと品質を両立できます。ここではエージェントを活用するメリットについて解説します。
求めるスキルを持つ人材を紹介してもらえる
エージェントは、インクルーシブデザインやアクセシビリティに関する実務経験を持った人材を紹介してくれます。
要件定義から参画できるUXデザイナーや、ガイドライン準拠の実装経験があるUIデザイナーなど、目的に合ったスキルを持つ人材を効率的に見つけることができます。採用要件を具体的に伝えることで、ミスマッチを防ぐことが可能です。
求めるスキルや経験を事前にジョブディスクリプションにまとめておくことでスムーズに理想の人材を確保できます。採用手法を問わず、作成しておくと便利です。以下より無料でダウンロードいただけるジョブディスクリプション作成ガイドを配布しています。ぜひお役立てください。
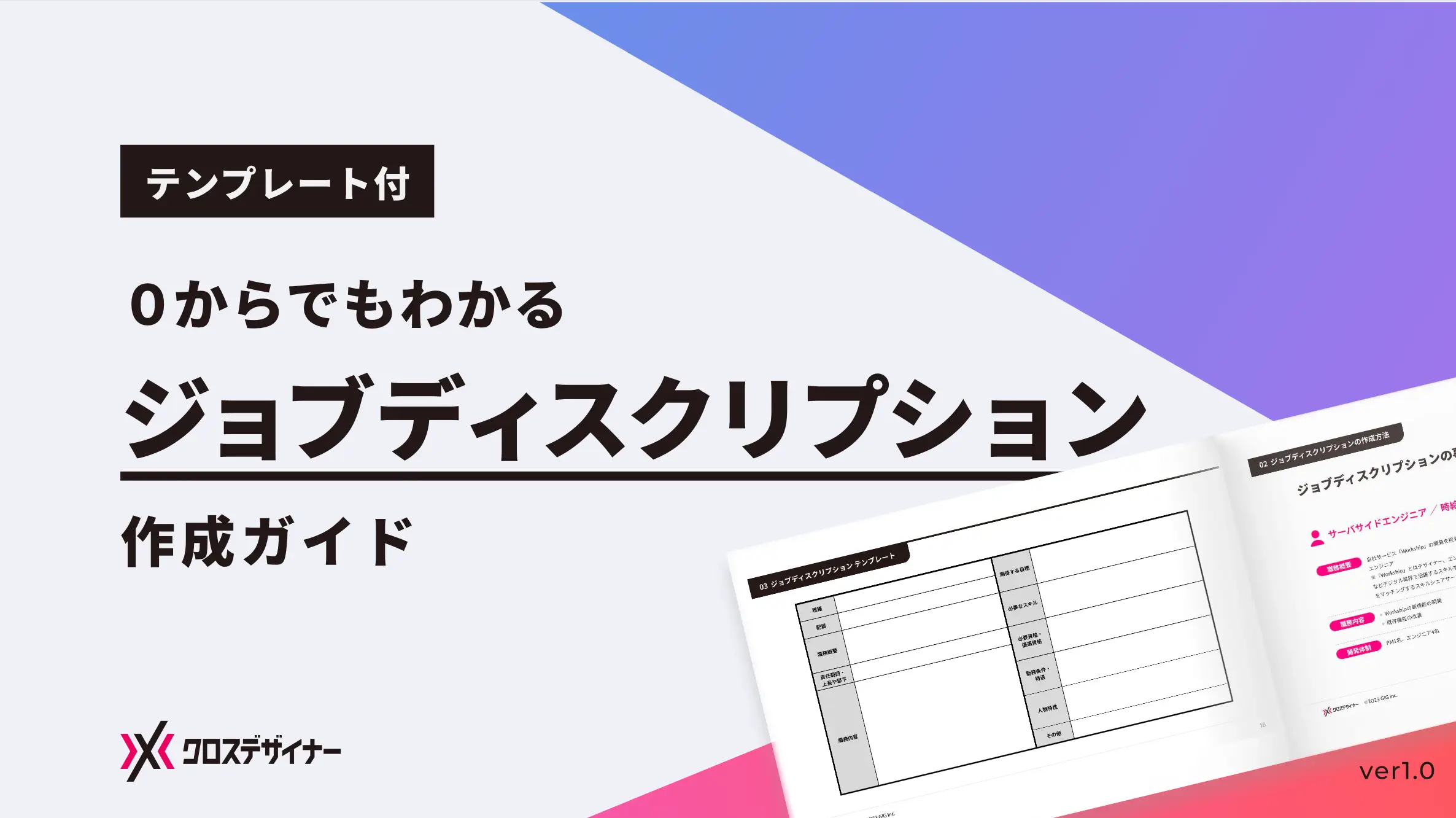
スポット依頼など柔軟に発注できる
正社員採用だけでなく、短期間のプロジェクトや一部業務のみを依頼するスポット的な発注も可能です。
たとえば、インクルーシブ対応を見直す段階だけUIデザイナーに参加してもらうなど、柔軟なリソース活用ができます。限られた予算でも外部の専門知見を取り入れることができ、非常に効率的です。
エージェントを活用する場合、基本的には業務委託契約です。正社員で採用するのとどちらがコストを抑えられるのか気になる人もいるでしょう。
以下の資料では採用コストについてまとめています。無料でダウンロードが可能です。

双方の合意があれば正社員採用もできる
フリーランスや業務委託からスタートした場合でも、パフォーマンスや相性を見ながら、正社員登用を視野に入れることも可能です。
エージェントによってはそのまま採用への移行をサポートしてくれる仕組みがあるため、長期的に活躍してもらいたい場合にも安心して依頼できます。
フリーランスとの業務委託契約はエージェントがサポートしてくれますが、自社でもある程度ノウハウをもっていると、よりスムーズです。以下の無料で配布している資料は、業務委託契約のテンプレートを配布中です。丸投げにせず、体制作りの一貫として理解を深めたい方はぜひダウンロードしてご利用ください。

インクルーシブデザインを依頼できるデザイナーをお探しならクロスデザイナーにご相談ください
インクルーシブデザインは、年齢や障がいの有無、文化的な背景などを問わず、すべての人々が心地よく利用できる体験を目指すデザインを指します。
Webサイトやプロダクトなどのビジュアルデザインは、インクルーシブデザインを目指して制作することで、すべての人により良い体験を提供することが可能です。
インクルーシブデザインに対応できるデザイナーをお探しなら『クロスデザイナー』へご相談ください。
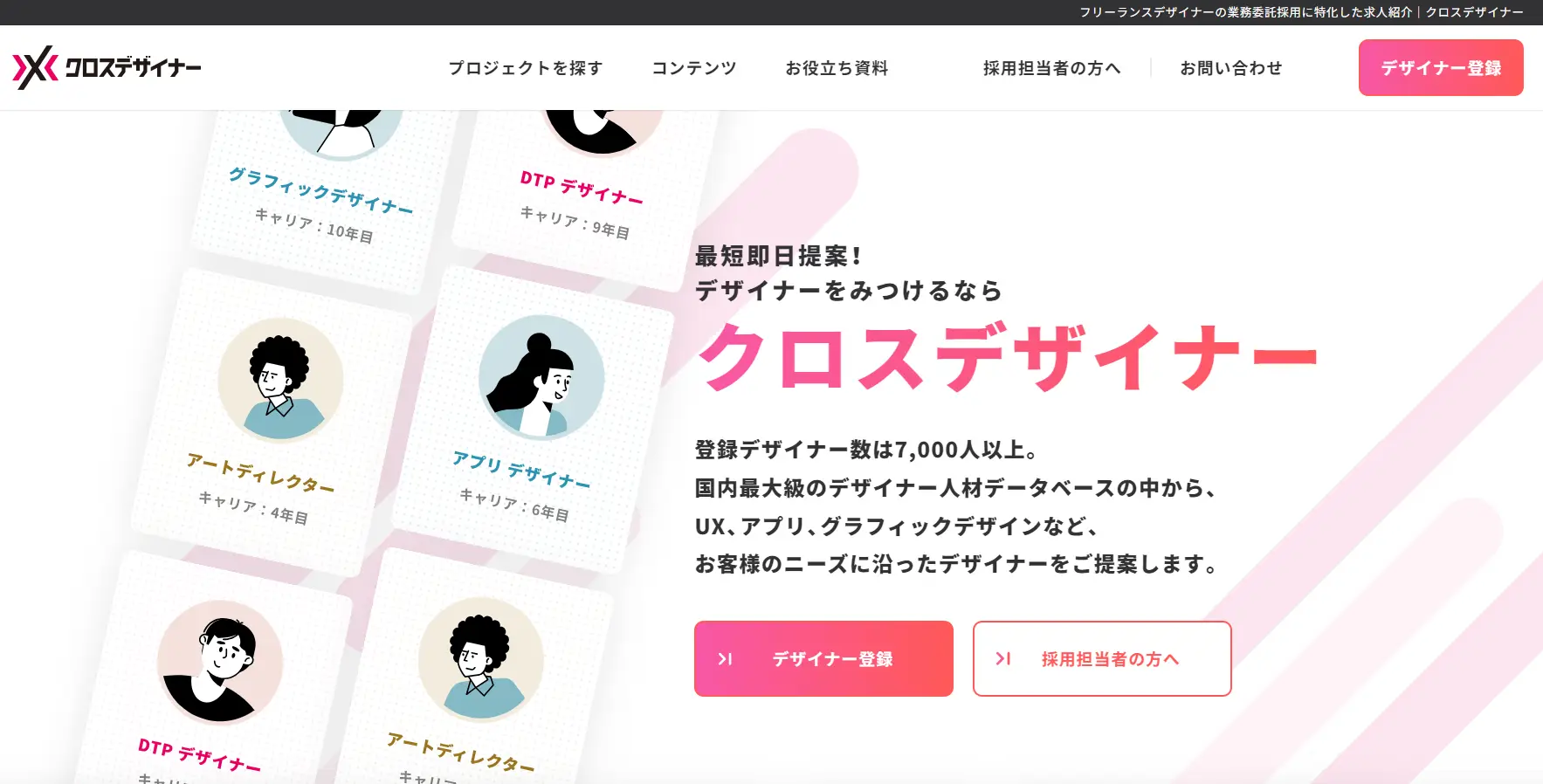
『クロスデザイナー』では、国内最大級のデザイナーが在籍しており、その経歴やデザイナーの種類もさまざまです。また、登録には厳正な審査が必要なため、ハイスキルなデザイナーが多く在籍しています。
以下では、クロスデザイナーに登録しているデザイナーのスキルや得意分野をご覧いただけます。無料でダウンロード可能なので、ぜひご活用ください。
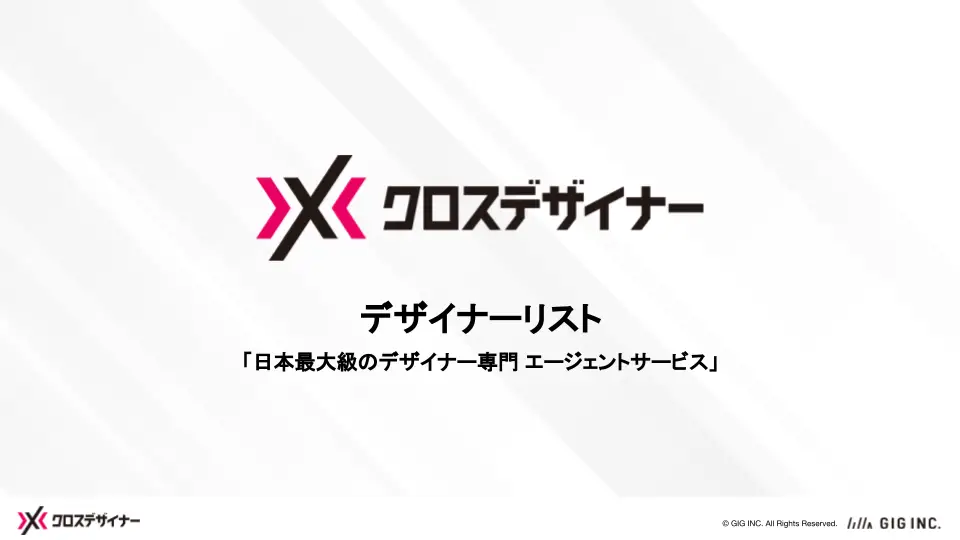
さらに、登録しているデザイナーと合意があれば正社員採用もできます。スカウトや人材紹介機能もあるため、採用難易度の高い、即戦力デザイナーの採用機会を最大限サポートしています。
エージェントに相談いただければ、最短3営業日でのアサインも可能です。また、週2〜3日の柔軟な依頼も可能なので、自社の作業量に応じて効率的に外注することが可能です。
こちらよりサービス資料を無料でダウンロードできます。即戦力デザイナーをお探しの方は【お問い合わせ】ください。平均1営業日以内にご提案します。
- クロスデザイナーの特徴
- クロスデザイナーに登録しているデザイナー参考例
- 各サービスプラン概要
- 支援実績・お客様の声
Documents