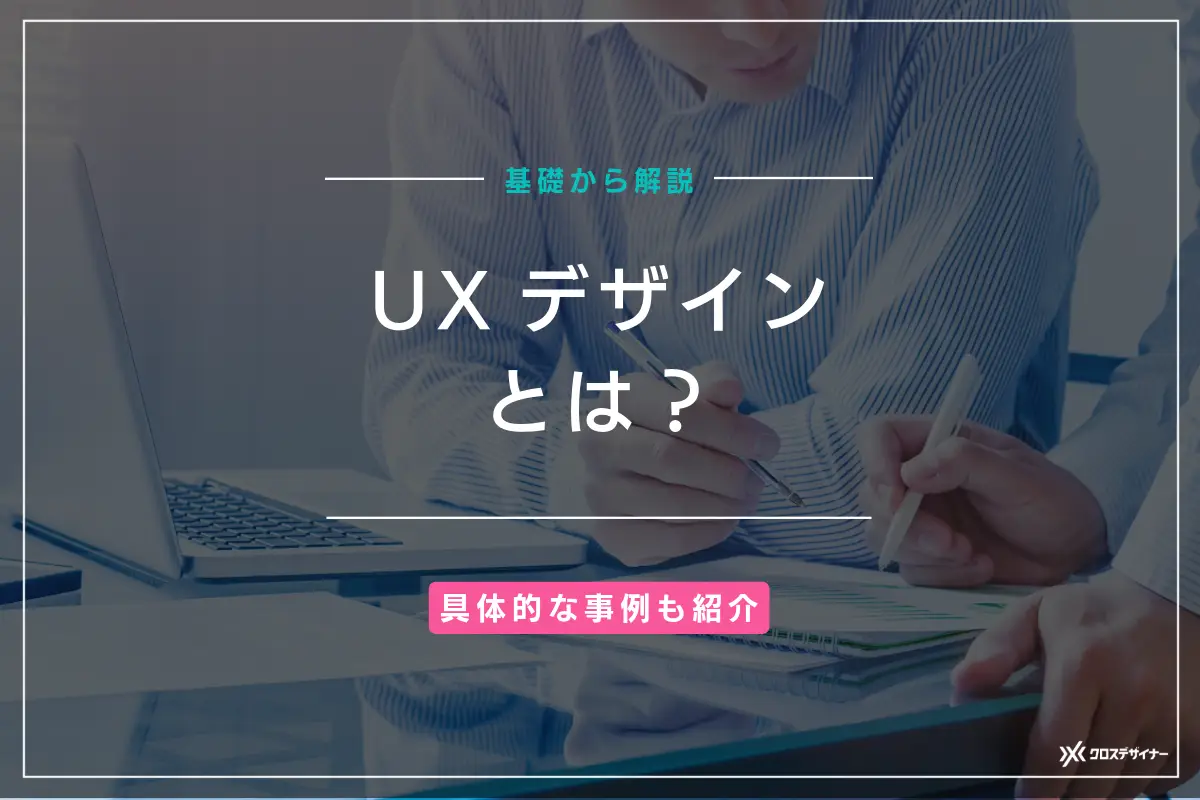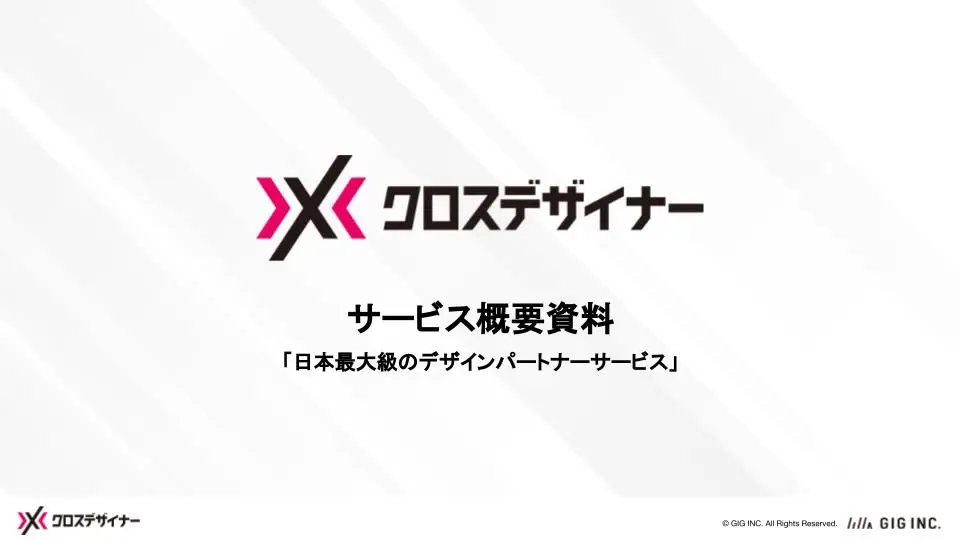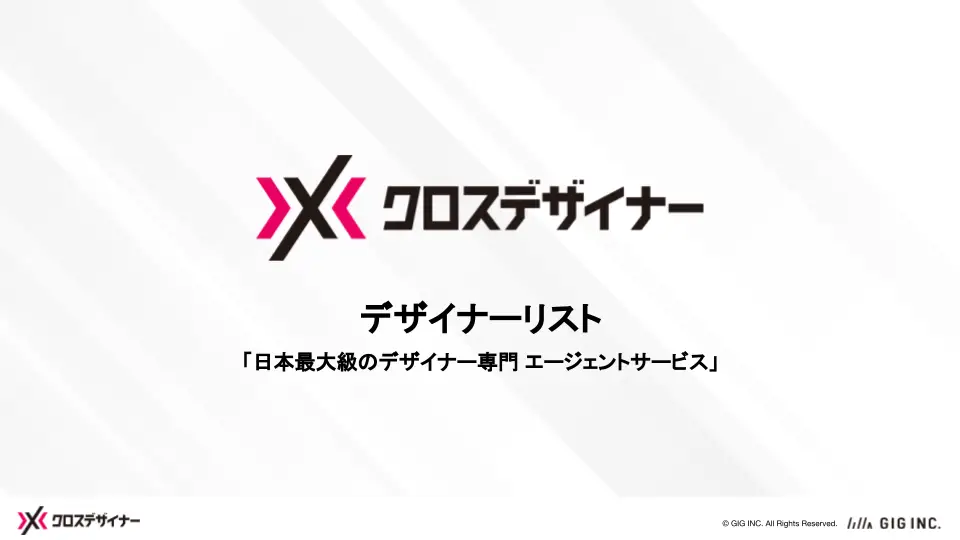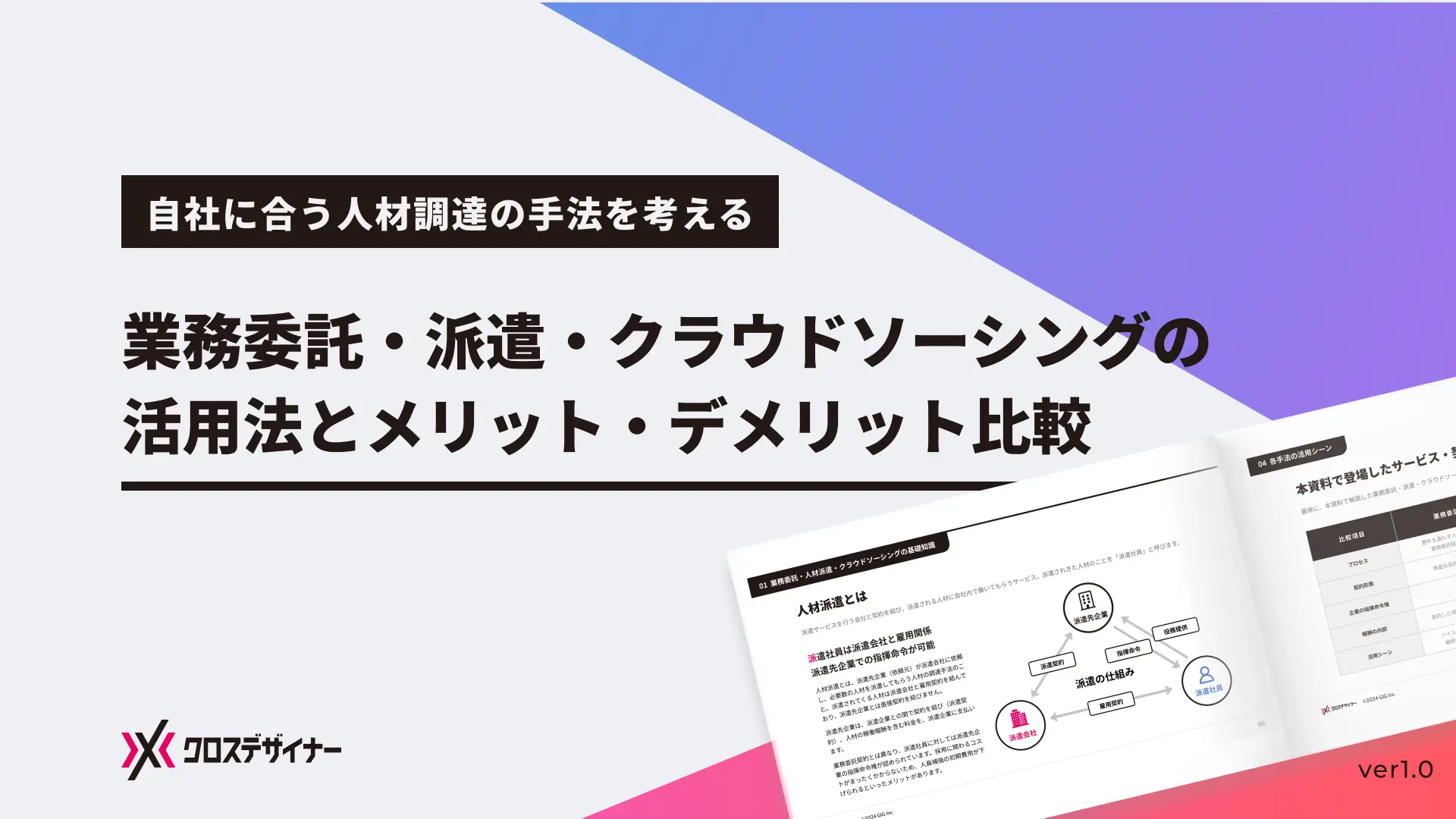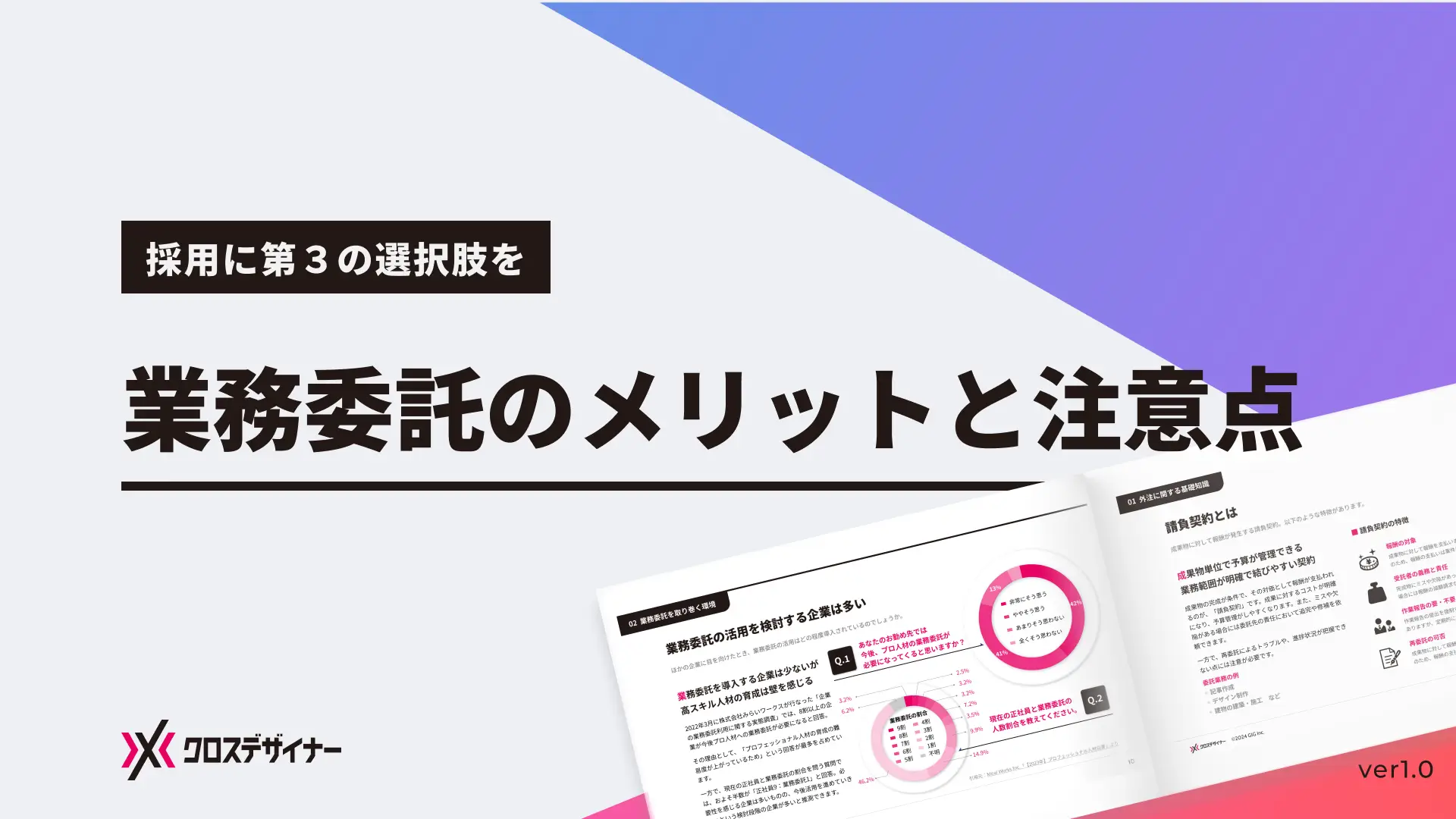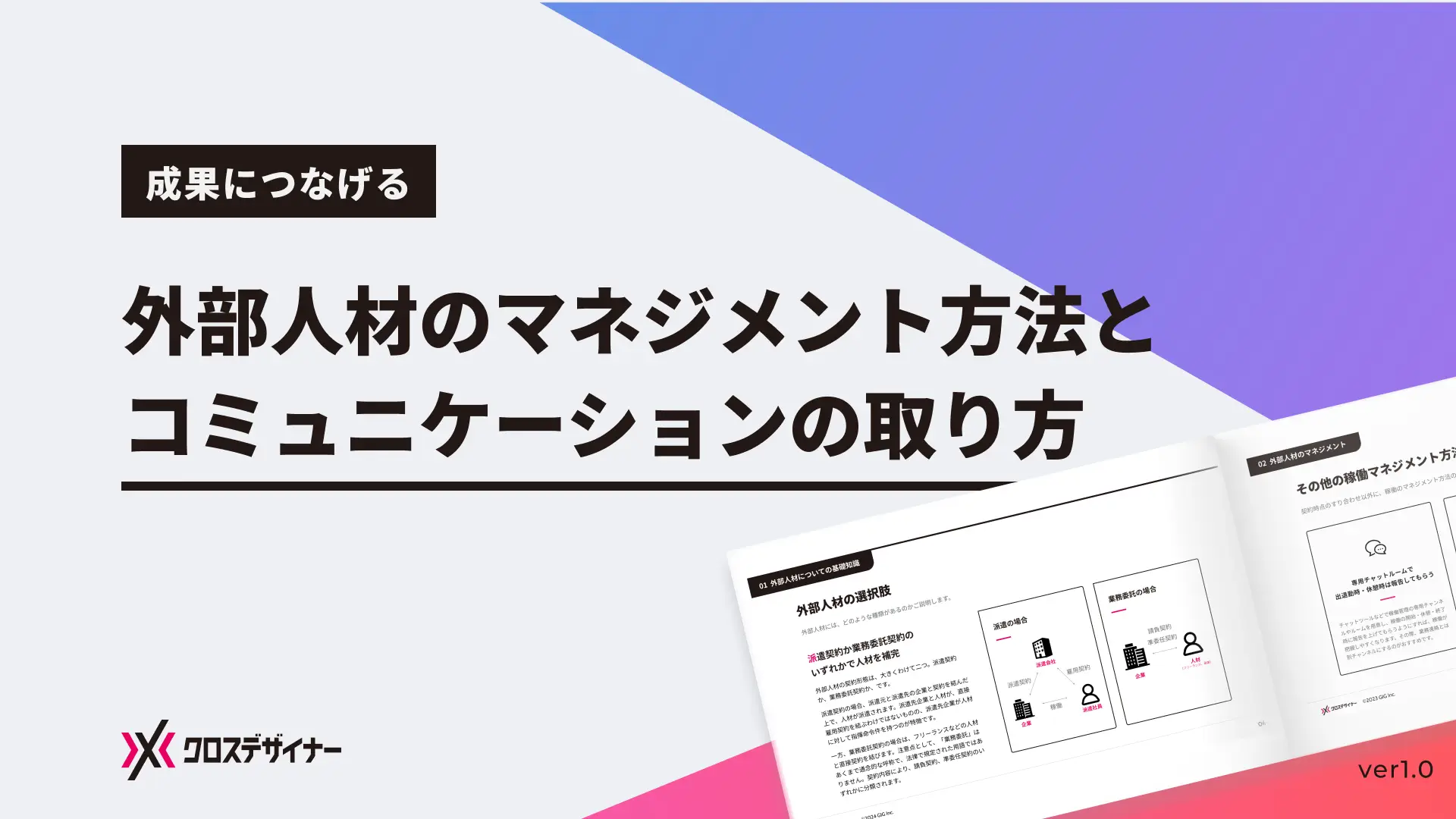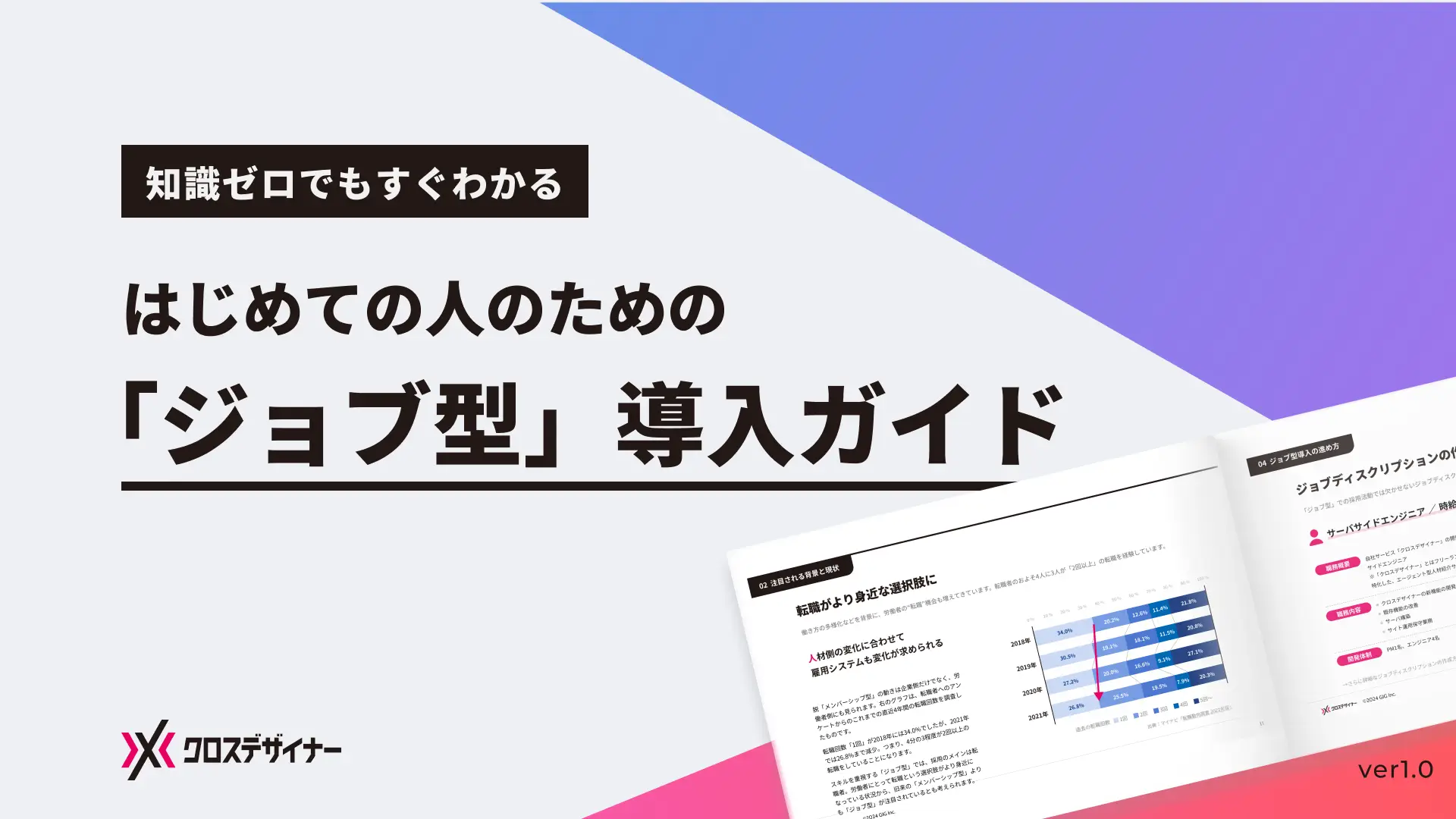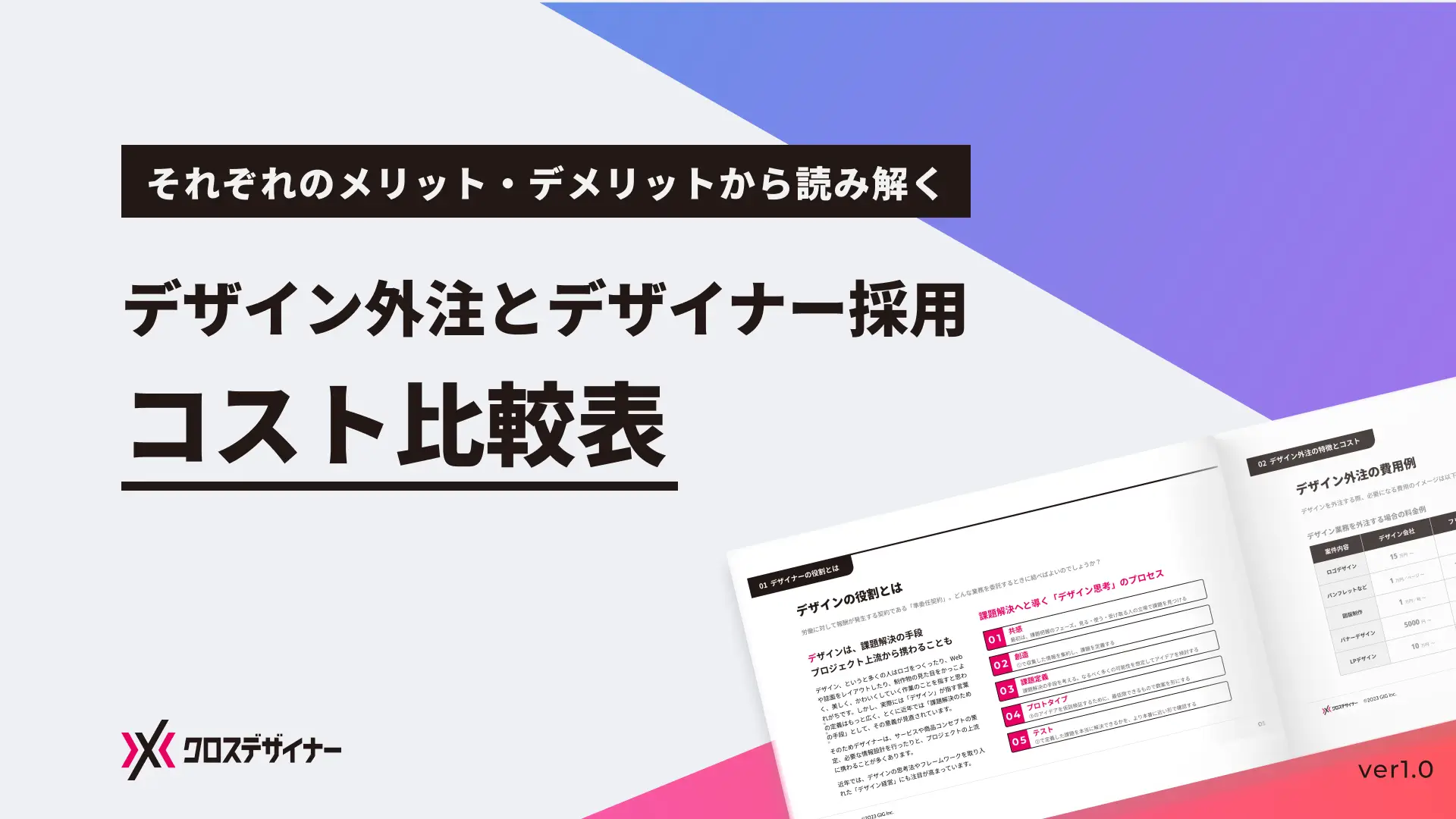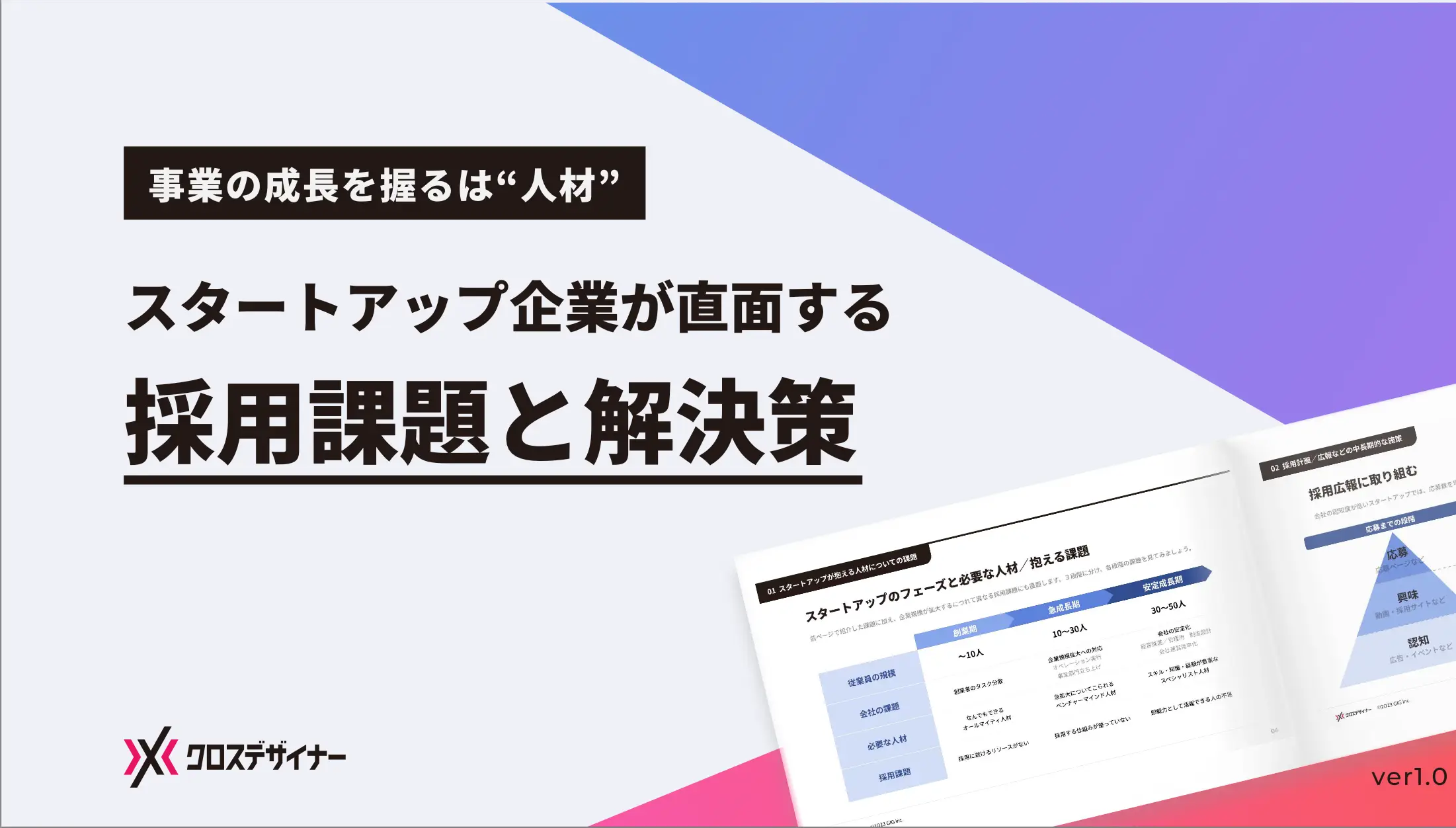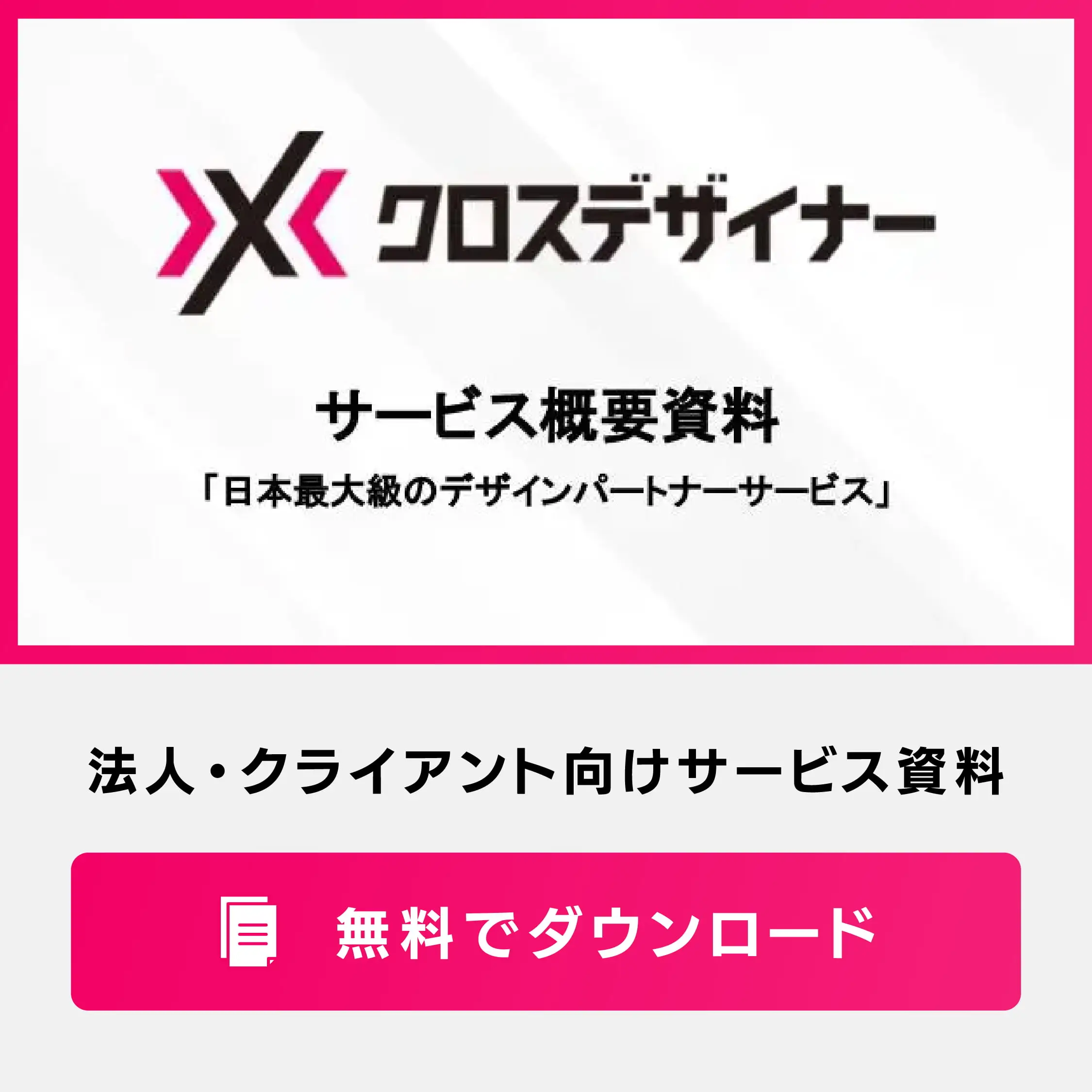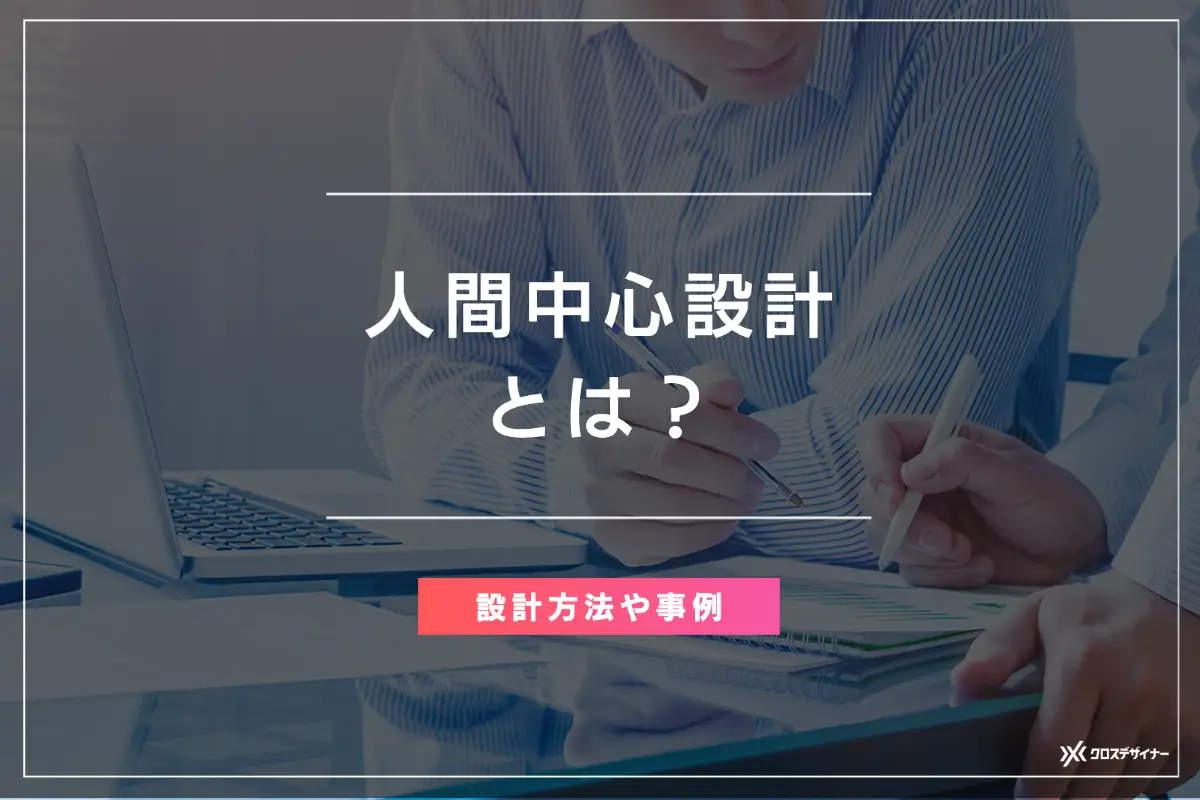
UXデザイナーは、ユーザーの体験全体を設計し、より使いやすく・心地よいプロダクトをつくる職種です。リサーチや情報設計、デザインだけでなく、チームとの協働や課題解決力も求められます。
近年では、Webデザイナーやエンジニア、ディレクターなどがスキルを活かしてUX領域へキャリアを広げるケースも増えています。
本記事では、UXデザイナーの仕事内容や求められるスキル、未経験からの転職ステップを解説します。将来性やキャリアパス、案件の探し方などもまとめました。
UXデザイナーとは
UXデザイナーとは、ユーザー体験(UX:User Experience)を設計するデザイナーです。見た目の美しさや操作性を整えるのではなく、「ユーザーがどう感じ、どのような行動をとるか」までを想定してプロダクト全体をデザインします。
たとえばアプリやWebサイトを使うとき、迷わず目的を達成できたり、「使いやすい」と感じられる体験を生み出すのがUXデザイナーの役割です。
UXデザインのプロセスは、ユーザーリサーチから課題発見、情報設計、UIデザイン、テスト・改善まで多岐にわたります。
つまり、UXデザイナーはデザイナーでありながら、マーケティングや心理学、エンジニアリングなど複数の領域を横断するポジションでもあります。
「人にとって心地よい体験を、ビジネスとして成立させる」この両立を図るのがUXデザイナーの使命です。
UIデザイナーとの違い
UXとUIはよく混同されますが、担当範囲が異なります。UIデザイナーは、画面上のボタンや色、レイアウトなど見た目と操作部分をデザインします。UXデザイナーは、ユーザーがプロダクトを通してどのような体験を得るか全体を設計する立場です。
たとえばUIデザイナーが「どんなボタンをどこに配置するか」を決めるなら、UXデザイナーは「ユーザーがそのボタンを押すまでの行動や感情」を設計します。UXデザイナーが定めた体験設計をUIデザイナーが具現化する流れでプロダクトが完成します。
関連記事:UIデザイナーに必要なスキルとは?UXデザイナーとの違いも解説
関連記事:UIとUXの違いとは?重要性や設計ポイント、外注のメリットも解説
UXエンジニアとの違いと関係
UXエンジニアとUXデザイナーは、どちらも「設計者」という点では共通しています。ただし、その出発点と得意領域が異なります。
UXデザイナーは、人の行動や感情から体験を設計する「体験の設計者」であり、どのような場面で、どのような気持ちで使われるかを想定し、理想的な体験の流れを描きます。
UXエンジニアは技術や構造から体験を形にする「仕組みの設計者」です。デザイナーが描いた設計図をもとに、どの技術を使えばそれをもっとも自然に再現できるかを考え、コードで実装します。
たとえばUXデザイナーが「操作を2ステップに減らしてユーザーのストレスを軽減したい」と考えたとき、UXエンジニアは「それをどんなUI構造やアニメーションで実現できるか」を探ります。
近年では、デザイナーが技術を理解し、エンジニアが体験を意識するケースも増えています。互いの思考を理解し合うことで、より洗練されたユーザー体験を作り出すことが可能です。
関連記事:エンジニアとデザイナーのスキルをもつ職種と仕事内容|採用するメリットも解説
UXデザイナーの仕事内容
UXデザイナーの仕事は、ユーザーが製品やサービスを通じて「快適に目的を達成できる体験」を設計することです。
そのために、プロジェクトの初期からリリース後まで、多様な工程に関わります。ここではUXデザインの6つの主要プロセスを、実際の仕事の流れに沿って紹介します。
1. 調査・分析で課題を見つける
現在のプロダクトがどのように認知されているのか、ユーザーは何を考えているのかなど市場調査を実施します。プロダクト開発にあたって欠かせない調査がUXリサーチです。
インタビューなどの定性調査とアクセス解析などの定量調査から得た結果をもとに、仮説を立てて改善策を立てていきます。具体的なUXリサーチのやり方は下記の記事で解説しています。
関連記事:UXリサーチとは?具体的な手法や実施のポイントを解説
関連記事:UXデザインで必須のユーザーテストとは? やり方とメリットを解説!
2. 要件定義とチーム連携をおこなう
クライアントやチームメンバーと仮設や各要件のすりあわせを行います。より良いユーザー体験を設計するために、どのような機能やコンテンツが必要なのか、分析結果をもとに洗い出していくフェーズです。
カスタマージャーニーマップを作成することで、ユーザー視点をもちやすくなります。クライアントとチームでコミュニケーションを取りながら進めていきます。ユーザーストーリーマッピングなども活用が可能です。
関連記事:カスタマージャーニーマップとは?作り方と4ステップを紹介
3. ワイヤーフレームで情報を設計する
2のフェーズで洗い出した機能やコンテンツをワイヤーフレームに落とし込んでいきます。ユーザーが一番求めている情報は何か、優先順位を決めてWebサイトの設計図を作成するフェーズです。
ここではビジュアルを作りこまず、要素の配置やコピーなどを明確にすることだけに注力します。ユーザーの行動を考えながら決めることが大切です。
紙に書く方法もありますが、クライアントと共有がしやすいツールもあります。下記の記事で便利な機能を備えたワイヤーフレームツールを紹介していますので、参考になさってください。
関連記事:UXデザインでよく使われるフレームワーク19選を目的別に解説
関連記事:おすすめのワイヤーフレームツール9選を紹介!特徴と機能を一覧で徹底解説
4. プロトタイプで体験を再現する
完全にデザインに落とし込む前に、プロトタイプを作成します。ワイヤーフレームでは定まっていなかった色や形などデザインを追加します。必要であればボタンを押したときに遷移するといった機能も付けて、テストを実施します。
テストはユーザーに実際に使ってもらうユーザビリティテストを実施することもあれば、2パターンのデザインを実際に稼働させるABテストなどの評価方法があります。テストを実施することで新たな課題の発見が可能です。
プロトタイプの作成方法や役立つツールについては、下記の記事でくわしく解説しています。
関連記事:Webデザインのプロトタイプとは?作成方法やおすすめツールを紹介
5. デザインを制作する
具体的にビジュアルデザインを作りこんでいくフェーズです。マイクロコピーなど、ユーザーに正確にわかりやすく伝わるように整えていきます。最高のユーザー体験を提供するため、わかりやすいコピーを検討してください。ボタンなどの色や形状にもこだわることが大切です。
チームで進めていくうえで欠かせないのがデザインガイドラインです。下記ではデザインガイドラインの作り方と注意点について解説しています。
関連記事:デザインガイドラインとは?作り方5ステップと基本項目9つ、3つの注意点を解説
6. テストと改善をくり返して成果を高める
デザインを作成したら終了というわけではありません。プロダクトに対するニーズやデザインは時代とともに変化します。完成後もデータを収集し、ブラッシュアップをくり返すことが大切です。
プロダクト開発に欠かせないユーザーテストやABテストについては、下記の記事でくわしく解説しています。ぜひ参考になさってください。
関連記事:UXデザインで必須のユーザーテストとは?やり方とメリットを解説!
関連記事:ABテストとは?サイト改善に導く方法とおすすめツールを解説!
UXデザイナーに求められるスキル
UXデザイナーには、デザイン力だけでなく「人を理解し、体験を設計する力」が求められます。業務範囲が広いため、調査・設計・協働など多角的なスキルが必要です。ここでは、UXデザイナーとして欠かせない5つのスキルを紹介します。
1. ユーザーリサーチスキル
UXデザインの出発点は「ユーザーを理解すること」です。インタビューやアンケート、データ分析などを通して、ユーザーの行動・感情・課題を把握する力が求められます。
どれだけ優れたデザインを考えても、実際のユーザー理解が浅ければ的外れな体験になってしまいます。課題の背景を読み解き、本質的なニーズを発見するスキルは、UXデザイナーの基本です。
関連記事:UXリサーチとは?具体的な手法7つや実施のポイントを解説
関連記事:デザインリサーチとは?ユーザーの潜在的ニーズを探る革新的な手法や目的、活用事例などを紹介
2. 分析・情報設計力
収集したデータや調査結果を整理し、体験全体の構造を設計する力が求められます。ユーザーの目的や行動パターンを分析し、情報をどの順で・どの深さで伝えるかを設計します。
このとき役立つのが、カスタマージャーニーマップやユーザーフローなどのフレームワークです。
また『Figma』『Adobe XD』などの設計ツールを活用して情報を可視化し、チーム全体で理解を共有することもポイントです。情報を正しく構造化する力が、ユーザーが迷わず目的を達成できるUXを支えます。
関連記事:UI/UXの分析・リサーチツール20選と費用や活用方法までを徹底解説
3. コミュニケーション能力
UXデザイナーはクライアントやチームとの関わりも深く、多くの議論を重ねる機会が多いため、コミュニケーション能力は必須です。対話に関する基本的なコミュニケーション能力だけではなく、クライアントの意図をくみ取る能力も求められます。
またプロトタイプを共有するときは、共有機能を備えたツールを使用するのが一般的です。チャットツールなどテキストコミュニケーションが中心となることも多いため、テキストでのコミュニケーションスキルも備えていると重宝されるでしょう。
関連記事:即戦力のデザイナーを採用するには?探し方とおすすめサービス5選
4. マネジメントスキル
UXデザイナーはプロジェクトチームを動かし、計画を進める役割をもっていることも多く、マネジメント力をもっている人は重宝されます。チームを率いるリーダーシップというよりも、進捗管理の役割が強いです。メンバー一人ひとりが主体的に動いてくれる組織体制を作るためのサポートを行います。
それぞれに目標を設定し、達成に向けてチームを主導していくのは大変な作業です。適切なサポートを行うためにも、UXデザイナーはさまざまな情報を集め、コミュニケーションを図り組織をデザインしていくマネジメント力が求められます。
関連記事:デザインマネージャーの役割とは?採用するためのポイントも紹介
関連記事:【企業向け】デザインリードとは?役割や採用方法をご紹介
5. デザイン思考
UXデザイナーの根底にあるのが「デザイン思考」です。課題を解決するために、ユーザー視点で考え、試し、改善をくり返す姿勢を指します。
とくに重要なのが共感力。ユーザーの感情や行動の背景を理解し、「なぜそう感じるのか」を探ることからすべてが始まります。
共感によって見えてくる“隠れた課題”を起点に、アイデアを発想し、検証していくプロセス全体がデザイン思考です。この考え方を実践することで、単なる見た目の改善ではなく、ユーザーの心に残る体験を生み出せます。
関連記事:デザイン思考とは?活用シーンやメリット、5つ実践プロセスから効果的な鍛え方までを徹底解説
関連記事:デザイン思考を実践するときに役立つフレームワーク10選
未経験からUXデザイナーになるには
UXデザイナーは、異なる職種からの転職・キャリアアップを目指しやすい職種です。Webデザイナーやエンジニア、ディレクター、グラフィックデザイナーなど、既に持っているスキルを活かせる要素が多く、専門的な学習を重ねれば十分に目指せます。ここでは、それぞれの職種からUXデザイナーを目指す場合の特徴とステップを紹介します。
グラフィックデザイナーから転職
グラフィックデザイナーは、広告や紙媒体などのビジュアルデザインを通じてブランドを表現する職種です。UXデザイナーへの転職に向いているのは、見た目の美しさだけでなく、使う人の体験までをデザインしたい人です。
転職を目指すなら、次のスキルを意識的に伸ばしましょう。
- デジタルデザインツールの操作
- 情報設計やユーザーフロー設計の理解
- UXリサーチ・ペルソナ設計
グラフィックデザインで培った表現力やブランド理解を活かしつつ、デジタル上での体験を設計する視点を身につけることがUXデザイナーへの転職を成功させる第一歩です。
関連記事:グラフィックデザイナーの転職エージェント おすすめ9選を紹介
Webデザイナーから転職
Webデザイナーは、企業サイトやサービスサイトなどの設計・デザインを担う職種です。UXデザイナーに向いているのは、見た目の美しさよりも「使いやすさ」「導線のわかりやすさ」に関心がある人です。
UXデザイナーを目指すなら、以下のスキルを強化しましょう。
- ユーザーリサーチ・テストの実践
- アクセス解析やヒートマップの分析
- 情報設計・カスタマージャーニーマップ作成
Webデザインの経験を活かし、データとユーザー行動をもとに改善を提案できるようになると、UX設計者としての評価が高まります。
関連記事:デザイナーのキャリアパス9選|市場価値が高い職種やスキルも解説
UIデザイナーからキャリアアップ
UIデザイナーは、アプリやシステムの操作画面を設計し、ユーザーが直感的に使えるデザインを形にする職種です。UXデザイナーに向いているのは、UI設計を超えて「ユーザー体験全体を設計したい」と考える人です。
キャリアアップのためには、以下のスキルを身につけましょう。
- UXリサーチ
- 課題設定・仮説検証のプロセス
- プロトタイピング・ユーザーテスト
UIデザイナーで培った操作性・構成力を活かし、体験全体を俯瞰して設計できるようになることで、UXデザイナーとしての幅が広がります。
Webディレクターから転職
Webディレクターは、Web制作全体を管理し、進行・品質・成果を統括する職種です。UXデザイナーへの転職に向いているのは、進行管理だけでなく「ユーザー視点で課題を解決する設計」に関心がある人です。
転職を考えるなら、次のスキルを磨くと良いでしょう。
- ユーザーリサーチ・課題定義スキル
- UX設計フレームワークの理解
- 人間中心設計(HCD)資格やUX理論の学習
ディレクションで培った俯瞰力に、ユーザー視点での課題解決力を加えることで、UXデザイナーとしての企画力が強みになります。
関連記事:デザインディレクションの方法は? 期待通りのデザインを納品してもらうコツを解説
フロントエンドエンジニアから転職
フロントエンドエンジニアは、デザインを実装し、ユーザーが実際に操作する部分を開発する職種です。UXデザイナーへの転職に向いているのは、「どうすればもっと使いやすくできるか」を考えながら実装している人です。
スムーズな転職のためには、以下のスキルを伸ばしましょう。
- UXリサーチ・ユーザビリティテスト
- ワイヤーフレーム・プロトタイピング
- 技術と体験設計をつなぐ思考力
UI実装の知識をもつエンジニアがUXデザインを理解すると、「再現性の高い体験」を生み出せる貴重な人材を目指せます。
関連記事:エンジニアとデザイナーのスキルをもつ職種と仕事内容|採用するメリットも解説
プロダクトマネージャーから転職
プロダクトマネージャー(PdM)は、事業目標に沿ってプロダクトを企画・運営する職種です。UXデザイナーに向いているのは、ビジネスだけでなく「ユーザー体験」から価値を生み出したい人です。
UXデザイナーへステップアップするには、以下のスキルを意識しましょう。
- ユーザーリサーチ・UXリサーチの理解
- 情報設計・ワークショップ設計
- デザインツール(Figma・UXPin)の習熟
課題設定やKPI設計といったPdMの強みを活かし、ユーザーの声を事業戦略へ結びつける力を磨くと、UXデザイナーとしての説得力が高まります。
カスタマーサクセスから転職
カスタマーサクセスは、顧客と直接やり取りしながら課題を解決し、サービス利用を支援する職種です。UXデザイナーに向いているのは、顧客の声をもとにサービスや体験を改善したい人です。
転職を目指すなら、次のスキルを重点的に身につけましょう。
- ユーザーリサーチ・インタビュー設計
- UI/UXの基本知識
- ペルソナ・カスタマージャーニー作成スキル
顧客理解の深さを活かして、ユーザー視点から課題を抽出し、改善提案につなげる力を伸ばすと、UX設計で強みを発揮できます。
UXデザイナーの将来性
UXデザインは一時的な流行ではなく、今後さらに需要が高まる領域です。デジタル化の加速やAI技術の進化により、サービスはますます複雑化しています。
そのなかで「人が快適に使える設計」を担うUXデザイナーは、企業にとって欠かせない存在になりつつあります。
UXデザイナーの需要が高い業界
UXデザイナーの活躍は、もはやWeb制作の領域だけにとどまりません。
モバイル端末の普及により、アプリやデジタルプロダクトの体験を重視する企業が増え、より良い顧客体験を届けるために採用が進んでいます。
特に、SaaS(クラウドサービス)やEC、金融、教育、ヘルスケアなど、ユーザーとの接点を多く持つ分野で需要が高まっています。さらに、行政サービスや医療の現場でもデジタル化が加速しており、「誰もが使いやすい設計」を担える人材が求められています。
求人・転職市場の動向
UXデザイナーの求人数は年々増加しています。とくに「UI/UXデザイナー」や「UXリサーチャー」といった兼任・専門職の募集が増えており、幅広いキャリアパスが用意されていることがわかります。
企業側は「経験年数」よりも、「課題を発見し、プロセスを言語化できる力」を重視する傾向があるため、実務経験が浅くても、リサーチ・検証のプロセスをポートフォリオで明確に示せる人は十分に評価される可能性があります。
年収とキャリアアップの方向性
UXデザイナーの平均年収は538〜631万円とされています。ただし、勤務先や経験・スキルによっては年収1,000万円以上の高年収も珍しくありません。
キャリアアップの方向性としては、UXデザインの上流を担うUXリサーチャーやサービスデザイナー、事業戦略まで踏み込むプロダクトマネージャー(PdM)などが挙げられます。また、UI設計とUX設計の両方を手がけるUI/UXデザイナーとしてのキャリアも目指せます。
UXデザインの経験は、事業づくりやマーケティングなど、他分野でも応用できるスキルセットとして評価されるものです。そのため、幅広い業界・業種での活躍を目指せます。
関連記事:UI/UXデザイナーになるには?仕事内容や求人の特徴を解説
今後求められるUX人材像
これからのUXデザイナーには、AIやデータ分析、エンジニアリングなどの領域と協働できる柔軟さが求められます。
AIがデザイン案を自動生成するようになっても「人がどう感じ、どう動くのか」を理解できるのは人間だけです。ビジネス・テクノロジー・デザインの3つをつなぎ、データや技術を味方にしながら、人の感情や心理を捉え、より良い体験をデザインしていく必要があります。
そのため、UXデザイナーは決してなくなる仕事ではありません。むしろ、人とテクノロジーの間に立ち、体験を豊かにするために進化を続ける職種だといえるでしょう。
関連記事:今、デザイナーに求められていることは?【フラー×GIG】
UXデザイナーへの転職を成功させる方法
UXデザイナーを目指すには、UXの知識を身につけ、実践的な経験を積むことが大切です。ここでは、未経験からUXデザイナーへの転職を成功させるための方法について解説します。
書籍で基礎知識や理論を学ぶ
まずはUXデザインの基本的な概念や考え方を理解することから始めましょう。ユーザー体験とは何か、なぜ重要であるのかを体系的に学ぶことで理解を深めることができます。おすすめの書籍は以下のとおりです。
基礎を本で学ぶことで、リサーチ・情報設計・プロトタイピングなど、UXデザインの全体像をつかむことができます。
関連記事:オブジェクト指向UIデザインとは?タスク指向UIとの違いと設計方法を解説
スクールで実践スキルを磨く
理論を理解したら、次は手を動かして実践スキルを磨きましょう。オンラインスクールや専門学校などでUXデザインについて学ぶことが可能です。実際の課題を通じてリサーチ・設計・検証の一連の流れを体験できます。
講師や受講生とのやり取りを通じて、現場に近いプロジェクト思考を学べる点が大きなメリットです。
スクールは以下のポイントを押さえて選びましょう。
- 実務に近い課題演習があるか
- 講師が現役UXデザイナーか
- ポートフォリオ支援や転職サポートがあるか
実践的な環境で学ぶことで、独学だけでは得られない思考力を養うことができます。
ポートフォリオを制作する
UXデザイナーの採用では、完成したデザインよりもプロセスの可視化が重視されます。そのため、ポートフォリオには成果物だけでなく、課題設定・仮説立案・検証・改善の流れをていねいにまとめましょう。
未経験者の場合は、自主制作や架空の案件でも構いません。ユーザーリサーチから体験設計までのプロセスを再現できれば、考え方や分析力を評価してもらえます。
スクールや個人プロジェクトで制作した内容を整理し、「なぜそう考えたのか」を説明できる構成に仕上げることがポイントです。
関連記事:デザイン思考とアート思考の違いは?ビジネスで必要とされる理由も
副業で小規模案件を受けてみる
学んだ知識やスキルを実践で確かめるには、副業として小規模案件を経験するのがおすすめです。クラウドソーシングサイトや知人経由の依頼など、まずはリサーチや改善提案といった部分的な関わりから始めても問題ありません。
実際のクライアントと接点を持つことで、ユーザーとビジネスの両面を理解する感覚が身につきます。小さな経験でも「実務での検証・改善経験」として転職活動で大きな強みになります。
関連記事:【フリーランス向け】デザイナーの案を獲得するポイントや注意点、おすすめサービスまで徹底解説
UXデザイン案件の獲得はエージェントを活用しよう
UXデザイナーとして経験を積むには、実務の機会を得ることが大切です。しかし、経験が浅いと個人で案件を探すのは難しいでしょう。そのようなときに頼りになるのがエージェントサービスです。UXデザインの案件獲得にエージェントを活用するメリットを紹介します。
スキルにあった案件を提案してくれる
UXデザインの案件は、リサーチ中心のものからアプリ全体の体験設計まで幅広く存在します。エージェントは登録時のスキルや経験をもとに、レベルに合った案件を提案してくれるため、無理なく実務経験を積むことが可能です。
自分では気づかない強みを活かせる案件を紹介してもらえるのも大きな魅力です。さまざまな案件を通して成長する機会が得られます。
契約まわりからサポートを受けられる
フリーランスとして案件を受けるときは、契約や報酬交渉、納品スケジュールなどの実務に着手するまで手間がかかるものです。エージェントを利用することで、これらの手続きを代行してもらえるため、デザイン業務に集中できます。
また、契約後も定期的なフォローがあり、困ったときに相談できる体制が整っているのも安心です。「初めての業務委託で不安がある」「クライアントとのやり取りに慣れていない」という人にとっても大きなメリットがあるでしょう。
双方合意もと正社員転換も目指せる
エージェントによっては、正社員への転換をサポートしています。一定期間、業務委託として実務を経て、企業・デザイナー双方が納得したうえで正社員化される流れです。
実際の案件を通じて企業の文化やチームとの相性を見極められるため、転職ミスマッチを防ぐことができます。副業から始めて本格的なキャリアに発展させるといった柔軟な働き方ができるのも、エージェントを利用するメリットといえます。
関連記事:「フリーランスの約35%が正社員転換を検討」フリーランス・副業向けマッチングサービス『Workship』がキャリア動向調査を実施
UXデザイナーとして活躍を目指すならクロスデザイナーがおすすめ
UXデザイナーはプロダクト開発において、クライアントの課題の発見やより良い体験を提供するために、マーケティングやデザインなどさまざまなスキルが必要です。デザイナーはどこで仕事をするかによって身につけられるスキルも変わるため、UXデザイナーとして活躍を目指すなら働く環境を重視している人も多いことでしょう。
フリーランスデザイナー専門のエージェントサービス『クロスデザイナー』は、UI/UXデザイナーをはじめ、Webデザイナーやグラフィックデザイナーなど多様な職種のプロジェクトを掲載しています。アプリデザインやコーディングなど、対応領域で絞り込んで探せるためスキルに見合った仕事探しにおすすめです。
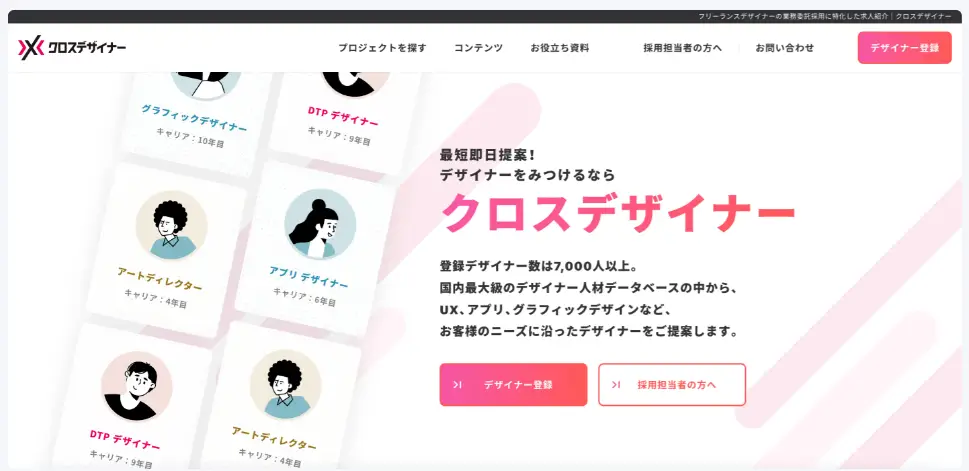
ご興味のある方は、以下よりクロスデザイナーにご登録ください。利用料はかからず、登録次第スタッフよりヒアリングを行わせて頂きます。
- 案件へのエントリー
- エージェントへの相談
- ポートフォリオの登録
- エージェントからの案件紹介
Documents