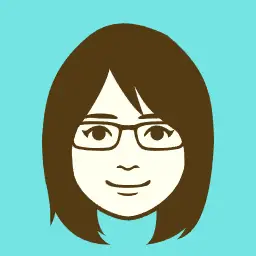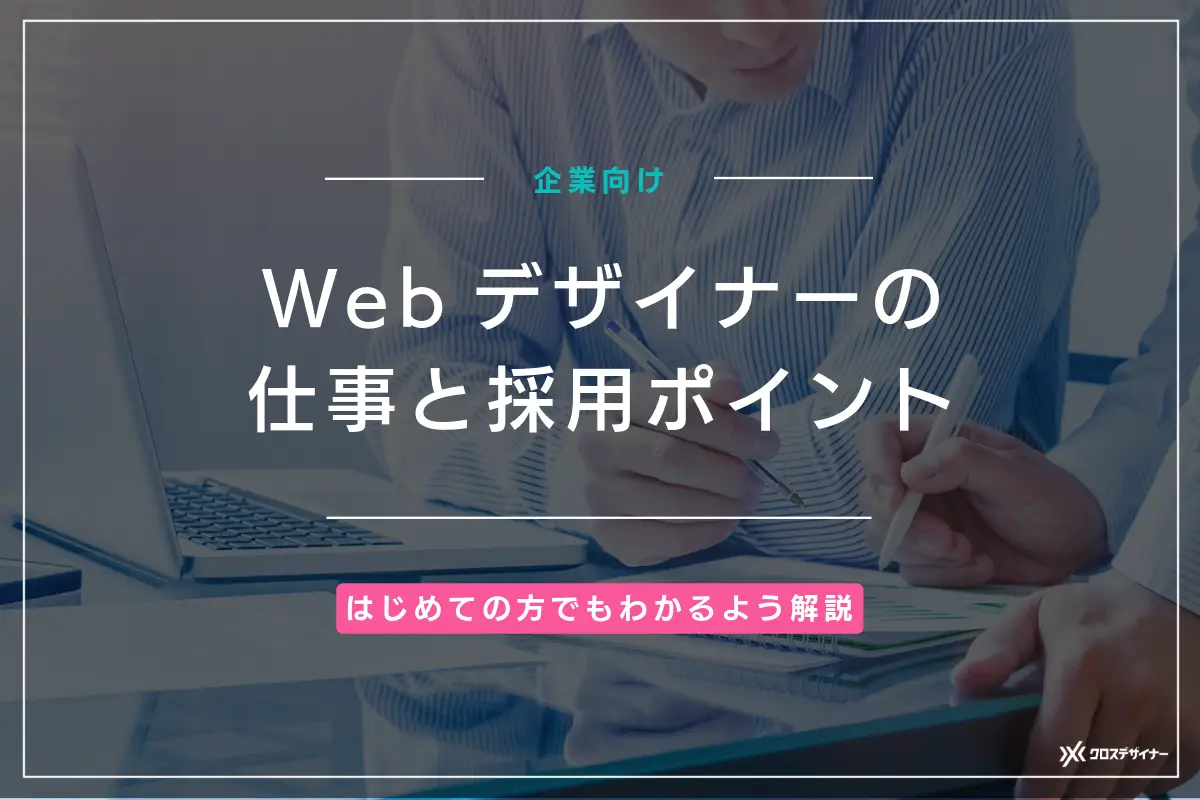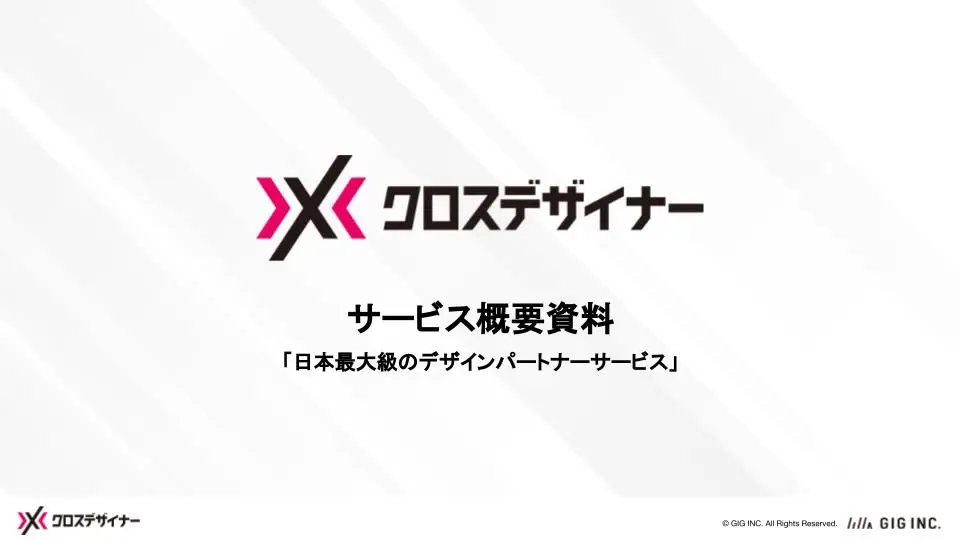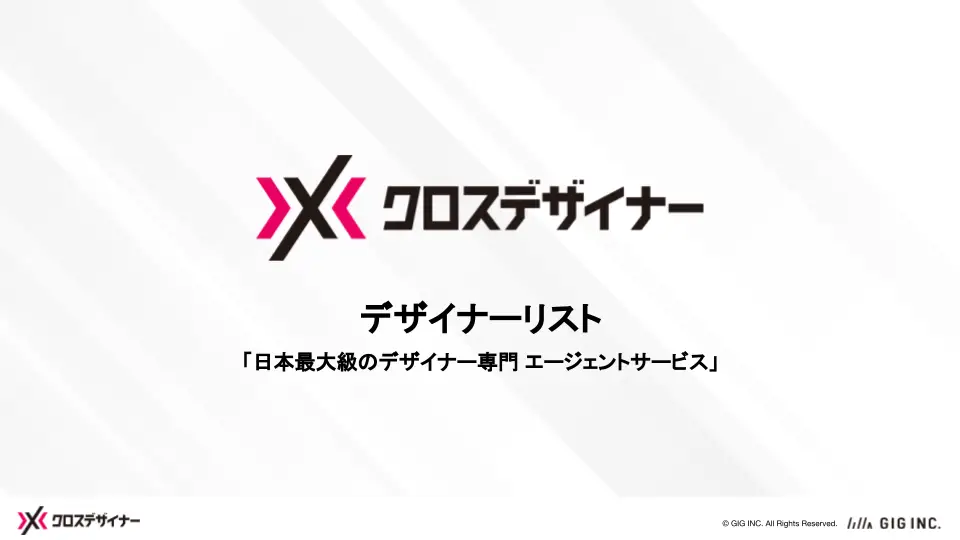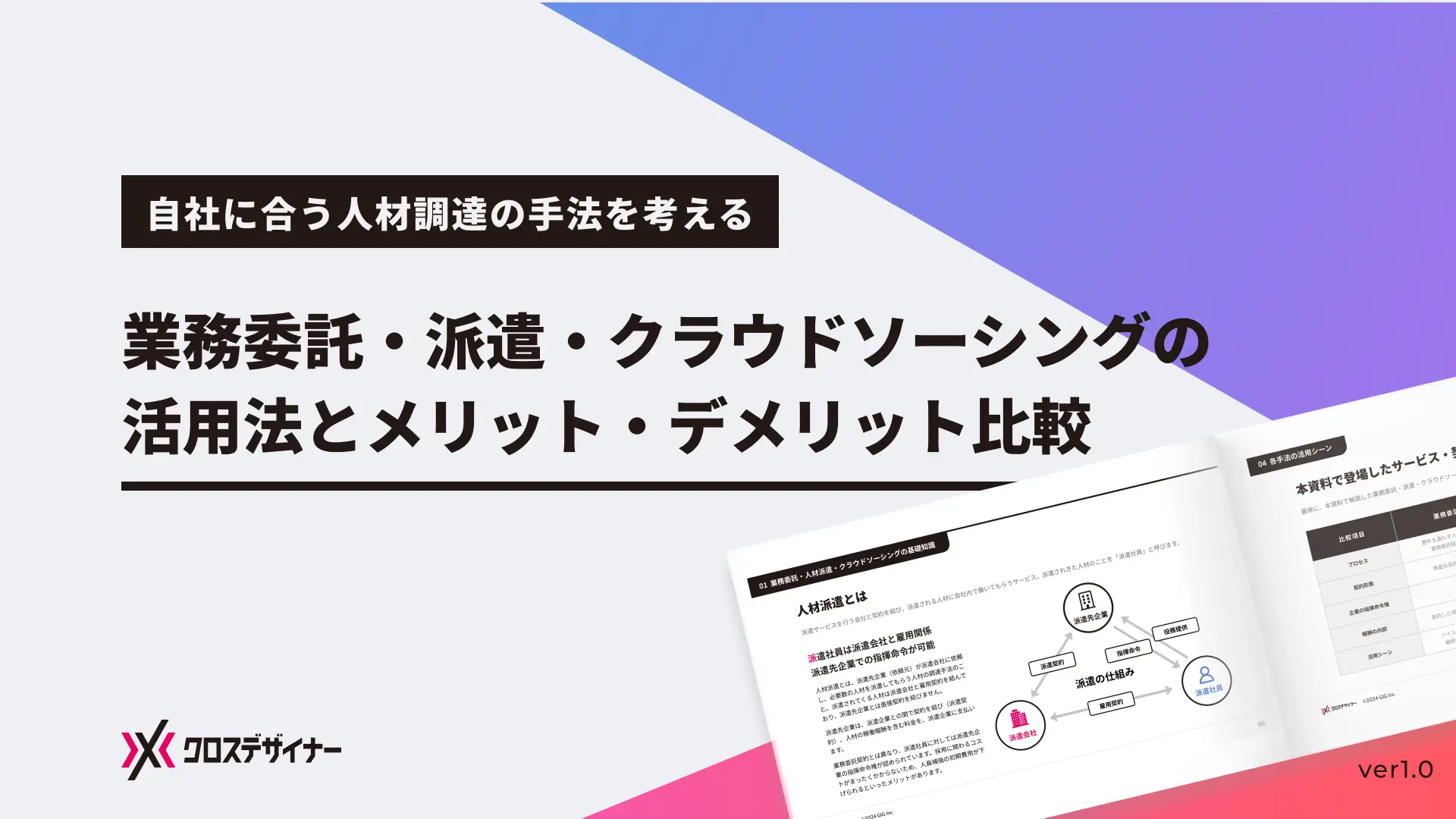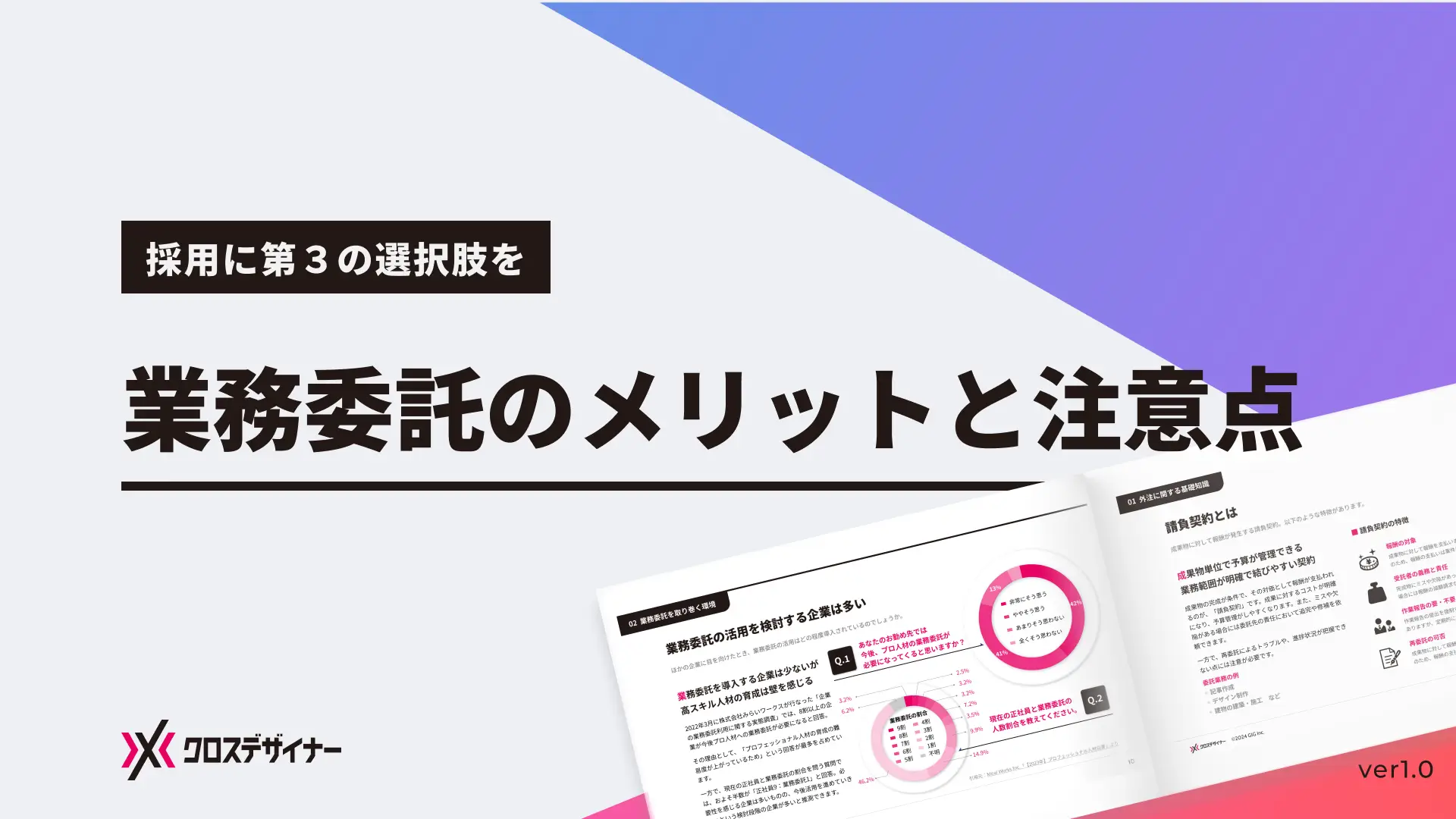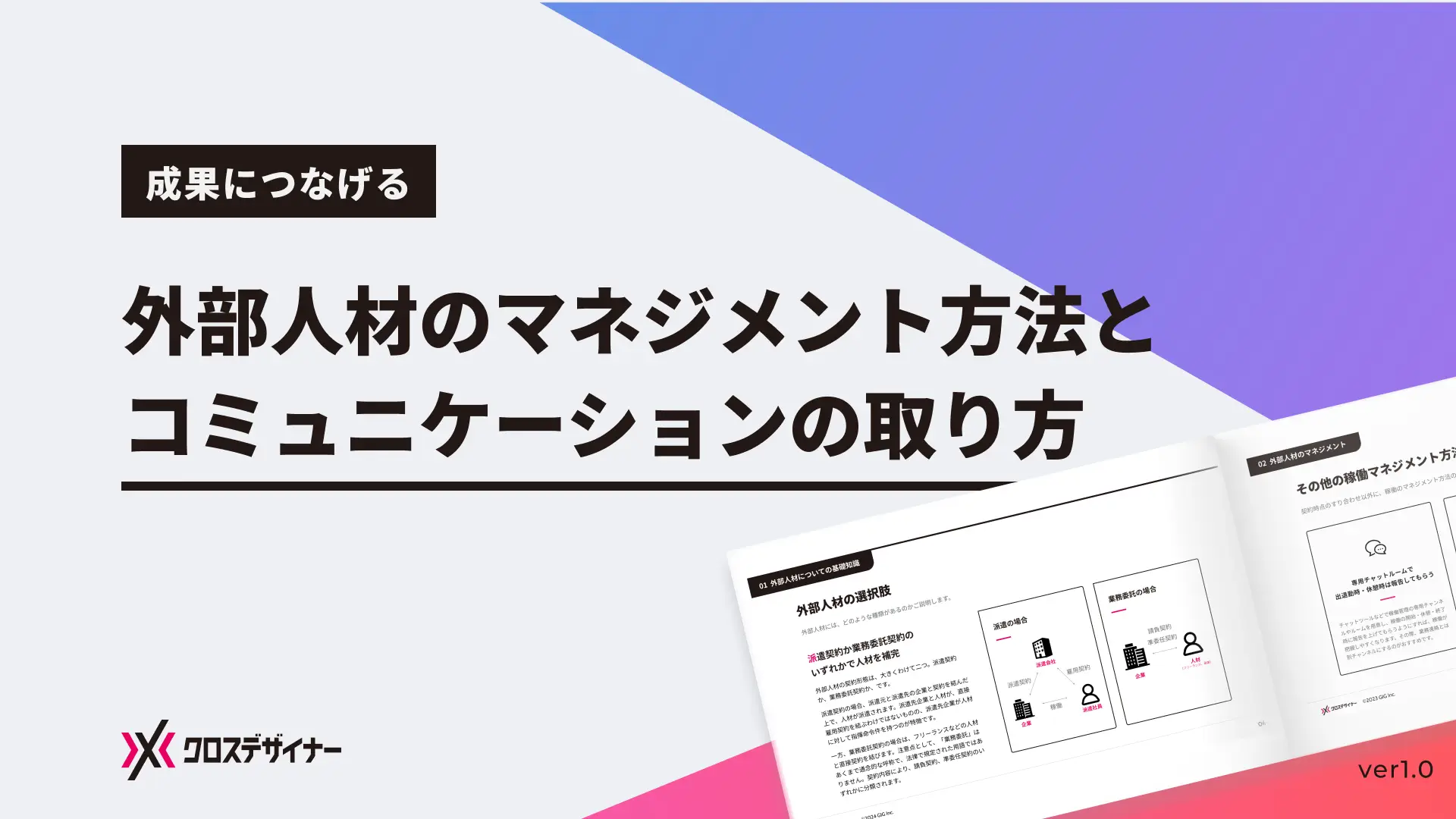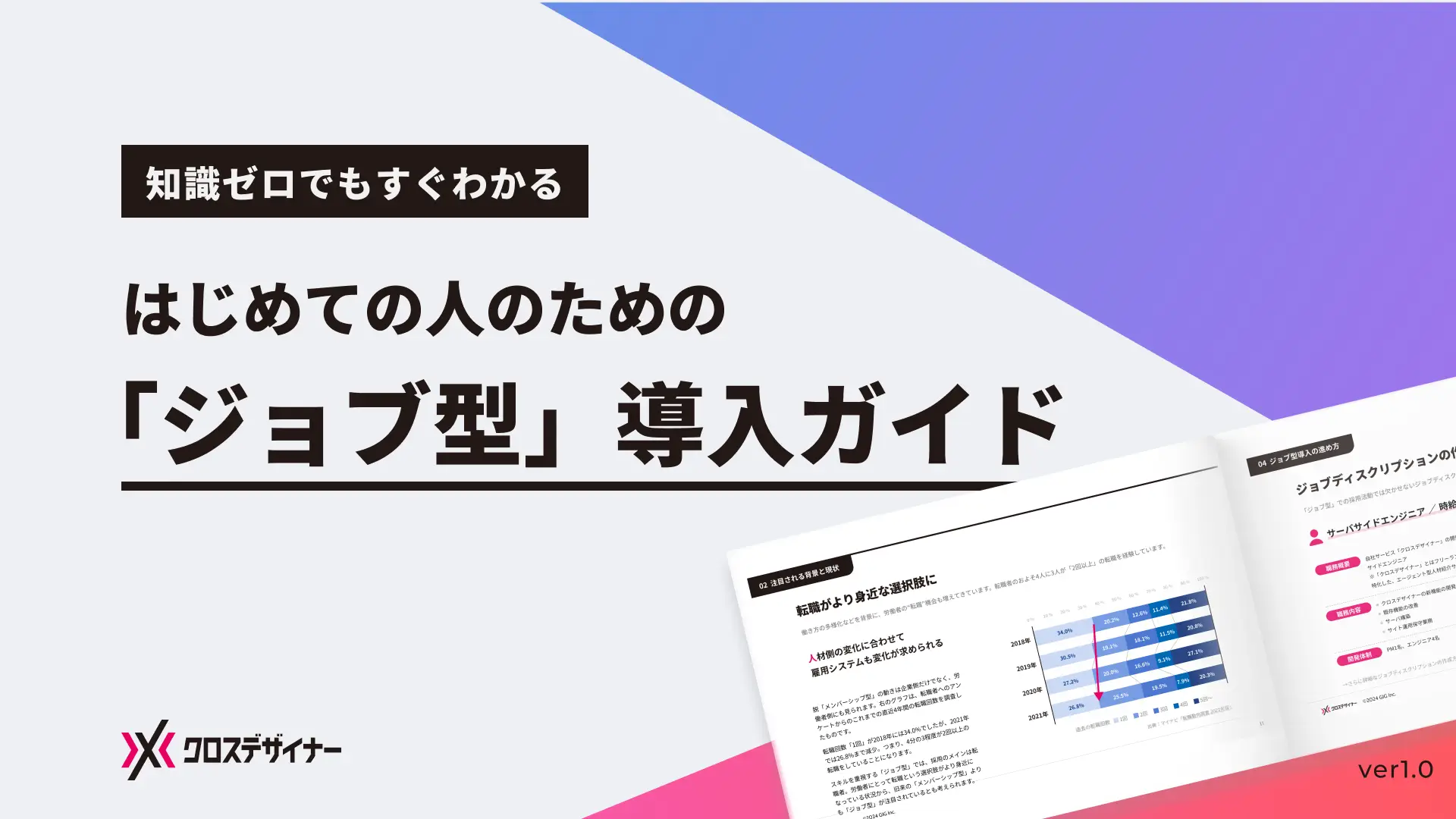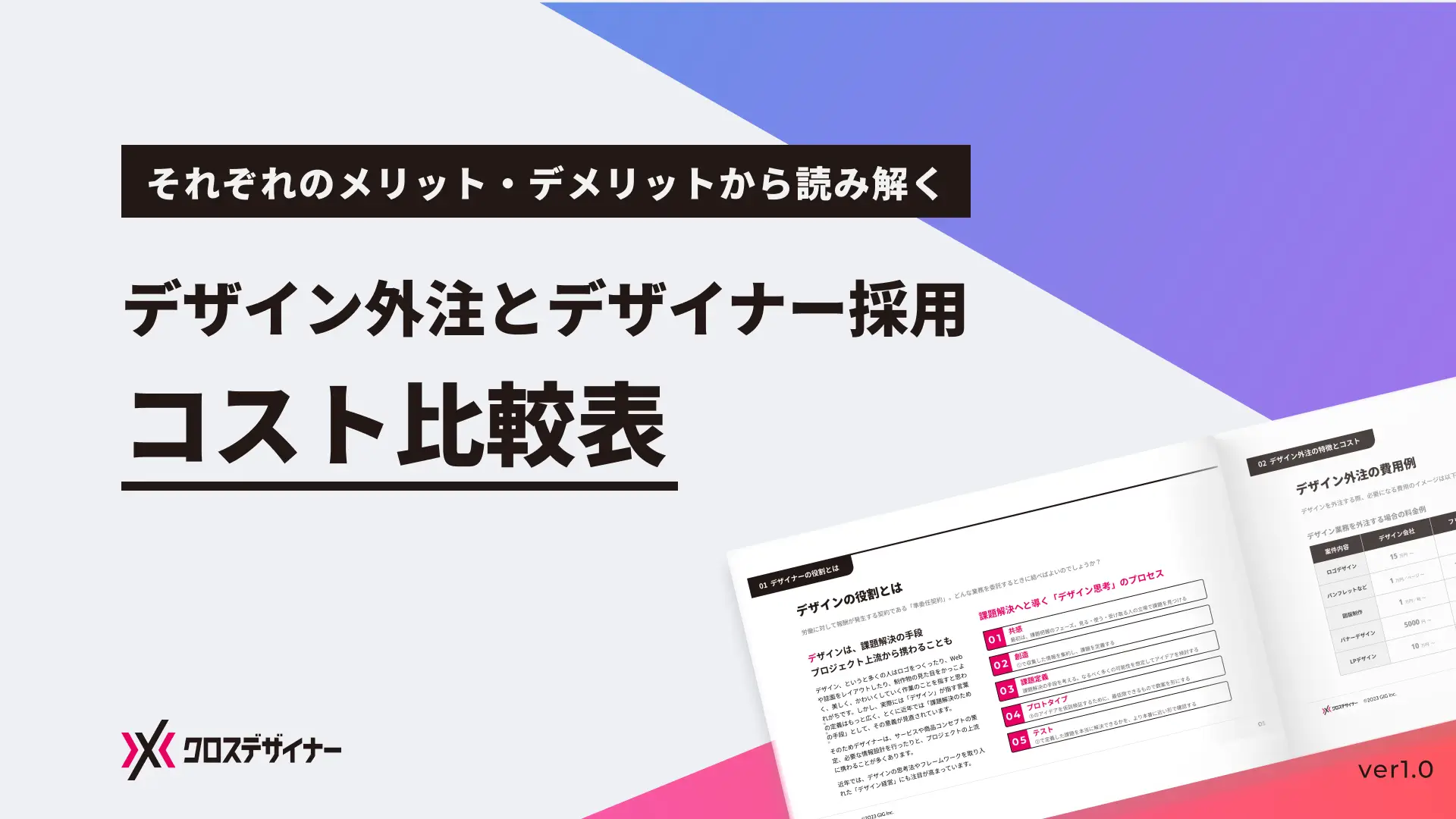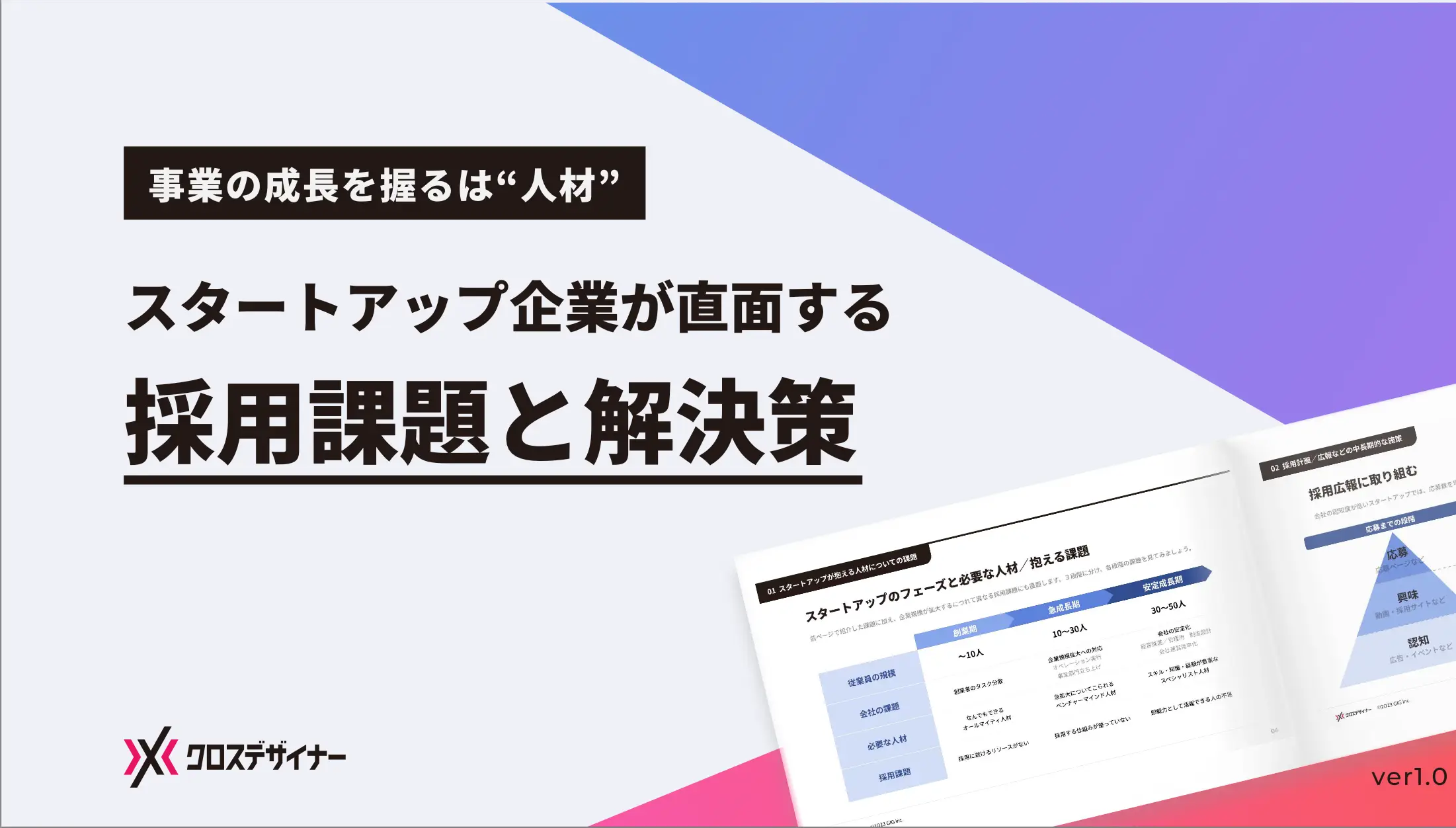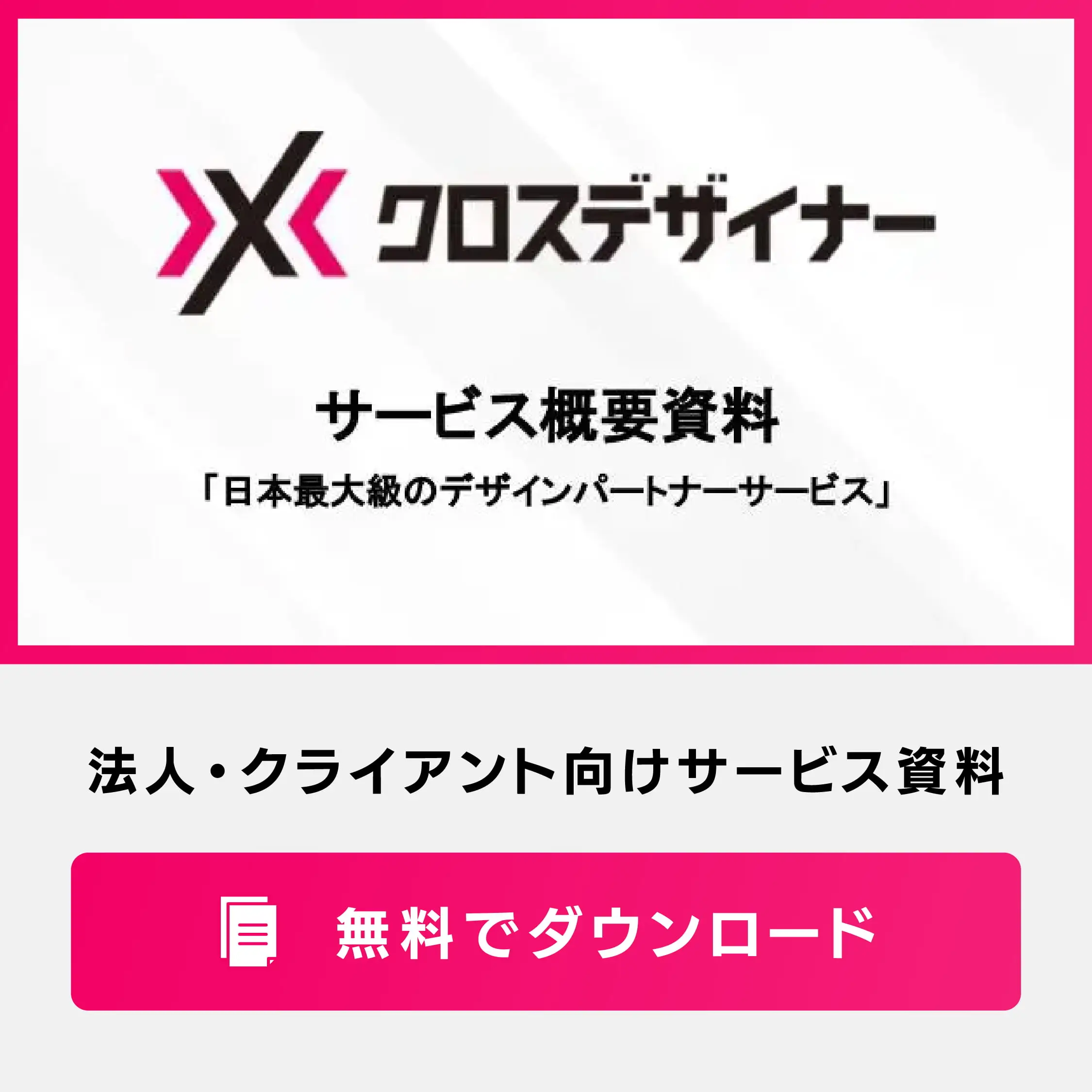新しい会社の立ち上げや、新商品を開発した際に必要となるのがロゴ制作です。ロゴは会社や商品の顔となるものであるため、長く使える品質の高いロゴを作りたいものですよね。
しかし、「自社でロゴを作れるスタッフがいない」や「費用の相場や依頼の仕方がわからない」という方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、ロゴ作成を外部に依頼する際に、押さえておくべきポイントを詳しく解説します。
予算やプロジェクトに合ったデザイナーの探し方も紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
ロゴ作成をプロのデザイナーに依頼する際の重要なポイント3つ
ロゴ作成の依頼先は、ロゴ作成サービスや制作会社から、フリーランスのデザイナーまでさまざまです。そのため、発注者側が自社に合った依頼先を見極める必要があります。
ロゴ作成を依頼する際の検討ポイントは、主に以下の3つです。
- デザイナーの選定
- 円滑なコミュニケーション
- 予算とスケジュール
それぞれ解説します。
1.デザイナーの選定
まずはじめに、ロゴ制作を依頼するデザイナー選びは非常に重要です。そこで、デザイナーのポートフォリオを確認し、過去の作品があなたのビジョンやブランドイメージに合っているかを見極めましょう。
また、デザイナーが過去に取り組んだ業界やスタイルが、求めるロゴデザインと相性が良いかも確認する必要があります。
2.円滑なコミュニケーション
デザイナーとの明確なコミュニケーションは、期待するロゴを実現するために不可欠です。ブランドの価値観、目指すイメージ、ロゴに込めたいメッセージなど、具体的な要望を伝えることが大切です。また、フィードバックのプロセスも重要で、デザイン案に対して具体的かつ建設的なフィードバックを提供することで、より良い結果につながります。
3.予算とスケジュール
ロゴ制作には費用と時間がかかります。そこでまずは、予算を明確にして、デザイナーと費用について事前に話し合いましょう。また、納期も重要な要素です。ロゴが必要となるイベントやプロジェクトのスケジュールに合わせて、デザイナーに納期を伝え、余裕を持ったスケジュールで進めるようにしましょう。
これらのポイントを踏まえ、デザイナーと協力しながら、効果的なロゴ制作を行うことができます。ロゴは企業や製品の顔となるため、慎重に進めることが重要です。
▼下記の資料では、業務委託・正社員・派遣など複数の雇用形態を比較し、特徴を解説しています。無料でダウンロードできますので、ぜひ貴社の外注業務にお役立てください。

ロゴ制作を外注する際の費用相場
ロゴ制作を検討する際に気になるのが、制作費用ではないでしょうか。
実は、ロゴの制作費に相場はないといわれています。なぜなら、依頼先や依頼内容によって、制作費が変わってくるからです。
フリーランスのデザイナーへの依頼なら数万円から可能ですが、実績のある制作会社や広告代理店に依頼した場合は数十万円かかるケースもあります。
そのため、まずはロゴ制作費の内訳を理解することからはじめましょう。
依頼先から上がってきた見積もりが、実績や依頼内容に合った適正価格かを判断する際に役立ちます。
ロゴ制作費の内訳
ここで、ロゴ制作を依頼した際の、デザイン費の内訳と算出方法について、日本グラフィックデザイン協会の「制作料金概念規定」に沿って説明します。
作業料
ロゴ制作に関わる人々の作業量が指標となり、一般的にデザイン制作にかかる工数を指します。
この作業料は、付加価値を左右するクリエイティブなデザインのa作業と、付加価値に関係の少ないカンプやフィニッシュなどのb作業に分けられます。
例として、日本グラフィックデザイナー協会による基準料金表から、商品名ロゴタイプの作業料の目安を紹介します。
作業区分 | 作業項目 | 単位 | 基準価格(円) |
a作業 | クリエイティブディレクション | 1テーマ | 45,000円 |
a作業 | デザイン | 1点 | 45,000円 |
b作業 | カンプ | 1点 | 40,000円 |
b作業 | フィニッシュ | 1点 | 40,000円 |
▲出典:日本グラフィックデザイン協会「デザイン料金表」より
このb作業は作業ごとの定額となりますが、a作業は量に応じて費用が高くなります。さらに、a作業はデザイナーの能力や知名度に応じた質的指数を乗じるため、担当者によって変わります。例えば、標準的な能力のデザイナーを1として、アートディレクターであれば3、アシスタントであれば0.5といった指数になります。
このように総工数は、デザイナーの能力や実績、要する時間によって異なりますが、工数の目安となる時間料金は、以下の計算式で算出することができます。
年収÷12ヵ月(平均月収)÷165時間(1ヵ月あたりの標準労働時間)×2(標準人件費比率は50%とする)=作業料
例えば、年収1,000万円のクリエイティブ・ディレクターであれば、時間料金は10,000円、年収500万円のデザイナーであれば時間料金は5,000円になります。
付加価値料
完成した制作物がもたらす付加価値に対してかかる料金です。
長期間さまざまな用途に使われる企業のロゴと、生産数の少ない商品のロゴでは、付加価値に大きな差があります。
そのような制作物の使用目的や量などの、制作者の能力や知名度以外で付加価値に影響する要因を、量的指数といいます。
この量的指数は、販促費や売上、粗利率などを参考にして決定されます。
例として、上で紹介した商品名ロゴタイプの量的指数を紹介します。
量的指数 | 内容 年間販促費 |
1 | 100万円程度 |
3 | 500万円程度 |
6 | 5,000万円程度 |
10 | 5億円程度 |
15 | 30億円程度 |
18 | 50億円程度 |
24 | 100億円程度 |
35 | 200億以上 |
▲出典:日本グラフィックデザイン協会「デザイン料金表」より
付加価値料は、作業料で説明した質的指数と、この量的指数を用いて、以下の計算式で算出されます。
a作業料×質的指数×量的指数=付加価値料
そのため、デザイナーの能力や知名度と、制作物の使用目的や量によって変わります。
提案にかかる費用
提案数は依頼先によってさまざまです。
提案数が多くなるほど費用は高くなることを念頭におき、初回提案数や追加で提案を依頼した際の費用をあらかじめ確認しておきましょう。
修正にかかる費用
見積もり時は、一般的な作業量を目安にして、デザイン費や作業料といった項目に計上されていますが、修正数が多くなるほど費用は高くなります。
修正を依頼する回数が多くなると、納品後、修正にかかった作業工数を請求された際に、見積もりより大幅にアップしてしまうことも。
経費
打ち合わせの際の交通費や通信費、見本を作成した際の材料費などが含まれます。
CI・VI・BI作成費
CIとは、「Corporate Identity(コーポレート・アイデンティティ)」の略で、会社の特色を、統一されたイメージやわかりやすいメッセージで発信し、社会的イメージや存在価値を高めていく企業戦略の一つです。
VIとは、「Visual Identity(ビジュアル・アイデンティティ」の略で、CIで制定された企業メッセージなどから、ロゴやコーポレートカラーなどを視覚的に表現すること。
BIとは、「Brand Identity(ブランド・アイデンティティ)」の略で、製品やサービスの特色を明確にして発信し、ブランド価値を高めていくことです。
ロゴはさまざまな用途に使われるもの。ルールを設けずに自由に使ってしまうと、会社や商品のイメージを損ねる場合もあります。そのような事態を防ぎ、ブランディング効果を高めるために、ロゴ使用に関する指針をまとめたデザインマニュアルを作成する費用です。
著作権譲渡費
ロゴは作成したデザイナーに著作権が発生するため、著作権譲渡費を支払い、著作権の譲渡を受ける必要があります。
詳しくは下記の関連記事も合わせてご覧ください。
関連記事:【種類別】デザイン依頼にかかる費用/料金相場は? 費用を抑えるコツも解説!
ロゴ制作を外注する際の流れを4ステップで解説
続いて、ロゴ制作にかかる期間を把握するために、依頼から納品までの流れを説明します。制作の流れを把握しておくと、スムーズに進行しやすくなるというメリットもあります。
1. 制作・見積もりを依頼
作りたいロゴのイメージを固めたら、制作会社やフリーランスのデザイナーの実績をチェックして、ニーズに合った依頼先を選定します。
依頼先は1つに絞らず、複数に見積もりを依頼して、比較・検討することをおすすめします。
2. 打ち合わせ・スケジュール調整
打ち合わせでは、会社や商品の特徴やターゲット、作りたいロゴのイメージなどをデザイナーに共有します。
納得のいくロゴをデザインしてもらうためには、デザイナーがイメージをくみとれるよう、できるだけ具体的に伝えましょう。
また、修正を依頼したい回数や社内確認に要する期間などを伝え、スケジュールを調整します。依頼先との打ち合わせまでに、部署内で回覧するタイミングや社内審査についても確認しておきましょう。
3. ロゴデザインの作成・提案・修正
デザイナーはヒアリングした内容を整理し、モチーフや書体、配色を考え、デザインワークを開始します。
デザインが完成したらプレゼンテーションです。提案されたロゴデザインの中から、一番希望に近いものを選びましょう。
納得がいかなかったり、イメージと異なったりした場合は、修正を依頼します。ただし、むやみに修正を繰り返して、納期が延びたり費用がかさんだりしないためにも、できるだけ具体的に依頼するよう注意しましょう。
4. 納品
納得のいくロゴができあがったら、データを納品してもらいます。納品されたら、サイズやファイル形式などが指定通りか、使用にあたってデータに問題がないかを確認しましょう。
ロゴ制作など、初めての外注では不安を感じる方も多いはず。そこで下記の資料では、外注の流れとポイントをステップ別に解説しています。無料でダウンロードできますので、ぜひご活用ください。

また、下記の記事も合わせてご覧ください。
関連記事:デザインの依頼方法6ステップを解説!依頼するメリットや注意点についても
ロゴ制作の依頼先4選とその特徴
ここで、ロゴ制作におすすめの4つの依頼先をご紹介します。価格や制作期間についても解説しているので、参考にしてください。
なお、依頼先を検討するポイントの一つであるクオリティについては、制作会社の公式サイトなどで制作実績をチェックします。フリーランスにはポートフォリオを提示してもらいましょう。
実績を見る際は、以下の4つの点について比較・検討します。
- 制作事例
- 実績数
- 受賞歴や認定歴などのデザイン評価
- ターゲットのレビュー
特にターゲットとなる人が、制作事例などを見て感じた率直なレビューを尊重することが重要です。
1. 制作会社に依頼する方法
コストや制作期間をかけても高品質のロゴを作りたい、CI・VI・BI戦略から依頼したいといった場合には、実績があり、人材が豊富な制作会社を選ぶとよいでしょう。
とはいえ、制作会社は数多くあるため、どこを選んだら良いかわからないといった方も多いでしょう。そのような場合は、ロゴ専門の制作会社に依頼するのがおすすめです。ロゴ制作経験の豊富なデザイナーやディレクターが対応してくれるところもあるため、比較的やりとりがスムーズなのが特長です。
価格はロゴ制作会社によって異なり、40,000円程度から100,000円以上と幅広いため、ニーズに合わせて選びましょう。
2. ロゴ販売サイトで購入する方法
ロゴのイメージがなかなか固まらない、とにかく急ぎでロゴがほしいといった方は、ロゴ販売サイトをチェックしてみることをおすすめします。
プロのデザイナーによるさまざまなテイストのロゴが豊富にそろっていて、希望のデザインを見つけたら、文字や色を指定して購入するだけ。
価格は10,000円程度からで、手軽で短納期、制作会社に比べると低価格な点が特長です。
3. クラウドソーシングで依頼する方法
クラウドソーシングなら、コンペ形式での依頼が可能で、在籍している数多くのデザイナーからロゴデザインを募集することができます。
ランサーズやココナラ、クラウドワークスは市場が活発で応募数も多く、価格も5,000円といった低価格帯であってもすぐに要望に合ったロゴを作成してもらえる可能性があります。
4. フリーランスに依頼する方法
クラウドソーシングは、ポートフォリオをチェックして気に入ったデザイナーが見つかれば、直接依頼することもできます。ただし、在籍しているデザイナーは新人から実績のあるベテランまでさまざま。
SNSやブログなどを通してフリーランスに依頼することも可能ですが、いずれの方法もニーズに合ったデザイナーを見つけるまでに時間がかかります。
そのため、フリーランスデザイナーをお探しの方は、デザイナー専門のマッチングサービスを利用するのがおすすめです。
なかでもクロスデザイナーはデザイナーに特化した国内最大級のエージェントサービスです。約7,000名の登録者全員が審査通過率5%の壁を突破した、ハイレベルなフリーランスデザイナーとマッチングできます。
関連記事:外注デザイナーを探す方法は?おすすめサービス12選と注意点を解説!
優秀なデザイナーを選ぶ際のポイント
優秀なデザイナーを選ぶ際には、まずデザイナーのポートフォリオを確認して、これまでの実績やデザインの特徴などを把握しましょう。その際に、自社の業界やニーズにマッチしたデザイナーを選ぶことが大切です。
また、過去のクライアントの評価を口コミなどで確認し、信頼できるデザイナーであることも重要なポイントです。デザイン作成では、発注者とデザイナーが密にコミュニケーションを取りながら制作に当たるため、コミュニケーション能力や、柔軟な対応力、問題解決能力があるかも確認する必要があります。
上記を重視した上で、費用が適正であるかなどを総合的に鑑みて、ロゴ制作を発注することが大切です。そこで次の章では、ロゴ制作の依頼に失敗しないためのチェック項目5つを解説します。
下記の資料では、デザイナーを取り巻く環境から採用のポイントまでを手軽に理解できるように簡潔にまとめています。無料でご覧いただけますので、ぜひご活用ください。

ロゴ制作の依頼先の失敗しない選び方5つ
以下では、ロゴ制作の依頼先を選ぶ際に失敗しないポイント5つについて解説します。
- これまでの実績を確認すること
- サポート体制を確認すること
- 費用と予算を確認すること
- コミュニケーションの質を確認すること
- 契約内容を確認すること
それぞれ解説します。
1.これまでの実績を確認すること
デザイナーのポートフォリオや過去のクライアントのリストを確認し、これまでに提供したサービスの質と多様性を評価します。成功したプロジェクトの事例は、その会社が自社のニーズに応えられる能力を持っているかの良い指標になります。
2.サポート体制を確認すること
ロゴ制作は、単にデザインを作るだけではなく、ブランド戦略やマーケティングにも関連しています。
そこで、依頼先がこれらの側面についてもサポートしてくれるかどうかを確認し、必要に応じてアドバイスやフィードバックを提供してくれるかを見極めることが重要です。
3.費用と予算を確認すること
ロゴ制作の費用は大きく異なることがあります。明確な見積もりを依頼し、隠れた費用がないかを確認します。また、最終的なデザインが予算内で収まるように、費用とサービスのバランスを取ることが重要です。
4.コミュニケーションの質を確認すること
デザインのプロセスはコミュニケーションが鍵となります。依頼先が要望を正確に理解し、適切なタイミングでフィードバックを提供してくれるかどうかを確認しましょう。
5.契約内容を確認すること
契約書には、納品物の詳細、著作権の取り扱い、支払い条件などが含まれています。これらの条件が自社の要望に合致しているかを確認し、不明点があれば事前に解決しておくことが大切です。
これらのポイントを押さえることで、ロゴ制作の依頼先選びで失敗するリスクを減らし、成功に導くことができるでしょう。
下記の資料では、業務委託人材の労務管理の注意点やポイントを、正社員と比較しながら解説しています。無料でダウンロードできますので、ぜひご利用ください。

ロゴデザインを依頼する際の注意点3つ
最後に、ロゴ使用に関するトラブルを避けるために、依頼時に注意すべき3つのポイントについて解説します。
1. 著作権の譲渡合意は書面で行う
ロゴは作成したデザイナーが著作権者となるため、ロゴデータが納品されても、著作権がデザイナーに残ったままロゴを使用すると、著作権を侵害してしまいます。
そのため、著作権譲渡契約書を作成し、デザイナーに依頼して著作権の譲渡を受ける必要があります。
後々契約の解釈についてトラブルになることを防ぐためにも、この譲渡合意は必ず書面で行うことが重要です。
文化庁の「著作権契約書作成支援システム」は、画面の案内にしたがって項目を入力するだけで、著作権等に関する契約書のひな型を作成することができます。
2. 似ているロゴがないか確認する
商標のトラブルを防ぐために、Googleの画像検索などを利用して、似ているロゴがないか確認しましょう。
特許庁のサイトで紹介されている特許情報プラットフォーム「J-PlatPat」は、商標に関する出願・登録情報や商品・役務名等を検索できます。「J-PlatPat」は工業所有権情報・研修館の無料サービスです。
また、商標検索サイト「Toresu商標検索」なら、ロゴデータをアップロードするだけで、商標登録されている類似ロゴを検索することができます。
3. 商標登録を検討している場合は予め伝えておく
商標登録を検討している場合は、ロゴ制作を発注する際に伝えて、商標登録の同意を得ておくことをおすすめします。
著作権の譲渡を拒否されてしまった場合、他人の著作物でも商標登録はできますが、著作権者の承諾を得なければ使用できないと商標法で定められているためです。
参考:特許庁「商標制度の概要」
下記の資料では、業務委託に必要な4種類の契約書をテンプレート付きで解説しています。無料でダウンロードできますので、ぜひご利用ください。

フリーランスに依頼するならクロスデザイナーがおすすめ!
本記事では、ロゴ制作を依頼する際のポイントについて、詳細に解説をしました。
会社や商品の顔となって、長期間、さまざまな用途に使われるロゴは、信頼できるデザイナーに依頼したほうがいいでしょう。
ロゴデザインの依頼について、理想のロゴを作りたいならクロスデザイナーがおすすめです。

フリーランスデザイナーに特化したエージェントサービスのクロスデザイナーは、登録時に厳正な審査基準を設けており、その通過率はわずか5%です。採用難易度の高い即戦力デザイナーの中から、自社にマッチしたデザイナーを最短即日で提案いたします。
また、双方の合意があれば、アサイン後に正社員への契約形態の変更も可能です。
クロスデザイナーには、WebデザイナーやUI/UXデザイナー、アプリデザイナーなどが多数在籍しているため、あらゆるクリエイティブにも対応できます。
こちらより、クロスデザイナーのサービス資料を無料でダウンロードできますので、即戦力の優秀なデザイナーをお探しの方は、ぜひ【お問合わせ】ください。平均1営業日以内にご提案いたします。
Documents