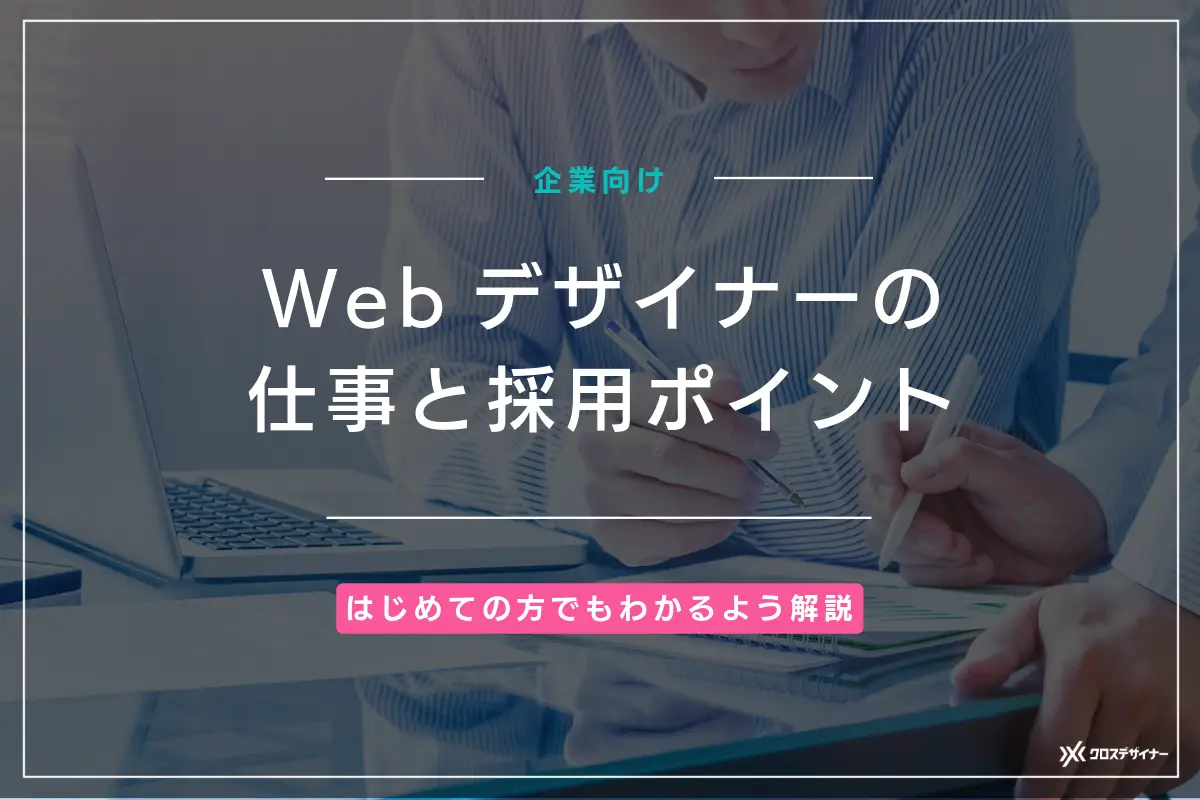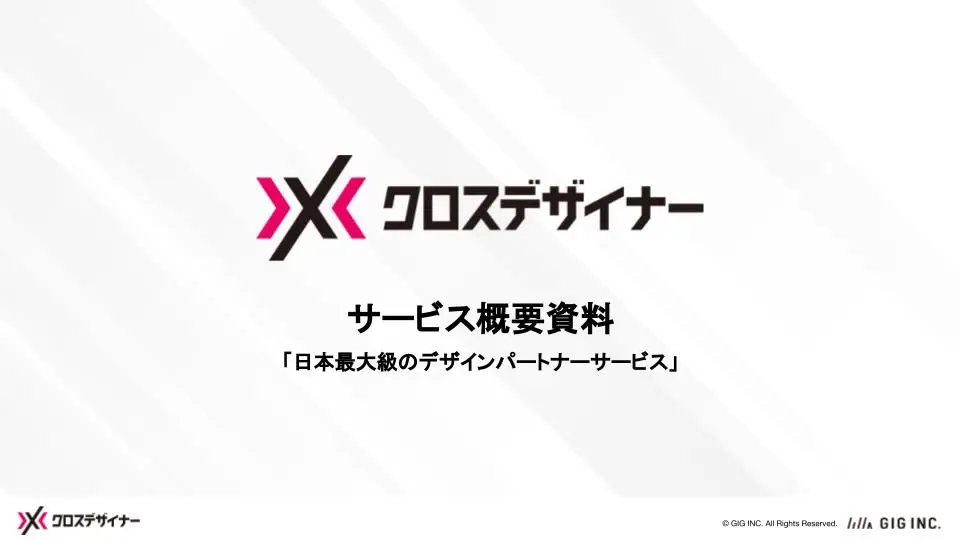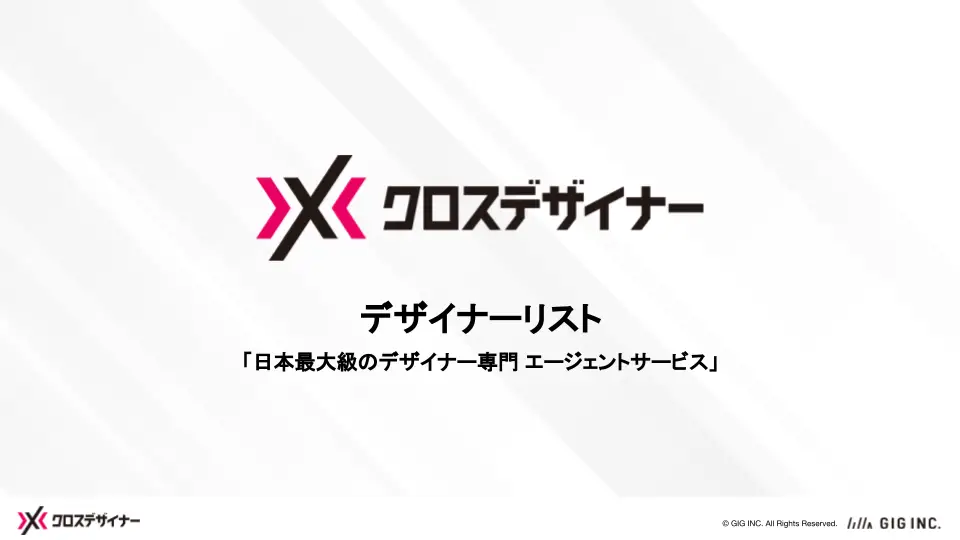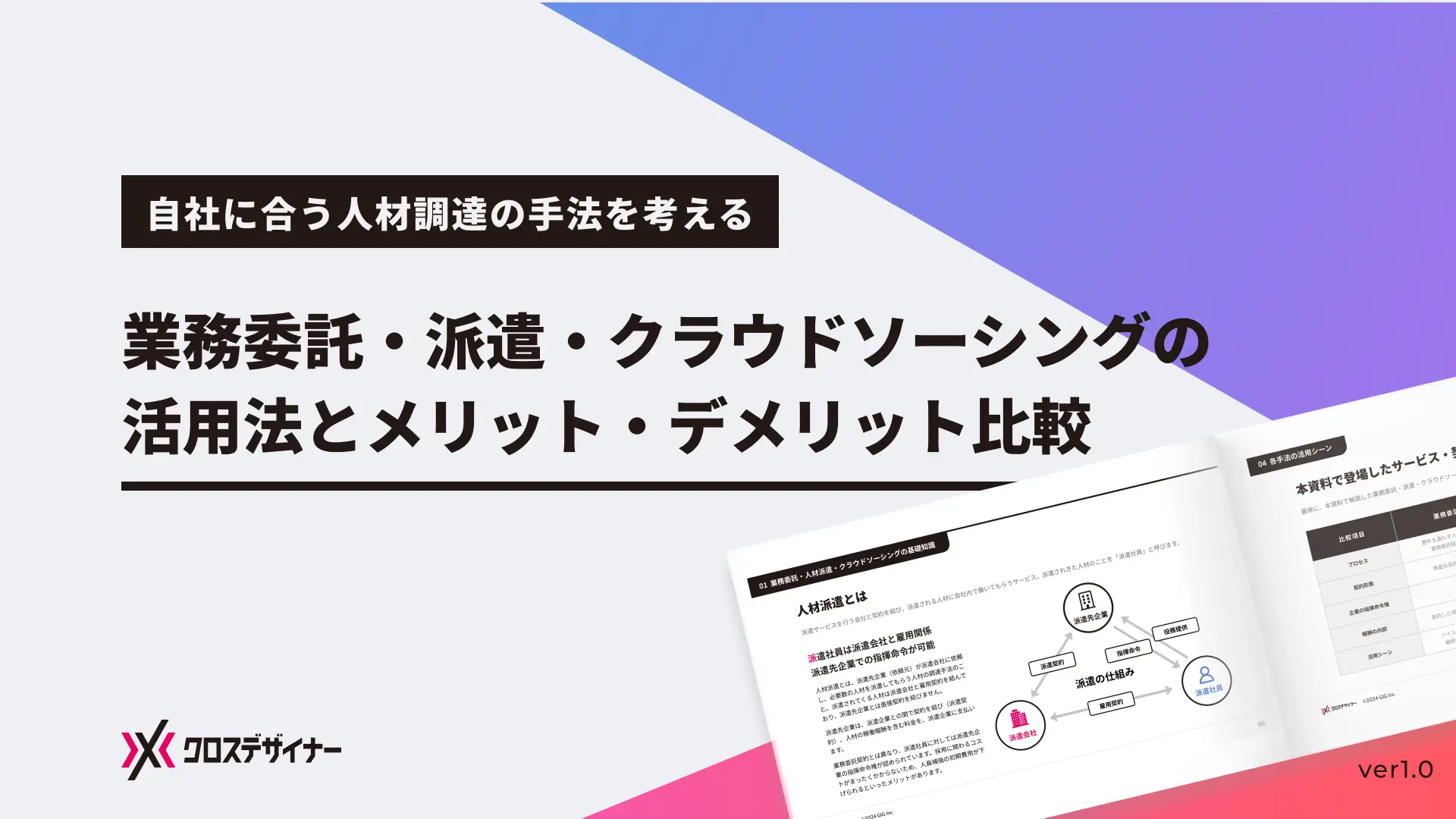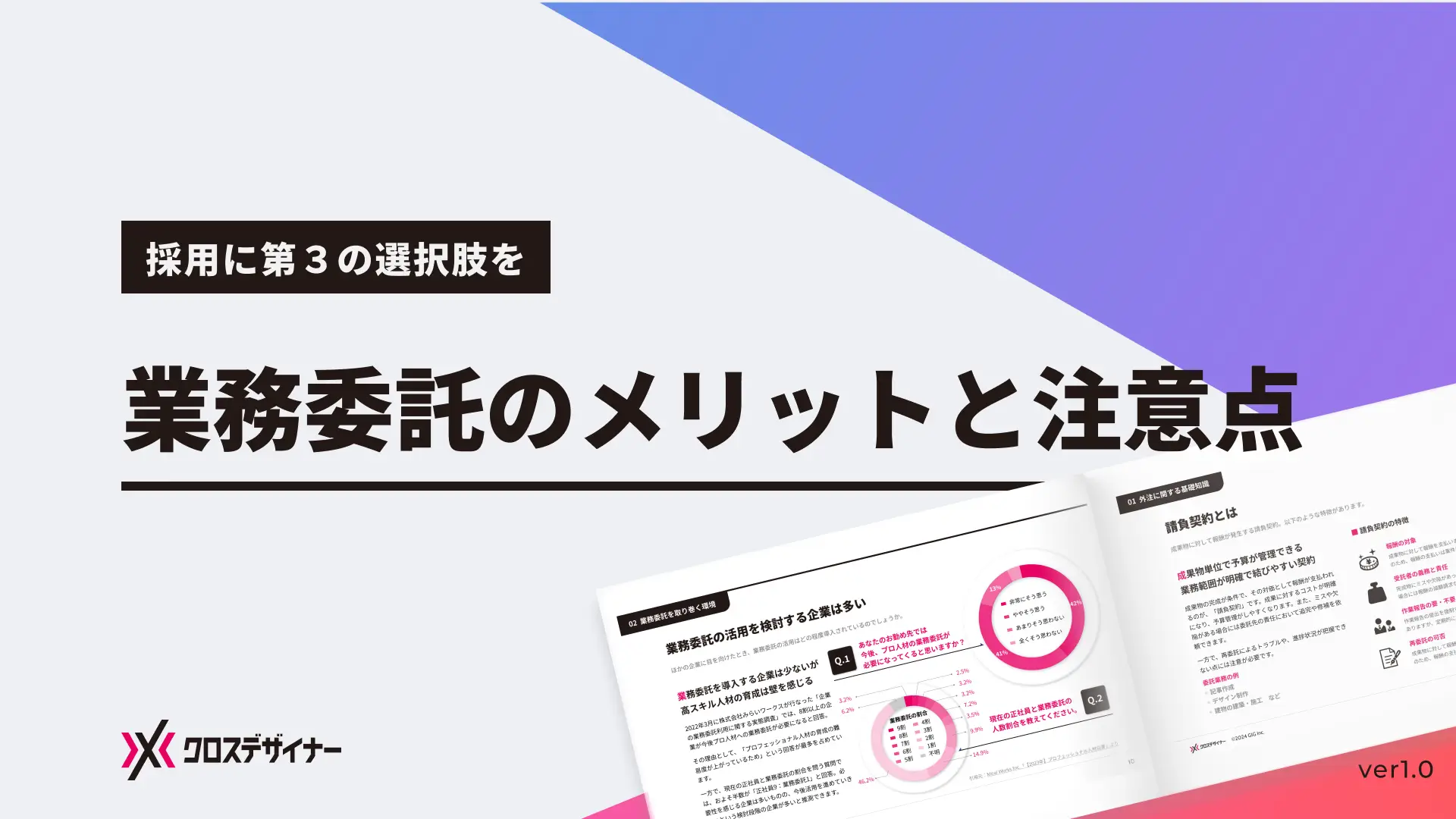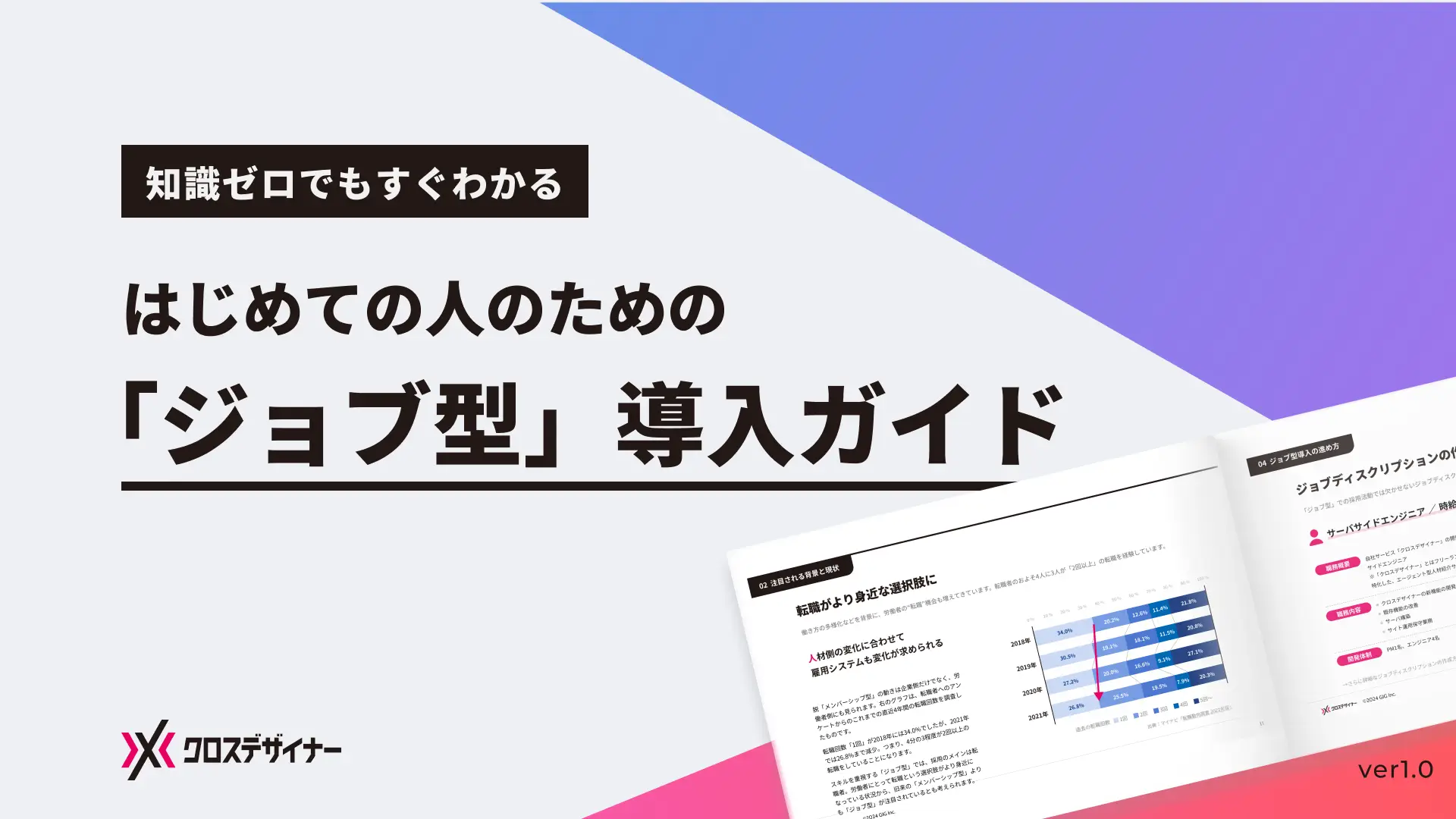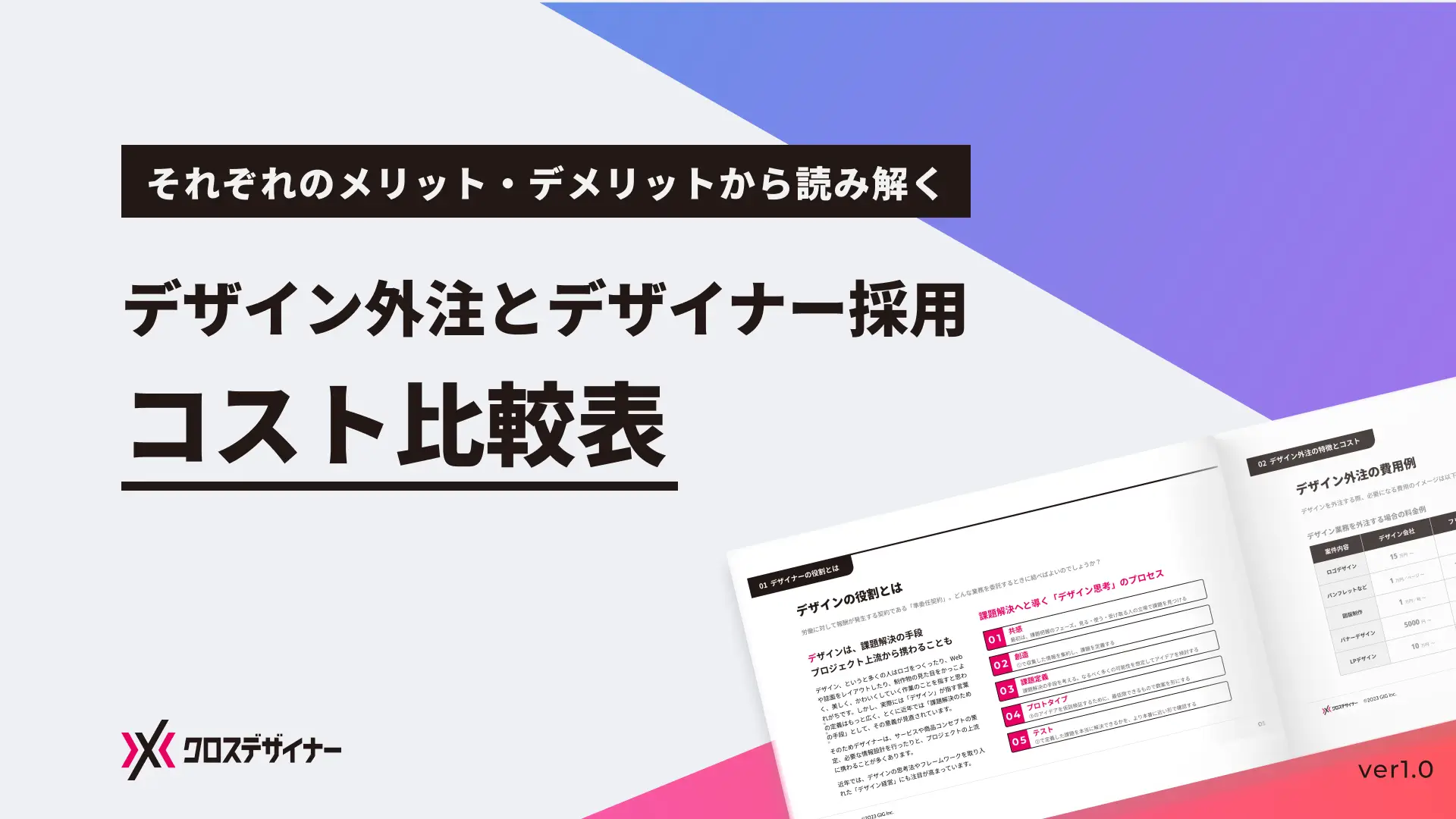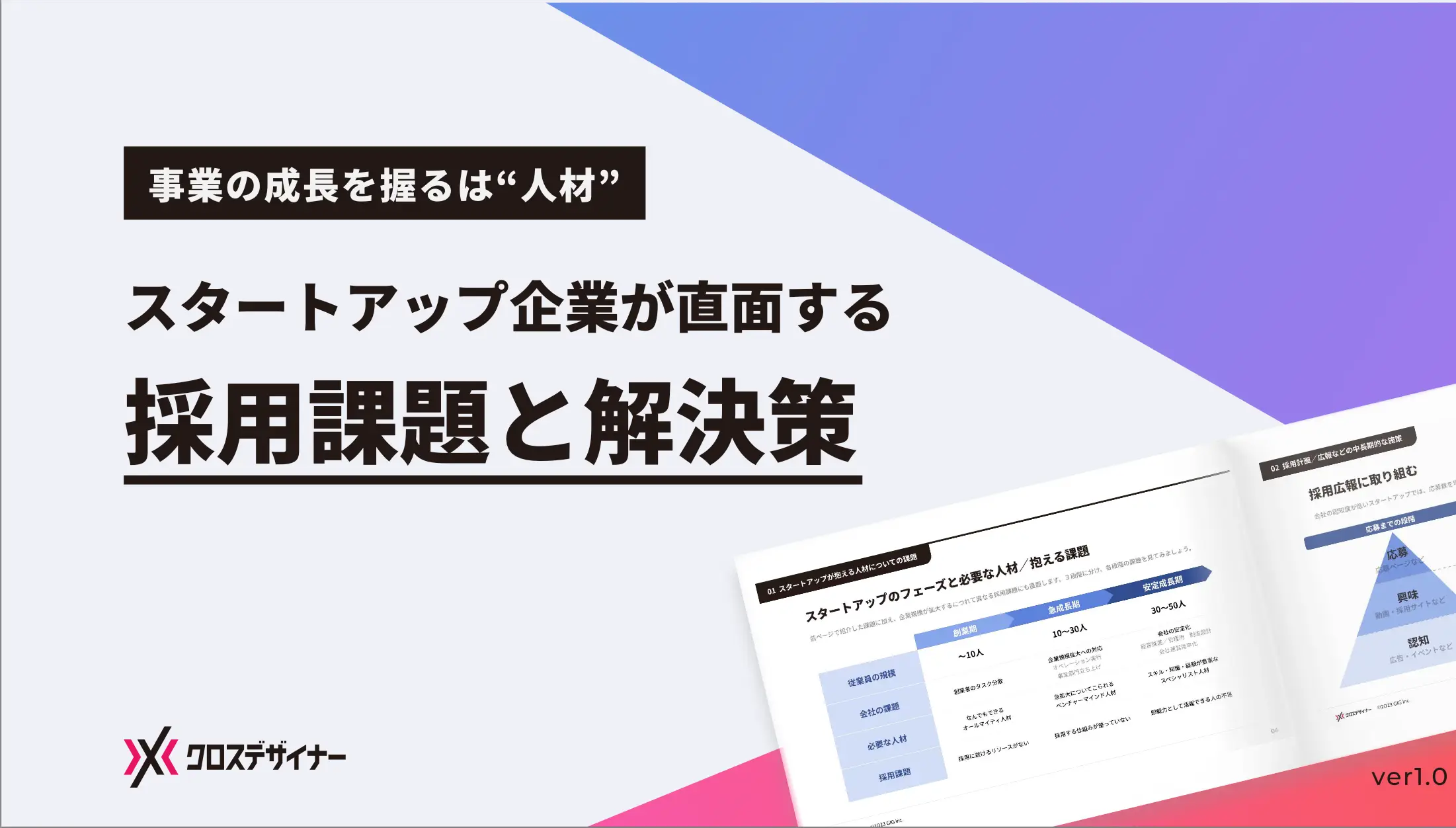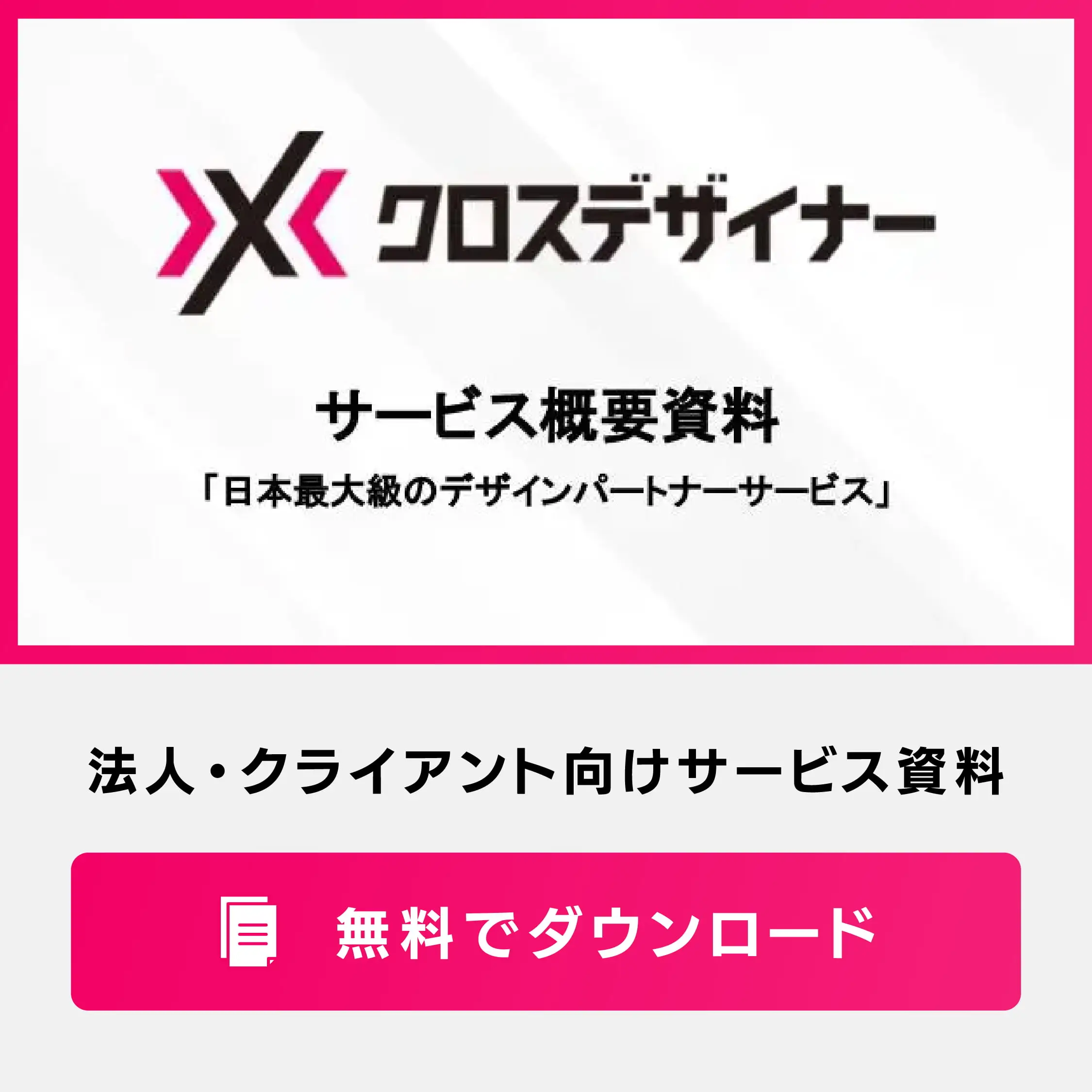「ブランドの魅力が伝わらない」「デザインが統一されていない」と悩む企業は少なくありません。商品やサービスが優れていても、企業イメージが整理されていなければ顧客には届きにくいものです。
そこで役立つのが「ブランディングデザイン」です。企業の価値や想いをデザインで表現し、認知度や信頼感を高めることができます。
この記事では、考え方や目的、構成要素から依頼方法までわかりやすく解説します。
ブランディングデザインとは?
ブランディングデザインとは、企業やサービスの価値や世界観を、ロゴ・カラー・フォント・ビジュアルなどの要素で一貫して表現する取り組みです。
見た目の美しさだけではなく、プロダクトのもつ「らしさ」をさまざまなデザインで表現することで、ユーザーからの信頼を得る役割を担っています。統一感のあるデザインは記憶に残りやすく、信頼や安心感を高める効果もあります。
市場で優位性を高めるにはプロダクトのもつ「らしさ」をデザインで表現し、差別化を図ることが大切です。企業が選ばれる理由をデザインで表現することが求められているのです。
ブランディングデザインは、効果が出るまでに数年かかることもあります。長期的にブランド価値を高めていくことで、認知度や信頼感が高まり、ユーザーから選ばれる企業として定着していきます。
ブランドとは
ブランドとは、「この企業といえばこれだ」「この商品ならこのイメージだよね」といったユーザーがもつ印象や信頼のことです。これらは目で見える商品名やロゴだけではなく、利用から得られる体験など見えないものでつくられています。
また、こうしたブランドの価値観を社員一人ひとりが理解することで、プロジェクトや人材育成における指針となり、企業全体の成長につなげることが可能です。
関連記事:BtoBブランディングが企業の成長の鍵を握る!効果や進め方を解説!
ブランディングデザインを成功させるコツ
ブランディングデザインは、ただ見栄えを整えるだけでは成果につながりません。ユーザーの心に届けるためには、戦略や体制を整えて、継続的に取り組むことが大切です。ここでは、ブランディングデザインを成功させるうえで押さえておきたい5つのポイントを紹介します。
1. ターゲット顧客の明確化
まず、誰に向けてブランドを届けたいのかをはっきりさせましょう。年齢や性別、職業などの属性だけではなく、価値観やライフスタイルまで具体的に描くことで、メッセージやデザインに一貫性が生まれます。
ターゲットがあいまいなまま進めると「誰にも響かないデザイン」になるおそれがあるため、ペルソナを設定してターゲット顧客像を明確にしましょう。
2. 一貫性のあるデザイン戦略の構築
ロゴやカラー、フォントなどのビジュアル要素はもちろん、広告やWebサイト、SNSでの言葉遣いにいたるまでトーンを統一するのがコツです。ここでは「デザイン思考」や「デザインの4原則(近接・整列・反復・対比)」が役立ちます。
一貫性があるほどブランドの世界観は強固になり、ユーザーは安心感を抱きやすくなります。
関連記事:デザイン思考とは?概要から活用方法をわかりやすく解説|導入するメリットやフレームワークも紹介
関連記事:デザイン思考を実践するときに役立つフレームワーク10選
3. フリーランスデザイナーの専門性の活用
フリーランスデザイナーは、ロゴやWebサイト制作、パッケージデザインなど特定の分野に強みをもつ人材が多く、その専門性を直接活用できるのが魅力です。
制作会社では幅広く対応してもらえますが、得意分野が見えにくいことがありますが、フリーランスならポートフォリオからスキルや実績を確認し、自社の課題に合う人を選ぶことができるのです。
専門分野に長けたデザイナーと組むことで、ブランド表現の精度や独自性を高めることができます。結果、競合との差別化にもつなげることが可能です。
関連記事:外注デザイナーを探す方法は?おすすめサービス10選と注意点を解説!
4. 定期的な評価とフィードバック
ブランドデザインは一度つくれば終わりではありません。実際に顧客にどう受け止められているかを調査し、必要に応じて修正を重ねる必要があります。
アンケートやインタビュー、Webサイトの分析結果をもとに効果を測定しましょう。得られたデータをデザイナーと共有し、改善点を明確にすることで、ブランド価値を高め続けることができます。
関連記事:企業ブランディングとは?重要性と実践のポイントを紹介
5. 長期的視点でのブランド育成
ブランディングは短期的に成果を出す施策ではなく、長期的に育てる取り組みです。時間をかけて一貫性のある表現を続けることで、顧客の記憶に残り、選ばれる理由が定着していきます。
ときには市場の変化に合わせた見直しも必要ですが、軸となる価値観はブレないようにたもつことが大切です。成功事例から学び、失敗しやすいポイントを避けながら、企業のブランド価値を積み重ねていきましょう。
関連記事:経営改革の一環としてデザイナー採用も刷新。スピードと柔軟性を両立し、ブランディングを加速させたMONOCO様の事例
ブランディングデザインの構成要素
ブランドを印象づけるデザインにはいくつかの基本要素があります。ここではブランディングデザインを構成する4つの要素をもとに、活用方法について解説します。
1. ロゴでブランドの印象が決まる
ロゴはブランドの「顔」であり、第一印象を左右する要素です。AppleのリンゴマークやNikeのスウッシュのように、シンプルで形がわかりやすいロゴは一度見ただけで記憶に残ります。
複雑なデザインよりも、直線や曲線など基本的な形をうまく組み合わせたロゴの方が認知されやすく、長期的に使われる傾向があります。ロゴ制作では「わかりやすさ」と「象徴性」のバランスを意識することが大切です。
関連記事:ロゴデザインの依頼方法は?事前の準備内容や費用相場も解説!
2. ブランドカラーは戦略的に使う
色は人の感情や印象に大きな影響を与える要素です。赤は情熱や活力、青は信頼や誠実といった心理的効果が知られています。
コカ・コーラが一貫して赤を使い続けているように、ブランドカラーを戦略的に定めることで、認知度を高めることができます。看板やCM、Webサイトなどあらゆるところで目にした瞬間に認知されるようになるのです。
このように色彩心理を理解してブランドカラーを選ぶことで、見る人の感情をコントロールし、自然とブランドを思い出してもらいやすくなります。
関連記事:オウンドメディアのデザイン参考事例8選|見やすい設計のコツ・外注方法を解説
3. フォントの選び方でデザインの魅せ方を考える
フォントは文字情報を伝えるだけではなく、ブランドの個性を表現する役割も担っている要素です。Googleが採用したフォント『Product Sans』のように、丸みを帯びた柔らかい書体は親しみやすさを、太字で直線的な書体は力強さを演出します。
 ▲出典:Google Product Sansタイポグラフィの基本原則を理解し、たとてばWebコンテンツでは見出しにはインパクトのある太字、本文には読みやすさを重視した細字を使うなど、用途に合わせた選び方をするとブランドの世界観がより鮮明になります。
▲出典:Google Product Sansタイポグラフィの基本原則を理解し、たとてばWebコンテンツでは見出しにはインパクトのある太字、本文には読みやすさを重視した細字を使うなど、用途に合わせた選び方をするとブランドの世界観がより鮮明になります。
読みやすさと雰囲気の両方を満たすフォントを選ぶことで、ブランドの世界観をより的確に表現することが可能です。
4. 写真やイラストで世界観を表現する
写真やイラストは、抽象的なコンセプトを具体的に伝える役割を果たします。たとえば、オンラインマーケットプレイス『Airbnb(エアビー)』が旅先をイメージさせる写真を多用したり、Starbucks(スターバックス)がシーズン限定メニューをイラストで演出したりするように、ビジュアルは感情的なつながりを生みやすい要素です。
被写体の距離感や光の当たり方、質感の表し方を工夫するだけで、あたたかみのある雰囲気や高級感など、ブランドのストーリーを直感的に伝えられるようになります。
関連記事:ビジュアルデザインとは?その役割や活用シーンについて解説
ブランディングデザインのKPI設計
ブランディグデザインに取り組むときは、どのような効果を生んでいるのかを測定し、改善に活かさなければなりせん。ここでは改善に役立つKPIの代表的な指標について解説します。
認知度と想起率
まず重要なのが「どれだけ知られているか」を示す認知度と、「状況に応じて思い出してもらえるか」を示す想起率です。これらはアンケート調査や街頭インタビュー、ブランド名の検索数の推移などから測定できます。
たとえば「飲料といえば?」と聞かれてコカ・コーラが出てくるのは高い想起率の証拠です。数値を定点観測することで、ブランドの浸透度を定量的に把握し、改善策を考える材料にできます。
Web行動データ
WebサイトやSNSのデータは、ブランドの関心度を測る手がかりです。ページビューや滞在時間、資料ダウンロード数などを分析することで、顧客がどのコンテンツに魅力を感じているかがわかるでしょう。
また、SNSでの「いいね」やシェア数もブランドへの共感度を示す指標となるものです。とくにキャンペーンやリブランディング直後は、データの変化を追うことで施策が狙いどおり届いているかを確認できます。
関連記事:ホームページでブランディングするメリットと効果的な外注方法も解説
組織内外からの評価
ブランドの強さは顧客だけでなく、社員や採用候補者など社内外からの評価にもあらわれます。社員アンケートで自社ブランドへの誇りを確認したり、採用活動で応募者がどのくらいブランドに魅力を感じているかをチェックするのも大切です。
さらに取引先やパートナー企業からの評価もブランド価値に直結します。こうした外部・内部のフィードバックを定期的に収集することで、企業やブランドが社会にどう受け止められているかを客観的に把握できます。
関連記事:ブランディングとは何か?依頼時の準備項目や発注先の選定ポイントを紹介!
ブランディングデザインでよくある質問
ブランディングデザインを検討する際に、良く聞かれる質問をご紹介します。
効果が出るまでにかかる期間は?
ブランディングデザインは、ブランドイメージが浸透するには半年から数年かかることがあります。新しいロゴやサイトを公開すると一時的に注目を集めることはありますが、短期的な成果を求める施策ではありません。
大切なのは、継続的に一貫したデザインを発信し続けることです。時間をかけて積み重ねることで、ようやく顧客に「この企業といえばこのイメージ」と認識され、信頼や選ばれる理由につながります。
ロゴ刷新のタイミングは?
ロゴ刷新は、企業の方向性が変わったときや、新しい市場へ参入するとき、ブランドが古く見えてしまうときがタイミングです。たとえば、リブランディングをきっかけにロゴを一新し、若い世代にアプローチする企業もあります。
ただし、ロゴ変更は大きなインパクトがあるため、慎重に判断すべきです。既存の顧客が混乱しないように、デザイン変更の背景や意図をしっかりと説明することも忘れてはいけません。
海外展開するときの注意点は?
海外市場に進出するときは、色やシンボルの意味が国や文化によって異なることに注意が必要です。日本では縁起の良い赤色も、地域によっては危険や警告を連想させることがあります。
また、文字の読みやすさやフォントの適合性も重要です。進出先の文化や習慣を事前にリサーチし、現地ユーザーの目線で違和感がないかを確認することが欠かせません。そのうえで、必要に応じてデザインを調整できる柔軟さをもつと、スムーズに受け入れられるブランドを築けます。
ブランディング費用はどのくらいかかる?
ブランディングデザインの費用は、依頼する範囲や依頼先によって大きく変わります。数万円で依頼できるケースもあれば、Webサイトや広告、ガイドラインを含めて数百万円規模になることもめずらしくありません。
制作会社はチーム体制のため、コストは高めになりがちです。フリーランスなら部分的な依頼ができるため、ロゴのみ数万円で依頼するなど、費用を抑えることができます。目的に応じて選ぶことが大切です。
パンフレットや名刺などの販促物のデザインもフリーランスへ依頼できます。
はじめてデザインを依頼するときは、わからないことも多いはず。以下の資料では、外注の進め方や注意点をまとめています。ダウンロードは無料です。

関連記事:ブランディングの費用相場は?内訳や費用を抑えるコツを解説
ブランディングデザイナーへの依頼の流れとポイント
ブランディングデザインを外注するときは、何を準備してどのように進めるのかを理解しておくことが大切です。ここでは5つのステップにわけて、押さえてほしいポイントを解説します。
1. ブランドコンセプトを整理する
まずは 「自社が大切にしたい価値観や方向性」 を言語化してまとめましょう。これがブランドコンセプトにあたります。
たとえば「信頼感を大切にしたい」「革新的な印象を与えたい」など、顧客にどんなイメージをもってほしいのかを決めてください。プロダクトの特徴や経営理念、これまでの活動内容をまとめておくと、コンセプトを形にしやすくなります。デザイナーと共有することで、認識のズレを防ぐこともできます。
関連記事:コーポレートブランディング会社10選!依頼するメリットや選び方も解説
2. ターゲット顧客と訴求軸を明確にする
次に大切なのは、「誰にブランドを届けたいのか」 を具体的に定めることです。たとえば「20代女性に親しみやすさを伝えたい」「経営層に信頼感を示したい」といった訴求軸を明確にします。
ターゲットがあいまいだとデザインの方向性がぼやけてしまい、誰の心にも残らないデザインとなります。顧客像がしっかりと作られていれば、訴求力の強いデザインと統一された表現により、ブランドの強みをしっかりと伝えることが可能です。
3. デザインガイドラインを用意する
ガイドラインは「ブランドのルールブック」 です。ロゴの使い方、カラーコード、フォントの指定などをまとめることで、どの媒体でも一貫性のある表現が可能になります。
ガイドラインの制作から依頼するときは、基本情報を社内で整理しておくことで、デザイナーが精度の高いガイドラインを作りやすくなります。
完成したガイドラインは社内外に共有し、ブランドイメージを長期的に守る土台として活用しましょう。
関連記事:デザインガイドラインとは?作り方5ステップと基本項目9つ、注意点3つも解説
4. ポートフォリオで実績を確認する
依頼する際は、必ずデザイナーのポートフォリオをチェックしましょう。 これまでの作品を見れば、得意分野やデザインの雰囲気が一目でわかります。たとえば「ロゴに強い」「Webに強い」など専門性は人によって異なるため、自社の目的に合うかどうかを判断する材料になります。ポートフォリオを比較することで、候補者のスキルやセンスの違いも見えてきます。
関連記事:ポートフォリオの意味や役割、評価ポイントをわかりやすく解説
関連記事:ポートフォリオの採用基準とは?効率的に評価するためポイント6つを解説
5. デザインのフィードバックで品質を高める
納品後のフィードバックは品質を大きく左右します。 仕上がったデザインをそのまま使うのではなく、「良い点」「改善したい点」を具体的に伝えることで次の提案のクオリティの向上が期待できます。
継続的に依頼する場合、こうしたやり取りが信頼関係の構築にもつながり、長期的に高品質なブランディングを実現できるようになります。
外注デザイナーとうまくコミュニケーションを取るにはいくつかポイントがあります。以下の資料では、外注デザイナーとのコミュニケーションの実践方法についてまとめています。無料でダウンロードできますので、業務委託人材のマネジメントにお役立てください。
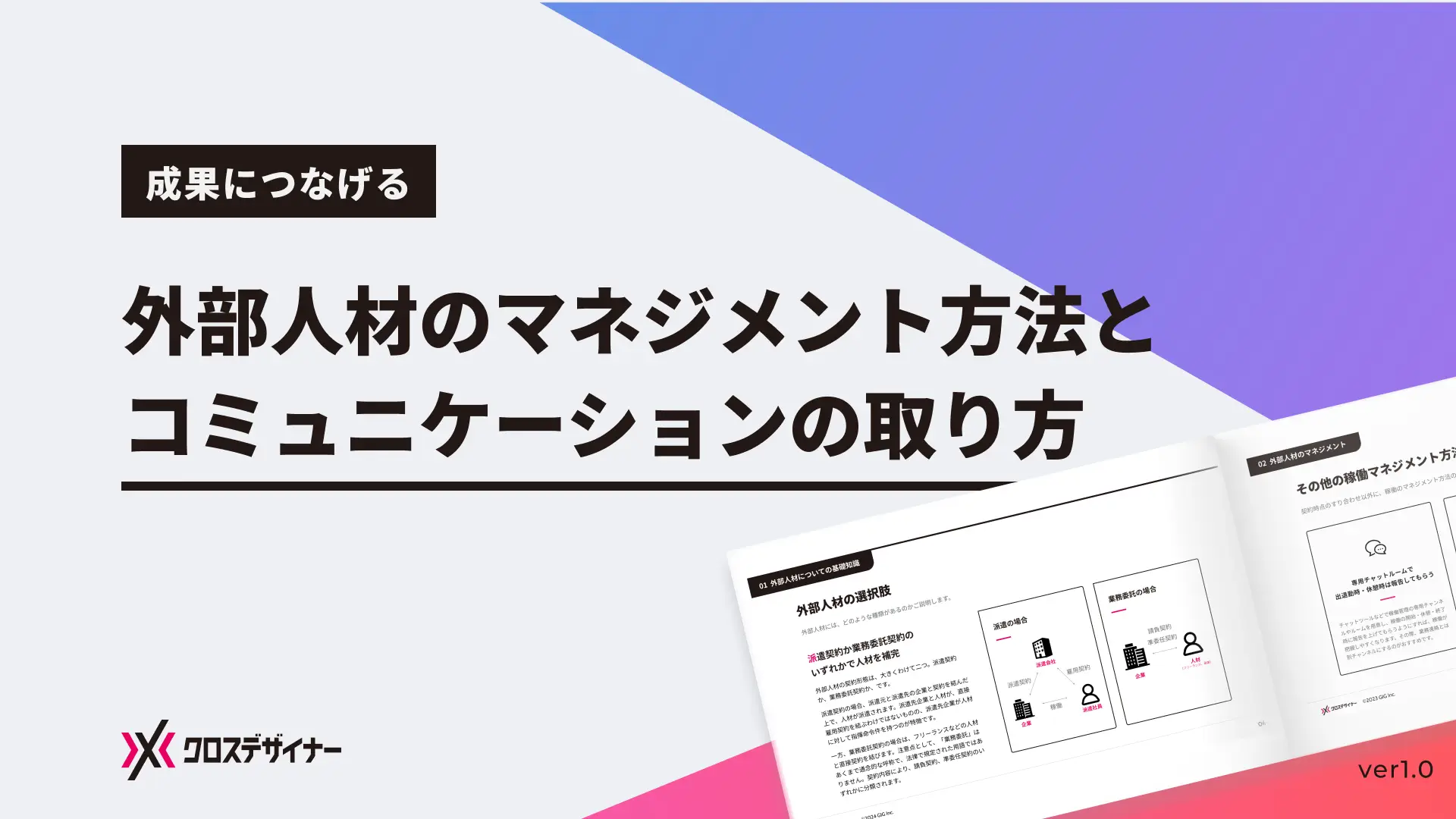
フリーランスデザイナーの採用はクロスデザイナーにおまかせ
ブランディングデザインは、企業価値の向上・維持を目的としたロゴやWebサイトなどの視覚的な要素をデザインすることです。ブランディングデザインに取り組むことで、企業価値の向上だけではなく、他社との差別化や宣伝費の削減につなげることが可能です。
ブランディングのための相談から制作まで受けている制作会社は多く存在しますが、予算が限られているならフリーランスを活用するのもおすすめです。スポット採用も可能なため、知見を得るためのデザインコンサル的な立場でプロジェクトに参画してもらえます。
フリーランスデザイナー専門のエージェントサービスの『クロスデザイナー』は、『Workship』に登録する約7,000人のデザイナーより貴社のご要望に沿った人材の提案が可能です。厳正な審査を通過したハイスキル人材が多く登録しています。業務委託契約についてもサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
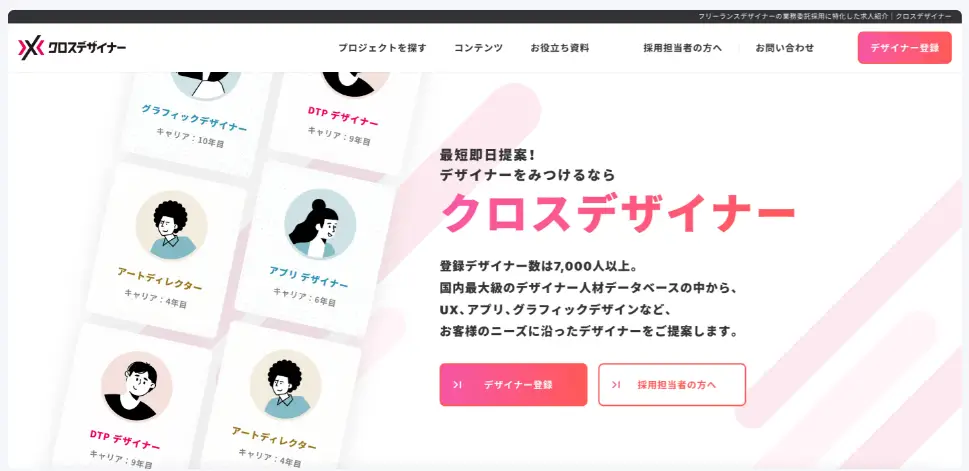
登録しているデザイナーとの合意があれば、正社員としての採用も可能です。また、スカウトや人材紹介機能もあるため、採用難易度の高い即戦力デザイナーを採用できるでしょう。
クロスデザイナーに相談いただければ、最短即日提案から3営業日でのアサインも可能です。また、週2〜3日の勤務といった柔軟な依頼も可能であるため、自社の作業量に応じて効率的な業務委託を実現できます。
こちらより、クロスデザイナーのサービス資料を無料でダウンロードできます。即戦力デザイナーをお探しの方は、【お問合わせ】ください。平均1営業日以内にご提案します。
- クロスデザイナーの特徴
- クロスデザイナーに登録しているデザイナー参考例
- 各サービスプラン概要
- 支援実績・お客様の声
Documents