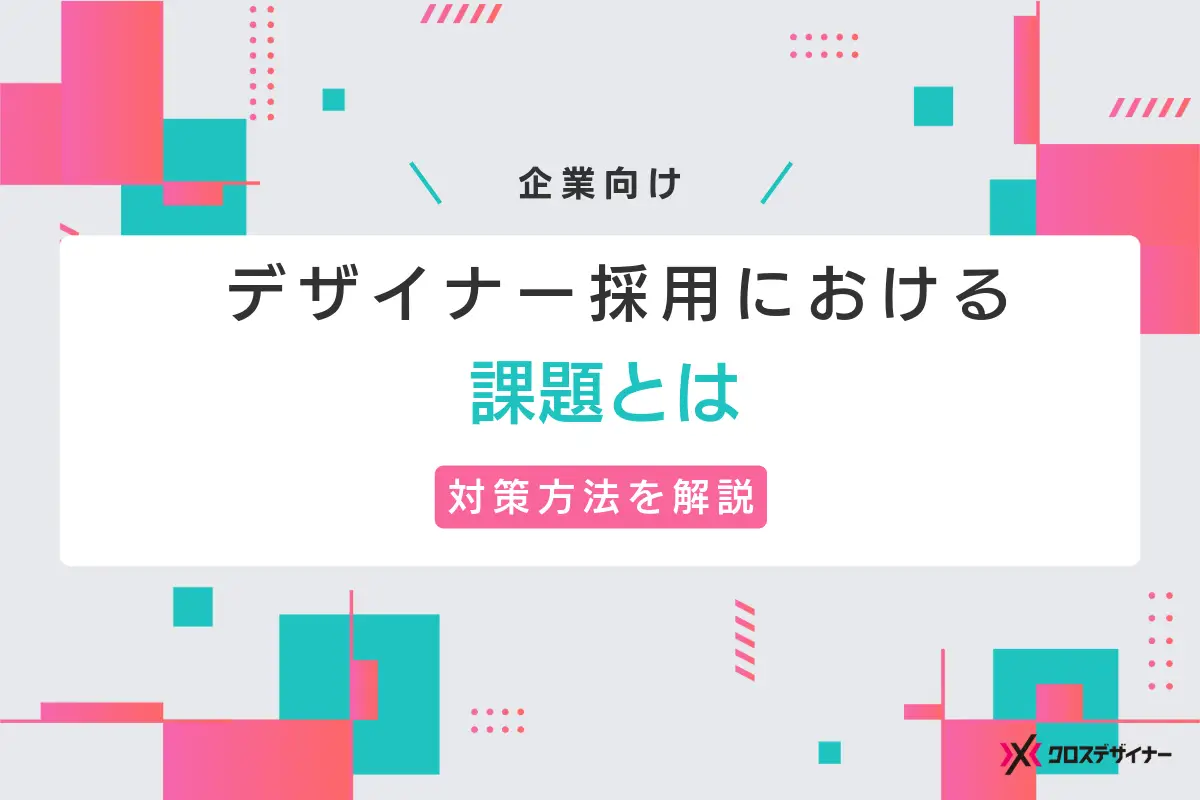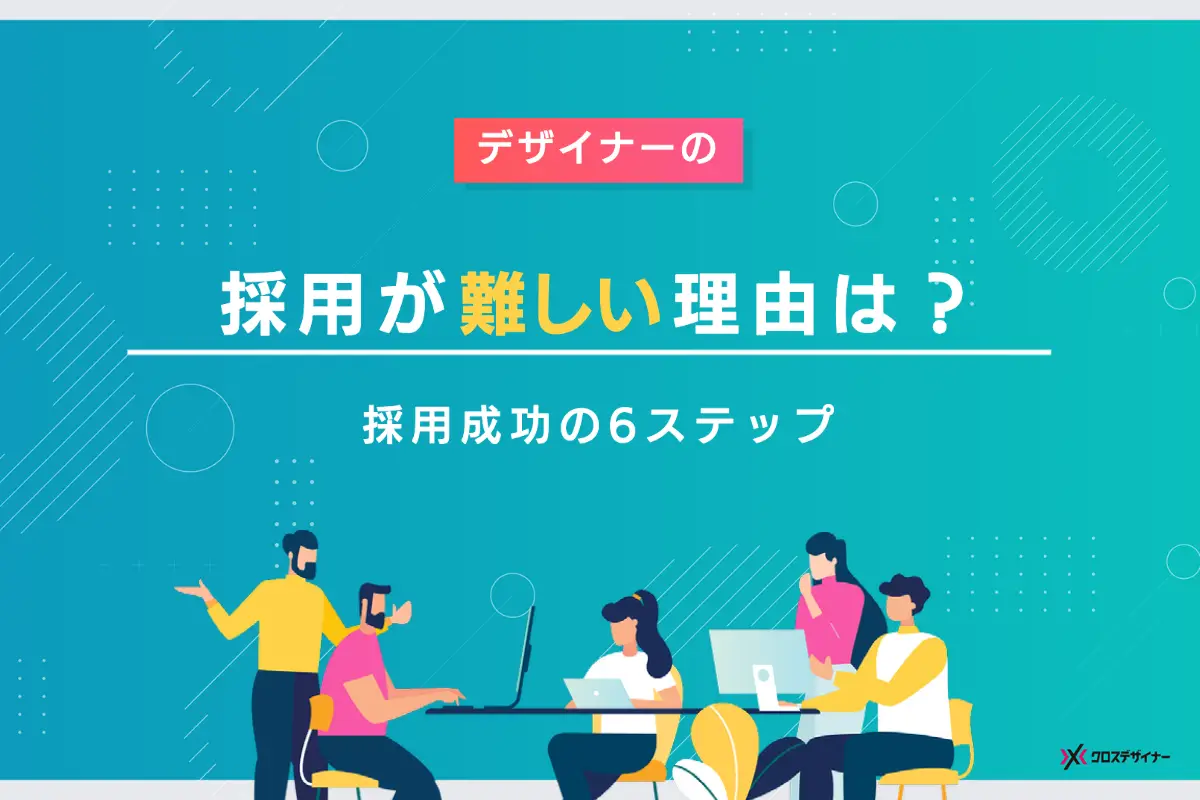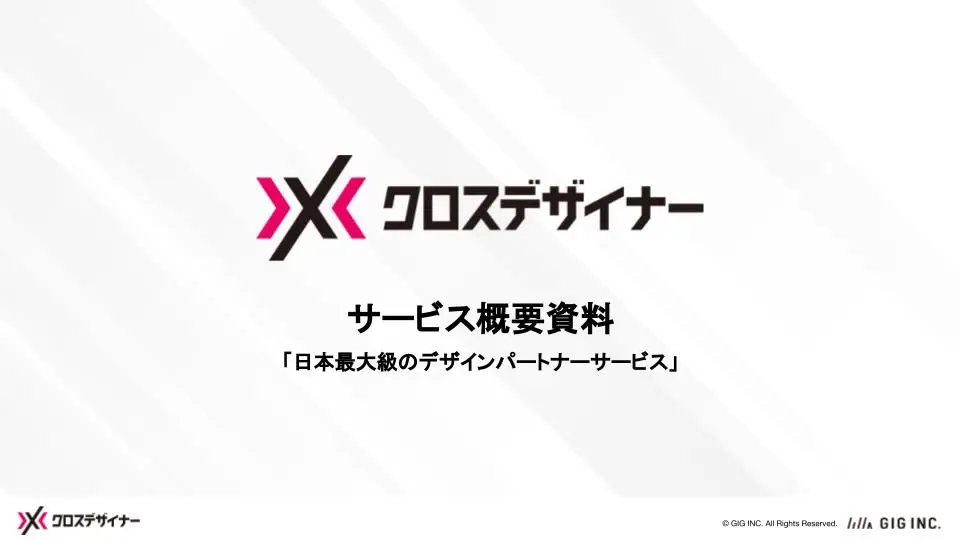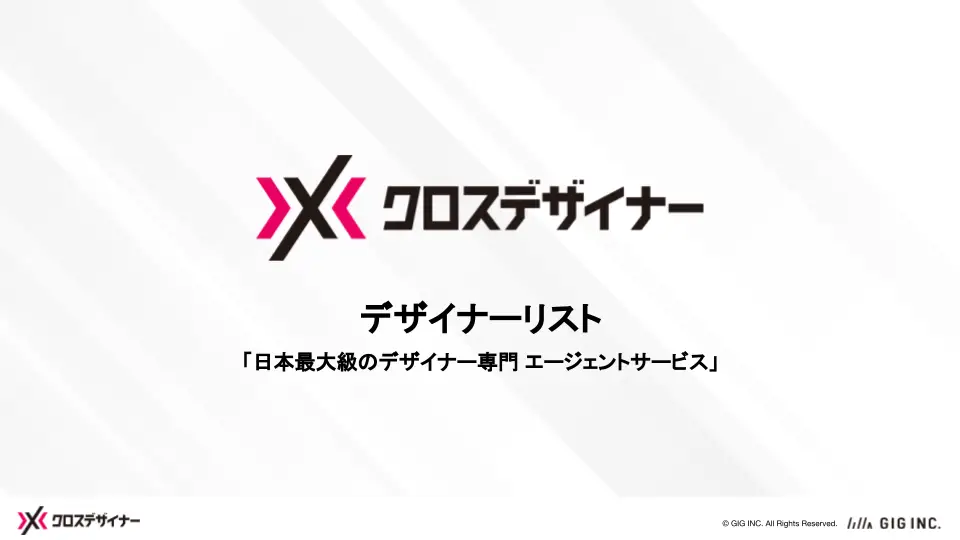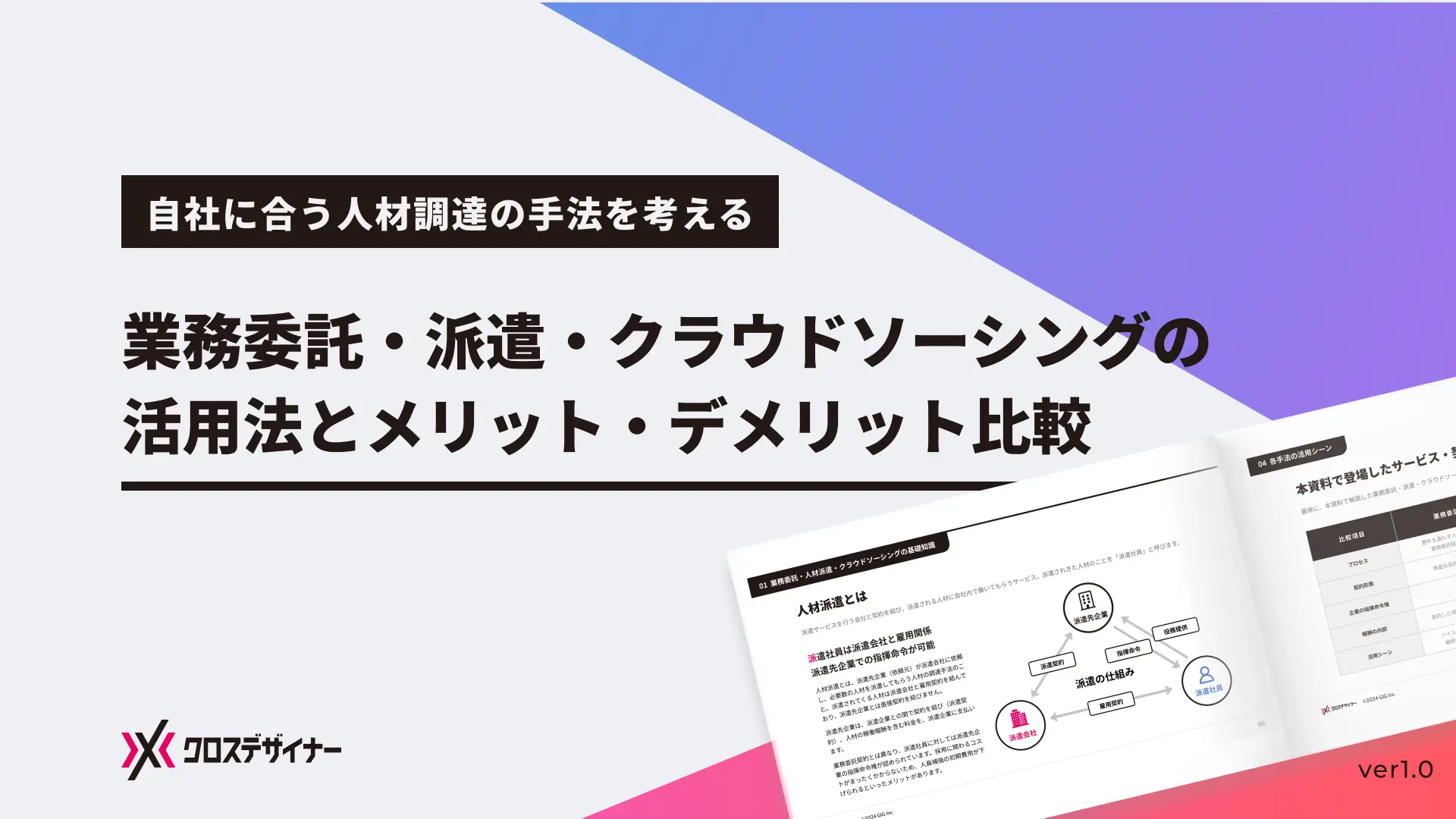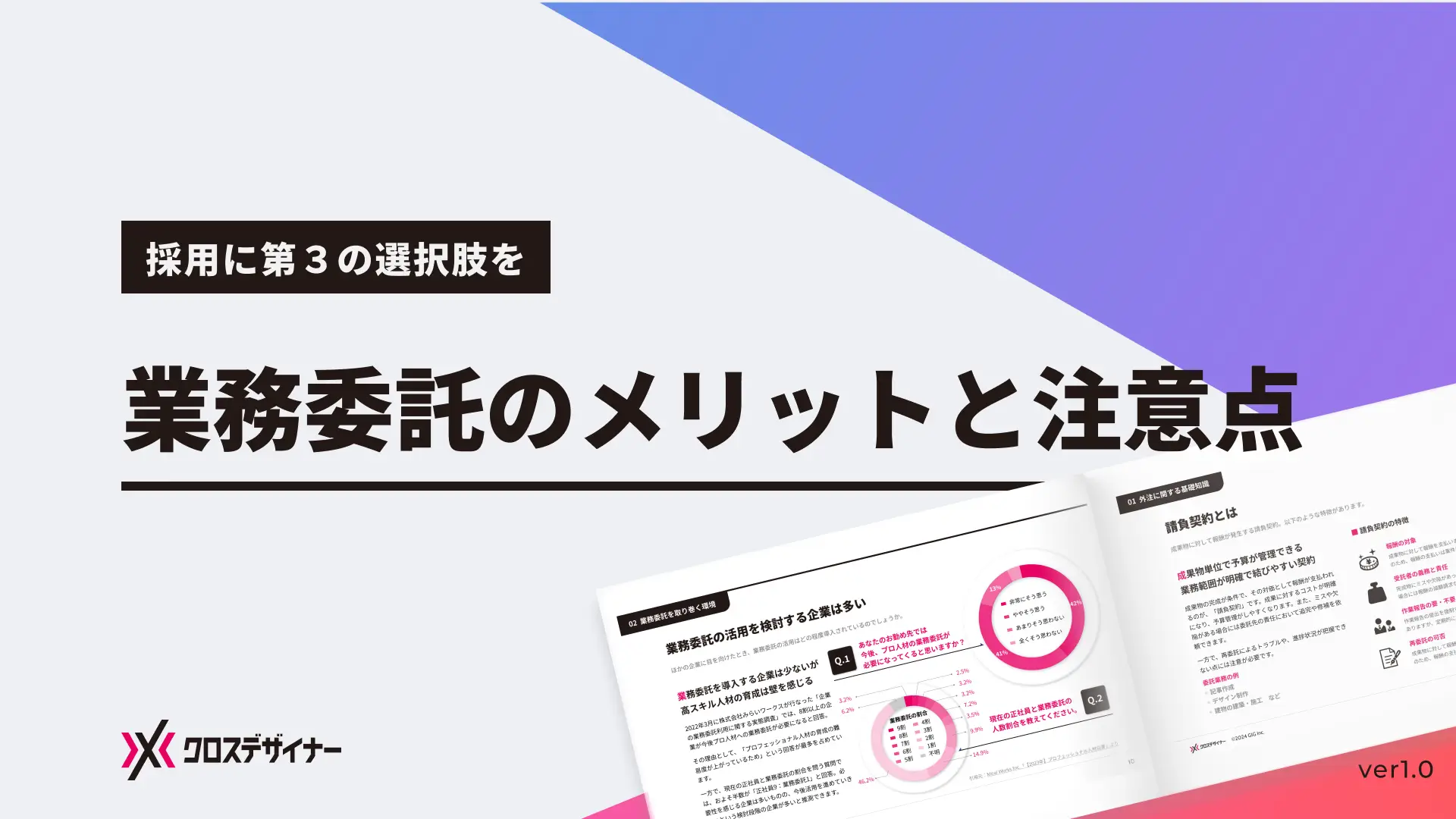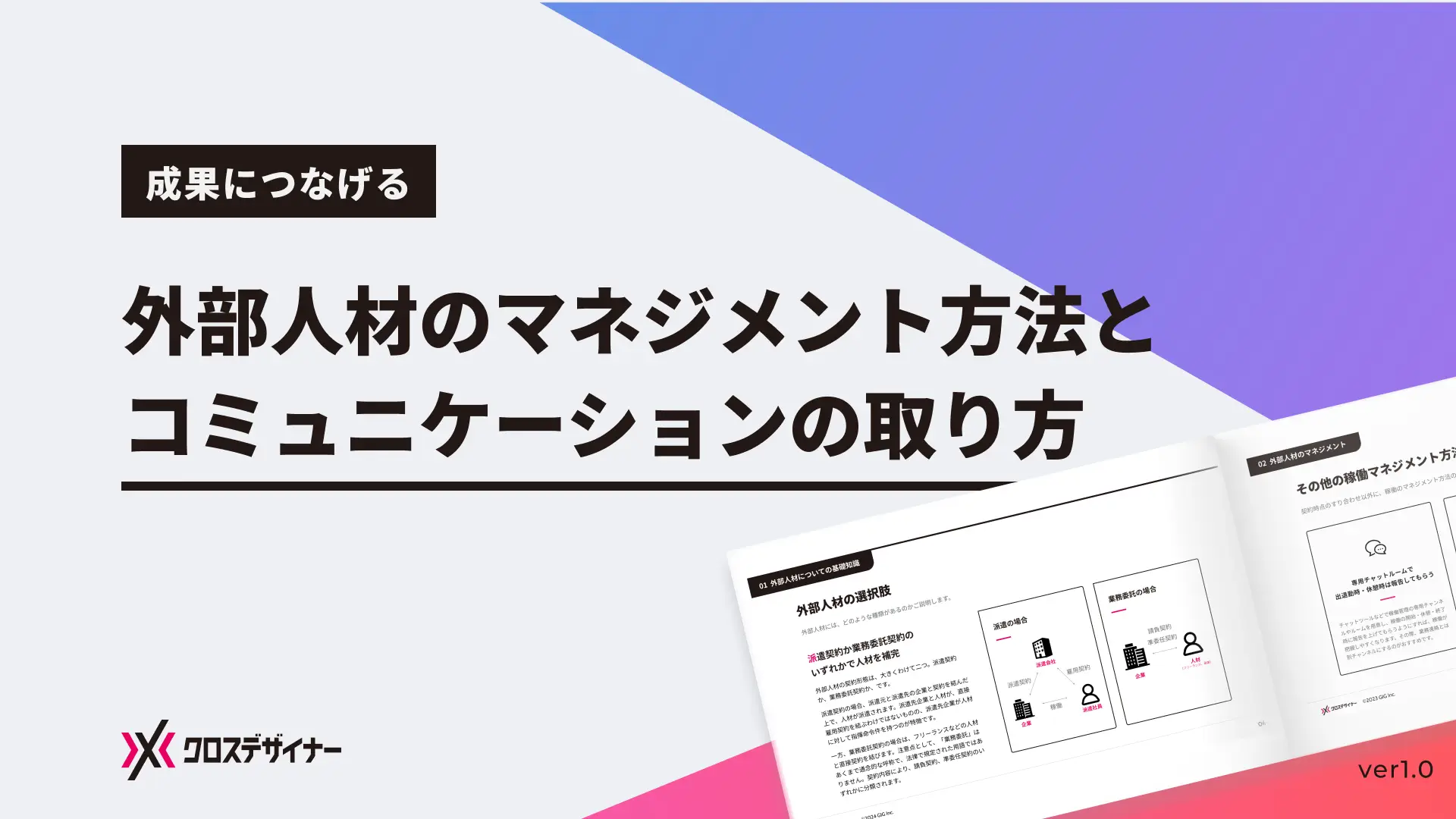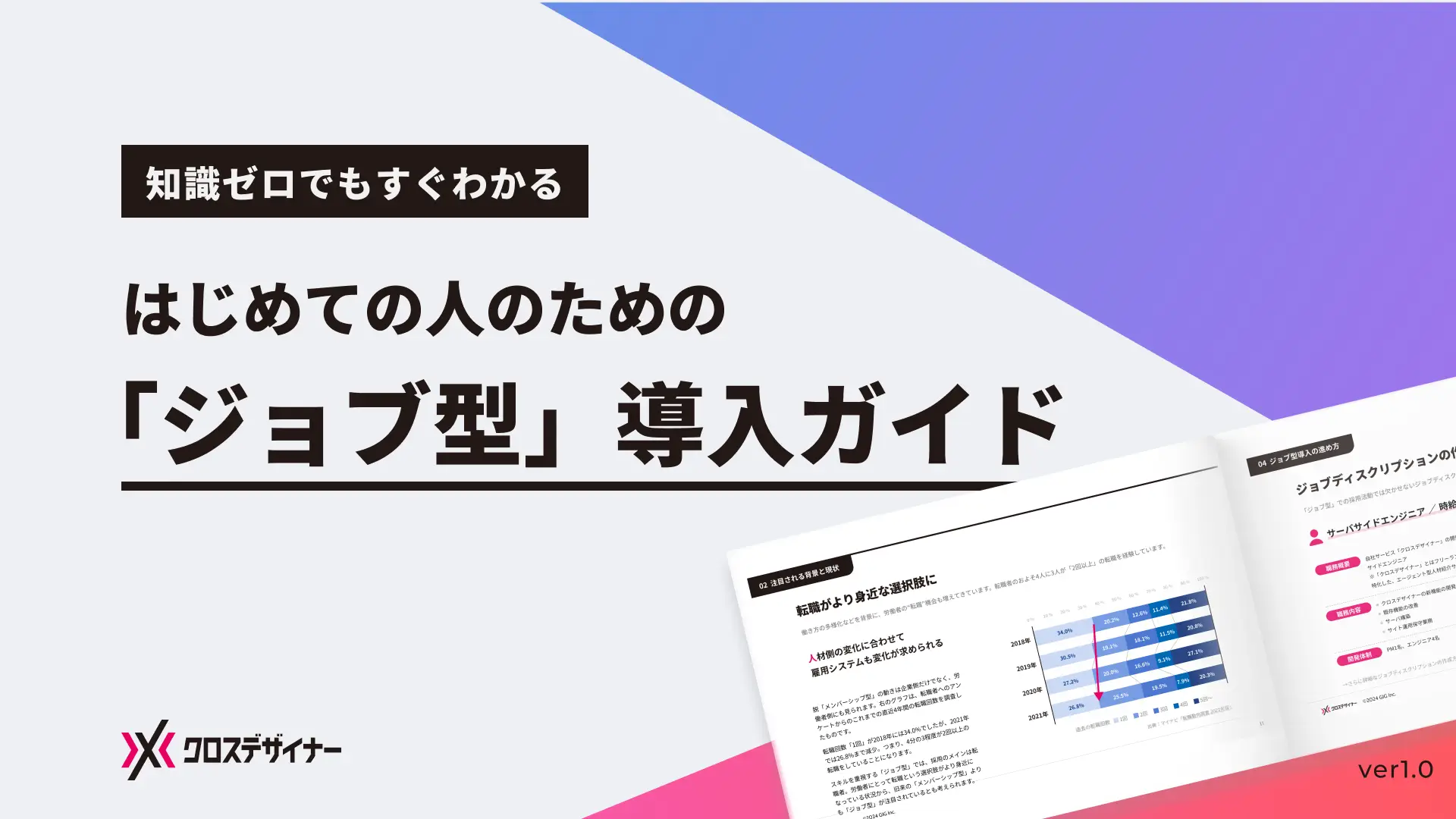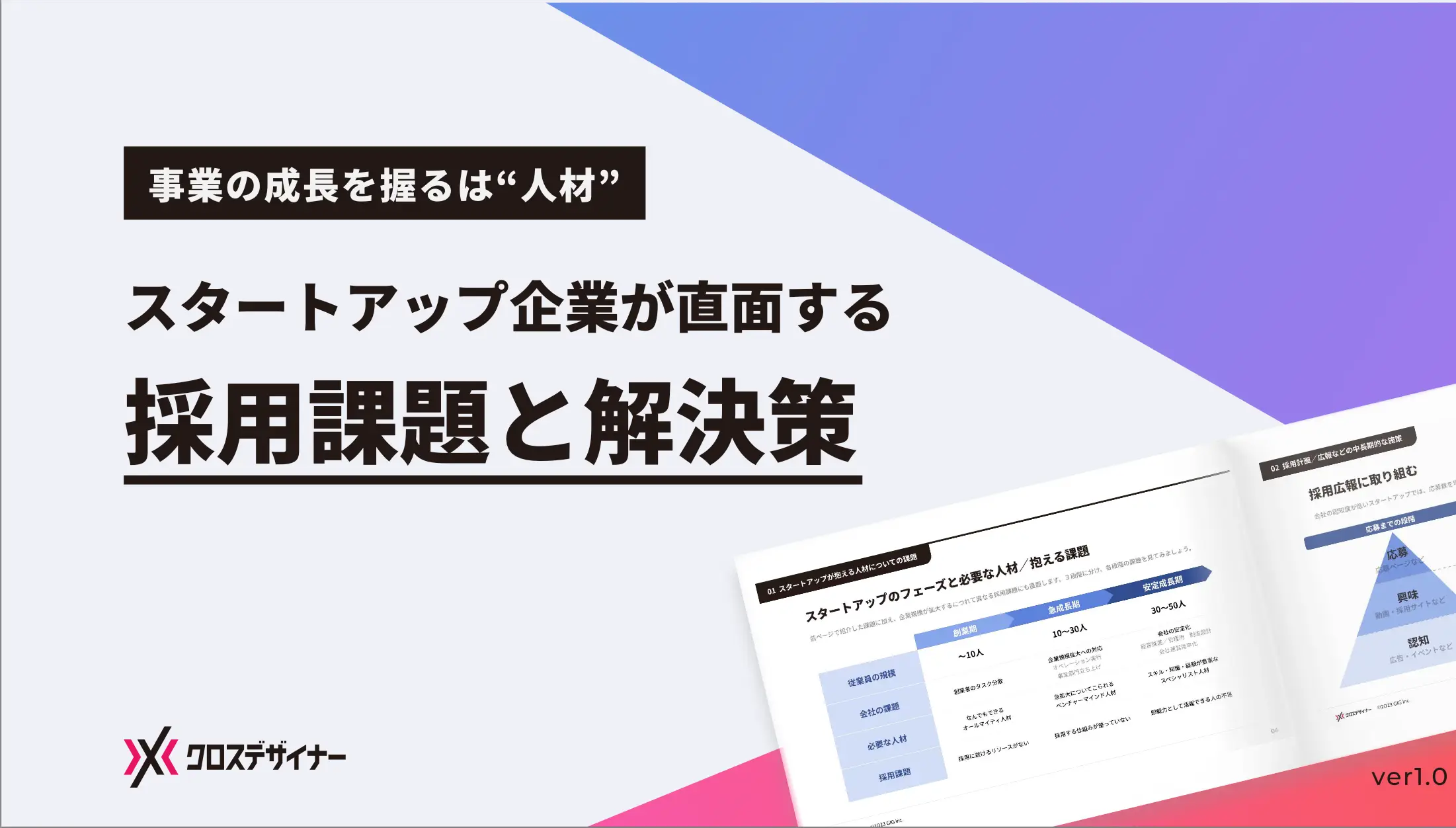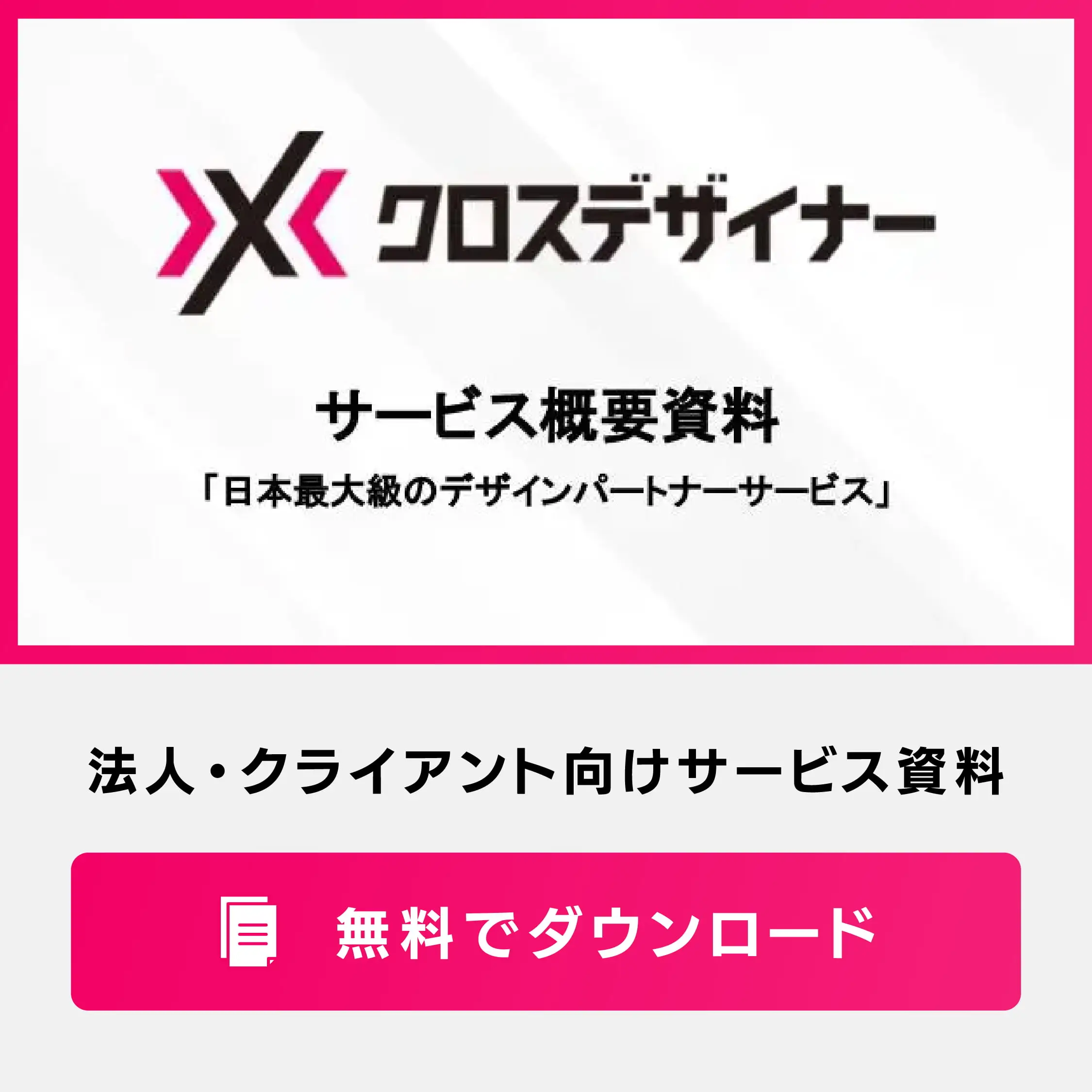業務委託契約を結ぶ際、源泉徴収の要否や納付方法に不安を感じたことはありませんか?
とくに個人事業主やフリーランスへの業務を委託する場合、報酬の支払時に企業側には源泉徴収義務が発生します。さらに、インボイス制度や電子帳簿保存法など、業務委託に関わる法制度は大きく変化しています。
企業は制度を正しく理解したうえで対応しないと、思わぬコスト増や税務リスクにつながるおそれがあるのです。
この記事では、業務委託における源泉徴収の基本から実務に役立つ情報まで解説します。優秀な人材を確保するためにも、ぜひ参考になさってください。
業務委託で源泉徴収が必要となるケース
業務委託契約における源泉徴収の要否は、「誰に」「どのような業務を委託するか」によって異なります。正しく判断しなければ、税務リスクや契約トラブルにつながる可能性があります。ここでは、契約形態や相手の立場に応じた源泉徴収の基本を解説します。
業務委託契約の種類と課税対象の違い
業務委託契約には、主に以下の3つの形態があります。それぞれ、契約目的や報酬の発生条件が異なり、源泉徴収の対象となるかどうかの判断にも影響します。
| 契約形態 | 内容 |
| 請負契約 | 成果物の完成に対して報酬が発生する |
| 準委任契約 | 作業の遂行に対して報酬が発生する |
| 委任契約 | 法律行為の代行に対して報酬が発生する |
これらのうち、所得税法第204条に該当する業務であれば、いずれの契約形態であっても源泉徴収が必要です。契約形態よりも業務の内容が判断の基準となります。
(参考:e-GOV法令検索「所得税法」)
関連記事:外注費の勘定科目の使い方と源泉徴収や消費税などの仕訳例も解説
個人事業主への支払いで対象となるもの
個人事業主への報酬で源泉徴収の対象になる業務には、次のようなものがあります。
- 原稿料、講演料、翻訳料、通訳料
- デザイン、Web制作、映像編集、イラスト制作などのクリエイティブ業務
- プログラミング、システム構築、コンサルティングなどの専門業務
- 弁護士、公認会計士、司法書士などの士業への報酬
単純なデータ入力や事務作業など、専門性が低く、所得税法上の対象に含まれない業務は源泉徴収の対象外となる場合があります。
(参考:国税庁「No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは」)
個人と法人では源泉徴収義務が異なる
源泉徴収が必要かどうかは、委託先が「個人」か「法人」かによっても異なります。
たとえば、同じデザイン業務でも、個人のフリーランスに発注する場合は、源泉徴収が必要です。法人として登記されたデザイン会社への依頼は、基本的に源泉徴収の必要はありません。例外としては、法人の馬主に賞金を支払うケースなどがあります。
委託先が法人か個人かわからないときは、契約前に確認しておくことが大切です。
個人事業主・副業フリーランスで変わるのか
副業として活動している会社員でも、業務内容が源泉徴収の対象に該当すれば、原則として源泉徴収をおこなわなくてはいけません。
たとえ開業届を出していない副業フリーランスであっても、原稿料や制作報酬を支払う場合、企業側に源泉徴収義務が発生します。
開業届を出しているかどうかよりも、「報酬を支払う相手が個人であるか」「業務内容が対象かどうか」が判断基準になります。
(参考:国税庁「No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは」)
▼下記の資料では、業務委託・正社員・派遣など複数の雇用形態を比較し、特徴を解説しています。無料でダウンロードできますので、ぜひ貴社の外注業務にお役立てください。

源泉徴収税額の計算と帳票の作成方法
源泉徴収を行う際には、税額の計算方法や記載すべき帳票について正しく把握する必要があります。ミスを防ぐためにも、基本ルールと書類対応を理解しておきましょう。
計算方法と税率の基本ルール
源泉徴収税額は、支払金額の総額(原則、税込金額)に対して、以下の税率を適用して計算します。
支払金額(A) | 税額 |
100万円以下 | (A)×10.21% |
100万円超 | (Aー100万円)×20.42%+102,000円 |
委託業務がデザイン制作だったときに、報酬50万円と120万円のそれぞれの源泉徴収税を計算してみましょう。
<50万円の報酬を支払う場合>
50万円 × 10.21% =源泉徴収税額51,050円
<120万円の報酬を支払う場合>
(120万円 - 100万円)× 20.42% + 102,000円 =源泉徴収税額142,840円
復興特別所得税は、東日本大震災の復興に必要な財源を確保するための税金です。2013年1月1日から2037年12月31日までの間、源泉徴収義務者は納税者の基準所得額より2.1%相当額を徴収しなければなりません。
源泉徴収税率 10.21% | |
所得税率 10% | 復興特別所得税率 0.21% |
基準所得額が100万円未満で所得税率が10%の場合、復興特別所得税率は「10%×2.1%=0.21%」となるため、あわせて10.21%を使用して納付額を求めます。
税込・税抜の判断とその影響
源泉徴収額の計算は、原則として税込金額を基準に行います。ただし、請求書に「報酬額」と「消費税額」が明確に区分されて記載されている場合は、税抜金額で計算することも可能です。
ただしこの取り扱いには条件があります。弁護士・税理士などの士業、またはインボイス(適格請求書)発行事業者であることが前提です。
適格請求書発行事業者でない個人事業主などが発行した請求書については、たとえ明確に区分されていても、税込金額での計算が必要になるため注意が必要です。
どちらの方法で処理するかは、インボイス登録の有無や、取引先との契約内容に応じて判断しなければなりません。
(参考:国税庁「No.6929 消費税等と源泉所得税及び復興特別所得税」)
支払調書と源泉徴収票の違い
源泉徴収に関連して発行される帳票には主に以下の2つがあります:
| 書類 | 発行対象 | 内容 |
| 支払調書 | 税務署および報酬の受取人 | 源泉徴収した金額や報酬額などを記載 |
| 源泉徴収票 | 従業員(給与所得者) | 年末調整後の所得税額などを記載 |
業務委託契約のフリーランスや個人事業主に対して発行するのは「支払調書」であり、源泉徴収票ではありません。名称が似ているため混同しないよう注意が必要です。
(参考:国税庁「No.2110 事業主がしなければならない源泉徴収」)
源泉徴収票の発行が必要なケース
業務委託先が給与所得者(正社員やアルバイトなど)である場合には、年末に源泉徴収票の発行が必要です。
個人事業主やフリーランスとの契約では、通常「支払調書」を発行します。源泉徴収票とは別の帳票であり、支払金額や源泉徴収税額などが記載されたものです。
ただし、税務に不慣れなフリーランスや副業者のなかには、源泉徴収票と支払調書を混同しているケースも少なくありません。その結果、源泉徴収票の発行を求めてきたり、書類の不備として誤解されたりすることがあります。
企業側としては、適切な帳票の種類や法的な発行義務について把握しておくとともに、ていねいに説明できる体制を整えておくことでトラブル防止につながります。
(参考:国税庁「法定調書(源泉徴収票、支払調書)の作成と提出」)
▼下記の資料では、デザイン業務の外注とデザイナー採用についてコストを中心に比較し、双方のメリット・デメリットを解説しています。無料でダウンロードできますので、ぜひご活用ください。
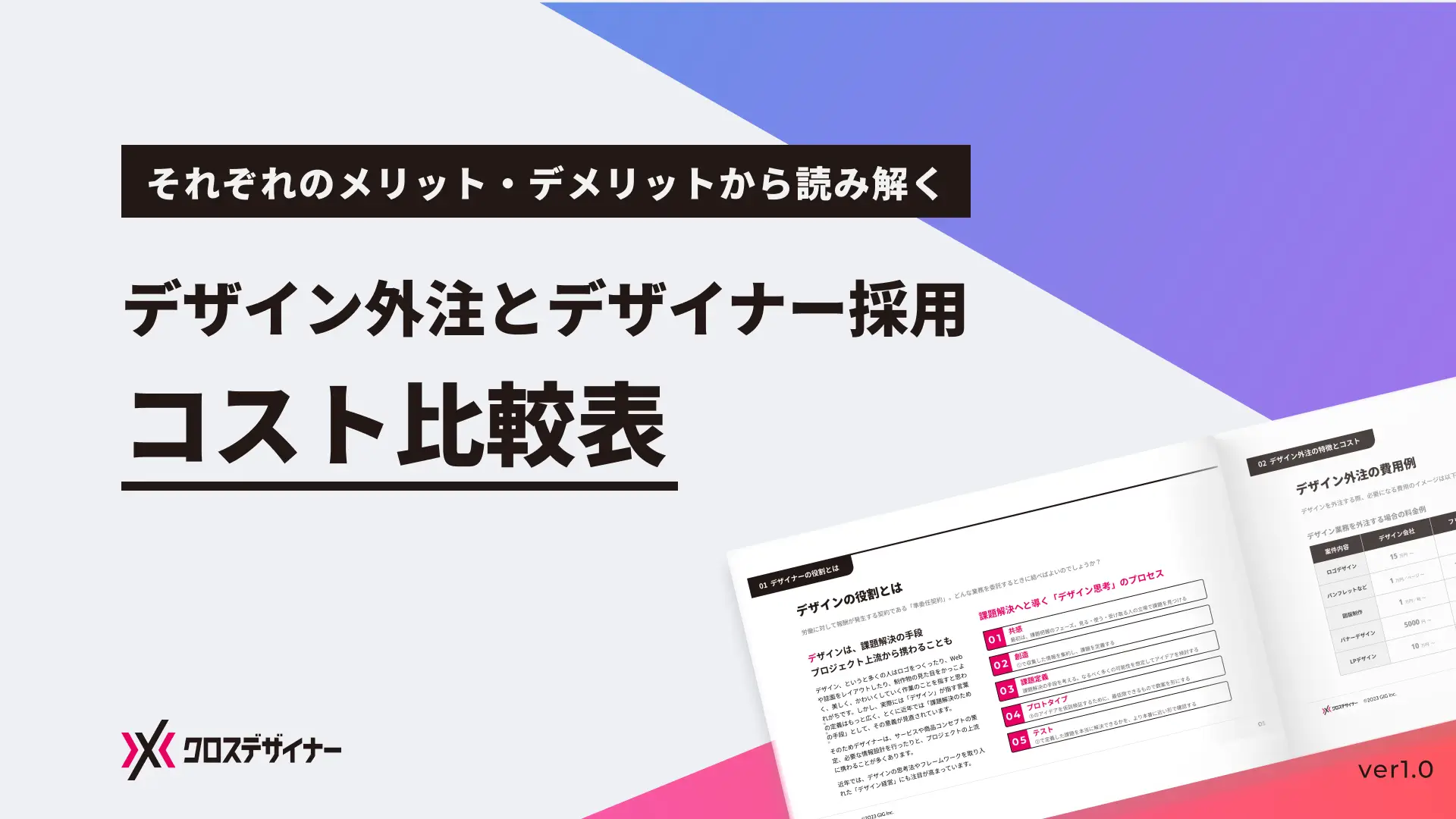
源泉徴収税の納付業務と注意点
源泉徴収を正しく行っても、納付期限や手続きを誤ると、税務署から指摘を受けるリスクがあります。企業側が担う納税義務として、納付方法・記載ルール・期限の管理を正しく理解しておくことが大切です。ここでは、申告・納付業務をスムーズに進めるためのポイントについて解説します。
源泉徴収税の納付と遅延ペナルティ
源泉徴収税の納付期限は、報酬を支払った月の翌月10日です。1日でも遅れると延滞税や不納付加算税(原則10%)の対象となるため注意が必要です。
<例>
8月中に報酬を支払った場合 → 9月10日までに納付
納付が遅れると、税務署から指摘を受けたり、税務調査で指摘事項に含まれることもあります。報酬を支払ったタイミングで社内の税務・経理と連携し、納付計画を立てておくと安心です。
(参考:国税庁「No.6929 消費税等と源泉所得税及び復興特別所得税」)
関連記事:業務委託に確定申告や源泉徴収は必要なし?委託と受託、双方の視点から解説
源泉徴収税は金融機関やe-Taxで納付できる
源泉徴収税は以下の方法で納付できます。
手続方法 | 概要 |
ダイレクト納付 | e-Taxで預貯金口座より振替納付 |
インターネットバンキング(登録方式) | インターネットバンキングから納付 |
インターネットバンキング(入力方式) | ATMで電子納税 |
クレジットカード納付 | 「国税クレジットカードお支払サイト」から納付 |
スマホアプリ納付 | |
コンビニ納付(QRコード) | QRコードをコンビニエンスストアに持参して納付 |
電子納税は便利な一方で、紙の領収書が発行されません。納税記録として、納付画面のキャプチャ保存や出力が必要になります。経理書類として記録管理できる体制を整えておくことが大切です。
(参考:国税電子申告・納税しステム e-Tax 電子納税)
納付書の記載・入力例
源泉徴収税の納付書は、支払う報酬の内容によって種類が異なります。
デザイナーなどの個人事業主に源泉徴収が発生する場合、所轄税務署に納める際は「報酬・料金等の所得税徴収高計算書」に記載します。
| 項目 | 記載 |
| 納期等の区分 | 報酬を支払った年月 |
| 区分 | 報酬の内容に合ったコード |
| 人員 | その月の報酬を支払った実人員 |
| 支払額 | その月に支払った報酬や生命保険などの総額 |
デザイン業務やライティング業務など、請負契約や準委任契約に基づく業務委託で源泉徴収を行う場合、区分コード「01(原稿料・講演料)」を使用することが多いです。
区分コードは国税庁の「納付書の記載のしかた(報酬・料金等の所得税徴収高計算書)」に掲載されています。内容に誤りや記載漏れがあると修正や再納付が必要になるため、各項目を正しく記入しましょう。
(参考:国税庁「納付書の記載のしかた(報酬・料金等の所得税徴収高計算書)」)
納期の特例が使える条件と申請手順
源泉徴収の納付は、原則として報酬を支払った翌月10日までに納付が必要です。しかし、常時雇用する従業員が10人未満の企業は、年2回にまとめて納付できる特例制度があります。
<適用条件>
- 常時雇用が10人未満(業務委託先やアルバイト等は除外)
- 所轄税務署に「納期の特例の承認申請書」を提出する
<納期スケジュール>
- 1月〜6月分:7月10日までに納付
- 7月〜12月分:翌年1月20日までに納付
特例の申請は年度途中でも可能ですが、適用開始には時間を要することがあるため、早めの準備が推奨されます。
インボイス制度が与える業務委託への影響
制度の変更は企業側の業務委託契約にも大きな影響を及ぼします。支払先のインボイス登録状況によっては仕入税額控除が受けられず、コスト構造や契約条件の見直しが必要になることもあります。
ここでは、インボイス制度が与える業務委託への影響について解説します。
インボイス施行後の基本的な対応
インボイス制度が施行される前は、課税事業者であれば免税事業者からの請求書でも仕入税額控除ができるケースがありました。しかし、現在は「適格請求書(インボイス)」を発行できる事業者(=登録した課税事業者)からの請求書でない限り、仕入税額控除は認められなくなりました。
取引先が未登録の場合、制度上控除できないぶんだけ、実質的に企業の負担が増えることになります。仕入税額控除を継続したい場合は、インボイス発行事業者との取引またはエージェント経由などの構造的対策が必要です。
2割特例終了による影響
「2割特例」とは、インボイス制度が始まったときに設けられた経過措置です。課税事業者へ移行したことで、発生する消費税の納付義務をスムーズに処理できるように、負担を軽減するための措置となります。
しかし、この特例制度は 2026年9月30日までの適用となっており、翌年からは廃止です。特例期間の終了後は、企業と委託先の双方が「簡易課税」または「本則課税」の選択を迫られ、税務負担が大きく変わる可能性があります。
とくにフリーランスや個人事業主など、小規模な委託先にとっては報酬の見直しや契約解除、登録への転換を検討する重要な分岐点となります。
フリーランスとの契約継続を判断する
適格請求書発行事業者でない個人事業主との取引では、仕入税額控除が受けられないため、発注企業にとっては実質的なコスト増となります。しかし、インボイス登録をしていないからといって、すぐに契約を打ち切ることが正解とは限りません。
とくにスキルや信頼性の高い人材とは、関係性を大切にしつつ、双方にとって納得できる条件での継続を目指すことが重要です。その一環として、取引コストの変化を踏まえたうえで報酬アップの交渉に応じるなどの柔軟な対応も求められるでしょう。
このように、制度変更によって委託費用や契約形態の見直しが必要となる場面では、費用対効果・人材確保・税務コストのバランスをとりながら、次の判断につなげることがポイントです。
業務委託費用と契約形態の見直しポイント
委託費用に係る税負担の考え方が変わりつつあります。報酬アップの相談や、正社員を希望するケースもあるなかで、企業側は費用対効果や採用方針をふまえて契約形態を見直す必要があります。ここでは、業務委託費用と契約形態を見直すためのポイントについて解説します。
報酬アップを依頼されたときの対応
インボイス登録によって消費税の納税義務が発生し、フリーランス側の実質的な手取りが減少するケースもあります。こうした背景から報酬アップの相談があった場合は、フリーランスの背景を理解したうえで、契約内容や成果の範囲を再確認しましょう。
源泉徴収の有無なども含め、税負担の分配を企業としてどう判断するかが求められます。
関連記事:デザイナーの年収はどのくらい?職種別の傾向と適正報酬の考え方を解説
正社員とフリーランスの採用コスト差
報酬アップの打診を受けた際、「それなら正社員として雇ったほうがいいのでは」と考える担当者も少なくありません。
しかし実際には、正社員の採用には求人広告費や選考・面接の手間、入社後の教育コストなどが発生し、採用コストは非常に高くなります。さらに雇用後は、社会保険料や福利厚生費などの固定費も企業側の負担となります。
一方で、フリーランスなら業務量に応じて必要なスキルだけを業務委託で依頼できるため、業務委託費用のみで済み、コストを抑えながら柔軟に対応できます。
また、フリーランスへの報酬支払いでは源泉徴収の義務が発生するケースもありますが、税額は報酬に対して一定割合で計算されるため、支払いのコントロールがしやすいというメリットもあります。
税務処理もきちんと管理すれば、大きな負担にはなりません。
関連記事:「フリーランスの約35%が正社員転換を検討」フリーランス・副業向けマッチングサービス『Workship』がキャリア動向調査を実施
業務内容にあわせて契約形態を見直す
コストを抑えつつ適切な人材活用をおこなうには、業務の内容や指示の仕方に応じて契約形態を見直すことが重要です。
たとえば、プロジェクト単位で成果物を納品するような業務であれば、業務委託契約を活用することで柔軟な発注が可能です。
日々の業務を社内メンバーと同じ体制で進める必要がある場合や、企業側が指揮命令を直接行う体制であれば、雇用契約のほうが適しているケースもあります。
契約形態を誤ると、形式上は業務委託でも実態は雇用に近い「偽装請負」とみなされるリスクもあるため注意が必要です。源泉徴収の対象範囲も契約形態によって異なるため、法務・労務・税務の観点からも整理しながら判断していきましょう。
関連記事:採用コストの相場と削減方法7選、効果的な人材獲得方法や注意点も解説
▼下記の資料では、業務委託の各契約形態ごとの概要や特徴を詳しく解説しています。無料でダウンロードできますので、ぜひ参考にしてください。

業務委託の源泉徴収でよく聞かれるトラブルと対応策
業務委託で源泉徴収する場合、契約形態や税務の知識が絡むため、社内でも判断がわかれたり、委託先と認識がずれたりすることがあります。ここでは、実務の現場でよく起こるトラブルの例と対応策について解説します。
源泉徴収の対象か判断できない
業務内容によって源泉徴収の要否がわかれるため「これは対象か?」と迷うケースは多いです。たとえば、デザインや執筆業務は対象ですが、事務代行などは対象外となる場合があります。
契約内容と業務実態を照らし合わせて、迷うときは国税庁のガイドラインを確認するか、税理士への相談が確実です。
源泉徴収額の計算ミスが発生した
源泉徴収額は、報酬金額に一定の税率をかけて算出されますが、「消費税を含めた金額で誤って計算した」「100万円超の税率(20.42%)の適用漏れ」など、ミスが発生するケースもあります。
ミスに気づいた時点での対応フローは以下のとおりです。
| ミスに気づいたときの状況 | 対応方法 |
| 納付前 | 正しい金額で納付し直す |
| 納付後(過少納付) | 修正して追加納付する |
| 納付後(過大納付) | 所轄税務署へ「還付請求」などの対応を検討する |
ミスを防ぐためには、請求書や明細書で消費税の内訳(税抜・税込)を明確に確認することが重要です。とくにインボイス制度では、適格請求書発行事業者からの請求書であれば税区分が記載されていますが、非登録事業者や不備のある書類では判断を誤る可能性があります。
関連記事:デザイナーに支払う報酬に源泉徴収が必要となるケースや計算方法を解説
源泉徴収の還付を求められた
フリーランスや個人事業主と取引する中で、「源泉徴収された税金を返してほしい」といった問い合わせを受けることがあります。企業側としては、還付の仕組みを正しく理解し、冷静かつていねいに対応することが大切です。
<基本的な対応>
- 受託者本人が確定申告で税務署から還付を受ける仕組みを説明
- 企業が直接返金したり追加の支払調整をしたりする必要はない
そのため、請求者が源泉徴収の仕組みに詳しくない場合でも、制度の概要と確定申告の必要性をていねいに案内しましょう。
また、もし企業側が源泉徴収の必要がない取引に対して誤って税を差し引き、すでに税務署へ納付してしまっていたケースでは、企業が「過納額還付請求書」を税務署に提出して還付を受ける必要があります。
誤徴収を避けるためにも、契約書に源泉徴収の有無を明記し、請求書にも報酬と消費税の内訳が明記されているかを確認する体制を整えることが重要です。
(参考:国税庁「No.2506 源泉徴収義務者が誤って源泉徴収した場合」)
納付期限を過ぎてしまった
源泉徴収税は、報酬支払月の翌月10日までに納付する義務があります。期限を過ぎた場合は、延滞税や不納付加算税などのペナルティが発生します。
とくに業務量の多い月や担当者交代時などは、納付忘れが起こりやすいため注意が必要です。
<納付が遅れた場合の対応>
- 気づいた時点ですぐに納付する
- 延滞税を含めた金額で納付する
- 再発防止策を検討する
再発防止策とは、担当者間の共有やリマインドなどです。複数人で納付スケジュールを共有することで防ぎやすくなります。
また、常時雇用10人以下の企業なら「納期の特例」を利用することで年2回まとめて納付も可能です。
あとから源泉徴収対象と判明した
契約時には源泉徴収が不要と判断していた業務でも、後から税務署の指摘や社内確認で「源泉徴収対象だった」と判明するケースがあります。
報酬の内容や契約形態が曖昧な場合、このような判断ミスは起こりがちです。
<よくあるケース>
- デザインや執筆など、源泉徴収対象となる業務内容であるにもかかわらず、対象外と誤認
- 業務委託先が「法人」だと思っていたが、実際は「個人事業主」だった
- 契約書に業務内容や源泉徴収の有無が明記されていない
<対応方法>
- 支払済の報酬から遡って源泉徴収分を算出
- 対象月の源泉徴収税を速やかに納付
- 業務内容や委託先の属性を整理し、次回以降の契約では明記する
誤りに気づいた時点で適切に対応することで、大きなトラブルに発展することを防げます。遅延している場合は、遅延税にも注意しましょう。
関連記事:業務委託契約を締結する際に起こりがちなトラブル事例6つと対処法を解説
源泉徴収をふまえた業務委託の導入方法
源泉徴収をするときは、契約書の整備から税務処理、体制づくりなどの準備が必要です。ここでは源泉徴収をふまえた業務委託の導入方法について解説します。
業務委託契約書とNDAも用意する
源泉徴収には納税者の氏名や住所などの個人情報が必要ですが、個人情報を提供するにあたって抵抗を示す個人事業主やフリーランスも少なくありません。NDA(秘密保持契約書)は預かった個人情報を適切に扱うことを約束する契約書です。
クラウドソーシングを利用する場合もNDAの締結は可能です。匿名で活動しているフリーランスや個人事業主が多いため、安心して受注してもらうためにもNDAの締結をお考えください。
▼下記の資料では、業務委託契約に不可欠な契約書の作成ポイントを網羅的に解説しています。無料でダウンロードできますので、ぜひご活用ください。

業務委託の受け入れ体制を作る
業務委託の導入には、税務・契約・業務進行の各面での分担と連携が求められます。社内で源泉徴収を正しく理解している担当者を明確にし、取引先に不安を与えないような体制を整備しましょう。
とくに初めて業務委託をする場合や、複数のフリーランスと取引するときは、対応フローの共有やマニュアル整備を進めておくと安心です。トラブルが起きたときのために、源泉徴収税について説明できる体制を整えておきましょう。
もし委託先が無申告でペナルティを受けて業務を続けられなくなると、企業側にとっても大きなデメリットとなります。業務委託契約を結ぶときに、内容について双方で確認しておくことが大切です。
関連記事:はじめての業務委託を成功させるポイントと注意点を徹底解説
はじめて外注するときは源泉徴収以外にも気になることが多いものです。
▼自社業務をはじめて外注する際は不安を感じる方も多いはず。下記の資料では、外注の流れとポイントをステップ別に解説しています。無料でダウンロードできますので、ぜひご活用ください。

エージェントを活用する
フリーランスや個人事業主と直接契約を結ぶことに不安があるときは、人材エージェントの活用も有効な手段です。
エージェント経由で業務委託契約を結ぶことで、源泉徴収や契約手続きなどの実務を代行してもらえるため、社内負担を大きく軽減できます。
また、スキルや実績に応じたマッチングが可能なため、適切な人材を効率的に採用できるのも大きな利点です。
関連記事:企業が業務委託にエージェントを活用するメリットと選び方のコツを解説
関連記事:人材紹介を利用する際のヒアリング項目と内容、依頼時のポイントを解説
業務委託人材を採用するならクロスデザイナーにおまかせください
業務委託は源泉徴収の対象です。委託先が正しい知識をもっているとは限りません。トラブルに備えて社内で体制を整えておくことが大切です。もし、ペナルティなど不安があるときは、業務委託契約をサポートするエージェントを活用する方法もあります。
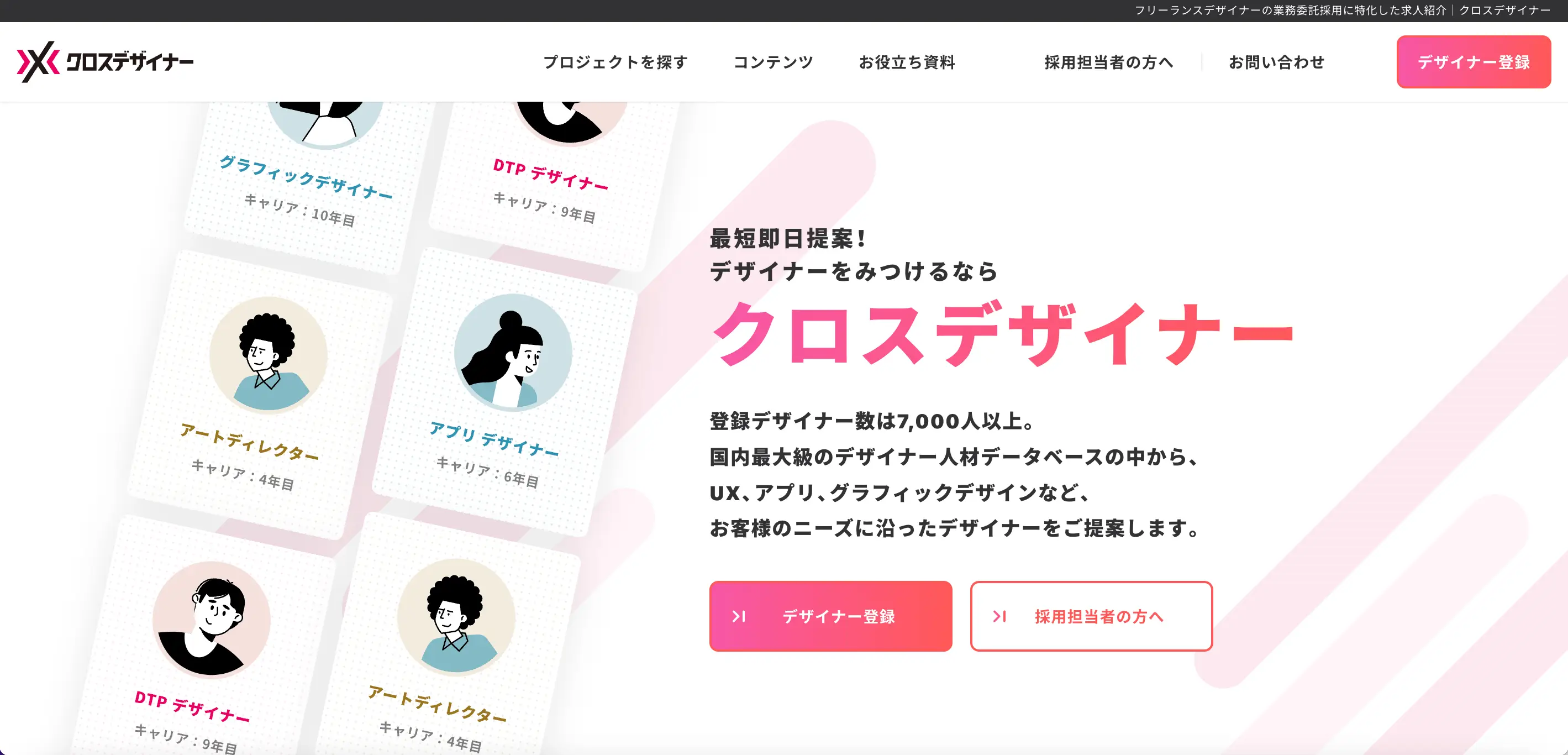
クロスデザイナーは国内最大級のデザイナー専門のプロ人材エージェントサービスです。『Workship』に登録する約7,000人のデザイナーより、自社の要望に応じた人材を紹介いたします。
不明点も多く聞かれる業務委託契約をサポートしているため、スムーズに即戦力人材を確保することが可能です。双方の合意があれば正社員への転換もできます。詳細は無料でダウンロードしていただけるサービス資料にまとめております。貴社のデザイナー採用にお役立てください。
- クロスデザイナーの特徴
- クロスデザイナーに登録しているデザイナー参考例
- 各サービスプラン概要
- 支援実績・お客様の声
Documents