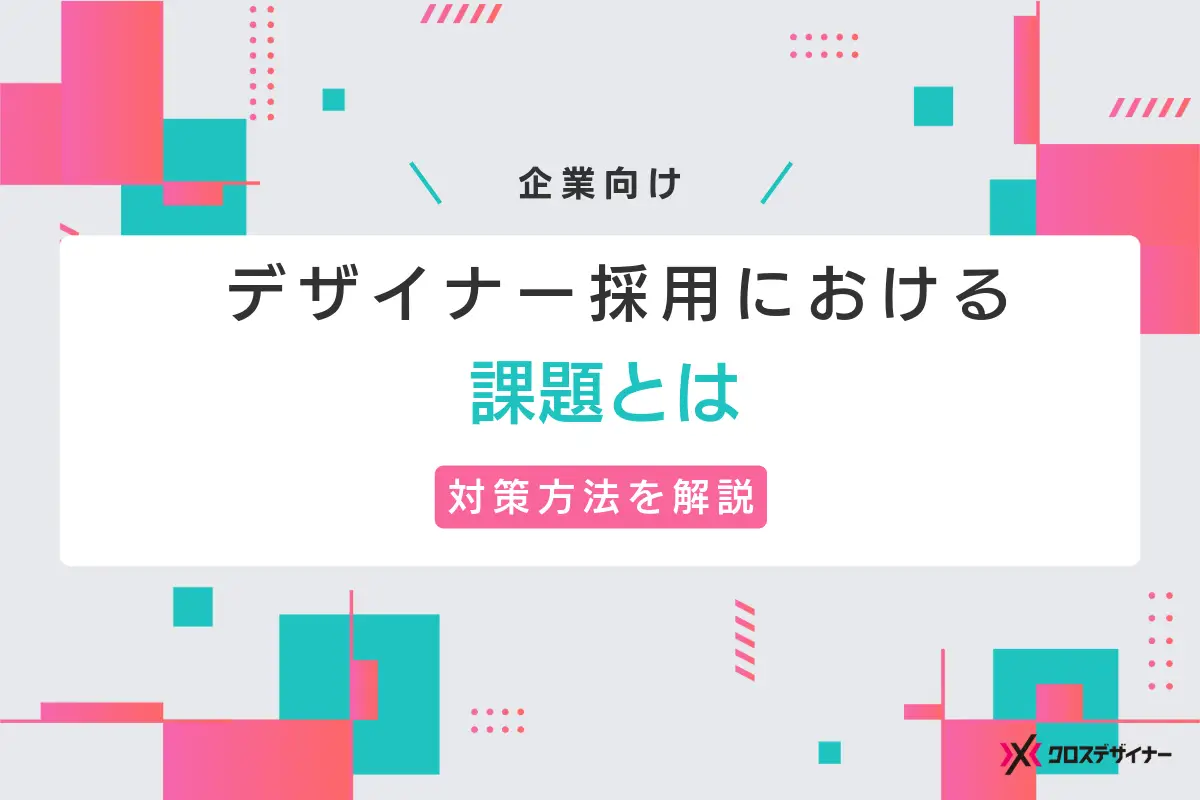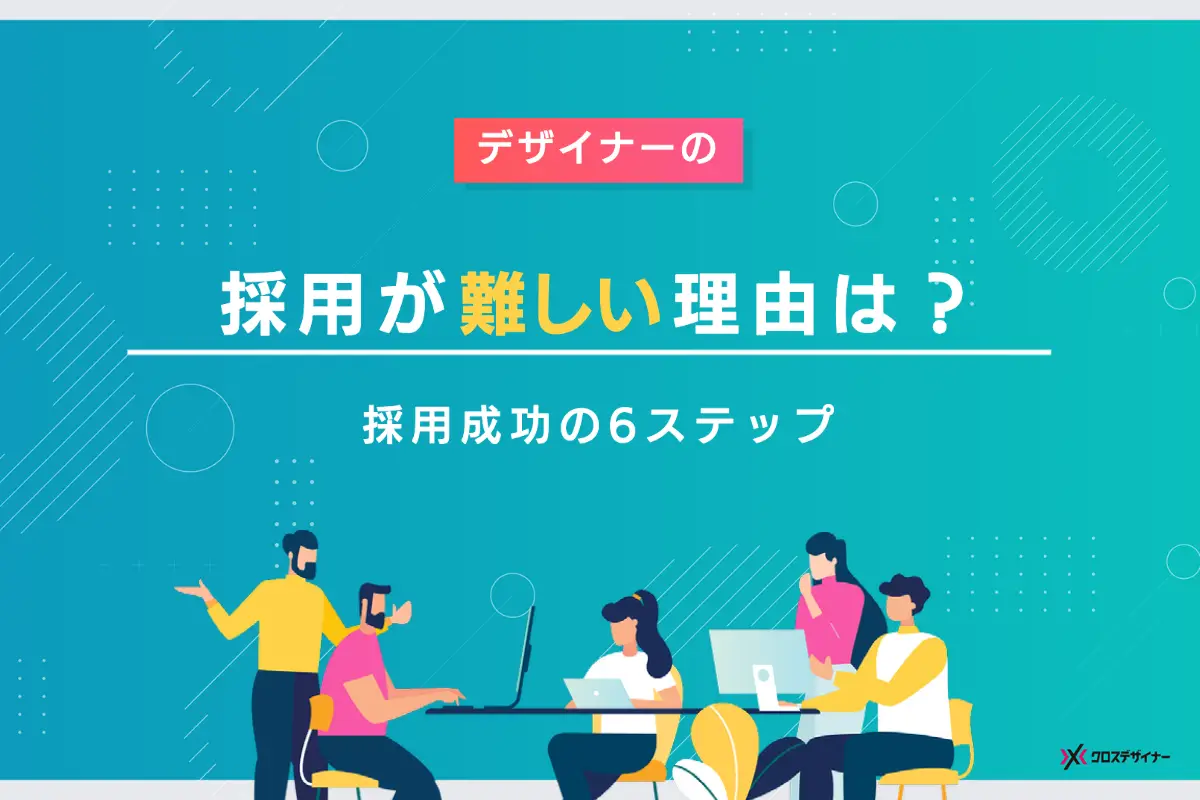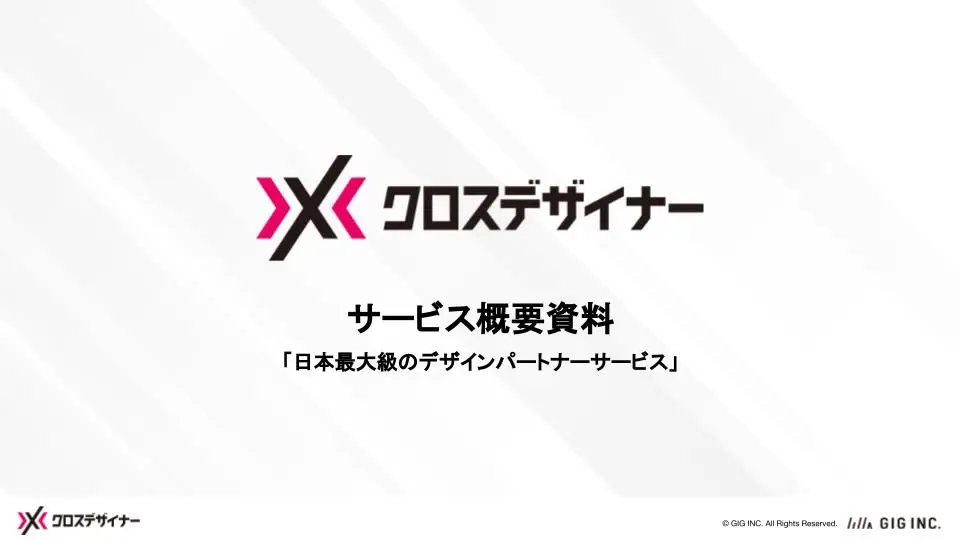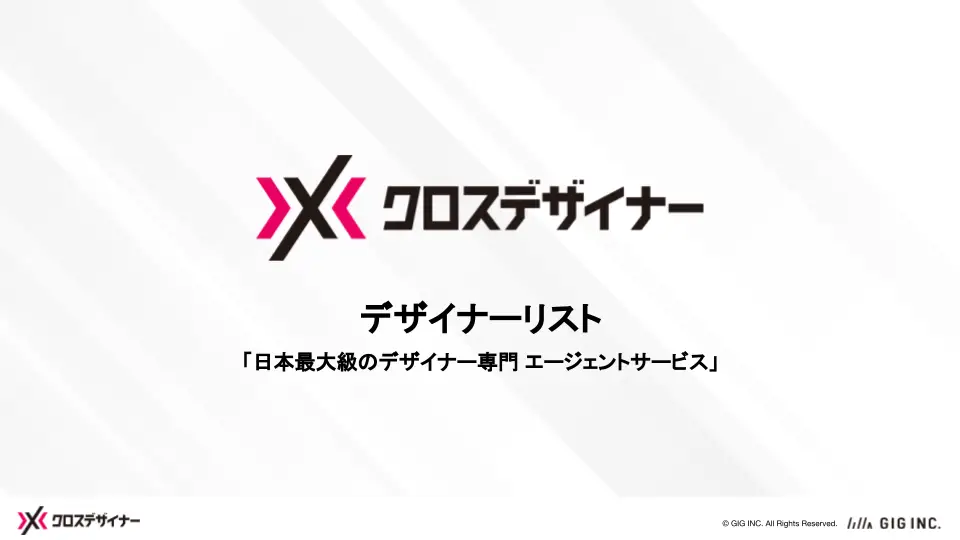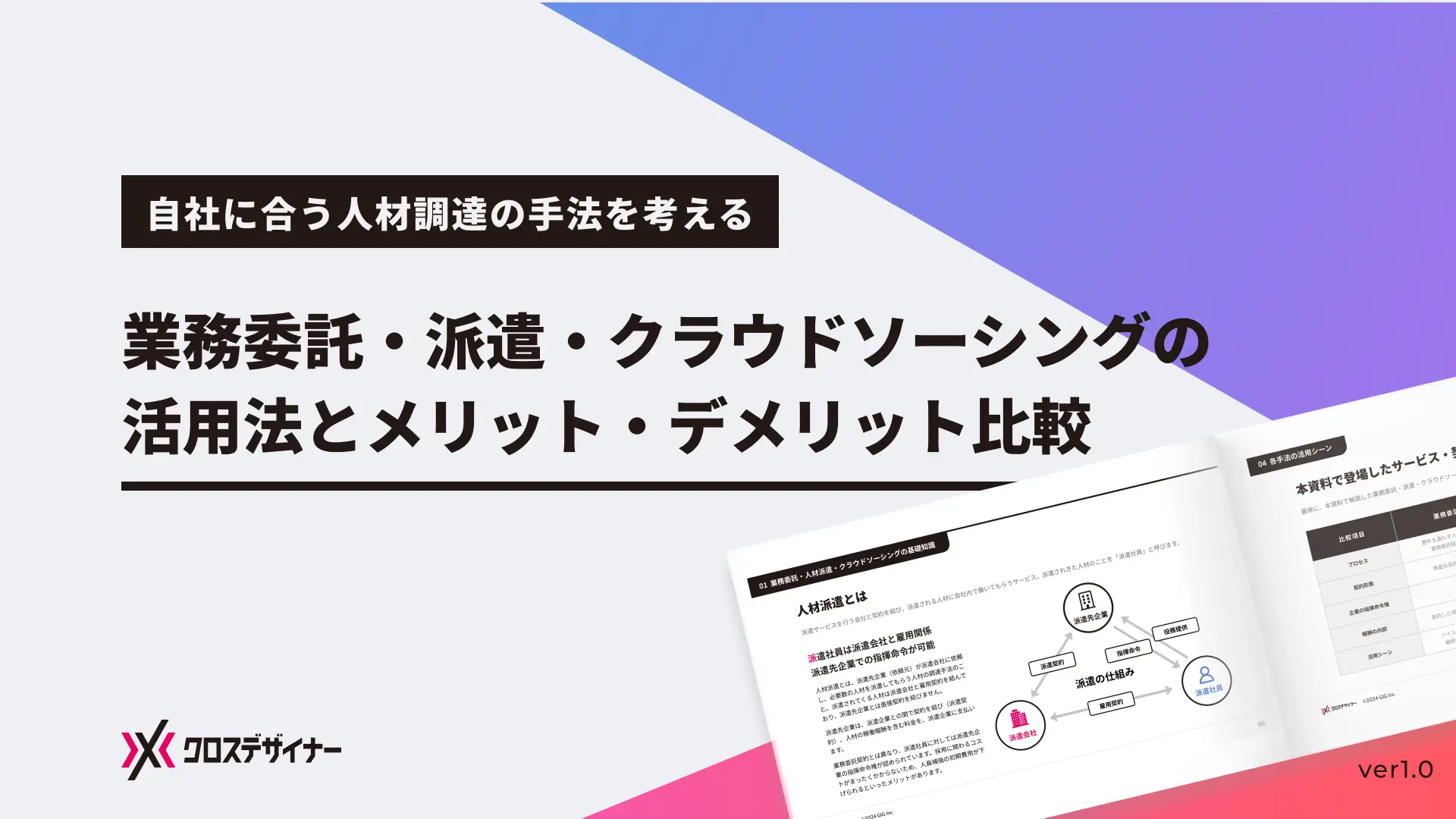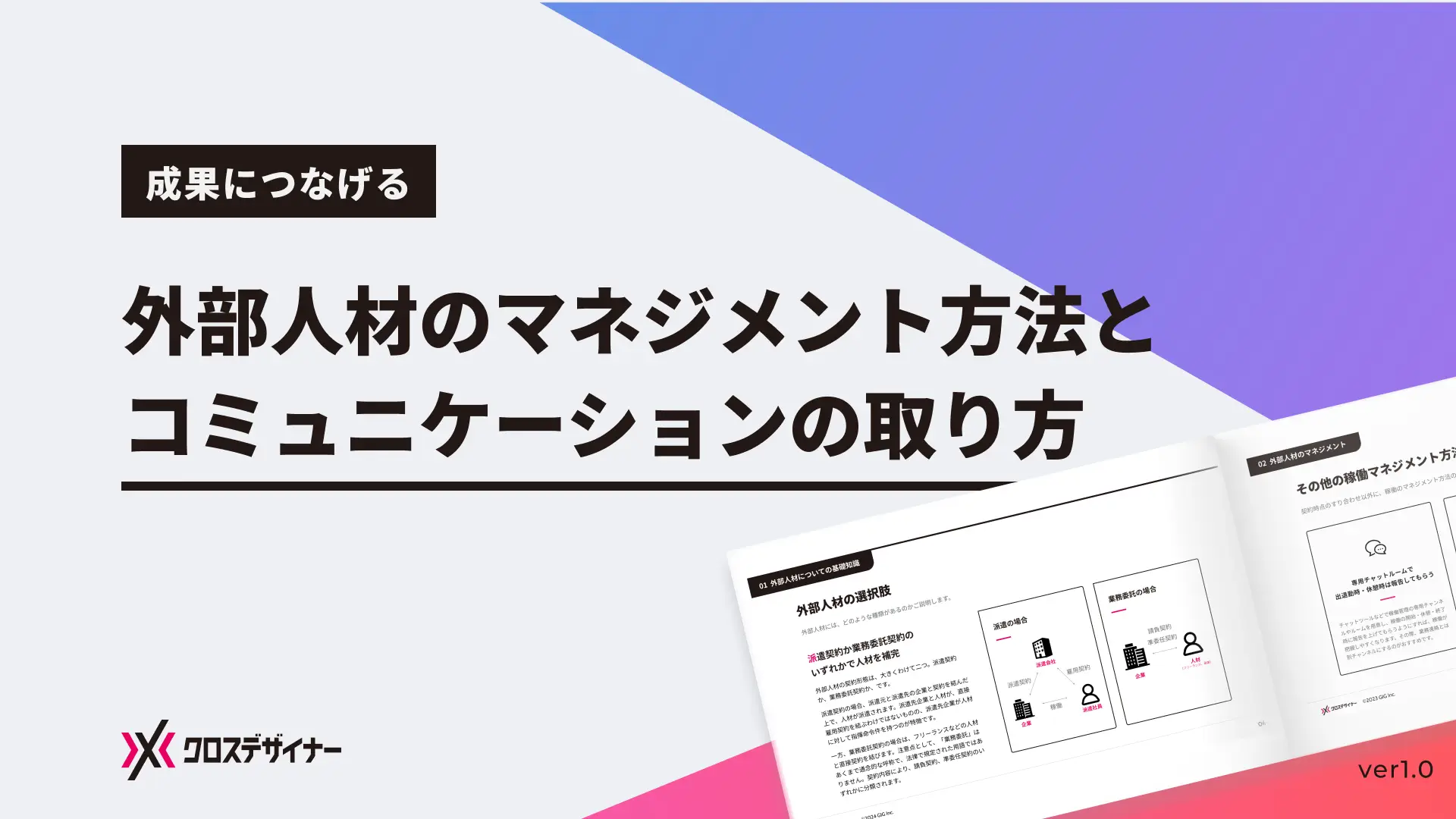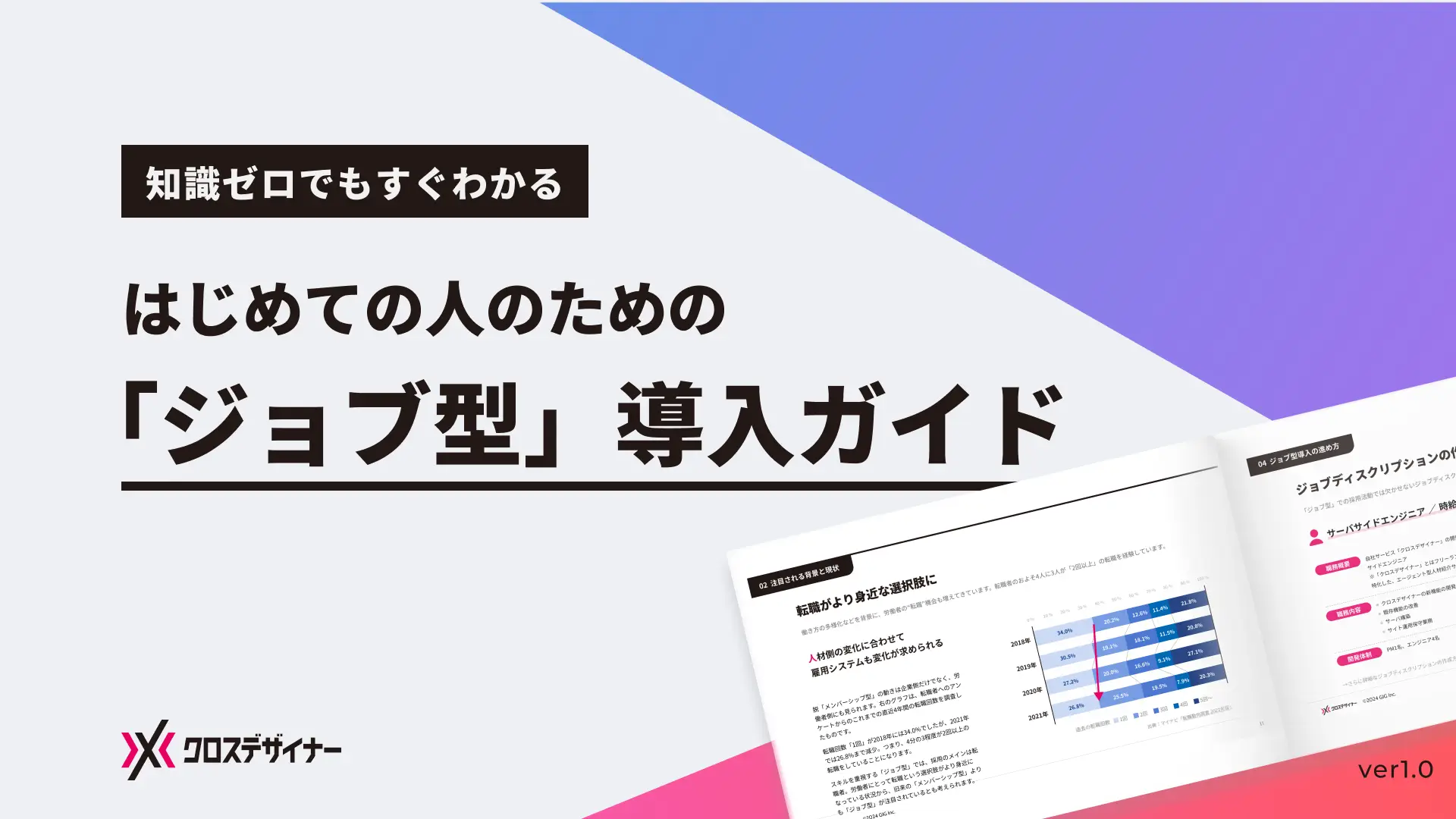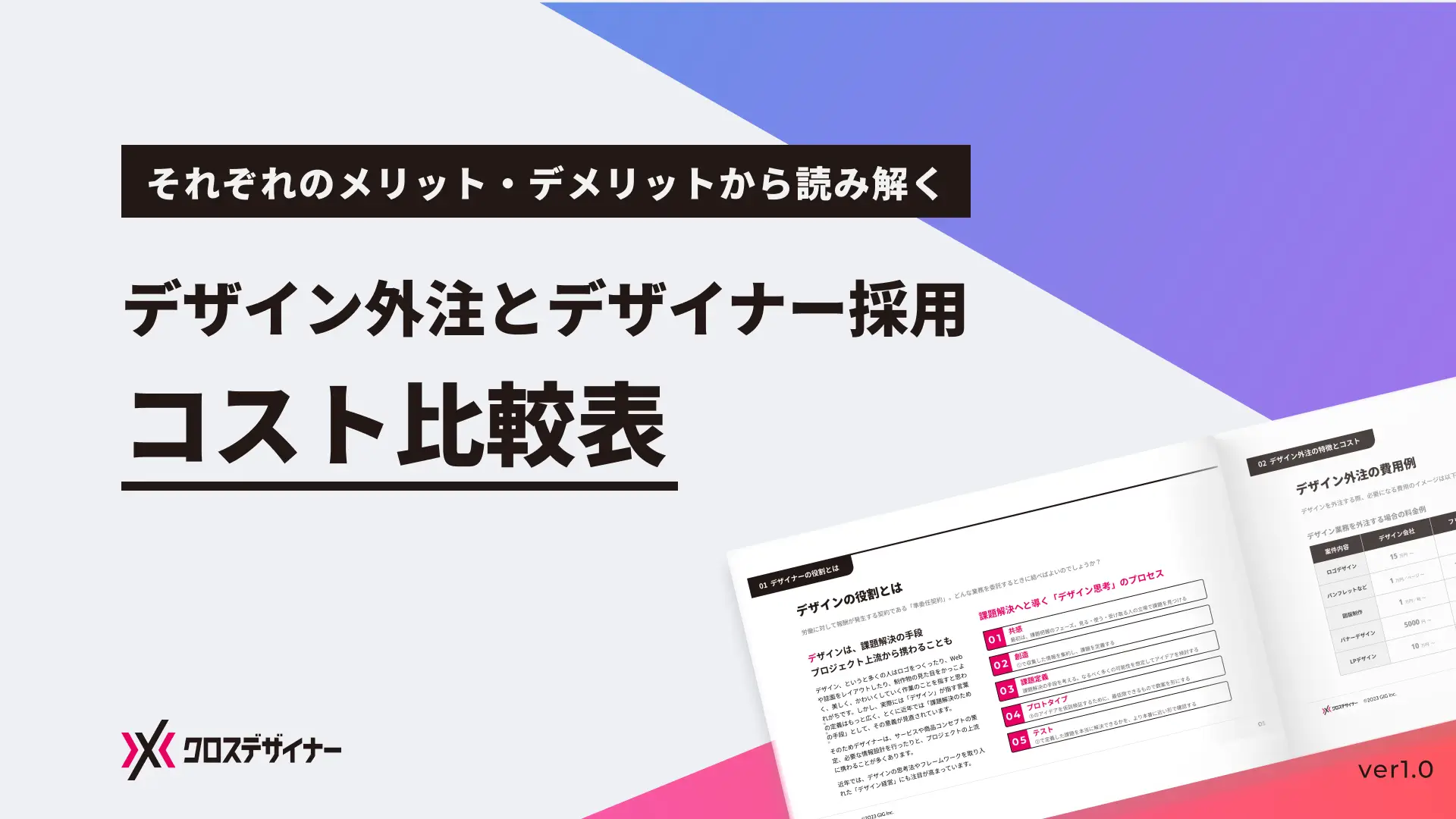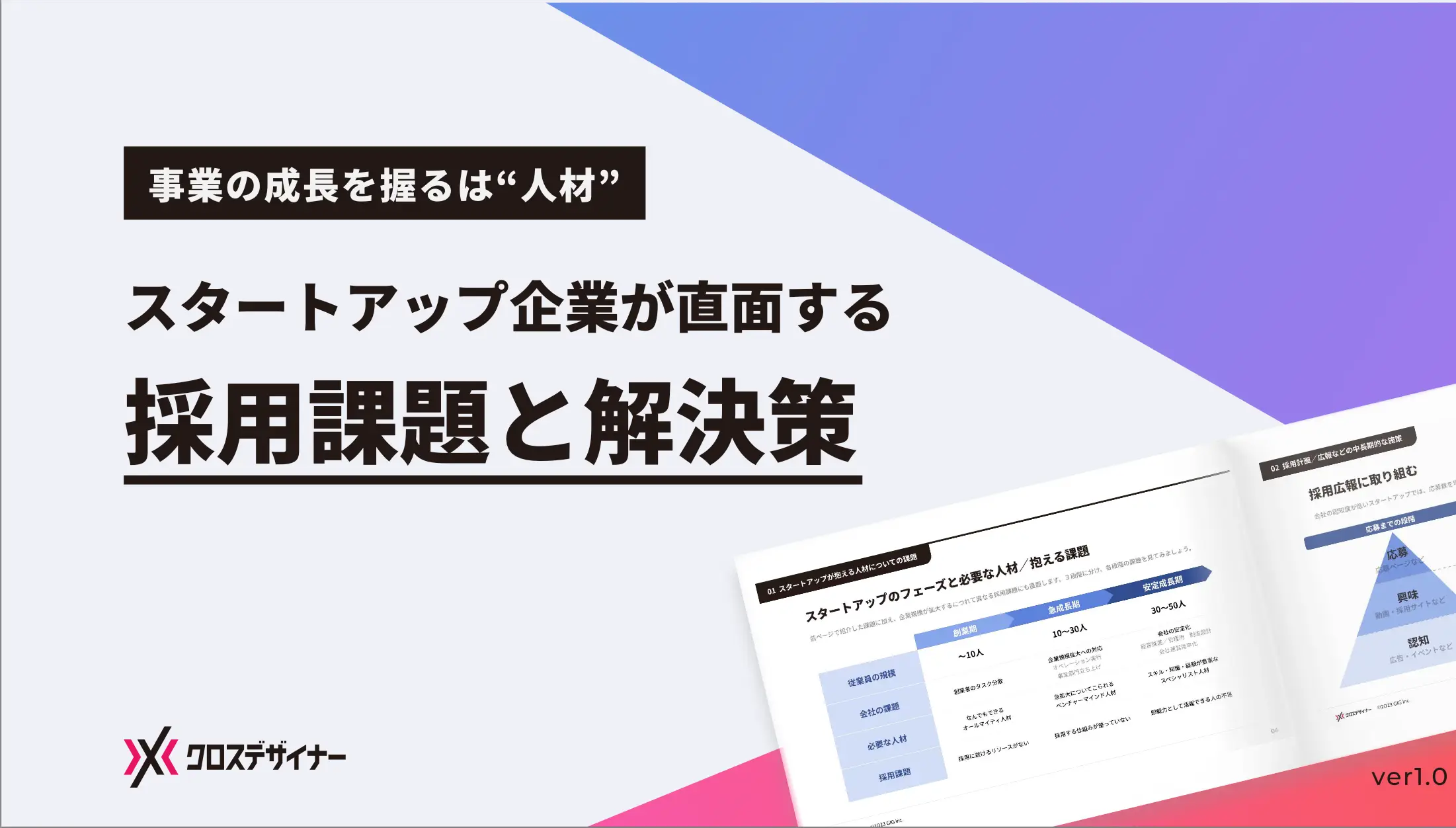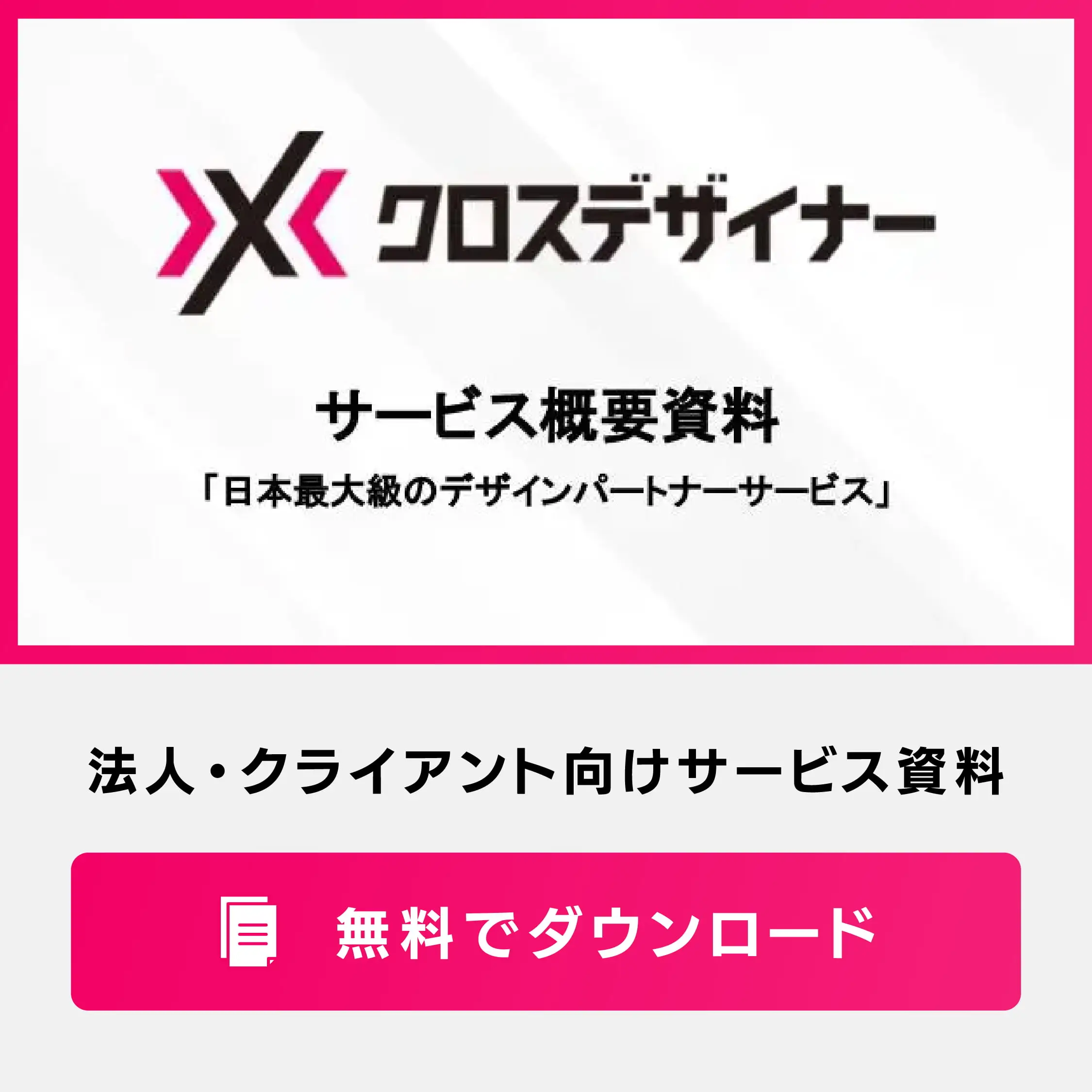社内の業務を外注する際には、外注費などの勘定科目の処理方法を事前に理解しておくことが重要です。
なぜなら、個人事業主に外注する際には源泉徴収が必要な場合もあるため、適正に処理する必要があるからです。
そこで本記事では、外注費の勘定科目の使い方や仕訳例を紹介します。源泉徴収や消費税についても解説していますので、外注をお考えの方はぜひ参考にしてください。
外注費とは?給与との違いや勘定科目の使い方も解説
外注費とは、自社業務の一部を外部の法人や個人に委託する際に発生する費用で、請負契約や業務委託契約に基づいて支払われる対価のことです。
外注費と給与の違いは、雇用関係の有無にあります。外注費は指揮監督を受けず成果物ベースで支払われ、消費税の課税対象となる点が特徴です。主にWebデザイン・システム開発・翻訳業務など専門性の高い業務で発生し、勘定科目「外注費」で処理されます。
ただし、個人事業主への支払いで、原稿料やデザイン料など一部の報酬に関しては源泉徴収が必要です。また、税務調査では業務実態が雇用関係に該当しないかを厳格に審査するため、契約書の整備が重要です。
外注費と給与の違い
外注費と給与は「労働対価」という点で共通しますが、契約形態や税務処理が異なります。
以下の表では、外注人給与の主要な違いを比較します。
比較項目 | 外注費 | 給与 |
契約形態 | 請負契約・委託契約(雇用関係なし) | 雇用契約(労働基準法適用) |
源泉徴収 | 原則不要(原稿料・デザイン料等は例外で10.21%徴収) | 必ず必要(給与所得として徴収) |
社会保険 | 加入不要(受託者自身で負担) | 事業主負担あり(健康保険・厚生年金等) |
消費税 | 課税対象(仕入税額控除可能) | 非課税 |
指揮監督関係 | 業務の進め方を受託者が自由に決定 | 時間・場所・方法を委託側が指定できる |
報酬請求権 | 成果物の完成後に発生 | 労働提供を受けた時点で発生 |
▼下記の資料では、業務委託・正社員・派遣など複数の雇用形態を比較し、特徴を解説しています。無料でダウンロードできますので、ぜひ貴社の外注業務にお役立てください。

外注費が発生する具体的な業務の事例
次に、外注費が計上される代表的な業務事例を業種別に分類します。
- IT業界:Webデザイン・システム開発
- クリエイティブ:広告制作・動画編集
- 製造業:部品加工・製品組立の外注
- 事務作業:データ入力・経理代行
- 専門業務:翻訳・通訳・技術調査 など
外注費に適用される勘定科目一覧
以下では、外注費関連で使用される主要勘定科目と適用例を表で解説します。
勘定科目 | 適用範囲 | 具体例 |
外注費 | 外部委託の基本科目 | デザイン・プログラミング業務 |
外注工賃 | 製造業の加工委託 | 部品の切削・塗装作業 |
業務委託費 | 継続的な業務委託 | 経理代行・営業支援 |
研究開発委託費 | 技術開発の外部委託 | 新製品の試作・実験 |
販売促進費 | 販促関連の外部発注(※外注費と異なる場合あり) | カタログ制作・サンプル作成 |
支払手数料 | 専門家報酬(税理士・弁護士等) | コンサルティング料・監査報酬 |
ただし、上記には次のような注意点があります。
・支払手数料は外注費と混同されやすいが、士業への報酬は別科目として処理します。
・販売促進費は目的が販促の場合に使用します(例:広告代理店への依頼)。
・外注工賃は製造業特有の科目で、加工委託時に明示的に使用するのが一般的です。
なお、源泉徴収の計算方法と納付期限については、下記を参考にしてください。
源泉徴収の計算方法と納付期限
所得税法上、業務委託契約を結ぶ業務には一部源泉徴収が必要なものがあります。
1. 原稿料や講演料など
2. 弁護士、公認会計士、司法書士等の特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金
3. 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
4. プロ野球選手、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金
5. 映画、演劇その他芸能(音楽、舞踊、漫才等)、テレビジョン放送等の出演等の報酬・料金や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金
6. ホテル、旅館などで行われる宴会等において、客に対して接待等を行うことを業務とするいわゆるバンケットホステス・コンパニオンやバー、キャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬・料金
8. プロ野球選手の契約金など、役務の提供にを約することにより一時的に支払う契約金
9. 広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金
(引用:国税庁「No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは」)
支払い先が企業や法人の場合、源泉徴収は不要です。外注工賃も基本的には源泉徴収は不要ですが、業務内容や契約形態によっては源泉徴収が必要なケースがあります。
支払う報酬から源泉徴収する場合、報酬額に10.21%(復興特別所得税を含む)を掛けます。
【源泉徴収の計算例】
報酬100,000円の場合:100,000×10.21%=10,210円
源泉所得税の納付期限は、支払月の翌月10日までです。源泉徴収をするかどうかは、外注先が開業届を出しているかどうかは関係ありません。対象業務であれば、源泉徴収が必要であることを覚えておきましょう。
ただし、発注側に事業所得がないときは源泉徴収は不要です。その場合は報酬を全額支払います。
(参考:国税庁「No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは」)
関連記事:デザイン外注と内製のメリット/デメリットは? 判断すべきポイントも解説
外注費の仕訳例
外注費を法人と個人に支払う場合の仕訳例と勘定科目について解説します。
法人に外注費を支払う場合
法人に外注費を支払う場合、源泉徴収は不要です。消費税が含まれる場合は、以下のように仕訳で明確に区別しなければなりません。
- 法人へ11万円(税込)の外注費を普通預金から支払った
【発注時の処理】
借方 | 貸方 |
外注費/100,000円 | 未払金/110,000円 |
上記はまだ実際に支払っていない状況ですので、貸方は「未払金」を計上します。なお、消費税の勘定科目は「仮払消費税」です。この金額は、仕入税額控除に計上できます。
外注先へ支払ったときは以下のように処理します。
【支払時の処理】
借方 | 貸方 |
未払金/110,000円 | 普通預金/110,000円 |
個人事業主・フリーランスに外注費を支払う場合(源泉徴収が必要なケースを含む)
個人事業主に外注費を支払うときは、源泉徴収が必要なケースがあります(所得税法第204条)。
- 個人事業主・フリーランスへ11万円(税込)の外注費を支払った
【発注時の処理】
借方 | 貸方 |
外注費/100,000円 | 普通預金/89,790円 |
源泉所得税を納付したときは、以下のように処理します。
【源泉徴収税の納付時】
借方 | 貸方 |
預り金(源泉所得税)10,210円 | 普通預金 10,210円 |
外注費に消費税が含まれる場合は、以下のように処理します。
【外注費と消費税の処理】
借方 | 貸方 |
外注費/100,000円 | 普通預金/99,790円 |
課税事業者との取引は、請求書にもとづいて消費税額を正しく計上しなければなりません。消費税部分の勘定科目は「仮払消費税」として仕訳します。
源泉所得税は税抜金額にもとづいて計算しましょう。
(参考:国税庁「No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは」)
外注費と混同しやすい勘定科目と注意点
外注費は広い定義であるため、他の勘定科目とも混同しやすいです。
何が外注費で、何が外注費ではないのか、事前に正しく知っておかないと外注費と混同して処理してしまうこともあります。特に「給与」と「外注費」は厳密に区別しなければ、追加徴税のリスクもあるため注意が必要です。
外注費と混同しやすい勘定科目としては、次の4つです。
- 支払手数料
- 販促費
- 広告宣伝費
- 給与
それぞれ簡単に解説します。
1. 支払手数料
「支払手数料」は、特定の業務に関連して発生する手数料や、公認会計士・弁護士・税理士など「士業(注:行政書士は対象外)」と言われる高度な専門的知識をもった人たちへ支払う報酬に使用する勘定科目です。
たとえば以下のようなものが該当します。
【支払手数料の例】
- 弁護士への契約書作成依頼料
- 税理士への月次報酬
- クラウドソーシングサービスの手数料
依頼した業務が源泉徴収の対象であるときは、個人であっても源泉徴収をしなければいけません。なお、弁護士法人事務所など法人である場合は源泉徴収は不要です。
2. 販促費
「販促費」は企業が販売促進をして売上向上のために支払った費用のことです。
【販促費の例】
- パンフレットの印刷費用
- Web広告への出稿費用
たとえば、設立30周年を記念したノベルティグッズのデザインをデザイナーに依頼し、30万円を支払ったとしましょう。このケースでは、デザイナーへ支払う費用は「外注費」。グッズ制作にかかる費用は「販促費」です。
それぞれ目的と性質が異なるため、勘定科目も異なります。適切な勘定科目を選ぶことが大切です。仕訳例は以下のとおりです。
【販促費の仕訳例】
- 設立30周年を記念したノベルティグッズの制作費用を普通預金から30万円支払った。
借方 | 貸方 |
販促費/300,000円 | 普通預金/300,000円 |
3. 広告宣伝費
「広告宣伝費」は、プロダクトの宣伝のために発生した費用を処理するための勘定科目です。広告制作や配信、掲載にかかる費用が該当します。
【広告宣伝費の例】
- Web広告の出稿費用
- テレビやラジオCMの制作・放映費用
- 新聞などへの広告掲載費用
外注費と広告宣伝費は、支払いの対象で判断します。
- Google広告への出稿費用:広告宣伝費
- 広告バナーのデザイン費用:外注費
広告の制作に関する費用は「外注費」と覚えておきましょう。仕訳例は以下の通りです。
【広告宣伝費の仕訳例】
- Google広告に普通預金から10万円支払った
借方 | 貸方 |
広告宣伝費/100,000円 | 普通預金/100,000円 |
このように広告を利用した場合は「広告宣伝費」として処理できます。また、広告宣伝費の対象がtoB(法人・企業)であるかは問いません。toC(一般消費者)向け広告でも勘定科目「広告宣伝費」として計上が可能です。
4. 給与
雇用契約の報酬は「給与」となり、(準)委任/請負契約に基づく報酬は「外注費」として扱います同じ業務であっても、給与と外注では税務上の扱いが全く異なるので注意が必要です。
税務調査が入った際に外注費が給与認定された場合、追加納税が課せられることがあります。
仮に請負契約で報酬を「外注費」としていても、その実態が「給与」に近いものであれば、給与とみなされる可能性が高まるため、注意しましょう。
関連記事:【企業向け】業務委託に源泉徴収は必要?対象となるケースや税額の計算方法を解説
給与を外注費として処理できない理由
外注費は、全額経費として計上が可能です。発注側が課税事業者であれば、消費税の仕入税額控除を受けることができます。仕入税額控除の額が大きければ課税所得額を抑えることが可能です。
対して、給与は不課税取引となるため、消費税の仕入額控除を受けることはできません。外注費は課税取引となることから、コスト管理において有利に働くことがわかります。外注費として適切に処理するには、業務委託契約であることを明確に示さなければいけません。適切な契約内容と事務処理を行ったうえで、外注費として処理することが大切です。
人件費など採用コストを少しでも抑えたいと考える経営者は少なくないでしょう。しかし、適切な勘定科目で計上しなければ、のちに大きなリスクを背負うことになります。
▼下記の資料では、採用コストが高騰する背景と要因だけでなく、採用コストを削減する方法も解説しています。無料でダウンロードできますので、ぜひ参考にしてください。

外注費が給与と判断された場合のペナルティ
外注費として計上した費用が、給与とみなされた場合、発注側は以下の対応が必要となります。
- 源泉所得税の支払い
- 控除されていた消費税の返還
- 過少申告加算税・延滞税の支払い
1. 源泉所得税の支払い
外注費が給与とみなされた場合、本来支払うべきだった源泉所得税を支払わなければなりません。
給与の場合、源泉所得税は給与を支払うときに発生します。しかし、外注費で処理していた場合、報酬額をそのまま外注先に支払っているため、未納状態となっているわけです。
外注費を給与として修正申告をして源泉所得税を納める場合、加算税や延滞税が発生します。正しく源泉徴収をしていれば払う必要はないものです。
(参考:国税庁「No.2026 確定申告を間違えたとき」)
2. 控除されていた消費税の返還
外注費に課せられる消費税は、仕入税額控除の対象ですが、給与には消費税がかかりません。そのため、外注費が給与とみなされると仕入税額控除が認められなくなるため、控除されていた消費税を返還しなければいけません。
返還により納める消費税は法人なら損金として、個人事業主なら必要経費として勘定科目「租税公課」で処理します。
(参考:国税庁「No.6451 仕入税額控除の対象となるもの」「No.6921 控除できなかった消費税等(控除対象外消費税等)の処理」)
3. 過少申告加算税・延滞税の支払い
外注費が給与とみなされ、源泉所得税の農夫と消費税を返還する場合、過少申告加算税と延滞税が課せられます。どちらも制裁的な意味をもつため、消費税のように経費として処理することはできません。
税務調査前に修正申告をすれば過少申告加算税がかからないこともあります。指摘を受けたら真摯に対応し、未納分をしっかりと納めることが大切です。
(参考:国税庁「延滞税の計算方法」)
業務委託にはフリーランスの活用がおすすめな理由3つ
以下では、業務委託先にフリーランスの活用をおすすめする主な理由を3つ紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
コスト削減と柔軟な契約が可能
企業が正社員を雇用すると、給与以外にも社会保険や福利厚生のコストが発生します。
一方、フリーランスとの業務委託契約では、必要な業務範囲に応じて契約を調整できるため、コストを抑えつつ必要なスキルを活用できるのが魅力です。
また、短期のプロジェクトや一時的な業務負荷増加にも柔軟に対応できるのが強みです。
専門スキルを持つ人材を活用できる
フリーランスは、特定の分野で専門性の高い能力を持つ人材が多いため、企業が内部で育成するのが難しい高度なスキルが求められるプロジェクトを迅速に遂行できます。
特にWebデザインやエンジニアリング、SEOやコンテンツマーケティングなどの分野では、即戦力となるフリーランスが多数存在しており、業務の質を高めることが可能です。
スピーディな業務遂行が可能
フリーランスは一般的に成果物ベースの契約が多く、無駄なミーティングや社内調整の時間を削減できます。そのため、短期間で業務を完了させたい場合やスピード感を持ってプロジェクトを進めたい場合に非常に有効です。
また、企業側も優秀なフリーランスと継続的な関係を築くことで、効率的な業務委託が可能となります。
関連記事:フリーランスに業務委託するメリットと契約方法、注意点を企業向けに解説
外注費の適切な管理方法5つ
業務委託やフリーランスへの支払いを適切に処理するためには、以下の点に注意する必要があります。ぜひ参考にしてください。
1.費用の分類
外注費は、企業の経理処理において「業務委託費」や「外注費」として計上されますが、内容によっては「給与」と見なされるケースがあるため注意が必要です。
例えば、業務の遂行に関する指揮命令権が企業側にある場合、税務上「給与」とみなされる可能性があるため、契約形態を明確にすることが重要です。
関連記事:どこまでの指示が偽装請負になる?業務委託契約との関係性まで解説
関連記事:偽装フリーランスとは?企業が注意すべき点を紹介
2.適切な契約書の作成
税務リスクを避けるためにも、フリーランスとの契約書を明確にし、業務範囲、報酬、納品条件などを詳細に記載することが重要です。
特に、「請負契約」か「委任契約」かを明確にすることで、支払い方法や責任範囲の整理が可能となります。
▼下記の資料では、業務委託契約に不可欠な契約書の作成ポイントを網羅的に解説しています。無料でダウンロードできますので、ぜひご活用ください。

3.消費税の考慮
外注費の支払い時には、請求書に消費税が含まれているかを確認する必要があります。
フリーランスが課税事業者である場合は、支払った消費税の仕入税額控除を受けることができます。しかし、外注先が免税事業者である場合には、支払った消費税分の仕入税額控除が受けられない可能性があるため注意が必要です。
企業として適切な税務処理を行うために、請求書の内容を正確に確認しましょう。
4.振込時の注意点
外注費の支払いを振込みで行う際には、振込手数料の負担をどちらが行うかを事前に決めておくことが大切です。
また、フリーランスによっては、源泉徴収が必要な場合もあるため、報酬の支払い時に注意が必要です。
5.経費としての計上
外注費は企業の経費として計上可能ですが、税務処理上、適切な証憑(請求書、契約書など)を保管しておく必要があります。
適切な会計処理を行うことで、税務調査の際にもスムーズに対応できますので、しっかりと管理しましょう。
関連記事:業務委託契約を進める流れとは?稼働開始後の注意点と合わせて解説
▼業務ごとに契約書を作成するのは発注側にとって負担でもあります。下記の資料では、業務委託に必要な4種類の契約書の作り方を、テンプレート付きで解説しています。無料でダウンロードできますので、ぜひ参考にしてください。

外注費を適切に管理するための重要ポイント3つ
外注費を適切に管理するためには、以下の3つのポイントが特に重要です。
1.契約内容を明確化し、証憑を適切に保管する
業務委託契約を締結する際には、業務範囲、報酬、納品条件を明確に記載することが重要です。
また、請求書や契約書などの証憑を整理・保管し、税務調査への対応ができるよう準備しておく必要があります。
特に、業務内容が曖昧なまま契約すると、後に税務上の問題が発生することもあるため注意しましょう。
2.税務処理を適切に行う
外注費の計上には、源泉徴収の有無や消費税の取り扱いを正しく理解することが欠かせません。フリーランスが免税事業者か課税事業者かを確認し、適切な消費税計算を行うことが求められます。
また、外注費が「給与」とみなされないよう、契約内容に業務の独立性が明記されているかもチェックしておきましょう。
3.支払い管理を徹底する
外注費の支払いは、支払いスケジュールを事前に定め、適切な管理を行うことでトラブルを防ぐことができます。また、振込手数料の負担や支払い期日の設定を明確にし、フリーランスとの信頼関係を維持することも重要です。
特に継続的な業務委託を行う場合、支払い管理のルールを統一しておくと良いでしょう。
▼業務委託はコスト面や柔軟性など、企業にとってもメリットも多くある一方で、経験がないとメリットがわかりにくく、不安を感じる企業も少なくありません。下記の資料では、業務委託のメリットと注意点を網羅的に解説しますので、ぜひご参照ください。
▼業務委託はコスト削減や柔軟性などのメリットが多い一方で、経験がないと不安を感じやすいのがデメリットです。下記の資料では、業務委託のメリットと注意点を網羅的に解説してますので、ぜひご参照ください。
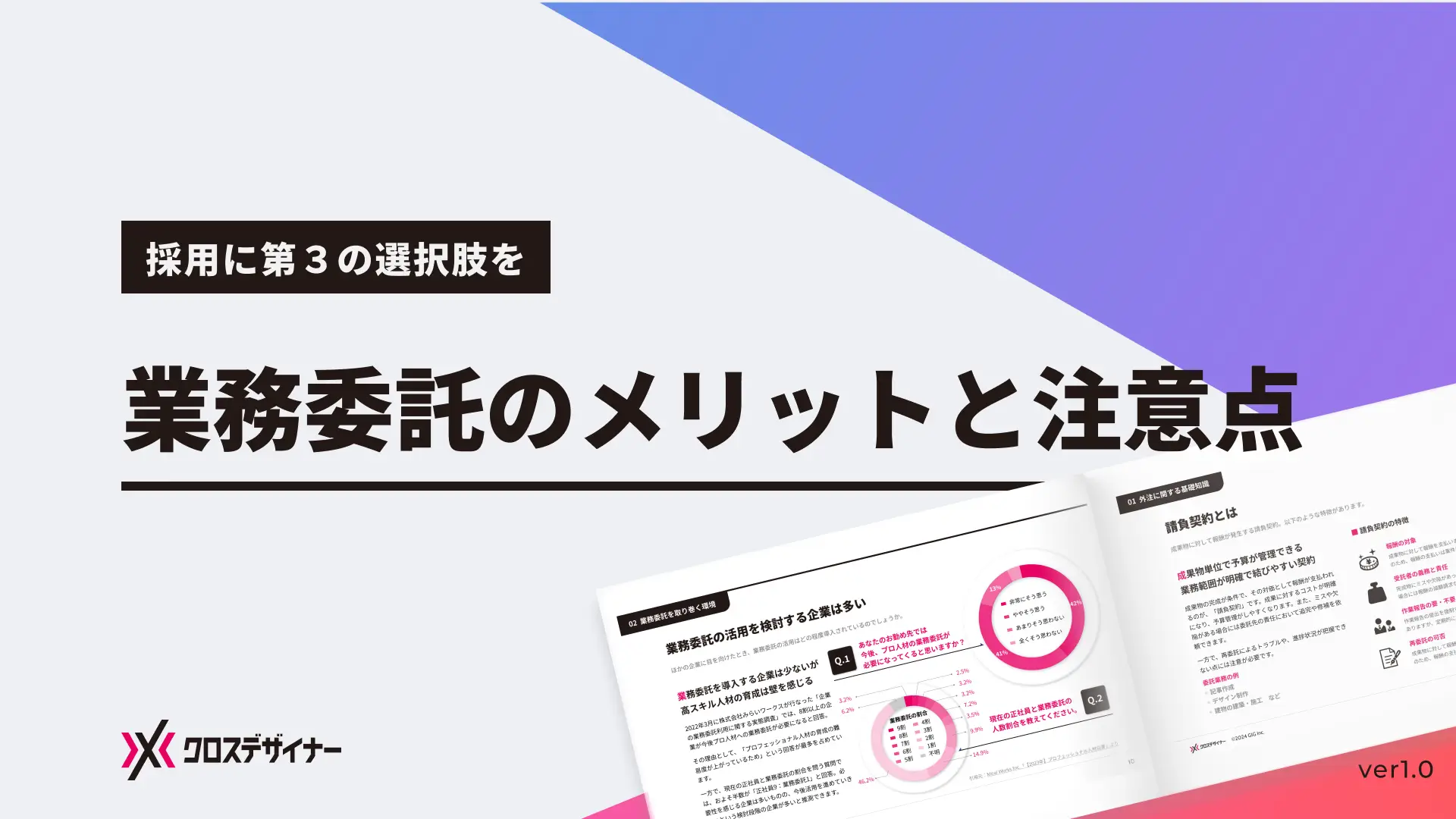
フリーランスデザイナーに外注するならクロスデザイナーがおすすめ
本記事では外注費の勘定科目について仕訳例や計上方法について解説しました。
業務の外注は外部のノウハウやリソースを活用できるメリットがある一方で、外注費が給与認定されると追加徴税のおそれもあります。外注費として認めてもらえるように、業務内容にあわせた契約を結び、適正な勘定科目を使用して処理をすることが大切です。
デザインを外注したいなら、クロスデザイナーがおすすめです。

クロスデザイナーは、7,000名以上のデザイナーが在籍するエージェントサービスです。
幅広いデザイン業務に対応しており、Webデザイン、UI/UXデザイン、アプリデザイン、DTPなど、各分野で最適なデザイナーを紹介可能です。さらにクロスデザイナーを介した3者間契約となっているため、複雑な契約書手続きなども全てお任せいただけます。
登録しているデザイナーとの合意があれば、正社員としての採用も可能です。また、スカウトや人材紹介機能もあるため、採用難易度の高い即戦力デザイナーを採用できるでしょう。
クロスデザイナーに相談いただければ、最短即日提案から3営業日でのアサインも可能です。また、週2〜3日の勤務といった柔軟な依頼も可能であるため、自社の作業量に応じて効率的な業務委託を実現できます。
こちらより、クロスデザイナーのサービス資料を無料でダウンロードできます。即戦力デザイナーをお探しの方は【お問い合わせ】ください。平均1営業日以内にご提案します。
- クロスデザイナーの特徴
- クロスデザイナーに登録しているデザイナー参考例
- 各サービスプラン概要
- 支援実績・お客様の声
Documents