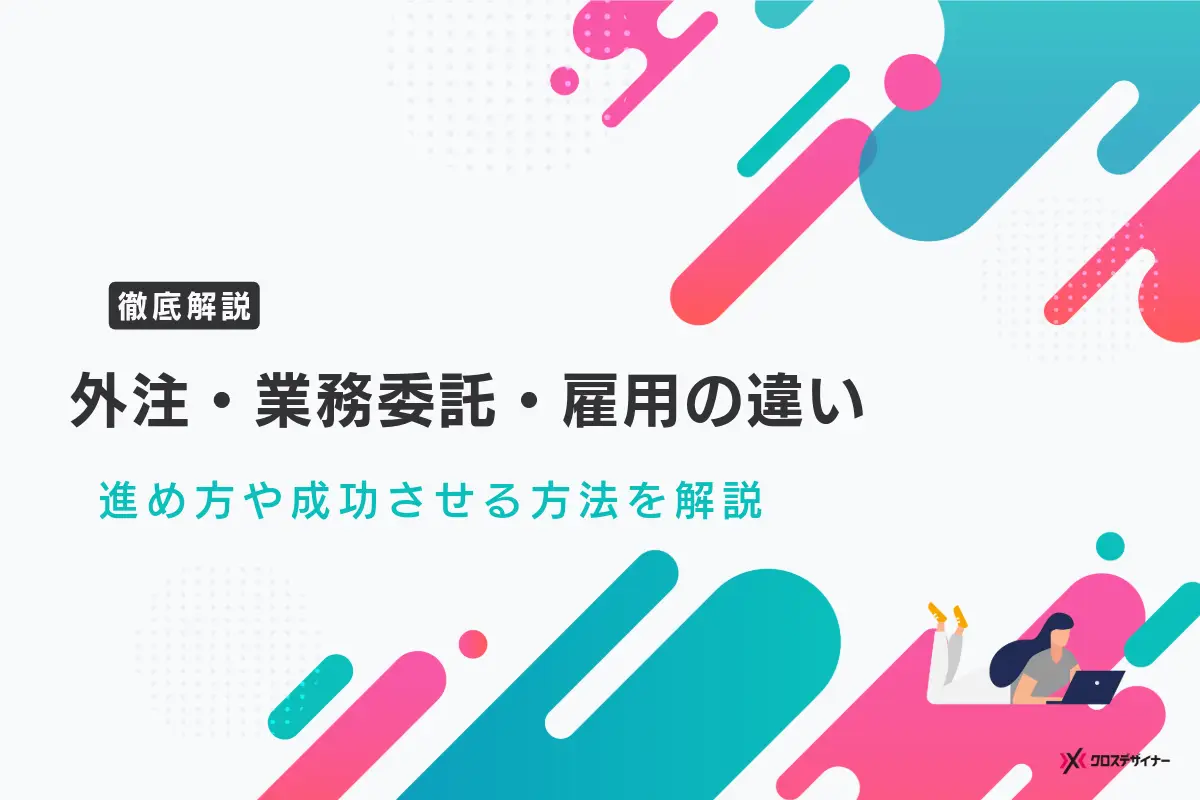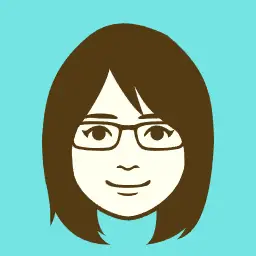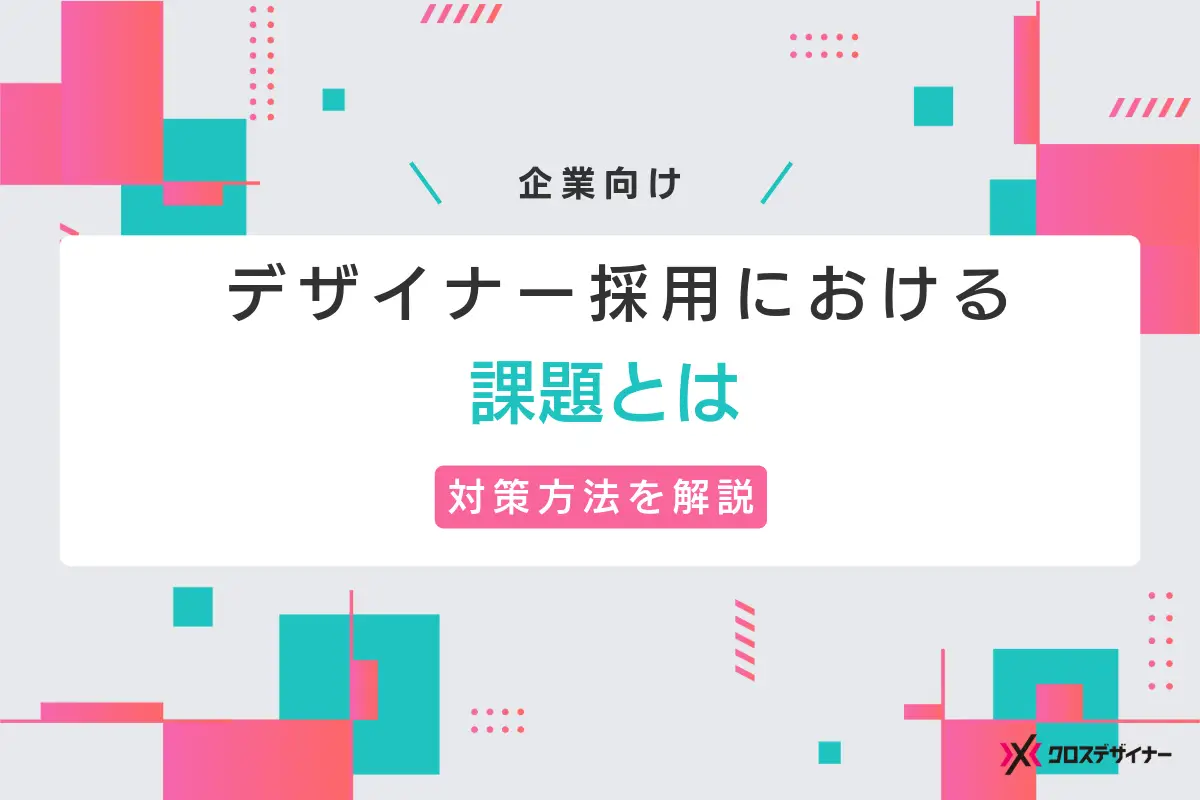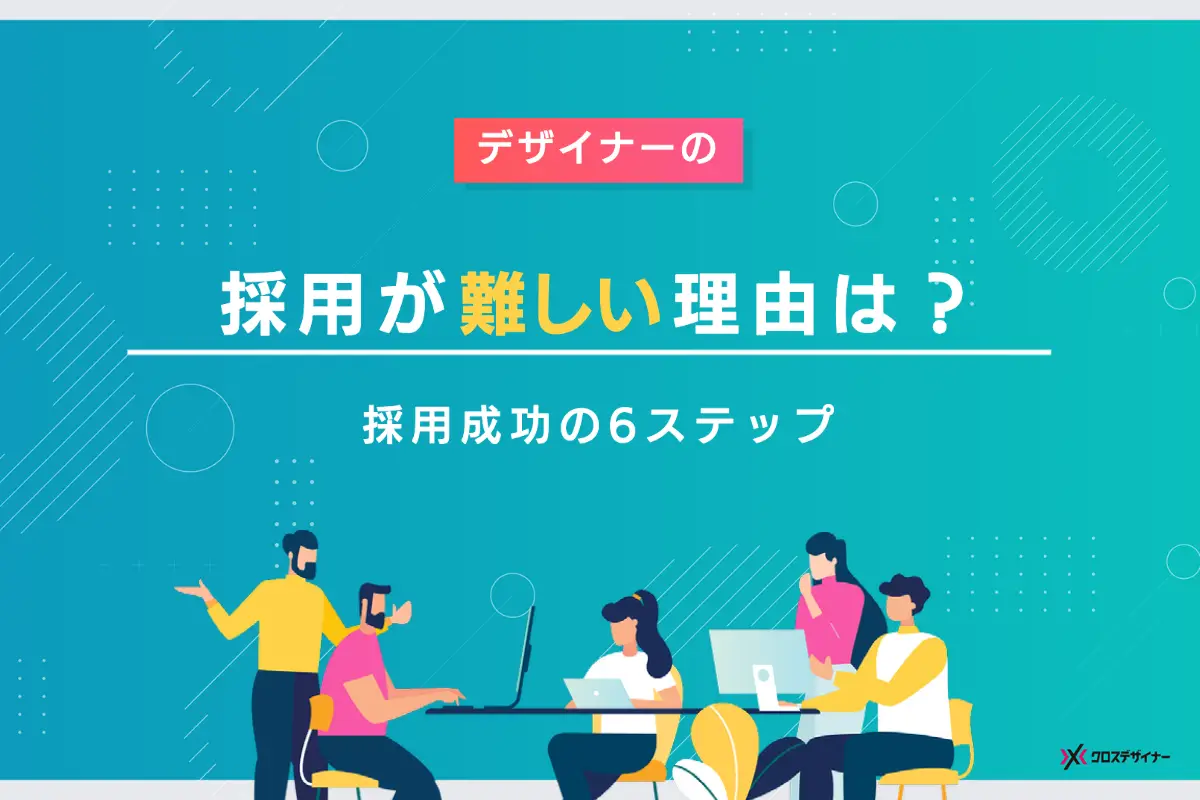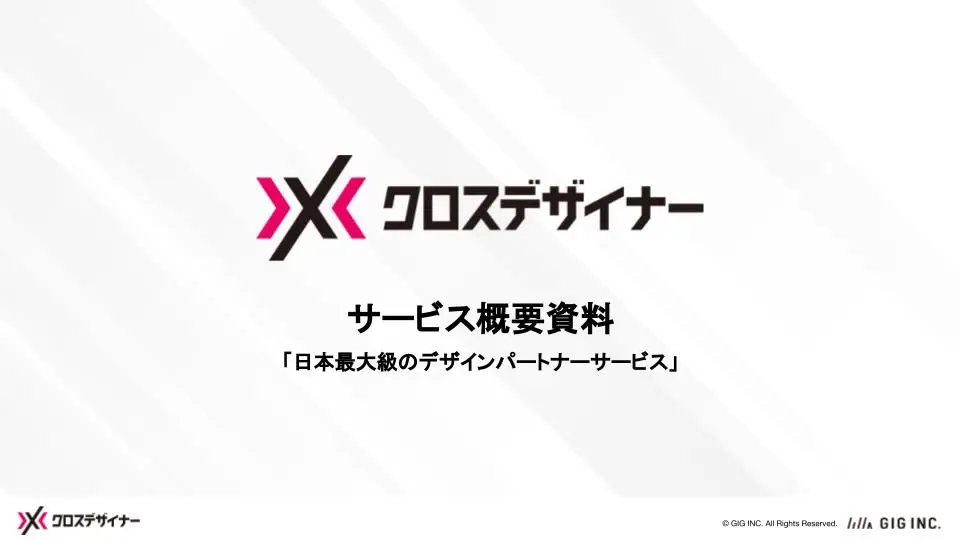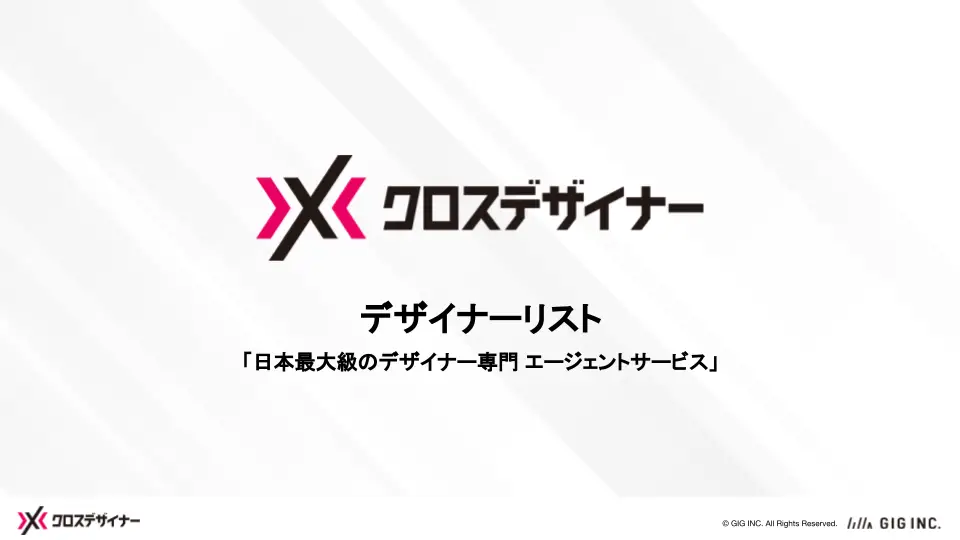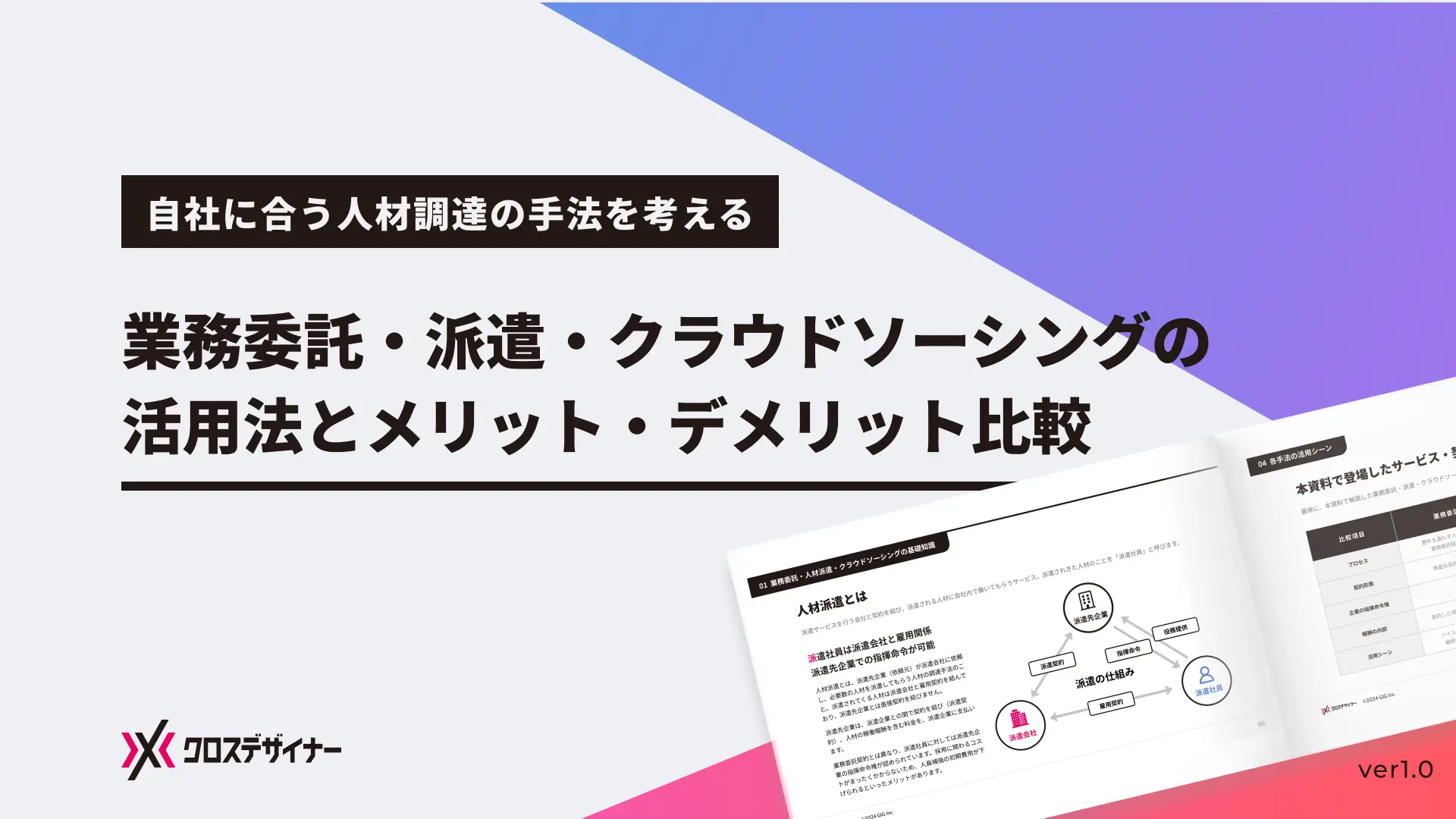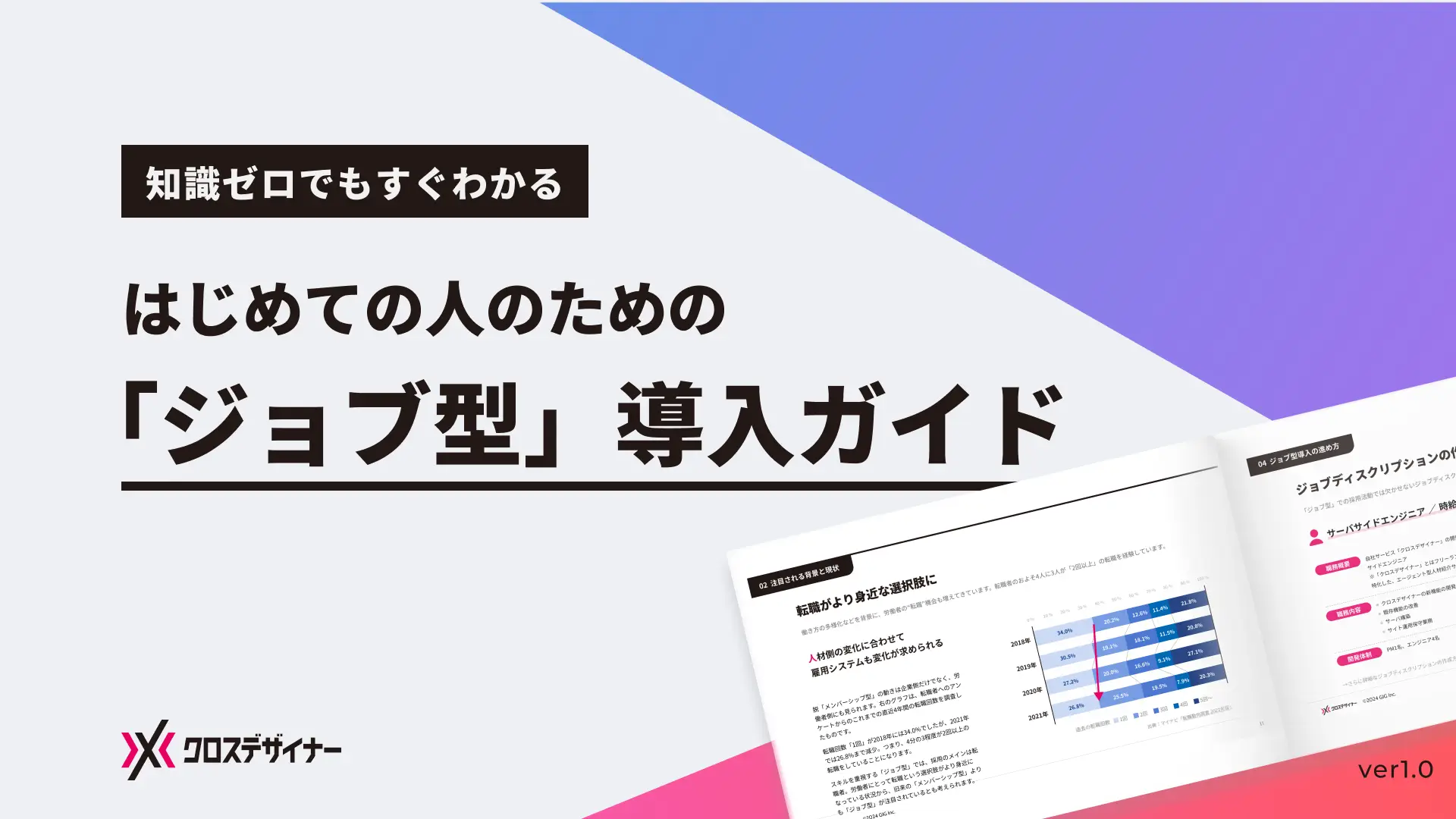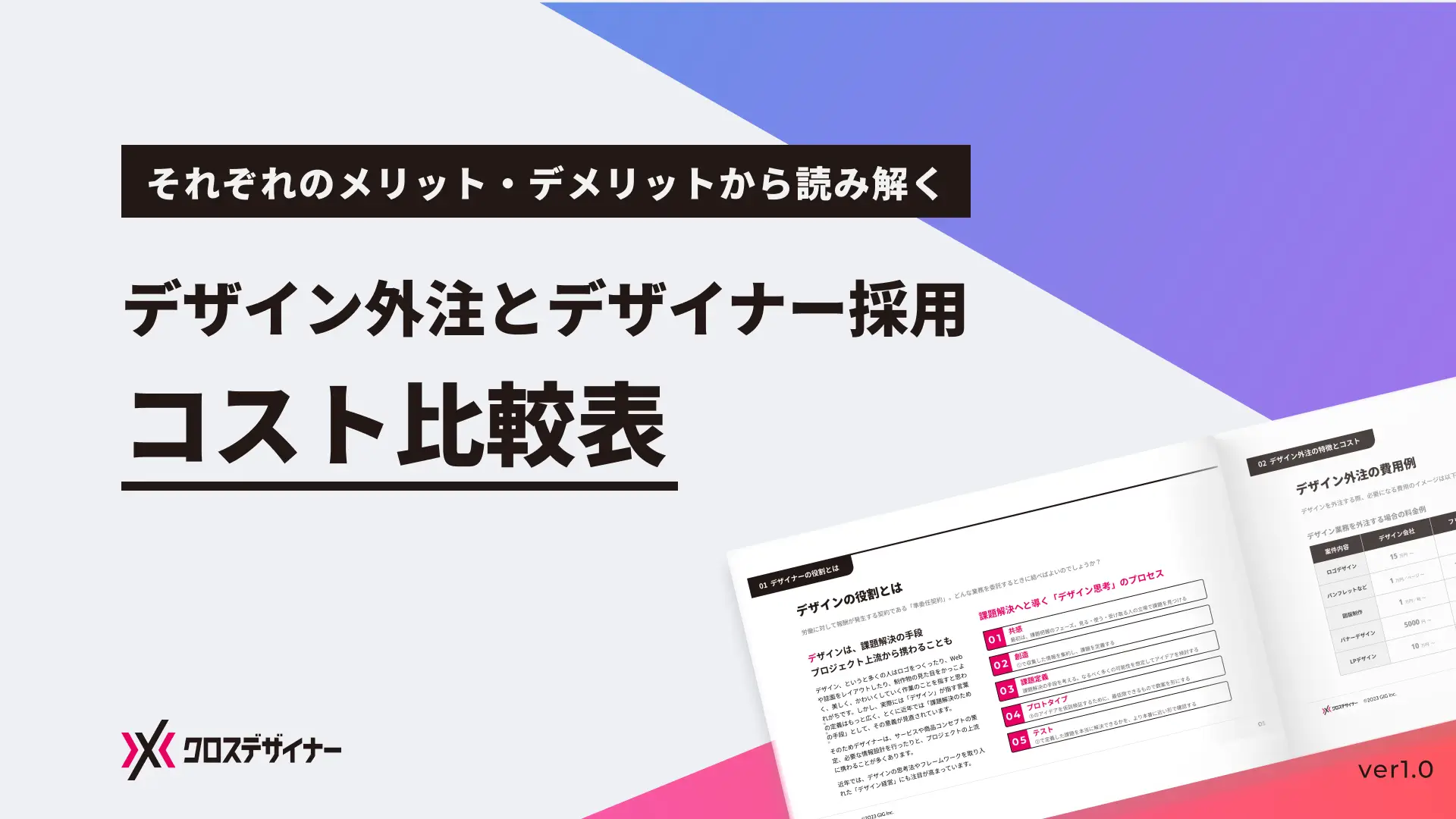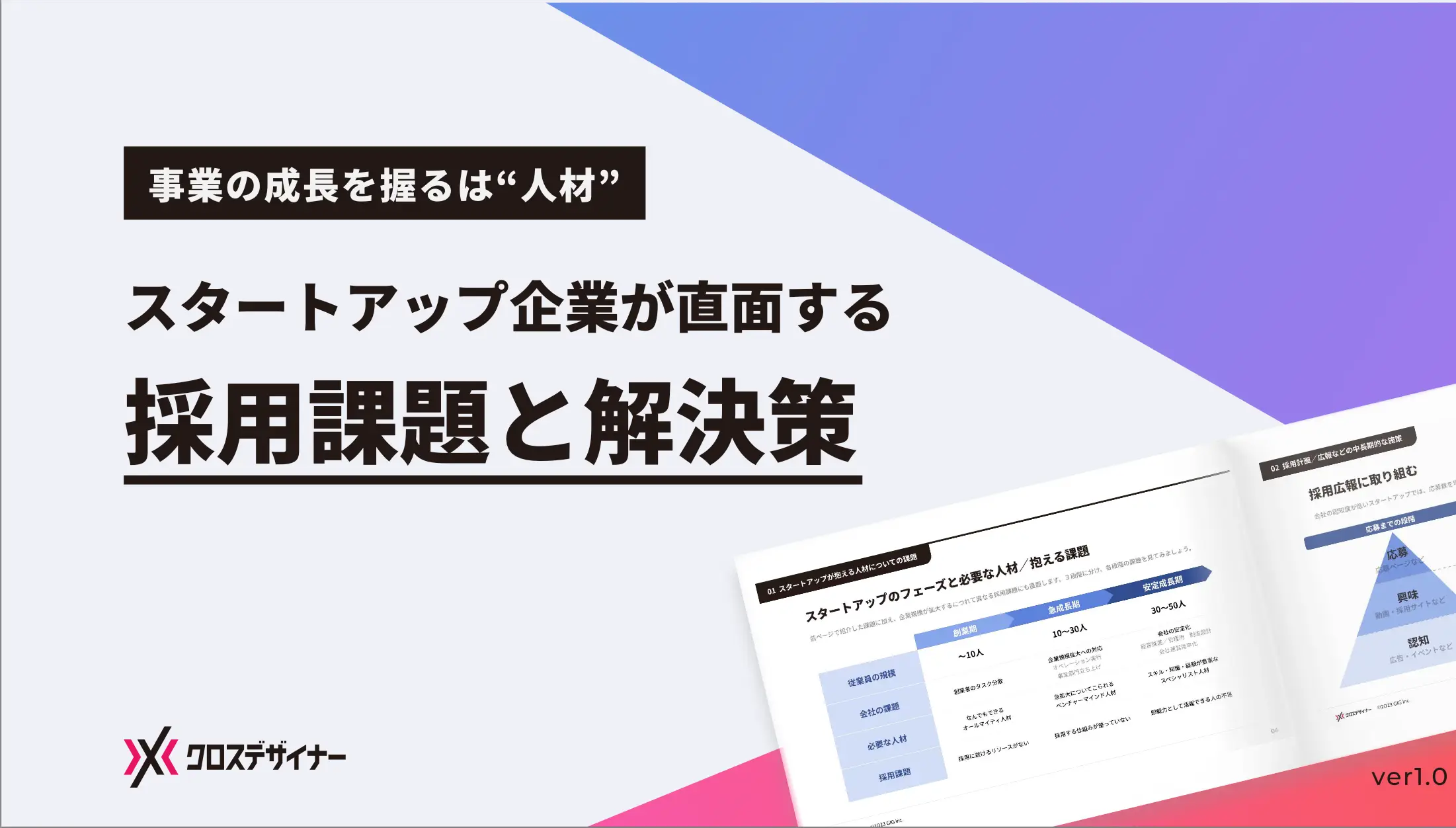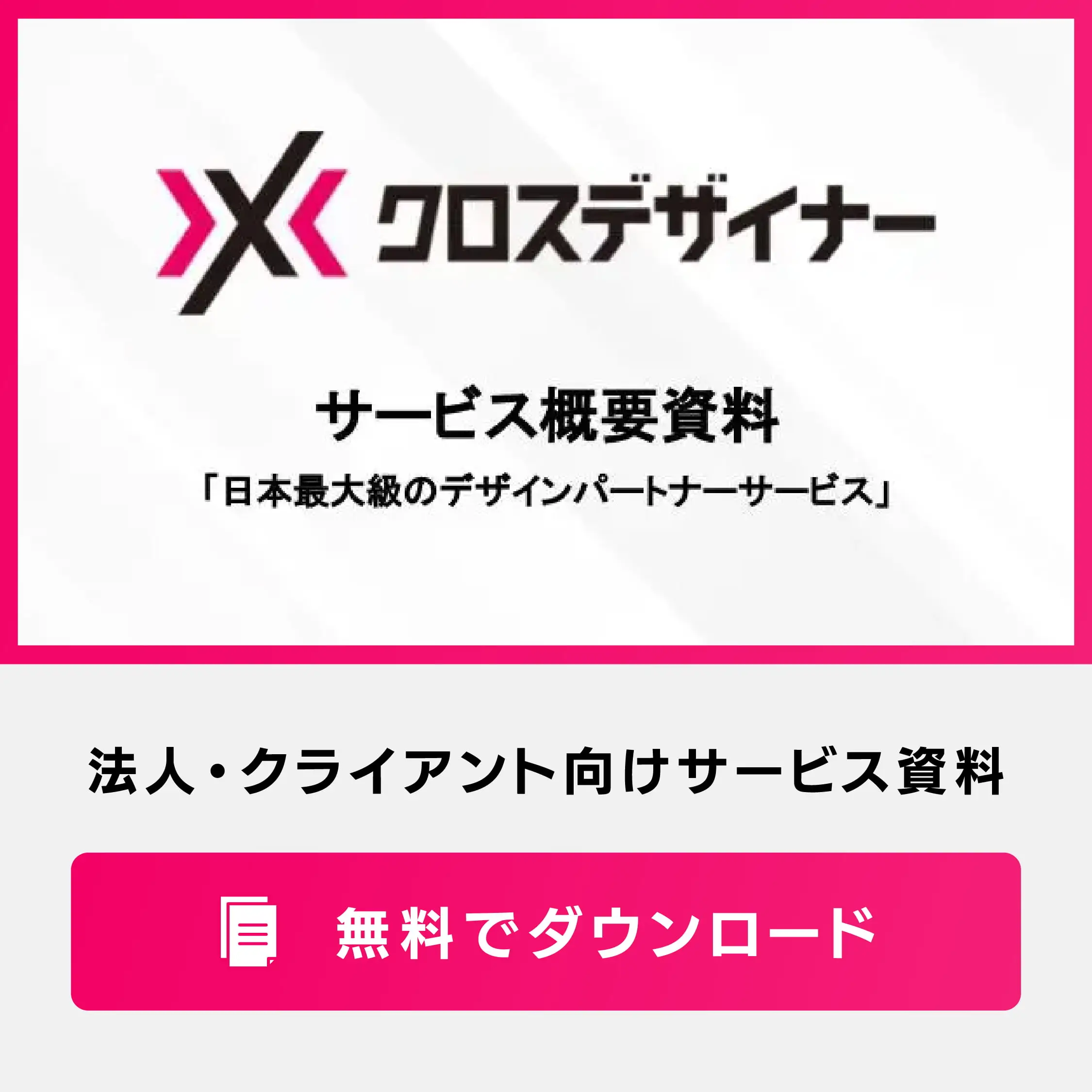「あふれた業務を外注するか、人材を雇用するか迷っているが、違いが分からない」このようなことで悩んでいませんか?
外注や業務委託は雇用契約と異なる点が多く、初めて取り入れる際は戸惑うこともあるでしょう。外注を成功させるには、契約内容の整理だけでなく、外注先との信頼関係を築くことが大切です。
この記事では、外注・業務委託・雇用契約の違いから、外注を円滑に進めるためのポイントまで解説します。長期的に協力できる人材を確保したい方は、ぜひ参考になさってください。
外注とは?
外注とは、企業がリソースを効率的に活用するために、社外の専門家や業者へ業務を依頼する方法を指します。プロジェクトの一部を外部に委託するときは、契約内容や責任範囲を正しく理解しておく必要があります。
業務委託契約との違い
業務委託は外注の一形態ですが、意味の範囲に違いがあります。外注は「社外に仕事を依頼・発注する」という広い概念で、契約形態を特定する言葉ではありません。
業務委託契約には「請負契約」「準委任契約(委任契約)」などがあり、成果物の範囲や責任の所在が異なります。契約を結ぶときは、対象業務の内容や成果物の定義を明確にし、誤解を防ぐことが重要です。
▼下記の資料では、業務委託の各契約形態ごとの概要や特徴を詳しく解説しています。無料でダウンロードできますので、ぜひ参考にしてください。

関連記事:【企業向け】請負契約とは? 準委任との違いやメリット・デメリットを解説
関連記事:準委任契約とは? 請負契約との違いやメリット・デメリット、注意点を解説
雇用契約との違い
外注と雇用契約の違いは、雇用関係があるかどうかです。外注の場合、依頼主に指揮命令権はなく、業務の進め方や勤務時間を指定できません。
雇用契約では勤務場所・時間の指定、業務指示が可能で、労働基準法や社会保険の対象となります。社会保険や労働保険などの加入義務が発生するため、企業側のコスト負担は大きくなります。
こうした費用が発生しない点は、外注の大きなメリットといえます。ただし、外注先は事業主としての責任をもち、対等な立場で協働する姿勢が求められます。
関連記事:雇用契約と業務委託の違いとは?メリット・デメリットや選び方を解説
下請け・外部委託との違い
外注・下請け・外部委託はいずれも「社外の相手に業務を任せる」という点で共通していますが、使われる場面やニュアンスが異なります。
「下請け」は製造業などでよく使われ、発注者の指示にもとづいて業務をおこなう立場を指します。「外部委託」は外注と近い意味ですが、業務委託に加えて人材派遣やアウトソーシングといった広い範囲を含みます。
これらの表現には「社外の人に任せる」という距離感があり、場合によっては冷たく聞こえることもあります。長期的な関係を築きたいときは、「外部パートナー」や「協業先」といった表現を選ぶと、より前向きな印象を与えられるでしょう。
関連記事:業務委託と外部委託の違いとは?それぞれの種類やメリット、注意点を解説
▼下記の資料では、業務委託・正社員・派遣など複数の雇用形態を比較し、特徴を解説しています。無料でダウンロードできますので、ぜひ貴社の外注業務にお役立てください。

外注の進め方とポイント
外注を単に人手を補う手段として考えるのではなく、社内の課題を解決し、成果を最大化できる方法として活用することが大切です。
ここでは、外注を効果的に進めるために押さえておきたいポイントを紹介します。
社内の準備と責任体制を整える
外注を進める前に、社内で目的と範囲を整理しておきましょう。
「何を、いつまでに、どのレベルまで仕上げたいのか」を明確にし、外注先とのやり取りを担当する窓口を決めておくとスムーズです。
また、成果物の確認や修正対応を誰が担うかを事前に決めておくことで、責任の所在があいまいにならず、トラブルを防ぎやすくなります。
関連記事:業務委託の契約不適合責任とは?善管注意義務との違いや法的性質を解説
専門性と品質基準を明確にする
外注先を選定するときは、求めるスキルや専門領域を具体的に定義しましょう。
「どのような成果物を期待しているのか」「どの水準の品質を求めるのか」といった基準を社内で共有しておくと、候補を比較しやすくなります。
検収基準や修正回数なども品質に影響するため、事前に取り決めておくと安心です。
決めた内容は依頼時にも提示することで、条件に合った外注先からの提案を得やすくなります。
関連記事:【企業向け】フリーランスWebデザイナーのスキルを見極める方法|評価基準も解説
外注に向いている業務か見極める
すべての業務が外注に適しているわけではありません。
マニュアル化できる定型業務や、専門知識が必要な領域は外注に向いています。ノウハウを社内に残したい業務や、社内調整が多い業務は内製化した方が効率的です。
自社のリソース状況や業務内容を踏まえて、外注と内製のバランスを取ることが大切です。
関連記事:効果的なクリエイティブの制作方法|内製と外注先の選び方も解説
セキュリティと法令順守を確認する
外注では、社内情報を共有する場面が多く発生します。
そのため、情報の取り扱いや守秘義務、個人情報・著作権などのルールを確認しておきましょう。
とくにクラウドサービスやフリーランスとの契約では、データ共有の範囲や責任の所在を明確にしておくと、トラブルを防ぎやすくなります。
関連記事:業務委託契約を締結する際に起こりがちなトラブル事例6つと対処法を解説
適宜フィードバックをして信頼関係を築く
契約で定めた納品物のやり取りだけでなく、定期的にコミュニケーションを取ることを意識しましょう。
進捗や成果に対してこまめにフィードバックをおこない、良い点を伝えることで相手のモチベーションが上がり、品質の向上にもつながります。
「任せきり」にせず、対等なパートナーとして成果を共有する姿勢が、長期的な協働関係の基盤になります。
関連記事:業務委託契約を締結する際に起こりがちなトラブル事例6つと対処法を解説
▼自社業務をはじめて外注する際は不安を感じる方も多いはず。下記の資料では、外注の流れとポイントをステップ別に解説しています。無料でダウンロードできますので、ぜひご活用ください。

外注費と給与の事務処理の違い
外注費と給与は、会計処理や税金の扱い、社会保険の負担が異なります。どちらの契約形態に該当するかを理解しておくと、経理処理の誤りを防ぎ、税務リスクの回避にもつながります。ここでは、外注費と給与の主な違いを整理します。
報酬と給与の違い
外注(業務委託)で支払うお金は「報酬」、雇用契約で支払うお金は「給与」として扱われます。報酬は成果物や業務の完了に対して支払われるのに対し、給与は労働時間や勤務に対して支払われます。
報酬は業務委託契約に基づく支払いのため、働き方や勤務時間の管理は含まれません。給与は、勤務時間や休日、残業の管理など、労働基準法にもとづく義務が発生します。
関連記事:業務委託の時給制は違法?適法となる契約方法や職種、注意点を徹底解説
会計処理の違い
外注費は「外注費」や「業務委託費」として経費計上されます。給与は「人件費」として処理され、源泉徴収税と社会保険料の控除をおこなったうえで支払います。外注費でも委託業務によっては、源泉徴収の義務があります。
同じ業務内容でも契約形態によって処理が異なるため、誤って外注費として計上すると、税務調査で指摘を受けるリスクがあります。契約書や請求書の内容を確認し、支払いの根拠を明確にしておくことが大切です。
関連記事:外注費の勘定科目の使い方と源泉徴収や消費税などの仕訳例も解説
所得税・消費税の扱い
給与には源泉徴収が義務づけられており、会社側が所得税を差し引いて納付します。
外注費は原則として源泉徴収の対象ではありませんが、例外として、デザイン・原稿・講演などの報酬は所得税法第204条により源泉徴収の対象となります。
また、給与は消費税の課税対象外ですが、外注費は課税対象です。仕入税額控除(※課税売上に対応する仕入の消費税を差し引ける制度)の対象となるため、請求書には適格請求書(インボイス)の発行が必要です。
(参考:国税庁「〔原稿等の報酬又は料金(第1号関係)〕」
関連記事:業務委託の源泉徴収とは?個人事業主への対応や税額計算・納付を企業向けに解説
社会保険の負担の違い
雇用契約で従業員を雇う場合、厚生年金保険・健康保険・雇用保険などへの加入が必要になります。企業はその保険料の一部を負担するため、人件費が増加します。
外注(業務委託)では雇用関係がないため、社会保険の加入義務はありません。
そのぶんコストを抑えられますが、外注先のスキルが高い場合、スキルに見合った報酬を設定しなければならないため、報酬単価が上がることもあります。
※制度や料率によって変更される場合があります。最新情報は厚生労働省・日本年金機構の公表内容をご確認ください。
▼業務委託はコスト削減や柔軟性などのメリットが多い一方で、経験がないと不安を感じやすいのがデメリットです。下記の資料では、業務委託のメリットと注意点を網羅的に解説してますので、ぜひご参照ください。
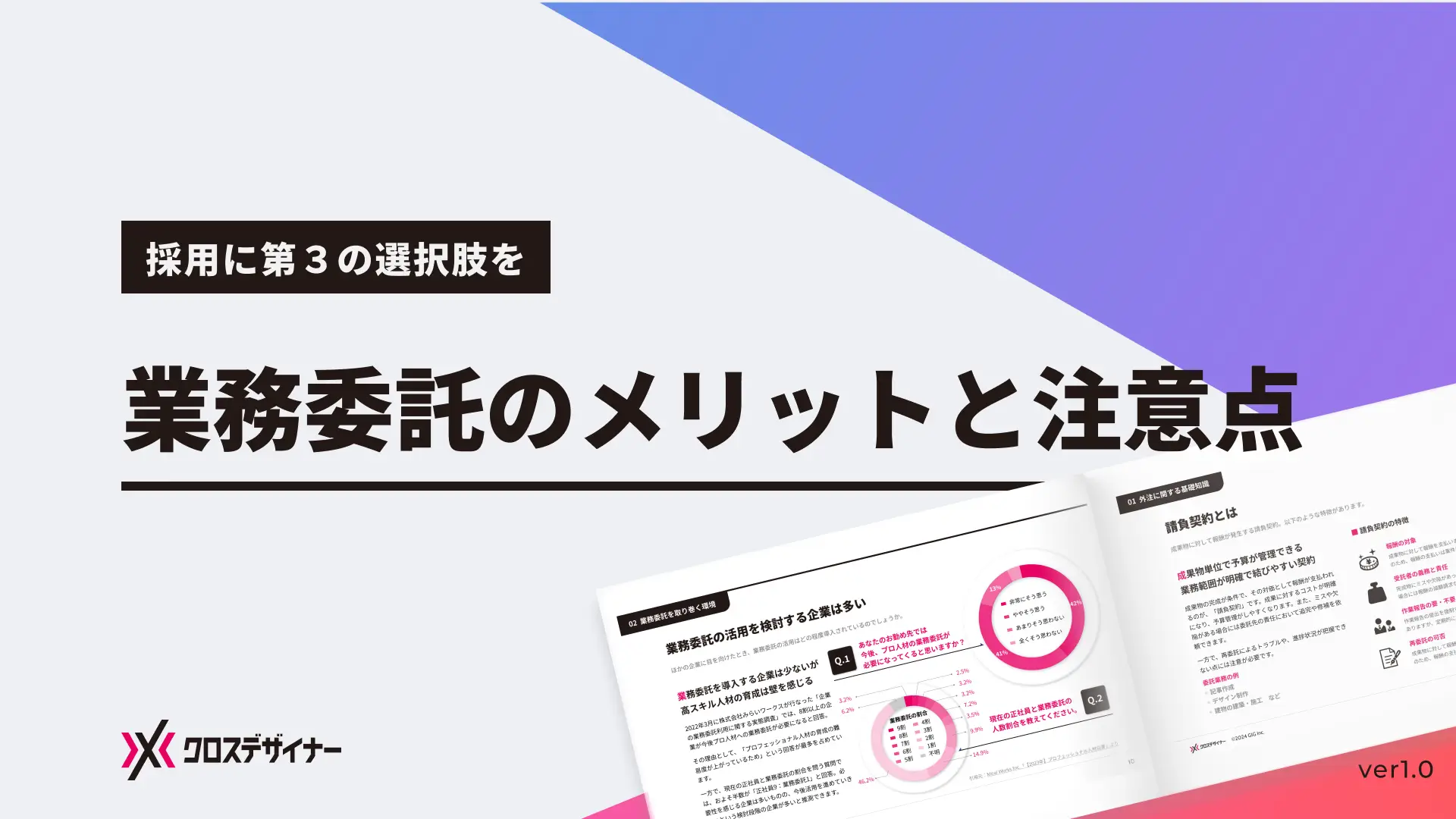
企業が外注を成功させる方法
外注を継続的に成功させるには、契約内容や実務の進め方を整理し、社内・外注先の双方が納得できる環境を整えることが重要です。
ここでは、企業が外注を適切に運用するためのポイントを紹介します。
1. 契約形態と実態を一致させる
契約書の内容と実際の業務の進め方が一致していることは、外注を円滑に進めるうえで欠かせません。
契約上は業務委託であっても、実際には勤務時間の指示や業務管理をしていると「雇用」と判断される場合があります。
業務の範囲や責任分担、成果物の条件などを明確にし、契約上の定義と実際の業務実態が一致しているかを定期的に確認しましょう。
2. 代替性と成果基準を明確にする
外注で支払う報酬は、成果物や完成した業務に対する対価です。依頼した業務が特定の人でなければ対応できない内容か、それとも他の人でも代替可能かによって、契約上の扱いが変わります。
成果物の納品を基準とするのか、作業時間や稼働日を基準とするのかを明確にし、請求・支払いの条件を整理しておきましょう。
この整理が、税務や契約上のリスクを減らすことにつながります。
関連記事:準委任契約の成果完成型とは?請負との違いやメリット・デメリットも解説
関連記事:準委任契約の履行割合型とは?成果完成型との違いや向いている業務を徹底解説
3. マネジメント方法を検討する
業務委託契約では、外注先に対して指揮命令をおこなうことはできません。そのため、業務の進行を「管理」ではなく「マネジメント」として捉えることが大切です。
進捗を確認する仕組みを整えたり、成果物レビューのルールを決めたりすることで、品質を担保しながらも外注先の裁量を尊重できます。プロジェクト管理ツールの利用なども有効です。
▼業務委託では外注先への指揮命令はできませんが、コミュニケーションやマネジメントが不可欠です。下記の本資料では、その実践方法を注意点と合わせて解説していますので、ぜひ参考にしてください。
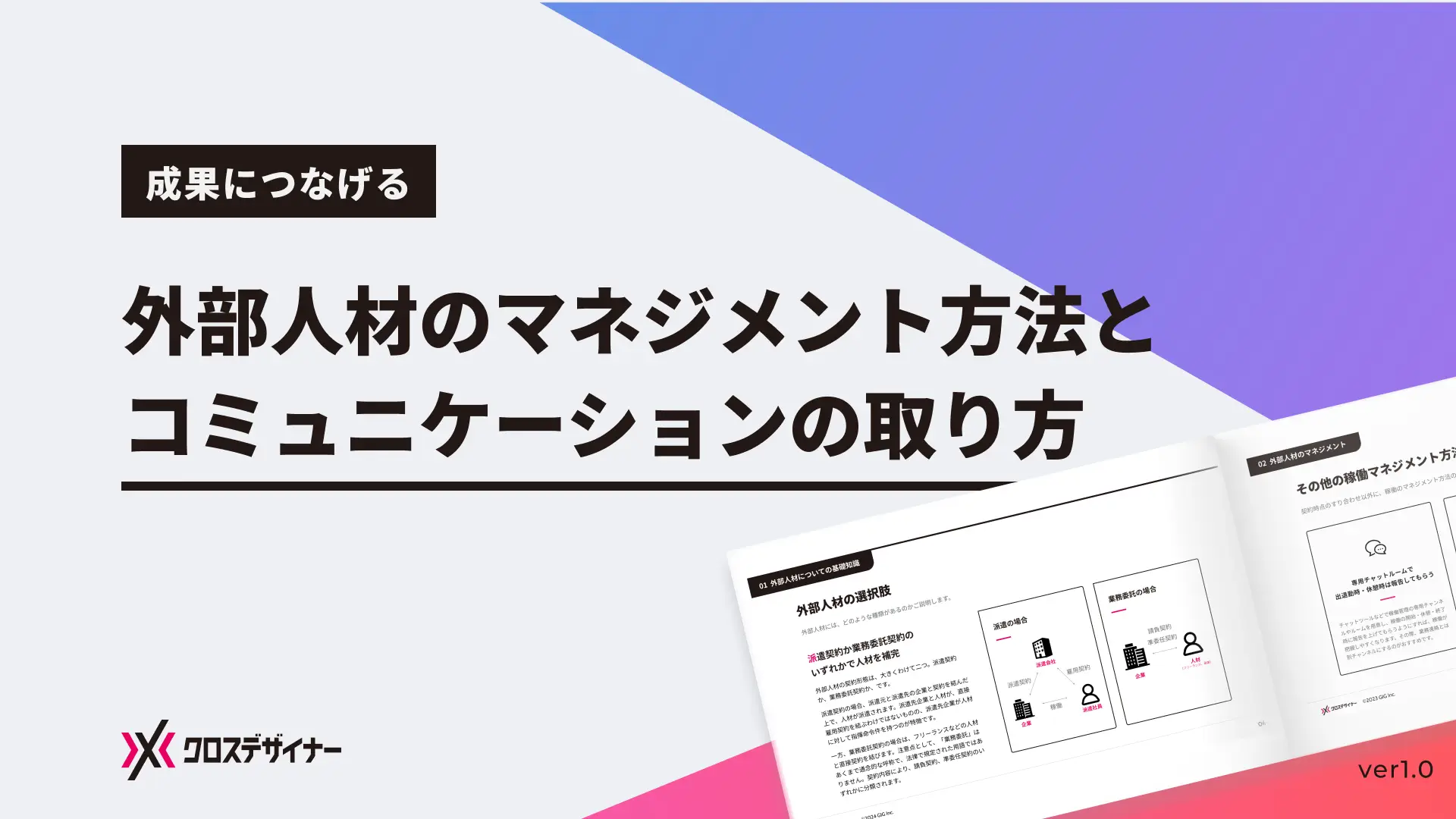
関連記事:デザイナーと円滑なコミュニケーションをとるコツは?工程別に解説
4. 作業環境を確認する
依頼する業務によっては、使用するツールやアプリケーション、制作環境が成果物の品質を左右します。そのため、外注先が必要な環境を整えているかを確認しておくと安心です。
デザインや開発などの専門職の場合、ライセンスの有無や使用ツールのバージョンを確認しておくことで、納品後の互換性トラブルを防げます。
企業側でツールを提供する必要があるかどうかも合わせて検討しておきましょう。
関連記事:在宅で働くグラフィックデザイナーと契約する際の注意点と業務委託のポイント
▼下記の資料では、契約をはじめとした業務委託人材の労務管理について詳しく解説しています。リスクを抑えて外部人材を活用するために、ぜひご活用てください。

5. 不明点は専門家に相談する
契約書の内容や税務上の判断に迷ったときは、税理士や社会保険労務士などの専門家に相談しましょう。契約の形式や支払い条件が、法律上どのように見なされるかを客観的に確認しておくことが大切です。
とくに外注の場合、管理が行き届きにくく、認識のすれ違いからトラブルが発生するケースも少なくありません。専門家に早めに相談することで、大きなリスクを避けやすくなります。
6.トラブル防止のために契約書を作成する
外注契約では、業務の範囲や納期、報酬、修正対応などを口頭で決めてしまうケースもありますが、トラブル防止のためには、必ず契約書を作成しましょう。
とくに、成果物の著作権・再利用・秘密保持などの扱いは、あとから問題になりやすい部分です。契約書に明記しておくことで、双方の立場を守ることができます。
▼下記の資料では、業務委託に必要な4種類の契約書の作り方を、テンプレート付きで解説しています。無料でダウンロードできますので、ぜひ参考にしてください。

外注はエージェントの活用がおすすめ
外注をスムーズに進めたいときは、エージェントサービスの活用も検討してみましょう。契約や報酬のやり取り、トラブル対応などを専門の担当者が代行してくれるため、初めて外注をする企業でも安心して依頼できます。
契約・報酬支払いを代行してくれる
エージェントサービスでは、企業とフリーランスの間に立ち、契約や報酬支払いの手続きを代行してくれます。
契約書の作成、請求書の処理、支払スケジュールの管理などを任せられるため、経理担当者の負担を大きく減らすことができます。
また、エージェントが仲介することで、契約内容や支払い条件のトラブルを防ぎやすくなります。とくに複数の外注先と取引する場合や、短期間で人材を確保したいときに効果的です。
関連記事:企業が業務委託にエージェントを活用するメリットと選び方のコツを解説
即戦力人材に短期間で出会える
エージェントは、専門スキルを持つ登録者の中から、条件に合う人材をスピーディーに紹介してくれます。募集から契約までのプロセスが短縮できるため、急な案件や繁忙期のリソース不足にも柔軟に対応できます。
また、エージェントには事前に実績やスキルを確認されたフリーランスが多く、自社に合った人材を精度高く見つけやすいのも特徴です。
事前に求めるスキルや経歴をまとめたジョブディスクリプションを作成しておくと、よりスムーズに提案してもらうことができるでしょう。
▼下記の資料では、ジョブディスクリプションの作成方法を初めての方でも安心のテンプレート付きで解説しています。無料でダウンロードできますので、ぜひご活用ください。
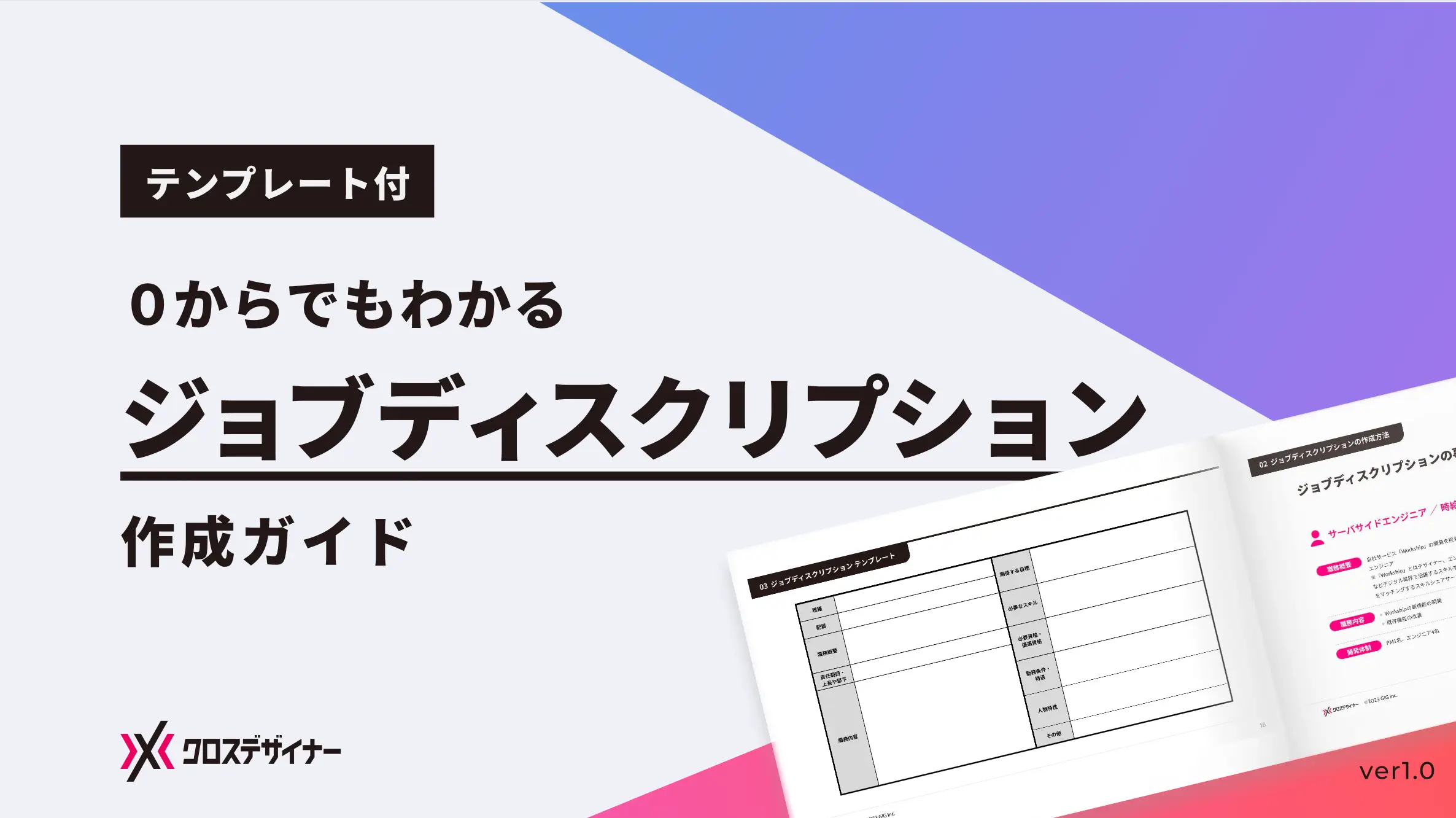
関連記事:【企業向け】人材紹介からの提案とは?書類で確認すべき点も紹介
トラブル時にサポートが受けられる
外注先とのやり取りで問題が発生した場合も、エージェントが仲介してサポートしてくれます。成果物の品質や納期、契約条件の調整など、第三者の視点から円滑な解決を促してくれるため安心です。
また、案件がスムーズに進んだときは、契約の延長や条件見直しなどのフォローも受けられます。単発契約で終わらせず、長期的なパートナーシップを築くうえでも有効です。
すべての対応をエージェントに頼らず、自社で体制を構築することも大切です。
▼下記の資料では、契約をはじめとした業務委託人材の労務管理について詳しく解説しています。リスクを抑えて外部人材を活用するために、ぜひご活用てください。

関連記事:業務委託契約を進める流れとは?稼働開始後の注意点と合わせて解説
フリーランスデザイナーへ外注するならクロスデザイナーがおすすめ
ここまで、外注の進め方や契約上の注意点、成功させるためのポイントを解説してきました。外注は、人手不足の解消だけでなく、専門スキルを取り入れて業務の質を高める有効な手段です。
ただし、契約手続きや報酬管理、品質コントロールなど、社内だけで対応するには負担が大きくなることもあるでしょう。
そのようなときに頼りにしてほしいのがフリーランスデザイナー専門のエージェントサービス『クロスデザイナー』です。
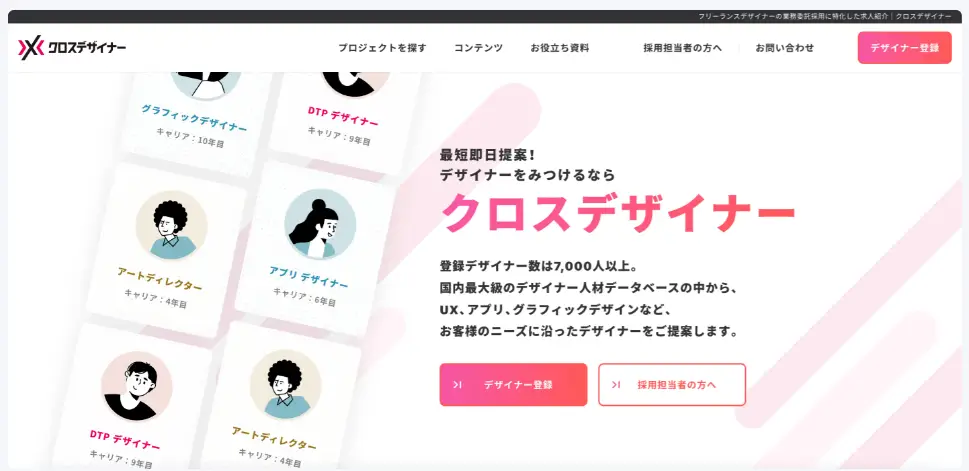
『クロスデザイナー』には厳正な審査を通過した即戦力デザイナーが7,000人以上在籍しています。採用コンサルタントが、自社に必要なデザイナーのスキルや要件をヒアリングして最適な人材を提案してくれるため、効率良く求めるスキルをもつ人材を確保できます。
こちらからサービス資料を無料でダウンロードできます。即戦力デザイナーをお探しの方は、【お問い合わせ】ください。平均1営業日以内にご提案します。
- クロスデザイナーの特徴
- クロスデザイナーに登録しているデザイナー参考例
- 各サービスプラン概要
- 支援実績・お客様の声
Documents